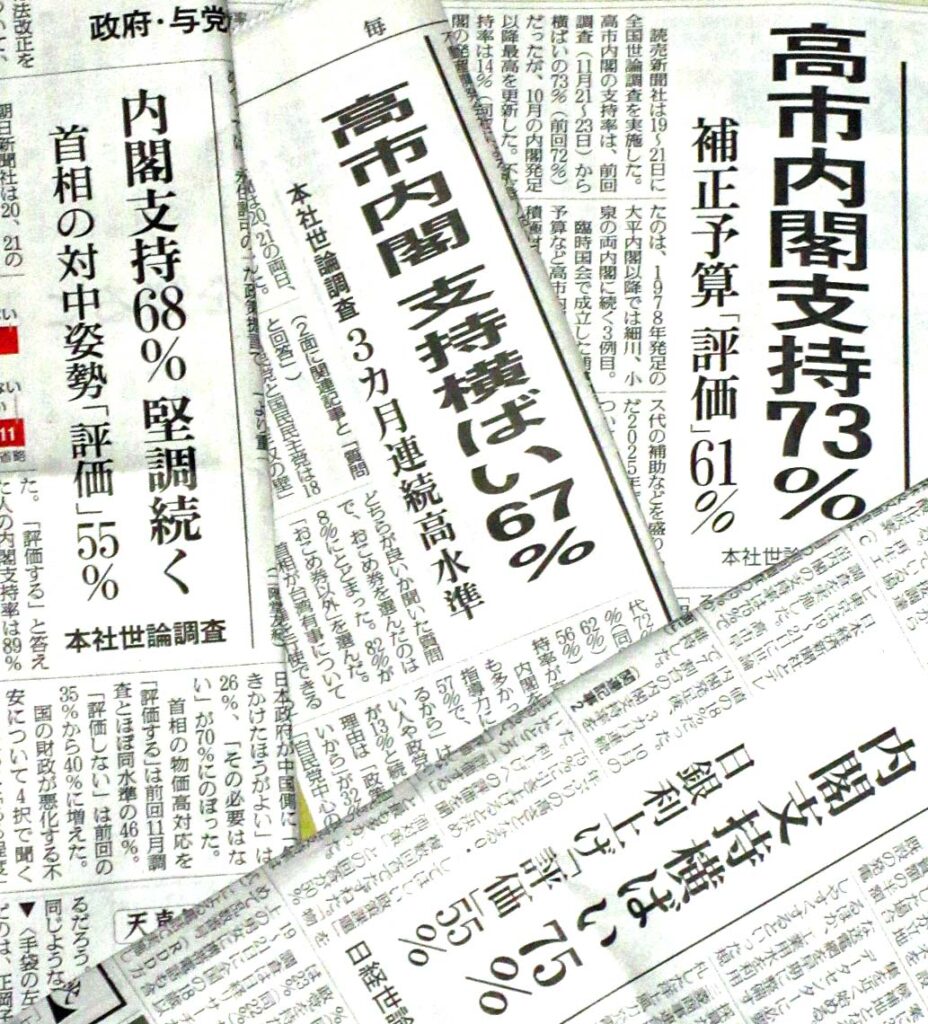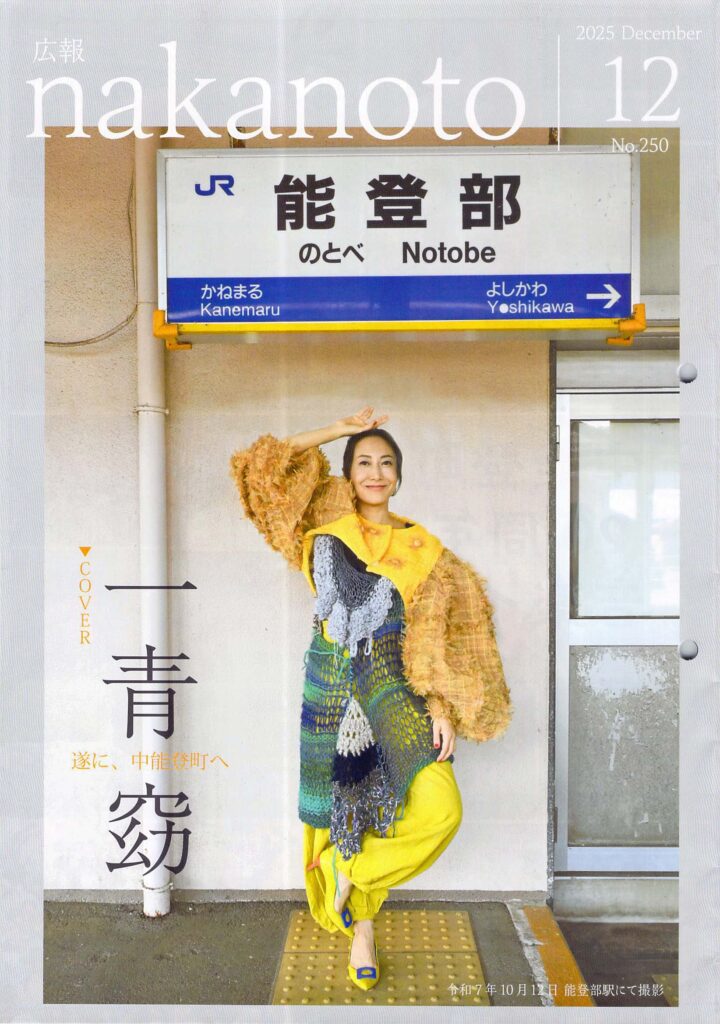★来年の世界の旅先ベスト20に「石川県」 能登ツーリズムに弾み

100年余りの歴史を刻むイギリス国営放送のBBCはグローバルメディアだ。BBCがニュースとして取り上げると、フランスのAFP通信やアメリカのニューヨーク・タイムズなども追いかけるように取り上げることもある。ニュースの取り上げ方も、グローバルメディアにありがちな上から目線ではなく、視聴者の目線に徹している。そうした影響力のあるBBCが今月12日(日本時間)に発表した「The 20 best places to travel in 2026」(2026年に訪れたい旅行先ベスト20)に、なんと「Ishikawa, Japan」が選ばれた。
国内のメディア各社が報じていたので、BBC公式サイトで調べてみた。中世の数々の建築で知られるサントドミンゴ(ドミニカ共和国)、美術館やオペラハウスラなどが集積する文化芸術都市として知られるフィラデルフィア(アメリカ)などと並んで石川県が紹介されている=写真・上=。画像部分は大名庭園で知られる金沢城の玉泉院丸庭園。見出しは「Why go: Traditional crafts and award-winning sake」、そして、紹介文の冒頭はこう記されている。「On New Year‘s Day 2024, a 7.6-magnitude earthquake devastated Japan’s remote Noto peninsula in Ishikawa Prefecture. Two years on, local leaders are urging visitors to return to help support the area‘s renewal.」

紹介文を以下、意訳する。見出し「なぜ行くのか:伝統工芸と誉(ほまれ)のある日本酒」。紹介文「2024年元日、マグニチュード7.6の地震が能登半島を襲った。2年が経ち、地元の人たちは地域再生を支援するためにぜひ能登を訪れてほしいと呼びかけている。金沢市は東京から新幹線で行け、有名な庭園である兼六園、そして伝統工芸の世界が広がる。金箔や加賀友禅で自分の作品をつくることもできる。そして、訪問者が最も心動かされるのは被災した能登だ。農家民宿では稲作などに参加でき、宿泊することで何世紀も続く白米千枚田を支えることにもなる。能登は海の幸や輪島塗、能登杜氏が造る日本酒で知られる。被災した能登の酒蔵を立て直すために『能登の酒を止めない』プロジェクトの取り組みが行われている」
上記の内容からも分かるように、BBCが「The 20 best places to travel in 2026」に「石川」を選んだ大きな理由に能登半島地震がある。欧米では被災地を巡る旅行を「ダ-クツーリズム(Dark tourism)」と呼んでいる。被災地や戦場跡地などを訪ね、死者を悼むとともに、悲しみを共有する観光とされている。すでに、能登ではインバウンド観光客が多く訪れている。ことし9月18日に輪島市の白米千枚田に立ち寄ると、インバウンド観光客が目立っていた。稲刈りは半分ほど終わっていたが、展望ができる高台からわざわざ下に降りてあぜ道を歩いて見学するグループの姿もあった=写真・下=。今回のBBCの選定で能登へのインバウンド観光にさらに弾みがつくかもしれない。
⇒25日(木)午後・金沢の天気 あめ