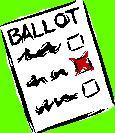郵政民営化に反対した人たちの精神構造の一端が理解できるようなコメントだった。広島6区で堀江貴文氏に勝った亀井静香氏が12日、TVメディアのインタビューで、296議席を得た自民について感想をこう述べた。「国民は覚せいしないといけない。これでは民主主義が滅んでしまう」と。郵政民営化は小泉内閣の暴挙だと反対し、今回の選挙も小泉総理の暴政だと言い放っていた。そして、自民が圧勝すると今度はその批判の矛先を有権者に向けているのだ。東京10区の小林興起氏も「(小池百合子氏に敗れたのは)マスコミが煽ったせいだ」と述べていた。要は、相手を批難することで存在感を示したい人たちのようだ。
◇
ところで、今回の「自在コラム」のテーマではインターネットが今回の選挙にどうかかわったのか、抽象論に陥らないように具体例から考察したい。選挙公示前の8月25日夜、自民党がメールマガジンの発行者やブログのユーザー(ブロガー)と党幹部との懇親会を開いて話題となった。招待されたのはネットエイジや「はてな」の運営会社や「忙しいあなたの代わりに新聞読みます」などのメールマガジン運営者、それにブロガーら33人。自民党から出席したのは武部勤幹事長と世耕弘成広報本部長代理だった。
自民党には「コミュニケーション戦略チーム」があり、有権者からのメールや電話の応対のほか、メディア対策も行っている。世耕氏はその中心メンバーだ。そして自らもブロガーである。今回の懇談会の仕掛け人はどうやら世耕氏であることが見えてきた。
そこで「もしや」と思い、世耕氏のブログ「世耕日記」を読むと8月25日付があった。懇談会の模様を記した文を引用する。「夜7時からブログ、メルマガ作者の皆さん33名と武部幹事長とで懇談会。安倍さんは台風で新幹線に閉じ込められてしまって間に合わない。政党とブロガーの対話は日本ではじめての企画であり、武部さんとブロガーの皆さんの波長が合うだろうか等心配事も多かったが、非常に実りある懇談であった。終了後は皆さんを総裁室にご案内して見学してもらう。居合わせた竹中大臣にも顔を出してもらい、非常に和気藹々とした雰囲気の中、企画は終了した。台風の中来て下さった33名の皆さんに感謝だ。」
ブログによると、和やかな雰囲気の会合であったことが分かる。とくに世耕氏が「政党とブロガーの対話は日本ではじめて」と記したように、確かに政党の取り組みとしては画期的なことではある。
この懇談会に出席した人はどう受け取ったのか。泉あいさんというブロガー(「GripBlog~私が見た事実~」を開設)は懇談会に参加した一人。泉さんの場合、「取材させて」と頼み込んだらタイミングよく「どうぞ」となったらしい。泉さんはその経緯について、「blog.goo」の選挙特集の中で寄稿している。以下、懇談会の模様をこう記している。「天下の自民党には、こんな多彩なキャラクターのおじさんたちがいましたが、自民党だけではなく、選挙の取材で他の政党の政治家ともお会いして、難しい政策論争をしている政治家も、実は威張った嫌な奴なんかじゃなく、普通の人なのだと知り、今までよりも政治を身近なものと感じられるようになりました。」。元OLの泉さんの目には好意的に映った。
ところが、違和感があったのはむしろ既存のマスメディアだったと記している。「今回の懇談会で威圧感を放っていたのは、政治家ではなくメディアの人たちでした。退室した後も、ガラスの壁に張り付いて中の会話に聞き耳を立てる必死な姿は、見習うべきものだと思いますが、どうも一段高い所から見下ろされているような気がして仕方がなかったです。」と。そして、「インターネットで、既存メディアとは違う、普通の人が身近に語ることのできる草の根ジャーナリズムを実現できる日が来るのは、そう遠くはない。自民党本部で私はそう感じました。」と記している。
泉さんの言葉は画期的である。既存のメディアを向こうに回して「草の根ジャーナリズム」を目指すと宣言しているのだ。この後、彼女はデジカムを担いで西へ東へと党首の街頭演説の録画に自費で出かけている。泉さんだけではない。こうした志(こことざし)の高いブロガーの出現のおかげで、既存のメディアでは報じられなかった選挙の別の一面を知ることができたと私は思っている。
⇒13日(火)午後・金沢の天気 晴れ
 決して美しい棚田ではない。田も畦(あぜ)も草がぼうぼう。それでも収穫の喜びは格別である。
決して美しい棚田ではない。田も畦(あぜ)も草がぼうぼう。それでも収穫の喜びは格別である。  穫の喜びである。田起こしから始め、苗床づくり、田植え、ようやく稲刈りにたどりついた達成感だ。そして「実りは美しい」という実感もわいた。
穫の喜びである。田起こしから始め、苗床づくり、田植え、ようやく稲刈りにたどりついた達成感だ。そして「実りは美しい」という実感もわいた。