☆凄みのあるニュース2題
トリノ冬季オリンピックは日本人のメダルが出ないせいか、日増しに興味が薄れていく。たまたま、ニュースサイト「AFP BB News」を眺めていると面白い記事に遭遇したので紹介する。
スペイン南部のウエルバ地方でイチゴ摘みのシーズンが到来し、この収穫のために東欧諸国などから3万の労働者が雇われている。その中に、ガーナ出身のスティーブンという人がいる。3年間砂漠を歩いてガーナからモロッコへ行き、2002年にスペインのカナリア諸島にボートでたどり着いたスティーブンさんは、現在は出稼ぎ労働の常連だ、という内容の短い記事だ。イチゴ摘みに3万人(ほどんどが女性)が出稼ぎに訪れ、その中に3年間砂漠を歩き、ボートでスペインにたどり着いた人もいる。ひと言、世界は凄まじい。
出稼ぎと言えば、稲刈りのシーズンになると、石川県の松任平野に能登の女性たちが大挙して稲刈りに訪れた時代があった。貴重な現金収入で、シーズンが終わりに近づくと金沢のデパートで買い物をして能登に戻り、今度は自分たちの田んぼの稲刈りをする。その稲刈りが終わると今度は夫婦で大阪や名古屋方面に出稼ぎに出る。春になると田を耕すために故郷に戻ってくる。スペインのイチゴ摘みから連想ゲームにようにし て稲刈りの女性のたちの光景が目に浮かんだ。能登の女性たちはよく働き、その分、亭主が楽をするので、「能登のトト楽」という言葉まであった。
て稲刈りの女性のたちの光景が目に浮かんだ。能登の女性たちはよく働き、その分、亭主が楽をするので、「能登のトト楽」という言葉まであった。
最近もう一つ気になったのが、東芝がイギリスの核燃料会社BNFL傘下の原子力大手、米ウエスチングハウス(WH)を総額54億ドル、6400億円で買収すると発表したニュース。欧米での原発の新規建設や中国、インドなどの需要拡大を見込んだ動きだが、実に思い切った決断をしたものだ。
原子炉には大きく分けて2つのタイプがあり、BWRと呼ばれる沸騰水型と、PWRと呼ばれる加圧水型。BWRは米ゼネラルエレクトリック(GE)が、PWRはWHがそれぞれ実用化した。GEと提携していた東芝はこれまでBWRを供給していたので、これで2つのタイプの原子炉を供給できるようになる。
その狙いは、世界のマーケットを睨んだというよりむしろ、日本には運転開始から30年を超える古い原子炉が増えているので、電力会社はいずれ老朽化対策に動かざるを得なくなる。そのためには2タイプの原子炉を供給できる企業がシェアを取れる。次世代DVD規格「HD DVD」の東芝が、対立規格「ブルーレイ・ディスク」のソニーを買収したようなそんな凄みのある話ではないか。
⇒18日(土)夕・金沢の天気 くもり
 吟醸といった高級化路線でブームをつくった日本酒の業界だが、最近はワインや焼酎に押されてかつての勢いはないと思っていた。ところが、妙なところからブームが起きているのである。カップ酒だ。そういえば、コンビニでも棚に占めるカップ酒の面積や種類が増えている。
吟醸といった高級化路線でブームをつくった日本酒の業界だが、最近はワインや焼酎に押されてかつての勢いはないと思っていた。ところが、妙なところからブームが起きているのである。カップ酒だ。そういえば、コンビニでも棚に占めるカップ酒の面積や種類が増えている。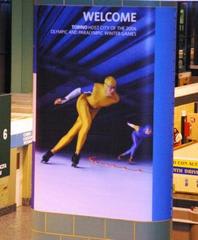 、オリンピックまで20日を切っていたのに空港は「オリンピック歓迎一色」ではないように思えた。
、オリンピックまで20日を切っていたのに空港は「オリンピック歓迎一色」ではないように思えた。 よっていたかもしれない。おそらく冬季五輪は「北のスポーツの祭典」あるいは「地域オリンピック」なのである。
よっていたかもしれない。おそらく冬季五輪は「北のスポーツの祭典」あるいは「地域オリンピック」なのである。 イタリア人はけばけばしく見えるものを高級そうに見せる天才かもしれない。ミラノの中心にあるドゥオモは、イタリアの代表的なゴシック建築でバチカンのサン・ピエトロ大聖堂に次ぐ教会建築として知られる。このドゥオモの前の広場とスカラ座の間を結ぶアーケードのある商店街ガレリア(長さ200㍍、高さ32㍍)=写真・上=には世界のブランドが集まる。ミラノ市が管理している。つまり、この威容を誇るテナントの大家さんが行政というわけだ。そして、その行政の指導の下、しっかりした「まちづくり」が垣間見える。
イタリア人はけばけばしく見えるものを高級そうに見せる天才かもしれない。ミラノの中心にあるドゥオモは、イタリアの代表的なゴシック建築でバチカンのサン・ピエトロ大聖堂に次ぐ教会建築として知られる。このドゥオモの前の広場とスカラ座の間を結ぶアーケードのある商店街ガレリア(長さ200㍍、高さ32㍍)=写真・上=には世界のブランドが集まる。ミラノ市が管理している。つまり、この威容を誇るテナントの大家さんが行政というわけだ。そして、その行政の指導の下、しっかりした「まちづくり」が垣間見える。 その一端がご覧の写真である。マクドナルドといえば、ハンバーガーの「マック」の愛称で知られ、日本でも世界でも同じあのロゴマークでおなじみである。ガレリアのマックのロゴはブラックとゴールドのツートンカラーである。向かい側のメルデスベンツも同じ配色である。実はこのガレリアではどんな世界的な企業であれ、ロゴは同じ色が条件となっているのだ。
その一端がご覧の写真である。マクドナルドといえば、ハンバーガーの「マック」の愛称で知られ、日本でも世界でも同じあのロゴマークでおなじみである。ガレリアのマックのロゴはブラックとゴールドのツートンカラーである。向かい側のメルデスベンツも同じ配色である。実はこのガレリアではどんな世界的な企業であれ、ロゴは同じ色が条件となっているのだ。 ザインはわれわれ日本人には真似ができないほどに洗練されている。もともとイタリア人の素質なのかもしれない。ミケランジェロやレオナルド・ダ・ビンチ、ラファエロといった名だたる天才芸術家を生む土地柄である。フィレンツェ周辺で生まれている。
ザインはわれわれ日本人には真似ができないほどに洗練されている。もともとイタリア人の素質なのかもしれない。ミケランジェロやレオナルド・ダ・ビンチ、ラファエロといった名だたる天才芸術家を生む土地柄である。フィレンツェ周辺で生まれている。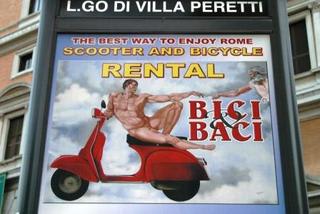 ったのか、という議論にもなる。フレスコ画という壁画技法がイタリアで、ジョット(1266-1337年)によって確立され、たまたま、その技法が生乾きの漆喰の上に塗るという一人一仕事の作業だった。したがって、そ
ったのか、という議論にもなる。フレスコ画という壁画技法がイタリアで、ジョット(1266-1337年)によって確立され、たまたま、その技法が生乾きの漆喰の上に塗るという一人一仕事の作業だった。したがって、そ れまで復数人の工房でなされた仕事が個人の仕事となり、才能ある個人の名が売れる時代と重なる。個人の発想や力量を競う時代になった。それがルネサンスを開花させたバックグラウンドだとの説もある。
れまで復数人の工房でなされた仕事が個人の仕事となり、才能ある個人の名が売れる時代と重なる。個人の発想や力量を競う時代になった。それがルネサンスを開花させたバックグラウンドだとの説もある。 「金沢の街並みの景観をぶち壊しているのは屋根の上のあの無粋なアンテナなんです。あれを変えようと思ってここ10年努力してきました」。地上波デジタル放送用の平面小型アンテア=写真=を次々と開発している創大アンテナ(金沢市)の高島宏社長がある研究発表会(2月3日・加賀市)の冒頭に語った言葉だ。美術学校を出た高島氏にとって屋根の上のまるでイバラのようなテレビアンテナが気に障っていた。そこで一念発起して平面アンテナの開発に取り組み、アンテナをいまでは切手サイズほどにした。
「金沢の街並みの景観をぶち壊しているのは屋根の上のあの無粋なアンテナなんです。あれを変えようと思ってここ10年努力してきました」。地上波デジタル放送用の平面小型アンテア=写真=を次々と開発している創大アンテナ(金沢市)の高島宏社長がある研究発表会(2月3日・加賀市)の冒頭に語った言葉だ。美術学校を出た高島氏にとって屋根の上のまるでイバラのようなテレビアンテナが気に障っていた。そこで一念発起して平面アンテナの開発に取り組み、アンテナをいまでは切手サイズほどにした。
 レオナルド・ダ・ビンチの「最後の晩餐」で有名なサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会の間近で。
レオナルド・ダ・ビンチの「最後の晩餐」で有名なサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会の間近で。  いているのか、とも思ったりした。
いているのか、とも思ったりした。 いたが、随分とインフラが進んでいる。
いたが、随分とインフラが進んでいる。 子を描いている。
子を描いている。 大雪にあって、雪を楽しむ。これほどぜいたくなことはない。金沢大学創立五十周年記念館「角間の里」ではきょう27日から「雪だるままつり」が始まった。市民ボランティア「里山メイト」の面々や市民参加で思い思いの雪だるまをつくって楽しむという趣向だ。
大雪にあって、雪を楽しむ。これほどぜいたくなことはない。金沢大学創立五十周年記念館「角間の里」ではきょう27日から「雪だるままつり」が始まった。市民ボランティア「里山メイト」の面々や市民参加で思い思いの雪だるまをつくって楽しむという趣向だ。 その中で、凝った作品を一つ紹介する。「チョンマゲだるま」とでも名付けたらよいのだろうか、殿様の雪だるまである。これは髷(まげ)を雪で作るのがが難しい。そして顔の表情がとてもユーモラスである。
その中で、凝った作品を一つ紹介する。「チョンマゲだるま」とでも名付けたらよいのだろうか、殿様の雪だるまである。これは髷(まげ)を雪で作るのがが難しい。そして顔の表情がとてもユーモラスである。