☆マスメディアの風圧と法
ゴールデン・ウイーク期間中の3日、珍事が起きた。有田陶器市が開催されている佐賀県有田町で強風で仮設テントが揺れ、中の棚に陳列してあった皿や小鉢などの陶器が次々と吹き飛ばされ割れた。被害は9点(19000円相当)だった。問題はその原因。午後2時10分ごろ、FBS福岡放送の取材ヘリコプターが上空を飛び、ヘリが低空で通過した直後 に突風が吹き、テントの中にあった棚の上の陶器が飛ばされたという。
に突風が吹き、テントの中にあった棚の上の陶器が飛ばされたという。
テレビ局側は「当時は高度150㍍を維持していた。上空から吹き下ろしの風が吹いていて、ヘリの風と相まって被害が出たのかもしれない」と説明した。以上が新聞各紙からピックアップした内容だ。しかし、航空法では、ヘリの最低飛行高度は例えば人家の密集した地域の上空では半径600㍍の範囲の最も高い障害物の高さにさらに300㍍の高度を加えとなっている。カメラマンが被写体に近づこうとすれば、高度を下げるしかない。そこでカメラマンは強くパイロットに低空を飛ぶよう希望したのだろうかと推測する。今回は皿や小鉢だったものの、一歩間違えて、子どもが吹き飛ばされていたなら大事件になっていた。
もう一つ、今度は法をめぐる風圧を新聞から拾った。4月に赴任した高松地検の川野辺充子検事正が就任会見で、男性記者が「年齢をうかがいたい」と質問した。検事正は「女性に年を聞くんですか、すごいですね」と答えなかった。今度は女性記者が「要職の方には年齢を伺っています」と食い下がったが、今度は「中央官庁でも公表しない方向になっています」と年齢の公表を断った。しかし、別の人事案件で法務省は一度は学歴と生年月日を非公表にしたものの、記者クラブが要求して、公表した例がある。川野辺検事正の場合は最終的に公表したものの、その混乱の原因となっているのが個人情報保護法である。
もともと民間の情報を守ろうとしたのが個人情報保護法であり、官庁が独占している情報を出させようとするのが情報公開法なのである。なのに「官」がちゃっかりと個人情報保護法の隠れ蓑をまとっている。つまり、官庁が個人情報保護法を盾に情報を出し渋っているのである。そこをマスメディアは見抜いているから今回の川野辺検事正に対する生年月日の公表要求のケースのように、官が情報を出し渋れば渋るほどマスメディアの風圧も厳しさを増すという構図になる。
端的に言えば、官庁の情報に関しては情報公開法の枠組みで整理したほうが一番すっきりするのである。まして公人である要職の人事などなおさらだ。
⇒3日(水)夜・金沢の天気 はれ
 村崎さんの大道芸はサルを調教して演じるのではなく、「同志的結合」によって共に演じるのだそうだ。だから「観客が見ると相棒のサルが村崎さんを曳き回しているようにも見える」との評もある。相棒のサルとは安登夢(あとむ)、15歳のオスである。村崎さんは「こいつの立ち姿が見事でね、伊勢の猿田彦神社で一本杉という芸(棒の上で立つ)がぴたりと決まって、手を合わせているお年寄りもいたよ」と目を細めた。
村崎さんの大道芸はサルを調教して演じるのではなく、「同志的結合」によって共に演じるのだそうだ。だから「観客が見ると相棒のサルが村崎さんを曳き回しているようにも見える」との評もある。相棒のサルとは安登夢(あとむ)、15歳のオスである。村崎さんは「こいつの立ち姿が見事でね、伊勢の猿田彦神社で一本杉という芸(棒の上で立つ)がぴたりと決まって、手を合わせているお年寄りもいたよ」と目を細めた。 同郷の民俗学者・宮本常一(故人)から猿曳きの再興を促され、日本の霊長類研究の草分けである今西錦司(故人)と出会った。司馬遼太郎が「人間の大ザル」とたとえたのは今西錦司のことである。商業的に短時間で多くの観客に見せる「猿まわし」とは一線を引き、日本の里山をめぐる昔ながらの猿曳きを身上とする。人とサルの共生から生まれた技。そこを今西に見込まれ、嘱望されて京都大学霊長類研究所の客員研究員(1978-88年)に。ここで、河合雅雄氏らさらに多くのサル学研究者と交わった。
同郷の民俗学者・宮本常一(故人)から猿曳きの再興を促され、日本の霊長類研究の草分けである今西錦司(故人)と出会った。司馬遼太郎が「人間の大ザル」とたとえたのは今西錦司のことである。商業的に短時間で多くの観客に見せる「猿まわし」とは一線を引き、日本の里山をめぐる昔ながらの猿曳きを身上とする。人とサルの共生から生まれた技。そこを今西に見込まれ、嘱望されて京都大学霊長類研究所の客員研究員(1978-88年)に。ここで、河合雅雄氏らさらに多くのサル学研究者と交わった。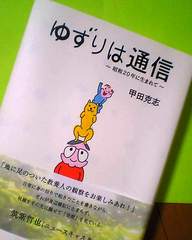 代金を振り込んでそのままにしてあったが、年度末に部屋の整理をしていて、ひょっこり出てきた。その書籍は498㌻もある。タイトルは「ゆずりは通信~昭和20年に生まれて~」。自らの
代金を振り込んでそのままにしてあったが、年度末に部屋の整理をしていて、ひょっこり出てきた。その書籍は498㌻もある。タイトルは「ゆずりは通信~昭和20年に生まれて~」。自らの 94日間で読んだ本は200冊に上ったという。百科事典のほか、中国の歴史書である「史記」や「白い巨塔」(山崎豊子著)、それに韓国語の勉強もしていたらしい。体重は8㌔減量。ダイエットした人なら想像はつくかもしれないが、3ヵ月で8㌔は無理のない数字である。適度な運動をし、間食せず、就寝前3時間は物を口にしなければ無理しなくともこのくらいの減量は可能だろう。
94日間で読んだ本は200冊に上ったという。百科事典のほか、中国の歴史書である「史記」や「白い巨塔」(山崎豊子著)、それに韓国語の勉強もしていたらしい。体重は8㌔減量。ダイエットした人なら想像はつくかもしれないが、3ヵ月で8㌔は無理のない数字である。適度な運動をし、間食せず、就寝前3時間は物を口にしなければ無理しなくともこのくらいの減量は可能だろう。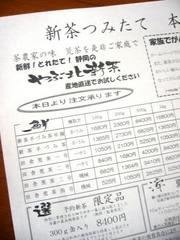
 それは戸室(とむろ)の方面に当たる。この地区は昔から「戸室石」を産出してきた。赤戸室あるいは青戸室などといまでも重宝されているのは磨けば光る安山岩で加工がしやすいからである。それより何より10数万個ともいわれる金沢城の石垣に利用されたことから有名になった。戸室から金沢城へと石を運んだ道沿いには「石引(いしびき)町」などの地名が今も残る。
それは戸室(とむろ)の方面に当たる。この地区は昔から「戸室石」を産出してきた。赤戸室あるいは青戸室などといまでも重宝されているのは磨けば光る安山岩で加工がしやすいからである。それより何より10数万個ともいわれる金沢城の石垣に利用されたことから有名になった。戸室から金沢城へと石を運んだ道沿いには「石引(いしびき)町」などの地名が今も残る。 今回の踏査でもかつての石切場の跡らしい場所がいくつかあり、いまでも石がむき出しになっている=写真・上=。案内役で地元の歴史に詳しい市民ボランティアのM氏が立ち止まり、「ここがダゴザカという場所です」と説明を始めた。
今回の踏査でもかつての石切場の跡らしい場所がいくつかあり、いまでも石がむき出しになっている=写真・上=。案内役で地元の歴史に詳しい市民ボランティアのM氏が立ち止まり、「ここがダゴザカという場所です」と説明を始めた。 ダゴザカから北にコースを回り込んで、今度は「蓮如の力水」という池=写真・下=を案内してもらった。浄土真宗をひらいた親鸞(しんらん)は「弟子一人ももたずさふらふ」と師匠と弟子の関係を否定し、ただ念仏の輪の中で布教したといわれる。後世の蓮如(1415-99年)は生涯に5人の妻を迎え、13男14女をもうけた精力家だ。教団としての体裁を整えたオーガナイザーでもある。その蓮如が北陸布教で使った道というのが、越中から加賀へと通じるブッキョウドウ(仏教道)である。尾根伝いの道は幅1㍍。夕方でも明るく、雪解けが早い。蓮如の力水はブッキョウドウのそばにある周囲50㍍ほどの泉である。山頂付近にありながらいまでもこんこんと水が湧き出ていて周囲の下の田を潤している。
ダゴザカから北にコースを回り込んで、今度は「蓮如の力水」という池=写真・下=を案内してもらった。浄土真宗をひらいた親鸞(しんらん)は「弟子一人ももたずさふらふ」と師匠と弟子の関係を否定し、ただ念仏の輪の中で布教したといわれる。後世の蓮如(1415-99年)は生涯に5人の妻を迎え、13男14女をもうけた精力家だ。教団としての体裁を整えたオーガナイザーでもある。その蓮如が北陸布教で使った道というのが、越中から加賀へと通じるブッキョウドウ(仏教道)である。尾根伝いの道は幅1㍍。夕方でも明るく、雪解けが早い。蓮如の力水はブッキョウドウのそばにある周囲50㍍ほどの泉である。山頂付近にありながらいまでもこんこんと水が湧き出ていて周囲の下の田を潤している。 今月6日に開花宣言をしたソメイヨシノはまだ散らずに私たちを楽しませてくれている。花冷えのおかげで葉が出るのが遅い分、花は命脈を保っているかのようである。パッと咲いて、パッと散るの桜の本来の有り様なのだろうが、長く咲き続ける桜も人生に似て、それはそれなりに味がある。
今月6日に開花宣言をしたソメイヨシノはまだ散らずに私たちを楽しませてくれている。花冷えのおかげで葉が出るのが遅い分、花は命脈を保っているかのようである。パッと咲いて、パッと散るの桜の本来の有り様なのだろうが、長く咲き続ける桜も人生に似て、それはそれなりに味がある。 
 も言おうか…。余談だが、天守閣のように見えるそれは櫓(やぐら)である。なぜ天守閣ではないのか。加賀藩は戦時には指令塔となる天守閣を造らなかったといわれる。初代の前田利家は秀吉に忠誠を尽くし、「見舞いに来る家康を殺せ」と言い残して床で最期を迎える。それ以降、加賀は西側と見なされ、徳川の世には外様の悲哀を味わうことになる。三代の利常はわざと鼻毛を伸ばし江戸の殿中では滑稽(こっけい)を装って、「謀反の意なし」を演じた。ましてや城に天守閣など造るはずもなかったというのが地元での言い伝えである。
も言おうか…。余談だが、天守閣のように見えるそれは櫓(やぐら)である。なぜ天守閣ではないのか。加賀藩は戦時には指令塔となる天守閣を造らなかったといわれる。初代の前田利家は秀吉に忠誠を尽くし、「見舞いに来る家康を殺せ」と言い残して床で最期を迎える。それ以降、加賀は西側と見なされ、徳川の世には外様の悲哀を味わうことになる。三代の利常はわざと鼻毛を伸ばし江戸の殿中では滑稽(こっけい)を装って、「謀反の意なし」を演じた。ましてや城に天守閣など造るはずもなかったというのが地元での言い伝えである。 の鋭角的なフォルムを優しく植物の桜が覆う。ただそれだけのアングルなのだが、それはそれで見方によっては美のフォルムのように思えるから不思議だ。上から3枚目の桜は石川門にかかる架橋から見たもの。円を描いて、桜が納まる。黒と白のコントラスト。地底から天空を仰ぎ見るような錯覚さえある。
の鋭角的なフォルムを優しく植物の桜が覆う。ただそれだけのアングルなのだが、それはそれで見方によっては美のフォルムのように思えるから不思議だ。上から3枚目の桜は石川門にかかる架橋から見たもの。円を描いて、桜が納まる。黒と白のコントラスト。地底から天空を仰ぎ見るような錯覚さえある。 花が三部咲きだった先週末、兼六園の近くの料理屋で開かれた会合に出席した。金沢大学と地元民放テレビ局が共同制作した番組の反省会である。番組は、大学のキャンパス(2001㌶)に展開する森や棚田を市民ボランティアとともに保全し、農業体験や動植物の調査を通じて地域と交流する、大学の里山プロジェクトの一年をまとめたものだ。ハイビジョンカメラで追いかけた里山の四季は「われら里山大家族」というドキュメンタリー番組(55分)となって先月25日に放送された。
花が三部咲きだった先週末、兼六園の近くの料理屋で開かれた会合に出席した。金沢大学と地元民放テレビ局が共同制作した番組の反省会である。番組は、大学のキャンパス(2001㌶)に展開する森や棚田を市民ボランティアとともに保全し、農業体験や動植物の調査を通じて地域と交流する、大学の里山プロジェクトの一年をまとめたものだ。ハイビジョンカメラで追いかけた里山の四季は「われら里山大家族」というドキュメンタリー番組(55分)となって先月25日に放送された。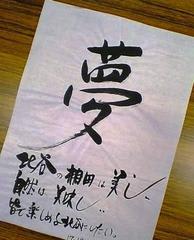 この番組に登場する市民ボランティアは、今の言葉で「キャラが立っている」と言うか、魅力的な人たちがそろった。その一人、男性のAさんは「夢を売るおっさん」というキャラクターで登場した。65歳。岐阜県大垣市の農家の生まれで、名古屋市に本社がある大手量販店に就職した。金沢に赴任し、北陸の食品商社に食い込んで、業界では知られた腕利きのバイヤーだった。定年後に里山プロジェクトに市民ボランティアとして参加し、棚田の復元に携わる。
この番組に登場する市民ボランティアは、今の言葉で「キャラが立っている」と言うか、魅力的な人たちがそろった。その一人、男性のAさんは「夢を売るおっさん」というキャラクターで登場した。65歳。岐阜県大垣市の農家の生まれで、名古屋市に本社がある大手量販店に就職した。金沢に赴任し、北陸の食品商社に食い込んで、業界では知られた腕利きのバイヤーだった。定年後に里山プロジェクトに市民ボランティアとして参加し、棚田の復元に携わる。
 はなく、言葉に気持ちがこもっていた。
はなく、言葉に気持ちがこもっていた。 視界」
視界」