☆「ニュース異常気象」3題
1月の積雪がゼロという金沢地方気象台始まって以来の暖冬異変。この異変は何も気象だけではないようだ。「ニュースの異常気象」を3題まとめてみる。
 関西テレビの番組「発掘!あるある大事典Ⅱ」で捏造問題が発覚して以来、テレビ業界全体の信頼度が落ちたように思える。そしてついにというか、きょう13日の閣議後の記者会見で、菅義偉総務相は「捏造再発防止法案」なるものを国会に提出すると述べたそうだ。その理由は「公の電波で事実と違うことが報道されるのは極めて深刻。再発防止策につながる、報道の自由を侵さない形で何らかのもの(法律)ができればいい」と。放送法第三条と第四条は、放送上の間違いがあった場合は総務省に報告し、自ら訂正放送をするとした内容の適正化の手順をテレビ局に義務付けている。さらにこれ以上の防止策となると、罰則規定の強化しかないのではないか。個別の不祥事イコール業界全体の規制の構図は繰り返されてきた負のスパイラルではある。
関西テレビの番組「発掘!あるある大事典Ⅱ」で捏造問題が発覚して以来、テレビ業界全体の信頼度が落ちたように思える。そしてついにというか、きょう13日の閣議後の記者会見で、菅義偉総務相は「捏造再発防止法案」なるものを国会に提出すると述べたそうだ。その理由は「公の電波で事実と違うことが報道されるのは極めて深刻。再発防止策につながる、報道の自由を侵さない形で何らかのもの(法律)ができればいい」と。放送法第三条と第四条は、放送上の間違いがあった場合は総務省に報告し、自ら訂正放送をするとした内容の適正化の手順をテレビ局に義務付けている。さらにこれ以上の防止策となると、罰則規定の強化しかないのではないか。個別の不祥事イコール業界全体の規制の構図は繰り返されてきた負のスパイラルではある。
「団塊の世代」を中心とした55~59歳の男性が自宅の火災で死亡するケースが全国で増えているそうだ。死者は「無職」「独り暮らし」の割合が高い。明確な理由は分かっていないが、家族との別居、深酒、タバコ火の不始末、火災へとこれも負のスパイラルである。北海道では、05年の男性の死者は57人おり、このうち56~60歳が全体の4分の1にあたる13人を占めたという。個人的な話だが、金沢の高校時代の知り合いがこれまで2人もアパートで孤独死している。2人とも上場企業の元サラリーマンだった。交通事故などの不祥事による退職、離婚、深酒、病死である。病死はアルコールによる肝硬変。60歳の定年時に熟年離婚がはやっているそうだ。おそらくろくなことはない。男は逆境に弱いのだ。
「発掘!あるある大事典Ⅱ」の捏造事件の続報が大きく扱われ、目立たない扱いで記事になっていたが、朝日新聞のカメラマンが写真に付ける記事を書く際に読売新聞の記事を盗用していたという事件もある意味で異常である。1月30日付の夕刊社会面に掲載された富山県立山町の「かんもち」作りの写真の記事を盗用したというもの。ローカル記事をインターネットで探して拝借するという構図だ。それにしても、ローカル記事なら東京で盗用してもバレないだろというのは安易に考えたものだ。カメラマンは実名公表のうえ、解雇となった。「もち」のツケは大きかった。
⇒13日(火)夜・金沢の天気 はれ
 捏造問題で、関テレの社長が2月7日、総務省近畿総合通信局を訪れ、捏造についてまとめた報告書を提出した。ところが、近畿総合通信局側は納得しなかったと、報じられている。なぜか。疑惑が次から次と出てきて、7日の説明は説明にならなかったからである。どとのつまり、「520回すべてを調査し報告しなければ、調査したことにはならない。これはあくまでも途中経過説ある」と監督官庁である近畿総合通信局側から灸を据えられたに違いない。こんなことは素人でも想像がつく。
捏造問題で、関テレの社長が2月7日、総務省近畿総合通信局を訪れ、捏造についてまとめた報告書を提出した。ところが、近畿総合通信局側は納得しなかったと、報じられている。なぜか。疑惑が次から次と出てきて、7日の説明は説明にならなかったからである。どとのつまり、「520回すべてを調査し報告しなければ、調査したことにはならない。これはあくまでも途中経過説ある」と監督官庁である近畿総合通信局側から灸を据えられたに違いない。こんなことは素人でも想像がつく。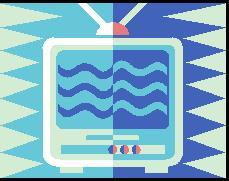 先日、あるテレビ局から金沢大学に取材の申し込みが電話あった。ニュースリリースなどの詳細をメールで送る旨を伝え、教えてもらったメールアドレスに送り、届いたら返信をくださいとお願いしたが、それがない。果たして送信できたのかとこちらが心配になって電話で確認すると、相手は「受け取りました」と。それだったら、受け取った旨の返信をくれればよいのにと思うことはしばしばある。その点、地元紙と呼ばれる新聞社は割とこまめに返信をくれる。
先日、あるテレビ局から金沢大学に取材の申し込みが電話あった。ニュースリリースなどの詳細をメールで送る旨を伝え、教えてもらったメールアドレスに送り、届いたら返信をくださいとお願いしたが、それがない。果たして送信できたのかとこちらが心配になって電話で確認すると、相手は「受け取りました」と。それだったら、受け取った旨の返信をくれればよいのにと思うことはしばしばある。その点、地元紙と呼ばれる新聞社は割とこまめに返信をくれる。 比べれば、ほぼ奇跡に近い。
比べれば、ほぼ奇跡に近い。 列記すると、各社一面を飾ったのが、NHKの番組が放送直前に改変されたとして、取材を受けた市民団体がNHKなどに総額4000万円の賠償を求めた控訴審判決で、東京高裁が取材された側の「期待権」を認めてNHKに200万円の賠償命令を命じたニュース。さらに同じ一面で、裁判員制度フォーラムを共催した産経新聞社などが謝礼を払ってサクラ(参加者)を集めていたこと。
列記すると、各社一面を飾ったのが、NHKの番組が放送直前に改変されたとして、取材を受けた市民団体がNHKなどに総額4000万円の賠償を求めた控訴審判決で、東京高裁が取材された側の「期待権」を認めてNHKに200万円の賠償命令を命じたニュース。さらに同じ一面で、裁判員制度フォーラムを共催した産経新聞社などが謝礼を払ってサクラ(参加者)を集めていたこと。 0日にホームページで公表した内容によると、捏造は3パターンである。一つは「データの捏造」。今回、被験者のコレステロール値、中性脂肪値、血糖値の測定せず、また、比較実験での血中イソフラボンの測定せず、さらに血液は採集をするも実際は検査せず、数字はすべて架空だった。二つ目が「コメントの捏造」である。米国テンプル大学アーサー・ショーツ教授の日本語訳コメントは内容は本人の話したものとはまったく違っていた。三つ目が「写真の捏造」である。やせたことを示す3枚は被験者とは無関係の写真だった。
0日にホームページで公表した内容によると、捏造は3パターンである。一つは「データの捏造」。今回、被験者のコレステロール値、中性脂肪値、血糖値の測定せず、また、比較実験での血中イソフラボンの測定せず、さらに血液は採集をするも実際は検査せず、数字はすべて架空だった。二つ目が「コメントの捏造」である。米国テンプル大学アーサー・ショーツ教授の日本語訳コメントは内容は本人の話したものとはまったく違っていた。三つ目が「写真の捏造」である。やせたことを示す3枚は被験者とは無関係の写真だった。 当初、「泡沫候補」とも言われていた元タレント候補が激戦を制したとあって、各新聞やテレビはトップニュースの扱いで報じた。ところが、このニュースを朝日新聞大阪本社はトップ扱いにしなかった。同じ朝日新聞でも、東京本社はトップだったのにである。大阪本社の一面トップは生活福祉資金の貸付金の272億円が未回収であることを報じたものだ。ホットなニュースである「そのまんま東氏当選」は準トップだった。なぜか、である。
当初、「泡沫候補」とも言われていた元タレント候補が激戦を制したとあって、各新聞やテレビはトップニュースの扱いで報じた。ところが、このニュースを朝日新聞大阪本社はトップ扱いにしなかった。同じ朝日新聞でも、東京本社はトップだったのにである。大阪本社の一面トップは生活福祉資金の貸付金の272億円が未回収であることを報じたものだ。ホットなニュースである「そのまんま東氏当選」は準トップだった。なぜか、である。 「単なる物販サイトではない。地域おこしの心意気でやっている」。北陸朝日放送(HAB)業務部、能田剛志部長は力を込めた。講演タイトルは「ECサイト『金沢屋』の6年で得たローカル独自のコマース展開とは」。放送エリアである石川県の地場産品にこだわり、この6年で生産者とともに100余りの商品を開発した。商品の採用が決まると、プロの写真家とライターが現地に入り、取材する。生産者の人となりや商品ができるまでの物語がテキストベースで紹介される。単に商品の画像を並べただけのショッピングモールとは異なり、手間ひま(コスト)をかけている。そのせいもあり、売上は緩やかな右肩上がりであるものの、単年度の黒字決算には至っていない。「(単年度黒字は)08年を目標にしている」と。今年5月、姉妹サイトとして「山形屋」(山形テレビ)が誕生した。システムと運営ノウハウを系列局にのれん分けするほどになったのである。
「単なる物販サイトではない。地域おこしの心意気でやっている」。北陸朝日放送(HAB)業務部、能田剛志部長は力を込めた。講演タイトルは「ECサイト『金沢屋』の6年で得たローカル独自のコマース展開とは」。放送エリアである石川県の地場産品にこだわり、この6年で生産者とともに100余りの商品を開発した。商品の採用が決まると、プロの写真家とライターが現地に入り、取材する。生産者の人となりや商品ができるまでの物語がテキストベースで紹介される。単に商品の画像を並べただけのショッピングモールとは異なり、手間ひま(コスト)をかけている。そのせいもあり、売上は緩やかな右肩上がりであるものの、単年度の黒字決算には至っていない。「(単年度黒字は)08年を目標にしている」と。今年5月、姉妹サイトとして「山形屋」(山形テレビ)が誕生した。システムと運営ノウハウを系列局にのれん分けするほどになったのである。 の里山自然学校からは研究員と、キャンパスでの炭焼きを目指す学生サークル 「CLUB炭焼き」の代表が出演する。NHK金沢放送局の夕方のワイド番組「デジタル百万石」 で午後6時30分ごろ放送だ。
の里山自然学校からは研究員と、キャンパスでの炭焼きを目指す学生サークル 「CLUB炭焼き」の代表が出演する。NHK金沢放送局の夕方のワイド番組「デジタル百万石」 で午後6時30分ごろ放送だ。 小学校にあった石炭ストーブではなく、炭を燃料としている。仕組みは ストーブに取り付けたタンク内で温まった水が、設置された配管内を循環し、部屋を暖めるというもの。当初、2005年8月ごろに、 金沢大学のOBで、バイオマス燃料の研究に取り組む北野滋さん(55)=明和工業社長(石川県能美市)=が炭ストーブの開発を大学へ提案。築300年の「角間の里」の木造の雰囲気と、そこを拠点に活動する「角間の里山自然学校」 のコンセプトとマッチしていたので、「角間の里」に設置が決まった。05年初頭の設置予定だったが、防災設備やスチームの配管、煙突の構造、 建物の外観とのすりあわせなどの問題をクリアーするのに遅れ、ようやく完成にこぎつけた。
小学校にあった石炭ストーブではなく、炭を燃料としている。仕組みは ストーブに取り付けたタンク内で温まった水が、設置された配管内を循環し、部屋を暖めるというもの。当初、2005年8月ごろに、 金沢大学のOBで、バイオマス燃料の研究に取り組む北野滋さん(55)=明和工業社長(石川県能美市)=が炭ストーブの開発を大学へ提案。築300年の「角間の里」の木造の雰囲気と、そこを拠点に活動する「角間の里山自然学校」 のコンセプトとマッチしていたので、「角間の里」に設置が決まった。05年初頭の設置予定だったが、防災設備やスチームの配管、煙突の構造、 建物の外観とのすりあわせなどの問題をクリアーするのに遅れ、ようやく完成にこぎつけた。