☆「雲を測る」スケール感の人
金沢21世紀美術館の屋上に据え付けられているブロンズ作品は「雲を測る男」である。その作者であるヤン・ファーブル(ベルギー)はあの有名な昆虫学者ファン・アンリ・ファ ーブルのひ孫だ。が、この作品を実際に見た人はブログの写真と実物はちょっと違うと言うだろう。そう、男が胴から腰にかけて白い布をまとっている。この写真を撮影した2004年9月、台風16号と18号が立て続けにやってきた。何しろ屋上に設置されているので台風で倒れるかもしれないと、まず布を胴体に巻いて、その上にワイヤーを巻いて左右で固定したものだ。
ーブルのひ孫だ。が、この作品を実際に見た人はブログの写真と実物はちょっと違うと言うだろう。そう、男が胴から腰にかけて白い布をまとっている。この写真を撮影した2004年9月、台風16号と18号が立て続けにやってきた。何しろ屋上に設置されているので台風で倒れるかもしれないと、まず布を胴体に巻いて、その上にワイヤーを巻いて左右で固定したものだ。
美術館はオープン前の一番あわただしいとき。案内役だった館長の蓑豊(みの・ゆたか)氏のそのときの言葉が振るっていた。「金太郎さんの腹巻のようでしょう」と。場を和ますユーモアの人である。その蓑氏が3月31日付で館長を退任する。
蓑氏は初代館長として、子どもが訪れやすい美術館というコンセプトで運営。開館2年余りで来館者は300万人を突破した。いまや兼六園や武家屋敷と並ぶ金沢の名所となった。金沢生まれ、慶應義塾大学(美学美術史)を卒業し、米国ハーバード大学で博士号取得。シカゴ美術館東洋部長などを歴任、現在、全国美術館会議会長も務めている。
その華麗な経歴に似合わず、話し振りは「人懐っこいオヤジさん」という感じ。アイデアがポンポンと飛び出す。開館当時語った目標の入場者は「1日千人」。この数字をいかに日々達成していくか。たとえば、館内にはこの建物に工事にかかわった2万人の名前を金属板に刻んで掲げてある。「その家族や兄弟、子孫が名前を見に足を運んでくれる。いいアイデアでしょう」とニヤリ。「その積み重ねで賑わいや30億、40億の経済の波及効果が生まれはず」とも。アメリカ仕込みの人の心をつかむアイデアと計算の緻密さが買われ、05年4月には金沢市助役にも抜擢された。
その蓑氏の手腕を、世界的な美術品オークション会社「サザビーズ」も欲していたようだ。退任後、蓑氏は再び米国ニューヨークに渡り、この5月からサザビーズ北米本社の副社長に就任する。「10年以上前からサザビーズに誘われていた。渡米後は世界の超一流の美術品に囲まれて暮らしたい」(20日付の朝日新聞)と語った。雲の大きさを測るような、スケール感のある人なのである。
⇒20日(金)夜・金沢の天気 くもり
 、最後のロール字幕では「車の燃費を良くすれば、無駄なエネルギー消費を防げます」と呼びかけている。このところトヨタがじりじりとアメリカでの自動車シェアを伸ばしているのも、おそらくこの映画のおかげだ。
、最後のロール字幕では「車の燃費を良くすれば、無駄なエネルギー消費を防げます」と呼びかけている。このところトヨタがじりじりとアメリカでの自動車シェアを伸ばしているのも、おそらくこの映画のおかげだ。 土地取引に関して国会で質問した衆院議員(国民新党)が脅迫された事件にからみ、議員を取材した録音データが漏洩し、インターネット上のブログに掲載された問題で、毎日新聞社は3月12日付でデータを外部に漏らした41歳の記者を諭旨解雇とした。記者が取材した録音データが入ったICレコーダーを議員の了解なしに第三者の取材協力者に渡したのである。その取材協力者とは元暴力団組長だったので背景の根深さと波紋を広げた。
土地取引に関して国会で質問した衆院議員(国民新党)が脅迫された事件にからみ、議員を取材した録音データが漏洩し、インターネット上のブログに掲載された問題で、毎日新聞社は3月12日付でデータを外部に漏らした41歳の記者を諭旨解雇とした。記者が取材した録音データが入ったICレコーダーを議員の了解なしに第三者の取材協力者に渡したのである。その取材協力者とは元暴力団組長だったので背景の根深さと波紋を広げた。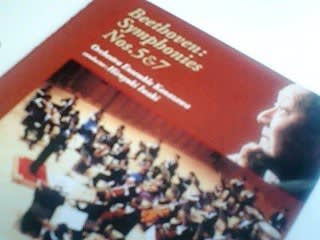 ヒトは都市化する動物であるとすれば地域の過疎化は当然至極、流れに棹をさす地域再生に向けた研究自体は無駄である。しかし、商品経済にほだされて、都会へと流れ生きる現代人の姿がヒトの一時的な迷いであるとすれば、自然と共生しながら生きようとするヒトを地域に招待し応援することは有意義である。私なりにこの命題を自問自答していたとき、これまで聴こうとしなかった7番の第1楽章と第2楽章に耳を傾けたみた。第2楽章の短調の哀愁的な響きにヒトの営みの深淵を感じ、目頭が熱くなるほどの感動を得た。そして、ベートーベンの曲想の壮大なスケールに気づき、7番の主題は「ヒトはどこから来て、どこへ行くのか」のテーマそのものではないのか、と考えるようになった。ここから「つまみ食い」の愚かさを知り、第1楽章から第4楽章までをトータルで聴くようになった。1月上旬のことだった。
ヒトは都市化する動物であるとすれば地域の過疎化は当然至極、流れに棹をさす地域再生に向けた研究自体は無駄である。しかし、商品経済にほだされて、都会へと流れ生きる現代人の姿がヒトの一時的な迷いであるとすれば、自然と共生しながら生きようとするヒトを地域に招待し応援することは有意義である。私なりにこの命題を自問自答していたとき、これまで聴こうとしなかった7番の第1楽章と第2楽章に耳を傾けたみた。第2楽章の短調の哀愁的な響きにヒトの営みの深淵を感じ、目頭が熱くなるほどの感動を得た。そして、ベートーベンの曲想の壮大なスケールに気づき、7番の主題は「ヒトはどこから来て、どこへ行くのか」のテーマそのものではないのか、と考えるようになった。ここから「つまみ食い」の愚かさを知り、第1楽章から第4楽章までをトータルで聴くようになった。1月上旬のことだった。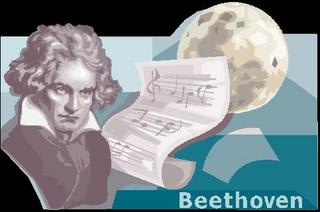 聴いているベト7は2002年9月にオーケストラ・アンサンブル金沢が石川県立音楽堂コンサートホールで録音したものだ。指揮者は岩城宏之さん(故人)。はまり込んだきっかけは、岩城さんがベートーベンのすべての交響曲を一晩で演奏したコンサート(2004年12月31日-05年1月1日・東京文化会館)での言葉を思い出したからだ。演奏会を仕掛けた三枝成彰さんとのトークの中で岩城さんはこんな風に話した。「ベートーベンの1番から9番はすべてホームラン。3番、5番、7番、9番は場外ホームランだね」「5番は運命、9番は合唱付だけど、7番には題名がない。でも、7番にはリズム感と同時に深さを感じる。一番好きなのは7番」と。
聴いているベト7は2002年9月にオーケストラ・アンサンブル金沢が石川県立音楽堂コンサートホールで録音したものだ。指揮者は岩城宏之さん(故人)。はまり込んだきっかけは、岩城さんがベートーベンのすべての交響曲を一晩で演奏したコンサート(2004年12月31日-05年1月1日・東京文化会館)での言葉を思い出したからだ。演奏会を仕掛けた三枝成彰さんとのトークの中で岩城さんはこんな風に話した。「ベートーベンの1番から9番はすべてホームラン。3番、5番、7番、9番は場外ホームランだね」「5番は運命、9番は合唱付だけど、7番には題名がない。でも、7番にはリズム感と同時に深さを感じる。一番好きなのは7番」と。 から量刑を軽く」と弁護士は公判の中でまくしたて、あえて争点にする。
から量刑を軽く」と弁護士は公判の中でまくしたて、あえて争点にする。
 ミツバチの集団失踪が相次いでいる。アメリカでのこと。全米養蜂協会によると、元気だったハチが翌朝に巣箱に戻らないまま数匹を残して消える現象は、昨年の10月あたりから報告され始め、フロリダ州など24州で確認された。しかし、ハチの失踪数に見合うだけの死骸は行動圏で確認されないケースが多く、失踪したのか死んだのかも完全には特定できないという。そんな中、原因の一つとされているのが、養蜂業者の減少で、みつの採集などの作業で過度のノルマを課せられたことによる“過労死説”だ。国家養蜂局(NHB)が緊急調査に乗り出した。ハチを介した受粉に依存するアーモンドやブルーベリーといった140億ドル(約1兆6000億円)規模の農作物への深刻な影響が懸念され始めた。(3月1日・産経新聞インターネット版より)
ミツバチの集団失踪が相次いでいる。アメリカでのこと。全米養蜂協会によると、元気だったハチが翌朝に巣箱に戻らないまま数匹を残して消える現象は、昨年の10月あたりから報告され始め、フロリダ州など24州で確認された。しかし、ハチの失踪数に見合うだけの死骸は行動圏で確認されないケースが多く、失踪したのか死んだのかも完全には特定できないという。そんな中、原因の一つとされているのが、養蜂業者の減少で、みつの採集などの作業で過度のノルマを課せられたことによる“過労死説”だ。国家養蜂局(NHB)が緊急調査に乗り出した。ハチを介した受粉に依存するアーモンドやブルーベリーといった140億ドル(約1兆6000億円)規模の農作物への深刻な影響が懸念され始めた。(3月1日・産経新聞インターネット版より)  記事を引用する。関テレの社長は、自らの責任問題を尋ねた記者の質問には直接答えず、「責任は重く受け止めている。再発防止、原因究明に努め信頼回復を図る」と話し、さらに「制作会社との契約では賠償責任があり、検討する」と語った。これが「賠償請求の可能性」として報道された。
記事を引用する。関テレの社長は、自らの責任問題を尋ねた記者の質問には直接答えず、「責任は重く受け止めている。再発防止、原因究明に努め信頼回復を図る」と話し、さらに「制作会社との契約では賠償責任があり、検討する」と語った。これが「賠償請求の可能性」として報道された。 「テレビ難民」問題化に国の先手
「テレビ難民」問題化に国の先手