★「不都合な真実」という授業
トヨタの株が2月末に3000円の大台に乗り、いまは調整局面に入っているものの、再び上昇するだろう。何しろ、アル・ゴア氏が主演するドキュメンタリー映画「不都合な真実」=写真は映画パンフ=では、トヨタが排気ガス規制車のトップをいっていると図表で説明し 、最後のロール字幕では「車の燃費を良くすれば、無駄なエネルギー消費を防げます」と呼びかけている。このところトヨタがじりじりとアメリカでの自動車シェアを伸ばしているのも、おそらくこの映画のおかげだ。
、最後のロール字幕では「車の燃費を良くすれば、無駄なエネルギー消費を防げます」と呼びかけている。このところトヨタがじりじりとアメリカでの自動車シェアを伸ばしているのも、おそらくこの映画のおかげだ。
ゴア氏ほど有能なコピーライターはいないだろう。映画の冒頭で自らを紹介するのに「一日だけ大統領になったゴアです」と。2000年に大統領に立候補。全国一般投票では共和党候補、ブッシュ氏より得票数で上回ったが、フロリダ州での開票手続きについての問題の後、落選が決定した。そのアメリカの選挙史上の前代未聞の出来事をこのワンフレーズで言い切るのである。
クリントン政権の副大統領を1993年から2001年まで務めた間、ゴア氏が企画した「情報スーパーハイウェイ構想」が呼び水となって、インターネットが爆発的に普及した。当時、日本のどのローカルにあっても、「○○情報スーパーハイウェイ構想」があった。その元祖である。 さらに、クリントン政権末期にナノテクノロジー研究に対して資金投下をした。これが、ナノテクノロジーという研究分野が世界的に注目されるきっかけになった。この意味で、彼は世界で有数の「トレンドメーカー」とも言えるかもしれない。そして、次なるトレンドが「不都合な真実」となる。
そのゴア氏が世界を飛び回って、「地球は人類にとって、ただ一つの故郷。その地球がいま、最大の危機に瀕している。キリマンジャロの雪は溶け、北極の氷は薄くなり、各地にハリケーンや台風などの災害がもたらさえる」と訴えている。地球温暖化の環境問題を切り口にしたスライド講演。そのままを映画化した。だからドキュメンタリー映画であり、教育映画であり、科学映画といった、従来の映画の域を超えて、映画メディアを使った「ゴアの授業」と言える。
この映画の凄みは、環境の危機を訴えているだけではなく、政治家らしい透徹した眼で「戦争の危機」をも訴えている。オイルの争奪戦ではない。水飢饉による、「水戦争」である。「ヒマラヤの氷が解ければアジアの水不足は深刻になる」とゴア氏は淡々と説明する。以下は映画では言及されていないが、上流の中国と、下流のインドで起こりうる「貯水ダムをめぐる戦争」といった事態を予感をさせるのに十分なのである。そして、中国でスライド講演をした折に、中国の大学生に「(思想ではなく)科学で論じよう」と訴えるシーンがある。この言葉の意味は中国においては実に政治的である。
この映画のまとめは、「地球温暖化に対する議論の時代は終わった。唯一残された議論は、どれだけ早く行動に移るかということ」。 そして誰に対して不都合かというと、石油メジャーや米国の自動車産業界をかばって、京都議定書(Kyoto Protocol)の批准を拒否している共和党の現政権ということになる。(3月15日、「金沢フォーラス」イオンシネマで鑑賞)
⇒17日(土)午前・金沢の天気 くもり
 土地取引に関して国会で質問した衆院議員(国民新党)が脅迫された事件にからみ、議員を取材した録音データが漏洩し、インターネット上のブログに掲載された問題で、毎日新聞社は3月12日付でデータを外部に漏らした41歳の記者を諭旨解雇とした。記者が取材した録音データが入ったICレコーダーを議員の了解なしに第三者の取材協力者に渡したのである。その取材協力者とは元暴力団組長だったので背景の根深さと波紋を広げた。
土地取引に関して国会で質問した衆院議員(国民新党)が脅迫された事件にからみ、議員を取材した録音データが漏洩し、インターネット上のブログに掲載された問題で、毎日新聞社は3月12日付でデータを外部に漏らした41歳の記者を諭旨解雇とした。記者が取材した録音データが入ったICレコーダーを議員の了解なしに第三者の取材協力者に渡したのである。その取材協力者とは元暴力団組長だったので背景の根深さと波紋を広げた。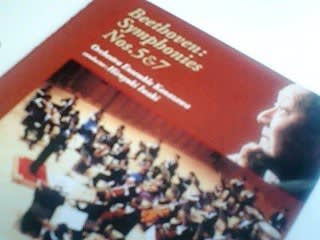 ヒトは都市化する動物であるとすれば地域の過疎化は当然至極、流れに棹をさす地域再生に向けた研究自体は無駄である。しかし、商品経済にほだされて、都会へと流れ生きる現代人の姿がヒトの一時的な迷いであるとすれば、自然と共生しながら生きようとするヒトを地域に招待し応援することは有意義である。私なりにこの命題を自問自答していたとき、これまで聴こうとしなかった7番の第1楽章と第2楽章に耳を傾けたみた。第2楽章の短調の哀愁的な響きにヒトの営みの深淵を感じ、目頭が熱くなるほどの感動を得た。そして、ベートーベンの曲想の壮大なスケールに気づき、7番の主題は「ヒトはどこから来て、どこへ行くのか」のテーマそのものではないのか、と考えるようになった。ここから「つまみ食い」の愚かさを知り、第1楽章から第4楽章までをトータルで聴くようになった。1月上旬のことだった。
ヒトは都市化する動物であるとすれば地域の過疎化は当然至極、流れに棹をさす地域再生に向けた研究自体は無駄である。しかし、商品経済にほだされて、都会へと流れ生きる現代人の姿がヒトの一時的な迷いであるとすれば、自然と共生しながら生きようとするヒトを地域に招待し応援することは有意義である。私なりにこの命題を自問自答していたとき、これまで聴こうとしなかった7番の第1楽章と第2楽章に耳を傾けたみた。第2楽章の短調の哀愁的な響きにヒトの営みの深淵を感じ、目頭が熱くなるほどの感動を得た。そして、ベートーベンの曲想の壮大なスケールに気づき、7番の主題は「ヒトはどこから来て、どこへ行くのか」のテーマそのものではないのか、と考えるようになった。ここから「つまみ食い」の愚かさを知り、第1楽章から第4楽章までをトータルで聴くようになった。1月上旬のことだった。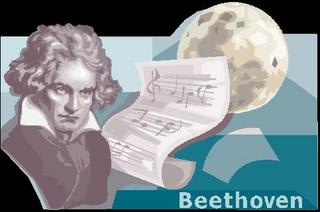 聴いているベト7は2002年9月にオーケストラ・アンサンブル金沢が石川県立音楽堂コンサートホールで録音したものだ。指揮者は岩城宏之さん(故人)。はまり込んだきっかけは、岩城さんがベートーベンのすべての交響曲を一晩で演奏したコンサート(2004年12月31日-05年1月1日・東京文化会館)での言葉を思い出したからだ。演奏会を仕掛けた三枝成彰さんとのトークの中で岩城さんはこんな風に話した。「ベートーベンの1番から9番はすべてホームラン。3番、5番、7番、9番は場外ホームランだね」「5番は運命、9番は合唱付だけど、7番には題名がない。でも、7番にはリズム感と同時に深さを感じる。一番好きなのは7番」と。
聴いているベト7は2002年9月にオーケストラ・アンサンブル金沢が石川県立音楽堂コンサートホールで録音したものだ。指揮者は岩城宏之さん(故人)。はまり込んだきっかけは、岩城さんがベートーベンのすべての交響曲を一晩で演奏したコンサート(2004年12月31日-05年1月1日・東京文化会館)での言葉を思い出したからだ。演奏会を仕掛けた三枝成彰さんとのトークの中で岩城さんはこんな風に話した。「ベートーベンの1番から9番はすべてホームラン。3番、5番、7番、9番は場外ホームランだね」「5番は運命、9番は合唱付だけど、7番には題名がない。でも、7番にはリズム感と同時に深さを感じる。一番好きなのは7番」と。 から量刑を軽く」と弁護士は公判の中でまくしたて、あえて争点にする。
から量刑を軽く」と弁護士は公判の中でまくしたて、あえて争点にする。
 ミツバチの集団失踪が相次いでいる。アメリカでのこと。全米養蜂協会によると、元気だったハチが翌朝に巣箱に戻らないまま数匹を残して消える現象は、昨年の10月あたりから報告され始め、フロリダ州など24州で確認された。しかし、ハチの失踪数に見合うだけの死骸は行動圏で確認されないケースが多く、失踪したのか死んだのかも完全には特定できないという。そんな中、原因の一つとされているのが、養蜂業者の減少で、みつの採集などの作業で過度のノルマを課せられたことによる“過労死説”だ。国家養蜂局(NHB)が緊急調査に乗り出した。ハチを介した受粉に依存するアーモンドやブルーベリーといった140億ドル(約1兆6000億円)規模の農作物への深刻な影響が懸念され始めた。(3月1日・産経新聞インターネット版より)
ミツバチの集団失踪が相次いでいる。アメリカでのこと。全米養蜂協会によると、元気だったハチが翌朝に巣箱に戻らないまま数匹を残して消える現象は、昨年の10月あたりから報告され始め、フロリダ州など24州で確認された。しかし、ハチの失踪数に見合うだけの死骸は行動圏で確認されないケースが多く、失踪したのか死んだのかも完全には特定できないという。そんな中、原因の一つとされているのが、養蜂業者の減少で、みつの採集などの作業で過度のノルマを課せられたことによる“過労死説”だ。国家養蜂局(NHB)が緊急調査に乗り出した。ハチを介した受粉に依存するアーモンドやブルーベリーといった140億ドル(約1兆6000億円)規模の農作物への深刻な影響が懸念され始めた。(3月1日・産経新聞インターネット版より)  記事を引用する。関テレの社長は、自らの責任問題を尋ねた記者の質問には直接答えず、「責任は重く受け止めている。再発防止、原因究明に努め信頼回復を図る」と話し、さらに「制作会社との契約では賠償責任があり、検討する」と語った。これが「賠償請求の可能性」として報道された。
記事を引用する。関テレの社長は、自らの責任問題を尋ねた記者の質問には直接答えず、「責任は重く受け止めている。再発防止、原因究明に努め信頼回復を図る」と話し、さらに「制作会社との契約では賠償責任があり、検討する」と語った。これが「賠償請求の可能性」として報道された。 「テレビ難民」問題化に国の先手
「テレビ難民」問題化に国の先手 関西テレビの番組「発掘!あるある大事典Ⅱ」で捏造問題が発覚して以来、テレビ業界全体の信頼度が落ちたように思える。そしてついにというか、きょう13日の閣議後の記者会見で、菅義偉総務相は「捏造再発防止法案」なるものを国会に提出すると述べたそうだ。その理由は「公の電波で事実と違うことが報道されるのは極めて深刻。再発防止策につながる、報道の自由を侵さない形で何らかのもの(法律)ができればいい」と。放送法第三条と第四条は、放送上の間違いがあった場合は総務省に報告し、自ら訂正放送をするとした内容の適正化の手順をテレビ局に義務付けている。さらにこれ以上の防止策となると、罰則規定の強化しかないのではないか。個別の不祥事イコール業界全体の規制の構図は繰り返されてきた負のスパイラルではある。
関西テレビの番組「発掘!あるある大事典Ⅱ」で捏造問題が発覚して以来、テレビ業界全体の信頼度が落ちたように思える。そしてついにというか、きょう13日の閣議後の記者会見で、菅義偉総務相は「捏造再発防止法案」なるものを国会に提出すると述べたそうだ。その理由は「公の電波で事実と違うことが報道されるのは極めて深刻。再発防止策につながる、報道の自由を侵さない形で何らかのもの(法律)ができればいい」と。放送法第三条と第四条は、放送上の間違いがあった場合は総務省に報告し、自ら訂正放送をするとした内容の適正化の手順をテレビ局に義務付けている。さらにこれ以上の防止策となると、罰則規定の強化しかないのではないか。個別の不祥事イコール業界全体の規制の構図は繰り返されてきた負のスパイラルではある。