★メモる2007年-2-
能登半島地震(今年3月25日発生)では死者1人、300人以上の重軽傷者を出した。この震災で一番被害を受けたのは、メディアとの接触機会が少なく「情報弱者」とされる高齢者が多い過疎地域だった。被災者はどのようにして情報を入手し、その情報は的確に伝わったのだろうか。そんな思いから金沢大学震災学術調査班に加わり、「震災とメディア」をテーマに被災者アンケートやメディアへのヒアリング調査などを実施した。
震災では誰もが「情報弱者」に
 アンケートの調査は、震度6強に見舞われ、住民のうち65歳以上が47%を占める石川県輪島市門前町で行った。当初は地震発生の翌日に被災地に入り、地域連携コーディネーターとして、学生のボランティア支援をどのようなかたちで進めたらよいか調査するのが当初の目的で被災地に入った。そこで見た光景が「震災とメディア」の調査研究をしてみようと思い立った動機となる。震災当日からテレビ系列が大挙して同町に陣取っていた。現場中継のため、倒壊家屋に横付けされた民放テレビ局のSNG(Satellite News Gathering)車をいぶかしげに見ている被災者たちの姿があった。この惨事は全国中継されるが、地域の人たちは視聴できないのではないか。また、半壊の家屋の前で茫然(ぼうぜん)と立ちつくすお年寄り、そしてその半壊の家屋が壊れるシーンを撮影しようと、ひたすら余震を待って身構えるカメラマンのグループがそこにあった。こうしたメディアの行動は、果たして被災者に理解されているのだろうか。それより何より、メディアはこの震災で何か役立っているのだろうか、という素朴な疑問だった。
アンケートの調査は、震度6強に見舞われ、住民のうち65歳以上が47%を占める石川県輪島市門前町で行った。当初は地震発生の翌日に被災地に入り、地域連携コーディネーターとして、学生のボランティア支援をどのようなかたちで進めたらよいか調査するのが当初の目的で被災地に入った。そこで見た光景が「震災とメディア」の調査研究をしてみようと思い立った動機となる。震災当日からテレビ系列が大挙して同町に陣取っていた。現場中継のため、倒壊家屋に横付けされた民放テレビ局のSNG(Satellite News Gathering)車をいぶかしげに見ている被災者たちの姿があった。この惨事は全国中継されるが、地域の人たちは視聴できないのではないか。また、半壊の家屋の前で茫然(ぼうぜん)と立ちつくすお年寄り、そしてその半壊の家屋が壊れるシーンを撮影しようと、ひたすら余震を待って身構えるカメラマンのグループがそこにあった。こうしたメディアの行動は、果たして被災者に理解されているのだろうか。それより何より、メディアはこの震災で何か役立っているのだろうか、という素朴な疑問だった。
被災者へのアンケート内容は、①地震発生時の状況や初期行動、②最も欲しいと思った情報や情報の入手手段、③発生1ヵ月後よく利用する情報源や求める情報内容などで、学生に手伝ってもらい聞き取り調査を行った。
震災は日曜日の午前9時42分に起きた。能登地方は曇り空だった。震災発生時の居場所は、居間など自宅にいたのは60人で、うち24人がテレビを見ていた。回答者110人の自宅は「全壊」18人、「半壊」19人、「一部損壊」60人で、「被害なし」は10人にすぎなかった。地震直後の初期行動として、屋内にいた36人が「屋外へ避難」した。「テレビをつけた」は4人、「ラジオをつけた」は6人である。つまり、震度6強の激しい揺れの直後、真っ先にメディアに接触を試みた人は1割に満たなかったわけである。
事実、震災の翌日26日に被災地入りし、何軒かの家の中を見せてもらったところ、一見被害がないように見える家屋でも、中では仏壇やテレビが吹っ飛んでいた。震災直後、さらに続いた余震(26日正午までに190回)の恐怖、そして一瞬の破壊で茫然自失としていた被災者が最初に接した情報源は何だったのか。ヒアリングでも多くの人が指摘したのは「有線放送」だった。同町にケーブルテレビ(CATV)網はなく(注=2006年度整備予定)、同町で有線放送と言えば、スピーカーが内蔵された有線放送電話(地域内の固定電話兼放送設備)のこと。この有線放送電話にはおよそ2900世帯、町の8割の世帯が加入する。利用料は月額1000円の定額で任意加入だ。普段は朝、昼、晩の定時に1日3回、町の広報やイベントの案内が流れる。防災無線と連動していて、緊急時には消防署が火災の発生などを生放送する。この日も、地震の7分後となる午前9時49分に「ただいま津波注意報が発表されています。海岸沿いの人は高台に避難してください」と放送している。街路では防災無線が、家の中では有線放送電話から津波情報が同時に流れた。ここで茫然自失としていた住民が我に返り、近所誘い合って高台の避難場所へと駆け出したのだ。この有線放送電話では、避難所の案内や巡回診療のお知らせなど被災者に必要なお知らせを26日に7回、27日には21回放送している。昭和47年(1972)に敷設が始まった「ローテク」とも言える有線放送電話が今回の震災ではしっかりと「放送インフラ」として役立ったのである。
震度6強の揺れにもかかわらず、道路が陥没して孤立した一部地区を除き、ほとんどの電話回線は生きていた。なぜか。北陸総合通信局情報通信部の山口浩部長(当時)によると、「本来あのくらいの規模の地震だと火災が発生しても不思議ではない。今回、時間的に朝食がほぼ終わっていたということで火災が発生しなかったために電話線が切れなかった。不幸中の幸いだった」と分析している。この有線放送電話には、一般加入電話や携帯電話のような震災発生時の受発信の規制はなく、安否情報の交換などにフルに利用された。 その後、同町では家屋の損壊あるいは余震から1500人が避難所生活を余儀なくされ、多くの住民は避難所で新聞やテレビやラジオに接触することになる。ここで、注目すべきメディアの活動をいくつか紹介しておきたい。震災の翌日から避難所の入り口には新聞各紙がドッサリと積んであった。新聞社の厚意で届けられたものだが、私が訪れた避難所(公民館)では、避難住民が肩を寄せ合うような状態であり、新聞をゆっくり広げるスペースがあるようには見受けられなかった。そんな中で、聞き取り調査をした住民から「かわら版が役に立った」との声を多く聞いた。 そのかわら版とは、朝日新聞社が避難住民向けに発行した「能登半島地震救援号外」だった。タブロイド判の裏表1枚紙で、文字が大きく行間がゆったりしている。住民が「役に立った」というのは、災害が最も大きかった被災地・輪島のライフライン情報に特化した「ミニコミ紙」だったからだ。
救援号外の編集長だった同社金沢総局次長の大脇和男記者から発行にいたったいきさつなどについて聞いた。救援号外は、2004年10月の新潟県中越地震で初めて発行したが、当時は文字ばかりの紙面で「無機質で読み難い」との意見もあり、今回はカラー写真を入れた。だが、1号(3月26日付)で掲載された、給水車から水を運ぶおばあさんの顔が下向きで暗かった。「これでは被災者のモチベーションが下がると思い、2号からは笑顔にこだわり、『毎号1笑顔』を編集方針に掲げた」という。さらに、長引く避難所生活では、血行不良で血が固まり、肺の血管に詰まるエコノミークラス症候群に罹りやすいので「生活不活発病」の特集を5号(3月30日付)で組んだ。義援金の芳名などは掲載せず、被災地の現場感覚でつくる新聞を心がけ、ごみ処理や入浴、医療診断の案内など生活情報を掲載した。念のため、「本紙県版の焼き直しを掲載しただけではなかったのか」と質問をしたところ、「その日発表された情報の中から号外編集班(専従2人)が生活情報を集めて、その日の夕方に配った。本紙県版の生活情報は号外の返しだった」という。
カラーコピー機を搭載した車両を輪島市内に置き、「現地印刷」をした。ピーク時には2000部を発行し、7人から8人の印刷・配達スタッフが手分けして避難所に配った。夕方の作業だった。地震直後、同市内では5500戸で断水した。救援号外は震災翌日の3月26日から毎日夕方に避難所に届けられ、給水のライフラインが回復した4月7日をもって終わる。13号まで続いた「避難所新聞」だった。
高齢者だけでなく、誰しもが一瞬にして「情報弱者」になるのが震災である。問題はそうした被災者にどう情報をフィードバックしていく仕組みをつくるか、だ。聞き取り調査の中で、同町在住の災害ボランティアコーディネーター、岡本紀雄さん(52)の提案は具体的だった。「テレビメディアは被災地から情報を吸い上げて全国に向けて発信しているが、被災地に向けたフィードバックが少ない。せめて地元の民放などが協力して被災者向けの臨時のFM局ぐらい立ち上げたらどうだろう」「新聞社は協力して避難住民向けのタブロイド判をつくったらどうだろう。決して広くない避難所でタブロイド判は理にかなっている」と。岡本さんは、新潟県中越地震でのボランティア経験が買われ、今回の震災では避難所の「広報担当」としてメディアとかかわってきた一人である。メディア同士はよきライバルであるべきだと思うが、被災地ではよき協力者として共同作業があってもよいと思うが、どうだろう。
もちろん、報道の使命は被災者への情報のフィードバックだけではないことは承知しているし、災害状況を全国の視聴者に向けて放送することで国や行政を動かし、復興を後押しする意味があることも否定しない。 今回のアンケート調査で最後に「メディアに対する問題点や要望」を聞いているが、いくつかの声を紹介しておきたい。「朝から夕方までヘリコプターが飛び、地震の音と重なり、屋根に上っていて恐怖感を感じた」(54歳・男性)、「震災報道をドラマチックに演出するようなことはやめてほしい」(30歳・男性)、「特にひどい被災状況ばかりを報道し、かえってまわりを心配させている」(32歳・女性)。
こうした被災者の声は誇張ではなく、感じたままを吐露したものだ。そして、阪神淡路大震災や新潟県中越地震など震災のたびに繰り返されてきた被災者の意見だろうと想像する。最後に、「被災地に取材に入ったら、帰り際の一日ぐらい休暇を取って、救援ボランティアとして被災者と同じ目線で現場で汗を流したらいい」と若い記者やカメラマンのみなさんに勧めたい。被災者の目線はこれまで見えなかった報道の視点として生かされるはずである。
⇒17日(月)夜・金沢の天気 あめ
 ことし3月25日の能登半島地震で「震災とメディア」の調査をした。その中で、「誰しもが一瞬にして情報弱者になるのが震災であり、電波メディアは被災者に向けてメッセージを送ったのだろうか」「被災地から情報を吸い上げて全国へ発信しているが、被災地に向けたフィードバックがない」と問題提起をした。その後、7月16日に新潟県中越沖地震が起きた。そこには、「情報こそライフライン」と被災者向け情報に徹底し、24時間の生放送を41日間続けた放送メディアがあった。
ことし3月25日の能登半島地震で「震災とメディア」の調査をした。その中で、「誰しもが一瞬にして情報弱者になるのが震災であり、電波メディアは被災者に向けてメッセージを送ったのだろうか」「被災地から情報を吸い上げて全国へ発信しているが、被災地に向けたフィードバックがない」と問題提起をした。その後、7月16日に新潟県中越沖地震が起きた。そこには、「情報こそライフライン」と被災者向け情報に徹底し、24時間の生放送を41日間続けた放送メディアがあった。 さらに同じ輪島でサバのダイナミックな食べ方を教わった。塩サバである。8月下旬、輪島の大祭が恒例だ。祭りが終わり、神輿や奉灯キリコをしまう。その後、直会(なおらい)があり、神饌(しんせん)やお神酒(みき)のお下がり物を参加者が分かち飲食する。このときに、塩漬けされたサバが大皿に乗って出てくる。お神酒を飲みながら、塩で身が硬くなったサバを手でむしって食べる。これがなんとも言えず美味なのだ。残暑の中、塩サバに日本酒を食するので当然、喉が渇く。そこで水の代わりにお下がりのスイカを食べる。冷やしてはないが清涼感があり甘い。するとまた塩サバが食べたくなる。手はサバの脂でベタベタになるが気にせず、むしり取る。そして飲む。またスイカを食べるという繰り返し。
さらに同じ輪島でサバのダイナミックな食べ方を教わった。塩サバである。8月下旬、輪島の大祭が恒例だ。祭りが終わり、神輿や奉灯キリコをしまう。その後、直会(なおらい)があり、神饌(しんせん)やお神酒(みき)のお下がり物を参加者が分かち飲食する。このときに、塩漬けされたサバが大皿に乗って出てくる。お神酒を飲みながら、塩で身が硬くなったサバを手でむしって食べる。これがなんとも言えず美味なのだ。残暑の中、塩サバに日本酒を食するので当然、喉が渇く。そこで水の代わりにお下がりのスイカを食べる。冷やしてはないが清涼感があり甘い。するとまた塩サバが食べたくなる。手はサバの脂でベタベタになるが気にせず、むしり取る。そして飲む。またスイカを食べるという繰り返し。 かつて別荘地が造成された。真っ先にその別荘地を買ったのは富山の人たちだったと聞いたことがある。「立山を見て余生を暮らせたら」。そんな思いが募ったのかもしれない。
かつて別荘地が造成された。真っ先にその別荘地を買ったのは富山の人たちだったと聞いたことがある。「立山を見て余生を暮らせたら」。そんな思いが募ったのかもしれない。 壁画「聖十字架物語」の修復現場=写真・上=は足場に覆われていた。鉄パイプで組まれた足場は高さ26㍍、ざっと9階建てのビル並みの高さである。天井から吊られた十字架像、窓にはめられたステンドグラスなどの貴重な美術品や文化財はそのままにして足場の建設が進んだのだから、慎重さを極めた作業だったことは想像に難くない。平面状に組んだ足場ではなく、立方体に組んであり、打ち合わせ用のオフィス空間や照明設備や電気配線、上下水道もある。下水施設は洗浄のため薬品を含んだ水を貯水場に保存するためだ。それに人と機材を運搬するエレベーターもある。
壁画「聖十字架物語」の修復現場=写真・上=は足場に覆われていた。鉄パイプで組まれた足場は高さ26㍍、ざっと9階建てのビル並みの高さである。天井から吊られた十字架像、窓にはめられたステンドグラスなどの貴重な美術品や文化財はそのままにして足場の建設が進んだのだから、慎重さを極めた作業だったことは想像に難くない。平面状に組んだ足場ではなく、立方体に組んであり、打ち合わせ用のオフィス空間や照明設備や電気配線、上下水道もある。下水施設は洗浄のため薬品を含んだ水を貯水場に保存するためだ。それに人と機材を運搬するエレベーターもある。 足場の最上階に上がると大礼拝堂の天井に手が届くほどの距離に達する。「壁画に触れないように気をつけて」とダンティさんは念を押す。宮下教授は「足場が出来る前までは下から双眼鏡で眺めていたのですが、足場に上がって直に見ると予想以上に傷みが激しく愕(がく)然としましたよ」と話す。ステンドグラス窓の一部が壊れ、そこから侵入した雨水とハトの糞で傷んだところや、亀裂やひび割れが目立つ=写真・下=。また、専門家の目では、70年ほど前の修復で廉価な顔料が施され変色が進んだところや、水分や湿気が地下の塩分を吸い上げ壁画面に吹き出した部分もある。
足場の最上階に上がると大礼拝堂の天井に手が届くほどの距離に達する。「壁画に触れないように気をつけて」とダンティさんは念を押す。宮下教授は「足場が出来る前までは下から双眼鏡で眺めていたのですが、足場に上がって直に見ると予想以上に傷みが激しく愕(がく)然としましたよ」と話す。ステンドグラス窓の一部が壊れ、そこから侵入した雨水とハトの糞で傷んだところや、亀裂やひび割れが目立つ=写真・下=。また、専門家の目では、70年ほど前の修復で廉価な顔料が施され変色が進んだところや、水分や湿気が地下の塩分を吸い上げ壁画面に吹き出した部分もある。 墓がある。そのサンタ・クローチェ教会の大礼拝堂の壁画の一部が金沢大学教育学部棟で復元された=写真=。
墓がある。そのサンタ・クローチェ教会の大礼拝堂の壁画の一部が金沢大学教育学部棟で復元された=写真=。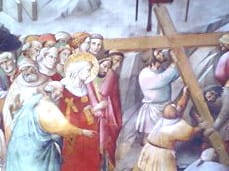 た壁画を1日一部分ずつ描き、今月23日までにほぼ描き終えた。顔料など多くの材料はイタリアで調達した。
た壁画を1日一部分ずつ描き、今月23日までにほぼ描き終えた。顔料など多くの材料はイタリアで調達した。 けさ(19日)の屋外の光景を見て、金沢の人、あるいは北陸人の季節感は一気に「冬モード」にスイッチが切り替わったのではないだろうか。薄っすらと雪化粧、初雪である。11月半ば、こんなに早く冬の訪れを感じたのは何年ぶりだろう。
けさ(19日)の屋外の光景を見て、金沢の人、あるいは北陸人の季節感は一気に「冬モード」にスイッチが切り替わったのではないだろうか。薄っすらと雪化粧、初雪である。11月半ば、こんなに早く冬の訪れを感じたのは何年ぶりだろう。
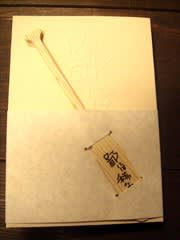 国内外の広告業界の動きや広告活動を紹介する週刊の専門紙「電通報」に平成18年4月から1年間連載された文をまとめたもの。主に月尾氏が全国18ヵ所で主宰する月尾塾での講演旅行などで出会った地域の愉快な人々が稀人(まれびと)として紹介されている。ちなみに、「加賀の稀人」は白波の立つ日本海をクルーザーで出航する豪快な上場企業の会長の話。この会長は創業者だけあって、物怖じしないのだが、暗雲の方向へ向かっていくので、さすがに地元の案内役が止め入った。「途中で日本海で行方不明」となっていたかもしれないと。そんな豪快さの持ち主は今日では稀人なのだろう。
国内外の広告業界の動きや広告活動を紹介する週刊の専門紙「電通報」に平成18年4月から1年間連載された文をまとめたもの。主に月尾氏が全国18ヵ所で主宰する月尾塾での講演旅行などで出会った地域の愉快な人々が稀人(まれびと)として紹介されている。ちなみに、「加賀の稀人」は白波の立つ日本海をクルーザーで出航する豪快な上場企業の会長の話。この会長は創業者だけあって、物怖じしないのだが、暗雲の方向へ向かっていくので、さすがに地元の案内役が止め入った。「途中で日本海で行方不明」となっていたかもしれないと。そんな豪快さの持ち主は今日では稀人なのだろう。
 昔からカニを食べると寡黙になる、というのが常識だが、この日は様子が違った。同席したのは宮崎、福岡、大阪、奈良、東京、仙台と出身はバラバラ。すると、食べ方が慣れないせいか、「カニは好きだが食べにくい」「身をほじり出すのがチマチマしている」などという話になる。出されたカニには包丁が入っていて、すでに食べやすくしてある。これを「食べにくい」といってはバチが当たるというものだ。つまり、カニの初心者なのだ。
昔からカニを食べると寡黙になる、というのが常識だが、この日は様子が違った。同席したのは宮崎、福岡、大阪、奈良、東京、仙台と出身はバラバラ。すると、食べ方が慣れないせいか、「カニは好きだが食べにくい」「身をほじり出すのがチマチマしている」などという話になる。出されたカニには包丁が入っていて、すでに食べやすくしてある。これを「食べにくい」といってはバチが当たるというものだ。つまり、カニの初心者なのだ。 確かにキャリーバッグはよく入る。改めてどんなモノが入っているのかチェックしてみた。1泊の出張の場合である。一日分の着替え、パソコンのACアダプター、シェーバー、くし、財布、手帳、単四電池3本、プリベイト式の乗り物カード(北陸鉄道アイカ、スイカ、地下鉄用プリベイトカード)と大学職員証)、名刺入れ、ボ-ルペン2本、マーカー(ピンク)、メモリースティック、通信用のFOMAカード、書類、ICレコーダー、デジタルカメラ、携帯電話それにモバイルPCである。重さにしてざっと10数㌔だろうか。これに、会議資料が何十セットが加わると、さらに重くなる。でも、全部一つのバッグに収納できるから不思議だ。
確かにキャリーバッグはよく入る。改めてどんなモノが入っているのかチェックしてみた。1泊の出張の場合である。一日分の着替え、パソコンのACアダプター、シェーバー、くし、財布、手帳、単四電池3本、プリベイト式の乗り物カード(北陸鉄道アイカ、スイカ、地下鉄用プリベイトカード)と大学職員証)、名刺入れ、ボ-ルペン2本、マーカー(ピンク)、メモリースティック、通信用のFOMAカード、書類、ICレコーダー、デジタルカメラ、携帯電話それにモバイルPCである。重さにしてざっと10数㌔だろうか。これに、会議資料が何十セットが加わると、さらに重くなる。でも、全部一つのバッグに収納できるから不思議だ。