★ベートーベン「熱狂の日」
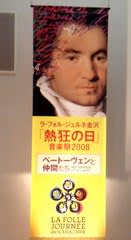 どこが「クラシックの民主化」なのかというと、①短時間で聴くクラシック②低料金で聴くクラシック③子どもも参加するクラシック・・・の3点に特徴があるそうだ。民主化というより、クラシックの裾野を広げるための音楽祭ともいえる。1995年にフランスのナント市で始まった音楽祭。この音楽祭の開催は世界で6番目、日本では東京に次いで2番目とか。
どこが「クラシックの民主化」なのかというと、①短時間で聴くクラシック②低料金で聴くクラシック③子どもも参加するクラシック・・・の3点に特徴があるそうだ。民主化というより、クラシックの裾野を広げるための音楽祭ともいえる。1995年にフランスのナント市で始まった音楽祭。この音楽祭の開催は世界で6番目、日本では東京に次いで2番目とか。
今回のテーマはベートーベン。おやっと思ったのはポスターや看板=写真=に描かれているベートーベンの肖像画だ。広告物のデザインはフランスの音楽プロデューサー、ルネ・マルタン氏の手による。日本人がベートーベンで思い出す肖像は、いかにも神経質でいかめしそうな顔つき。しかし、「民主化」をめざす音楽祭では、参加者の心を解きほぐさなければならない。柔和な顔つきのベートーベンが広告物に描かれた訳はこんなところか。
1日夜、県立音楽堂で開かれた公開マスタークラス&レクチャーコンサートに出かけた。「『月光』の日」と銘打った催し。ピアニストのクレール・デゼールさん(パリ国立高等音楽院教授)が若手のピアニストやピアニストの卵に「月光」をレッスンするというもの。受講者の平野加奈さん(東京芸大2年生)が曲を一通り弾く。その後の通訳つきのレクチャーが面白い。「あなたの1楽章はショパンっぽい感じがした。左と右の手がどちらか遅いとロマンチックになる。でも、ベートーベンは左と右が同時なのよ。するともっと深くなる。ベートーベンらしくなるのよ」「ここはアジダートなの。そうね、怯えるって感じかしら。台風が突然やってきて、心臓がバクバクする。そんな不気味な感じね」
クレールさんの公開ピアノレッスンを聞きながら、指揮者の岩城宏之さん(06年6月逝去)が生前語った言葉を思い出した。岩城さんはベートーベンのシンフォニー1番から9番を一夜で連続演奏するという「離れ業」を2年連続(04年と05年の大晦日)やってのけた。私はこの2回の番組制作に関わり、東京で「振るマラソン」を聴くことができた。思い出したのは、その時、ステージで語った岩城さんの言葉だ。コンサートのプロデューサーである三枝成彰さんから、岩城さんに「ところで岩城さんが好きなシンフォニーは何番なの」と水が向けられた。すると、岩城さんは「最近は8番かな。5番や7番、9番のように前衛的ではないけれど、コントラストが鮮やか。作曲技法が駆使されていて、4楽章なんかフレーズの入り組みがとても精緻。円熟しきった作曲家ベートーベンの会心の出来が8番なんだね」と。このとき、プロ中のプロのお気に入りは8番なのだ、と印象づけられたものだ。
ピアニストのクレールさん、指揮者の岩城さんの2人の言葉から伝わってきたものは、演奏する側を介した等身大のベートーベンの姿ではないだろうか。凄みをきかせたベートーベンがほらそこにいるよ見てごらん、という臨場感だ。
⇒2日(金)夜・金沢の天気 はれ
 朝の日課なので、青空に映えるこいのぼりを見るとすがすがしい。通りがかりの学生たちが「こいのぼりをこんなに間近に見るのは初めて」とか「大学でこいのぼりを揚げているのは金大だけとちがうか…」などと言いながら見上げている。聖火リレーをめぐる騒ぎに比べれば、実にのどかな光景ではある。
朝の日課なので、青空に映えるこいのぼりを見るとすがすがしい。通りがかりの学生たちが「こいのぼりをこんなに間近に見るのは初めて」とか「大学でこいのぼりを揚げているのは金大だけとちがうか…」などと言いながら見上げている。聖火リレーをめぐる騒ぎに比べれば、実にのどかな光景ではある。 その法隆寺で、日本工芸のルーツといわれるのが「国宝 玉虫厨子(たまむしのずし)」。日本史では飛鳥美術の代表作とされる。が、現在のわれわれが目にするは黒光り、古色蒼然とした造作物という印象しかない。すでに描かれていたであろう仏教画や装飾などは、イメージをほうふつさせるほどに残されてはいない。歴史の時空の中で剥離し劣化した。
その法隆寺で、日本工芸のルーツといわれるのが「国宝 玉虫厨子(たまむしのずし)」。日本史では飛鳥美術の代表作とされる。が、現在のわれわれが目にするは黒光り、古色蒼然とした造作物という印象しかない。すでに描かれていたであろう仏教画や装飾などは、イメージをほうふつさせるほどに残されてはいない。歴史の時空の中で剥離し劣化した。 奥能登・珠洲市に古民家レストランと銘打っている店がある。確かに築110年という古民家には土蔵があり、その座敷で土地の郷土料理を味わう。過日訪れると、中庭で野点が催されていて、ご相伴にあずかった。
奥能登・珠洲市に古民家レストランと銘打っている店がある。確かに築110年という古民家には土蔵があり、その座敷で土地の郷土料理を味わう。過日訪れると、中庭で野点が催されていて、ご相伴にあずかった。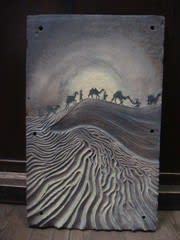 節を重んじ、相和すことを重んじる。そんな凛(りん)とした雰囲気が感じられる野点だった。
節を重んじ、相和すことを重んじる。そんな凛(りん)とした雰囲気が感じられる野点だった。
 ミシュランガイド東京に掲載されているレストランは150軒で、最も卓越した料理と評価される「三つ星」は8軒。「二つ星」は25軒、「一つ星」は117軒選ばれている。フランスやイタリア料理が多いのかと思いきや、ガイド全体では日本料理が6割を占めている。和食への評価が世界的に高まっていることがベースにあるのだろう。ちなみに、一つ星は「カテゴリーで特に美味しい料理」、二つ星は「遠回りしてでも訪れる価値がある素晴らしい料理」、三つ星は「そのために旅行する価値がある卓越した料理」の価値基準らしい。
ミシュランガイド東京に掲載されているレストランは150軒で、最も卓越した料理と評価される「三つ星」は8軒。「二つ星」は25軒、「一つ星」は117軒選ばれている。フランスやイタリア料理が多いのかと思いきや、ガイド全体では日本料理が6割を占めている。和食への評価が世界的に高まっていることがベースにあるのだろう。ちなみに、一つ星は「カテゴリーで特に美味しい料理」、二つ星は「遠回りしてでも訪れる価値がある素晴らしい料理」、三つ星は「そのために旅行する価値がある卓越した料理」の価値基準らしい。 なく、静かで落ち着いていて、客層は老紳士・淑女然としたお年寄りが多いのだ。
なく、静かで落ち着いていて、客層は老紳士・淑女然としたお年寄りが多いのだ。 変えられてしまった人々も多い。そんな被災者の生の声をつづった「住民の生活ニーズと復興への課題」というリポートがある。金沢大学能登半島地震学術調査部会の第2回報告会(3月8日)で提出されたものだ。その中からいくつか拾ってみる。
変えられてしまった人々も多い。そんな被災者の生の声をつづった「住民の生活ニーズと復興への課題」というリポートがある。金沢大学能登半島地震学術調査部会の第2回報告会(3月8日)で提出されたものだ。その中からいくつか拾ってみる。 ろう。その玉虫厨子を現代に蘇らせるプロジェクトが完成し、その制作過程を追ったドキュメンタリー映画が輪島市と金沢市で上映されることになった(3月16日付・北陸中日新聞)。
ろう。その玉虫厨子を現代に蘇らせるプロジェクトが完成し、その制作過程を追ったドキュメンタリー映画が輪島市と金沢市で上映されることになった(3月16日付・北陸中日新聞)。  15日の新聞各紙にこんな事件が報じられた。石川社会保険事務局は14日、野々市町の男性が約43万円の還付金詐欺の被害にあったと発表した。同事務局によると、12日午後1時半ごろ、男性方に「タナカ」と名乗る男から「過去5年間の医療費の返還金があり、昨年10月に案内のはがきを送った」と電話があった。男性がはがきを見ていないと答えると「返還金の期日が過ぎているのでATM(現金自動出入機)から振り込む」と言われたため、近くのATMに行った。そこで男から操作を指示され、口座から43万3097円を振り込んだという。手の込んだ、計算し尽された詐欺である。
15日の新聞各紙にこんな事件が報じられた。石川社会保険事務局は14日、野々市町の男性が約43万円の還付金詐欺の被害にあったと発表した。同事務局によると、12日午後1時半ごろ、男性方に「タナカ」と名乗る男から「過去5年間の医療費の返還金があり、昨年10月に案内のはがきを送った」と電話があった。男性がはがきを見ていないと答えると「返還金の期日が過ぎているのでATM(現金自動出入機)から振り込む」と言われたため、近くのATMに行った。そこで男から操作を指示され、口座から43万3097円を振り込んだという。手の込んだ、計算し尽された詐欺である。