☆文明論としての里山22
「トキ 穴水にきました!」。知り合いの女性からメールが入ったのは16日15時41分だった。電話をすると、「つがい(ペア)で来ていて、地元のケーブルテレビが撮影に成功したらしい」と興奮気味だった。ビッグニュースは地元でまたたく間に広がり、話題が沸騰していたのだろう。ペアで来たというのは事実に反していたが、地元の人がこれだけ興奮するには訳がある。石川県穴水(あなみず)町は本州最後のトキが捕獲された地なのである。
トキが教えてくれる「里の道」
 1970年1月、能登半島では「能里(のり)」の愛称で呼ばれていたオスが繁殖のため、この地で捕獲された。その後、人工繁殖のため佐渡トキ保護センターに移送された。能里は翌年死んで、本州のトキは絶滅する。当地の人たちにすれば、トキの姿を目にしたのは実に40年ぶりということになる。
1970年1月、能登半島では「能里(のり)」の愛称で呼ばれていたオスが繁殖のため、この地で捕獲された。その後、人工繁殖のため佐渡トキ保護センターに移送された。能里は翌年死んで、本州のトキは絶滅する。当地の人たちにすれば、トキの姿を目にしたのは実に40年ぶりということになる。
当然、マスメディアのニュースになった。翌日付の紙面からその日の様子を拾ってみる。町役場に知らせた同町曽福の農業Sさん(69)によると、トキは同日午前10時50分ごろ、Sさんの自宅と近い水田でエサをついばんでいた。役場の職員らと一緒に5、6メートルほど近づいたが、怖がる様子は見せず、水田を動き回っていたという。約30分後、カラスの鳴き声に驚いて飛び立ち、独特のトキ色(朱色)の羽を見せて七尾市方面(穴水より南方向)に去っていった。石川県の自然保護課が、環境省に確認したところ、このトキは足輪の色から「個体番号04」のメスの可能性が強い。2008年9月に佐渡で放され、幅40キロメートルの佐渡海峡を越えて、新潟や福島、宮城、山形など広い範囲を移動したあと、富山県黒部市にしばらく滞在していた。3月27日には石川県加賀市にも飛来し話題となった。
当時の様子からいくつかのことが確認できる。トキは本来、人影を恐れて谷内田、あるいは山田と呼ばれる奥まった田んぼの生き物(カエルやドジョウなど)をついばみにくる、とされていた。ところが、今回、「5、6メートルほど近づいた」が、物怖じしなかったということは、人工繁殖なので野生に復帰しても人影を気にしないということだろうか。もう一つ。カラスの鳴き声に驚いて飛び立ったとある。放鳥以来、トキがカラスに空で追い掛け回されている姿の写真が紙面で掲載されていた(09年1月20日付・新潟日報)。このことからも、トキは適応能力や学習能力が高い鳥だと分かる。
話はくどくなるが、人影におののかないトキが出現しているというのは、人と生き物の共生という視点で考えるならば、ある意味で歓迎すべきことである。トキはかつて能登半島などで「ドォ」と呼ばれていた。田植えのころに田んぼにやってきて、早苗を踏み荒らすとされ、害鳥として農家から目の敵(かたき)にされていた。ドォは、「ドォ、ドォ」と追っ払うときの威嚇の声からその名が付いた。米一粒を大切にした時代、トキを田に入れることでさえ許さなかったのであろう。昭和30年代の食料増産の掛け声で、農家の人々は収量を競って、化学肥料や農薬、除草剤を田んぼに入れるようになった。人に追われ、田んぼに生き物がいなくなり、トキは絶滅の道をたどった。
いまその発想は逆転した。トキが舞い降りるような田んぼこそが生き物が育まれていて、安心そして安全な田んぼとして、そこから収穫されるお米は「朱鷺の米」(佐渡)に代表されるように高級米である。人は生き物を上手に使って、食料の安心安全の信頼やブランドを醸し出す時代である。農家も生きる、トキも生きる、そんなパラダイス(楽園)ができないだろうか。
農薬害について警鐘を発した、レイチェル・カーソンの名著『沈黙の春~生と死の妙薬~』の中で、このような文がある。「私たちは今、2つの道の分岐点に立っている。・・・私たちが長い間歩んできたのは、偽りの道であって、それは猛スピードで突っ走ることのできるハイウェイのように見えるが、行く手には大惨事が待っている。もう一つの道は、人もあまり通らないが、それを選ぶことによってのみ私たちは、私たちの住んでいる地球の保全をまっとうするという最終の目標に到達できるのである」
我々が歩むべき道は、化学肥料と農薬にまみれた食料増産という「ハイウェイ」ではない。低価格かもしれないが、そこには「死の妙薬」が仕込まれている。そうではなくて、我々が歩むべきはトキが舞い降りる「里の道」だろう。それは食料問題にとどまらず、自然環境と人との生き方という話にもなってくるからだ。これを言うと、「ハイウェイ」を走る都会の人たちの中には「我々の食料をどうしてくれる」と凄む人もいる。安心安全な食料を得たければ、築地ではなく、どうぞ里に来てください。その目で食料生産の現場を見て、直接仕入れてください。そんなふうに言えばよい。「安全と水と食料はただ同然」という時代はもう終わっている。自己責任で選ぶ時代、生きる道の選択のときがきたのかもしれない。(※写真はトキ、岩田秀男氏撮影=1957年、輪島市三井町洲衛)
⇒17日(土)夜・金沢の天気 くもり
 政権交代で、「地域主権」という言葉がクローズアップしてきた。前政権では「地方分権」という言葉だった。分権という言葉は「分け与える」というお上が権限を払下げるというイメージがあり、現政権では「地域のことは地域で」というという意味合いなのだろう。言葉遊びのような感じもするが、それはどうでもよい。中央政府が「分権だ」「地域主権だ」と言いながら、これほど有権者レベルで上がらない議論もない。なぜか。それはすでに国のミクロなレベルではすでに「自分たちでやっている」という意識があるからだ。つまり、この論議というのは、中央政府と県や市町村との間の権限をめぐる駆け引きの話である。一方で、すでに地域では自治会や町内会で自主的に暮らしにかかわるさまざまな議論をしている。その論議は、「行政に頼ろう」や「国に頼ろう」という論議ではない。いかにしてこの地域をよくしていくか、コミュニケ-ションを絶やさず、お互いを気遣って、どうともに生きていくかの論議である。そんな論議や現場の話し合いの姿をいくつも見てきた。
政権交代で、「地域主権」という言葉がクローズアップしてきた。前政権では「地方分権」という言葉だった。分権という言葉は「分け与える」というお上が権限を払下げるというイメージがあり、現政権では「地域のことは地域で」というという意味合いなのだろう。言葉遊びのような感じもするが、それはどうでもよい。中央政府が「分権だ」「地域主権だ」と言いながら、これほど有権者レベルで上がらない議論もない。なぜか。それはすでに国のミクロなレベルではすでに「自分たちでやっている」という意識があるからだ。つまり、この論議というのは、中央政府と県や市町村との間の権限をめぐる駆け引きの話である。一方で、すでに地域では自治会や町内会で自主的に暮らしにかかわるさまざまな議論をしている。その論議は、「行政に頼ろう」や「国に頼ろう」という論議ではない。いかにしてこの地域をよくしていくか、コミュニケ-ションを絶やさず、お互いを気遣って、どうともに生きていくかの論議である。そんな論議や現場の話し合いの姿をいくつも見てきた。 この記事を読んで、「日本の未来を担う子どもたちよ頑張れ」と共感した大人はいるだろうか。確かに、国際的な学力調査で日本の順位が下がったことを意識して、応用力などを育てることなどに力点を入れた内容を盛り込んでいると記事で説明がされている。が、極論すれば「詰め込み」にすぎない。多くの読者はそう感じたに違いない。電車の中や家庭でテレビゲームに熱中する子どもたちの姿や、「詰め込み」重視の学校での姿を現実的に見てきて、これでよいと思う大人はいないだろう。なぜか、いまの子どもたちに欠けているのは「人間力」、あるいは「生きる力」ではないかと思うからだ。
この記事を読んで、「日本の未来を担う子どもたちよ頑張れ」と共感した大人はいるだろうか。確かに、国際的な学力調査で日本の順位が下がったことを意識して、応用力などを育てることなどに力点を入れた内容を盛り込んでいると記事で説明がされている。が、極論すれば「詰め込み」にすぎない。多くの読者はそう感じたに違いない。電車の中や家庭でテレビゲームに熱中する子どもたちの姿や、「詰め込み」重視の学校での姿を現実的に見てきて、これでよいと思う大人はいないだろう。なぜか、いまの子どもたちに欠けているのは「人間力」、あるいは「生きる力」ではないかと思うからだ。 黄砂研究の第一人者といえば、金沢大学フロンティアサイエンス機構の岩坂泰信特任教授だ。シンポジウムの開催のお手伝いをさせていただく傍ら、岩坂氏の講演に耳を傾けていると、いろいろな気づきがある。印象に残る言葉は「能登半島は東アジアの環境センサーじゃないのかな」である。黄砂と能登半島を考えてみたい。
黄砂研究の第一人者といえば、金沢大学フロンティアサイエンス機構の岩坂泰信特任教授だ。シンポジウムの開催のお手伝いをさせていただく傍ら、岩坂氏の講演に耳を傾けていると、いろいろな気づきがある。印象に残る言葉は「能登半島は東アジアの環境センサーじゃないのかな」である。黄砂と能登半島を考えてみたい。 帯の上空で亜硫酸ガスが付着すると考えられる。日本海の上空では、海からの水蒸気が黄砂の表面に取り付き、汚染物質の吸着を容易にしているのではないかと推測される。
帯の上空で亜硫酸ガスが付着すると考えられる。日本海の上空では、海からの水蒸気が黄砂の表面に取り付き、汚染物質の吸着を容易にしているのではないかと推測される。  『なぜ飼い犬に手をかまれるのか』(日高敏隆著、PHPサイエンス・ワールド新書、09年)はタイトル名で注文してしまった。「飼い犬に手をかまれる」という言葉は、部下の反逆を意味する。それに、「なぜ」と付されると、科学の領域のような感じがして手を伸ばしたくなるものだ。動物行動学者の日高氏については、個人的に一度だけ
『なぜ飼い犬に手をかまれるのか』(日高敏隆著、PHPサイエンス・ワールド新書、09年)はタイトル名で注文してしまった。「飼い犬に手をかまれる」という言葉は、部下の反逆を意味する。それに、「なぜ」と付されると、科学の領域のような感じがして手を伸ばしたくなるものだ。動物行動学者の日高氏については、個人的に一度だけ 修了生はどんな研究課題に自ら取り組んできたのか紹介する。ある40歳の市役所の職員は、岩ガキの養殖を試み、それが果たして経営的に成り立つのかと探求した。年々少なくなる地域資源を守り、増やして、生かしていこうという意欲的な研究だ。さらに、その実験を自費で行った。コストをいとわず、可能性を追及する姿こそ尊いと心が打たれた。また、32歳の炭焼きの専業者は、生産から販売までに排出する二酸化炭素が、全体としてプラスなのかマイナスなのかという研究を行った。土壌改良剤として炭素が固定されることを考慮に入れて、全体としてマイナスであると結論付けた研究だった。膨大なデータを積み上げ、一つの結論を導いていくという作業はまさに科学そのものである。しかし、自らの生業を科学することは、なかなかできることではない。その結果として逆の答えが出たら怖いからだ。そこに、果敢に挑戦し自らの生業の有用性を立証していくという勇気は感動ものである。
修了生はどんな研究課題に自ら取り組んできたのか紹介する。ある40歳の市役所の職員は、岩ガキの養殖を試み、それが果たして経営的に成り立つのかと探求した。年々少なくなる地域資源を守り、増やして、生かしていこうという意欲的な研究だ。さらに、その実験を自費で行った。コストをいとわず、可能性を追及する姿こそ尊いと心が打たれた。また、32歳の炭焼きの専業者は、生産から販売までに排出する二酸化炭素が、全体としてプラスなのかマイナスなのかという研究を行った。土壌改良剤として炭素が固定されることを考慮に入れて、全体としてマイナスであると結論付けた研究だった。膨大なデータを積み上げ、一つの結論を導いていくという作業はまさに科学そのものである。しかし、自らの生業を科学することは、なかなかできることではない。その結果として逆の答えが出たら怖いからだ。そこに、果敢に挑戦し自らの生業の有用性を立証していくという勇気は感動ものである。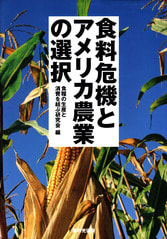 まず、この本を手にした経緯から。今月4日と5日、金沢大学が能登半島で展開して「能登里山マイスター」養成プログラムなどを見学させてほしいと、愛媛大学社会連携推進機構から村田武特命教授ら3人が訪れた。村田氏は欧米の農業政策などが専門で、CSAやスローフードなど生産者と消費者を結ぶ動きにも詳しい。そこで、能登に足を運ばれたついでに、新年度の同プログラムの授業をお願いしたところ、快く引き受けていただいた。講義は「世界の農業と家族農業経営~アメリカの『コミュニティが支える農業』(CSA)運動~」と題して。その講義の参考文献としてリストアップして頂いたのが、村田氏が執筆に加わった上記の本である。ちなみに、講義は4月23日(金)午後6時20分から、能登空港ターミナルビルで。一般公開型の授業なので誰でも自由に聴講できる。
まず、この本を手にした経緯から。今月4日と5日、金沢大学が能登半島で展開して「能登里山マイスター」養成プログラムなどを見学させてほしいと、愛媛大学社会連携推進機構から村田武特命教授ら3人が訪れた。村田氏は欧米の農業政策などが専門で、CSAやスローフードなど生産者と消費者を結ぶ動きにも詳しい。そこで、能登に足を運ばれたついでに、新年度の同プログラムの授業をお願いしたところ、快く引き受けていただいた。講義は「世界の農業と家族農業経営~アメリカの『コミュニティが支える農業』(CSA)運動~」と題して。その講義の参考文献としてリストアップして頂いたのが、村田氏が執筆に加わった上記の本である。ちなみに、講義は4月23日(金)午後6時20分から、能登空港ターミナルビルで。一般公開型の授業なので誰でも自由に聴講できる。 珠洲市三崎町にあるコミュニティ・レストラン「へんざいもん」。小学校の廃校舎の調理室を利用した、毎週土曜日のお昼だけのレストランだ。近所の主婦たち4、5人が食材を持ち寄って集まり、700円の定食メニューを提供してくれる。秋になると土地で採れるマツタケを具材に「まつたけご飯定食」が目玉となる。特に宣伝はしていなが、どこからうわさが立ってこの日は利用者がぐっと増える。そのほか、魚介類や山菜類、根菜、菜っ葉ものすべて近くの海、山、畑で採れたもの。ちなみに「へんざいもん」とは、この土地の方言で、漢字を当てると「辺菜物」。つまり「この辺りで採れた物」のこと。地産地消を地でいく屋号なのである。
珠洲市三崎町にあるコミュニティ・レストラン「へんざいもん」。小学校の廃校舎の調理室を利用した、毎週土曜日のお昼だけのレストランだ。近所の主婦たち4、5人が食材を持ち寄って集まり、700円の定食メニューを提供してくれる。秋になると土地で採れるマツタケを具材に「まつたけご飯定食」が目玉となる。特に宣伝はしていなが、どこからうわさが立ってこの日は利用者がぐっと増える。そのほか、魚介類や山菜類、根菜、菜っ葉ものすべて近くの海、山、畑で採れたもの。ちなみに「へんざいもん」とは、この土地の方言で、漢字を当てると「辺菜物」。つまり「この辺りで採れた物」のこと。地産地消を地でいく屋号なのである。 農薬や除草剤、化学肥料を使わなくても農業はできると説くのだから、これまでそれらを一手に販売してきた農協の立場は180度ひっくり返る。しかも、この講演会を実施したのは、冒頭で紹介した農協や市役所の職員たちである。トップダウンではない。職員たちの発案によるボトムアップの企画だ。税金は一切使わない。1500円の前売券にはそのような意味がある。それより、農協の組合長が実行委員長となり、「日本の農業を変えよう」と自然栽培の木村氏を講師に招いたところがポイントであり、メッセージ性がある。これは、単に石川県能登半島での一つのシーンではない。
農薬や除草剤、化学肥料を使わなくても農業はできると説くのだから、これまでそれらを一手に販売してきた農協の立場は180度ひっくり返る。しかも、この講演会を実施したのは、冒頭で紹介した農協や市役所の職員たちである。トップダウンではない。職員たちの発案によるボトムアップの企画だ。税金は一切使わない。1500円の前売券にはそのような意味がある。それより、農協の組合長が実行委員長となり、「日本の農業を変えよう」と自然栽培の木村氏を講師に招いたところがポイントであり、メッセージ性がある。これは、単に石川県能登半島での一つのシーンではない。 何も、昔に戻ってクヌギやコナラを切り出して炭を焼こう、木の葉から肥料をつくろうと言っているのではない。21世紀における里山の保全と利用を考えていこうという期待感である。あるいは、里山という生態系を見直すことで得られる新たな価値を再評価したいという思いもある。最近、一般的にも使われ始めた生態系サービスを地域の里山に見出すことから始めてもよい。とはいえ、一度失われた関係価値を取り戻すには時間がかかる。
何も、昔に戻ってクヌギやコナラを切り出して炭を焼こう、木の葉から肥料をつくろうと言っているのではない。21世紀における里山の保全と利用を考えていこうという期待感である。あるいは、里山という生態系を見直すことで得られる新たな価値を再評価したいという思いもある。最近、一般的にも使われ始めた生態系サービスを地域の里山に見出すことから始めてもよい。とはいえ、一度失われた関係価値を取り戻すには時間がかかる。