★文明論としての里山3
日本の里山は、1960 年代から始まったとされる燃料革命や大規模な宅地開発などで、その役目を終えて荒廃の道をひた走っているかのように見えた。ところが、ここ数年で里山の価値が見直されつつある。多くの動植物を育み、人が恩恵を受ける場所としての里山。「生態系サービス」という言葉が使われ始めていることはその象徴である。里山を守るための行政や市民などによる取り組みが始まっている。里山保全は日本の環境問題(二酸化炭素の吸収、生物多様性の保全)を打開するキーワードの一つになっているともいえる。
ジョグラフ氏が見た能登半島の里山
 さらに、<SATOYAMA=里山>は国際用語として認知されようとしている。その認知度を一気に高めたのが、生物多様性条約第9回締約国会議(CBD/COP9、ドイツ・ボン)で日本の環境省と国連大学高等研究所が主催したサイドイベント「日本の里山・里海における生物多様性」(2008年5月28日)だった。スピーチの中で、環境省の黒田大三郎審議官(当時)らが「人と自然の共生、そして持続可能社会づくりのヒントが日本の里山にある」と述べ、科学者による知識と伝統的な自然との共存を組み合わせることを目的とした「里山イニシアティブ」を生物多様性の戦略目標として提唱した。さらに、石川県の谷本正憲知事は「石川の里山里海は世界に誇りうる財産である」と強調し、森林環境税の創設による森林整備、条例の制定、景観の面からの保全など具体的な取り組みを紹介した。
さらに、<SATOYAMA=里山>は国際用語として認知されようとしている。その認知度を一気に高めたのが、生物多様性条約第9回締約国会議(CBD/COP9、ドイツ・ボン)で日本の環境省と国連大学高等研究所が主催したサイドイベント「日本の里山・里海における生物多様性」(2008年5月28日)だった。スピーチの中で、環境省の黒田大三郎審議官(当時)らが「人と自然の共生、そして持続可能社会づくりのヒントが日本の里山にある」と述べ、科学者による知識と伝統的な自然との共存を組み合わせることを目的とした「里山イニシアティブ」を生物多様性の戦略目標として提唱した。さらに、石川県の谷本正憲知事は「石川の里山里海は世界に誇りうる財産である」と強調し、森林環境税の創設による森林整備、条例の制定、景観の面からの保全など具体的な取り組みを紹介した。
これに、生物多様性条約事務局長のアフメド・ジョグラフ氏は、日本が提唱する里山イニシアティブに「成長を続けて現代的な社会を形成した一方で、文化や伝統、そして自然との関係を保ってきた。そのコンセプトは世界で有効であり、日本の経験に大きな期待が集まっている」と、条約事務局として支援を表明した。COP10の名古屋開催が予定されていたこともあり、会場に集まった海外の環境NGOや研究機関、メディアの関係者の脳裏には2010年のテーマとして<SATOYAMA=里山>が刻まれた。
その後、ジョグラフ氏は谷本知事がスピーチで紹介した日本の里山を実際に見てみたいと能登半島を訪れる。名古屋市で開催された第16回アジア太平洋環境会議(エコアジア、2008年9月13日・14日)に出席した後、15日に石川県入り、16日と17日に能登を視察した。初日は能登町の「春蘭の里」、輪島市の千枚田、珠洲市のビオトープ、能登町の旅館で宿泊し、2日目は「のと海洋ふれあいセンター」、輪島の金蔵地区を訪れた。珠洲の休耕田をビオトープとして再生し、子供たちへの環境教育に活用している加藤秀夫氏(同市立西部小学校長=当時)から説明を受けたジョグラフ氏は「Good job(よくやっている)」を連発して、持参のカメラでビオトープを撮影した=写真=。ジョグラフ氏も子供たちへの環境教育に熱心で、アジアやアフリカの小学校に植樹する「グリーン・ウェーブ」を提唱している。訪れた金蔵地区で、里山に広がる棚田で稲刈りをする人々や寺参りをする人々を目の当たりにしたジョグラフ氏は「日本の里山の精神がここに生きている」と述べた。金蔵の里山に多様な生物が生息しており、自然と共生し生きる人々、信仰心にあふれる里人の姿に感動したのだった。
能登視察はジョグラフ氏にとって印象深かったのだろう。その後の生物多様性に関する国際会議で、「日本では、自然と共生する里山を守ることが、科学への崇拝で失われてしまった伝統を尊重する心、文化的、精神的な価値を守ることにつながっている。そのお手本を能登半島で見ることができる」と述べていたそうだ。
⇒30日(水)夜・金沢の天気 くもり
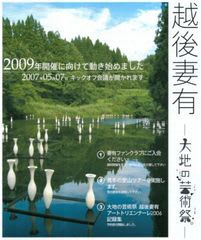 日本でも食の問題が起きた。どこの国で生産されたのかも不明な食材や加工食品を、安全性を二の次にして安価というだけで市場に流す。そのため価格では太刀打ちできない国内の小生産者は生産を止め、地域そのものが疲弊していく。地域の労働の担い手は都会に出て行く。土地を離れた労働者は現金収入によって生活をする非熟練労働者になる。彼らを待ち受けているのは結局、失業と貧困である。 これまで、「国民の経済」に歪みや偏りが起こると政府は、税金や補助金や社会保障給付というカタチで所得の再配分を行ってきた。ところが、一部を除いて世界的な不況となると自動車産業などグローバル企業でさえ赤字決算に陥る。日本を始め欧米は軒並み巨額な国債発行で財政をしのいでいが遅かれ早かれ国家自体が破綻する。民主党政権が、郵貯の民営化にストップをかけたのも、再び郵貯を「国債消化機関」として復活させようとしているからだとの見方もある。資本主義だけではなく、政治も国家も疲弊している。
日本でも食の問題が起きた。どこの国で生産されたのかも不明な食材や加工食品を、安全性を二の次にして安価というだけで市場に流す。そのため価格では太刀打ちできない国内の小生産者は生産を止め、地域そのものが疲弊していく。地域の労働の担い手は都会に出て行く。土地を離れた労働者は現金収入によって生活をする非熟練労働者になる。彼らを待ち受けているのは結局、失業と貧困である。 これまで、「国民の経済」に歪みや偏りが起こると政府は、税金や補助金や社会保障給付というカタチで所得の再配分を行ってきた。ところが、一部を除いて世界的な不況となると自動車産業などグローバル企業でさえ赤字決算に陥る。日本を始め欧米は軒並み巨額な国債発行で財政をしのいでいが遅かれ早かれ国家自体が破綻する。民主党政権が、郵貯の民営化にストップをかけたのも、再び郵貯を「国債消化機関」として復活させようとしているからだとの見方もある。資本主義だけではなく、政治も国家も疲弊している。 プロテスタントの教義は、身分は低くとも自分の仕事に誇りを持って専念しなさいと人々を諭した。これがカルヴァンが説いた予定調和説の「あらかじめ神が決めたこと」だ。プロテスタントの教会には階級序列がなく、人々にも上昇志向や贅沢志向というものがなかった。こうした生真面目な精神性が、高い生産性と「働いて貯める」倫理を生みだし、それが資本主義の蓄積へと間接的に連なって行く。一方、カトリック社会では階級序列があり、より高い階級へ上昇できる可能性がある。すると、今の仕事はより高い地位に就くための通過地点にすぎないと考える人々は実入りのよい仕事に目を向け、現状の仕事に専念しなくなる。その結果として生産性は低くなる、とウェーバーは分析したと覚えている。
プロテスタントの教義は、身分は低くとも自分の仕事に誇りを持って専念しなさいと人々を諭した。これがカルヴァンが説いた予定調和説の「あらかじめ神が決めたこと」だ。プロテスタントの教会には階級序列がなく、人々にも上昇志向や贅沢志向というものがなかった。こうした生真面目な精神性が、高い生産性と「働いて貯める」倫理を生みだし、それが資本主義の蓄積へと間接的に連なって行く。一方、カトリック社会では階級序列があり、より高い階級へ上昇できる可能性がある。すると、今の仕事はより高い地位に就くための通過地点にすぎないと考える人々は実入りのよい仕事に目を向け、現状の仕事に専念しなくなる。その結果として生産性は低くなる、とウェーバーは分析したと覚えている。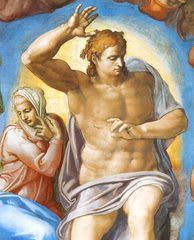 アメリカで一番有名な社説というのがある。取り上げるタイミングとしては少々遅きに失したが、「サンタはいるの」という8歳の女の子の質問に答えた社説だ。1897年9月、アメリカの新聞ニューヨーク・サンに掲載され、その後、目に見えないけれども心に確かに存在し、それを信じる心を持つことの尊さを説いた社説と評価され、掲載されてから110年余り経った今でも、クリスマスの時期になると世界中で語り継がれている。その社説を掲載する。
アメリカで一番有名な社説というのがある。取り上げるタイミングとしては少々遅きに失したが、「サンタはいるの」という8歳の女の子の質問に答えた社説だ。1897年9月、アメリカの新聞ニューヨーク・サンに掲載され、その後、目に見えないけれども心に確かに存在し、それを信じる心を持つことの尊さを説いた社説と評価され、掲載されてから110年余り経った今でも、クリスマスの時期になると世界中で語り継がれている。その社説を掲載する。 池の水面に映える。兼六園の心象風景は季節ごとに異なるのだ。
池の水面に映える。兼六園の心象風景は季節ごとに異なるのだ。 桜が晩春を締めくくる。桜にも役どころというものがある。
桜が晩春を締めくくる。桜にも役どころというものがある。 新聞各紙やテレビのニュースをまとめる。11月27日、フロリダ・オーランドの自宅前でウッズが乗用車で自損事故を起こし重傷との一報を、地元テレビ局が報じた(11月27日)。スーパースターのけが。マイケル・ジャクソンの急逝も記憶に新しいアメリカでは、国民の関心が一気にウッズに集中したのも無理はない。ウッズは顔面に軽い傷を負った程度で、病院で手当して帰宅したが、ウッズの退院後の姿を取材しようと、「ゲートコミュニティ」と呼ばれる塀で囲まれた高級住宅街のメインゲートにはテレビ中継用のSNG(Satellite News Gathering)車がずらりと並んた。このSNG車はカメラで撮影した素材(映像と音声)を電波として通信衛星を経由させ、本局に伝送する装置を搭載していて、パラボラアンテナが付いている。つまり、「おわん」の付いた車が横一列に並ぶ、日本のニュース現場ではおなじみの光景がオーランドでも再現されたのである。
新聞各紙やテレビのニュースをまとめる。11月27日、フロリダ・オーランドの自宅前でウッズが乗用車で自損事故を起こし重傷との一報を、地元テレビ局が報じた(11月27日)。スーパースターのけが。マイケル・ジャクソンの急逝も記憶に新しいアメリカでは、国民の関心が一気にウッズに集中したのも無理はない。ウッズは顔面に軽い傷を負った程度で、病院で手当して帰宅したが、ウッズの退院後の姿を取材しようと、「ゲートコミュニティ」と呼ばれる塀で囲まれた高級住宅街のメインゲートにはテレビ中継用のSNG(Satellite News Gathering)車がずらりと並んた。このSNG車はカメラで撮影した素材(映像と音声)を電波として通信衛星を経由させ、本局に伝送する装置を搭載していて、パラボラアンテナが付いている。つまり、「おわん」の付いた車が横一列に並ぶ、日本のニュース現場ではおなじみの光景がオーランドでも再現されたのである。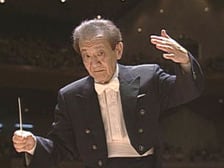 ある。これは世界の奇観であろう。
ある。これは世界の奇観であろう。 Go、Go! マツイ…」というサビの部分は松井選手が出番になるとヤンキー・スタジアムに響いたのだった。
Go、Go! マツイ…」というサビの部分は松井選手が出番になるとヤンキー・スタジアムに響いたのだった。 アメリカ東部を覆った強い寒気。ワシントンでは吹雪が止まず、バスや鉄道はほぼすべてが運行停止になった(18日)。ワシントンに隣接するバージニア州では、積雪最大56㌢が予想されたことから、非常事態宣言が出された。ヨーロッパ各地では、寒さの影響でヨーロッパ大陸とイギリスを結ぶ高速鉄道「ユーロスター」の4つの便がトンネル内で相次いで故障して立ち往生し、2500人の乗客が一時閉じ込められた。氷点下のフランス側から比較的暖かいトンネルに入った時に生じた温度差が故障の原因らしい。
アメリカ東部を覆った強い寒気。ワシントンでは吹雪が止まず、バスや鉄道はほぼすべてが運行停止になった(18日)。ワシントンに隣接するバージニア州では、積雪最大56㌢が予想されたことから、非常事態宣言が出された。ヨーロッパ各地では、寒さの影響でヨーロッパ大陸とイギリスを結ぶ高速鉄道「ユーロスター」の4つの便がトンネル内で相次いで故障して立ち往生し、2500人の乗客が一時閉じ込められた。氷点下のフランス側から比較的暖かいトンネルに入った時に生じた温度差が故障の原因らしい。 きのう(19日)、金沢大学と能美市が主催する「タウンミーティングin能美」が開催された。会場は同市辰口にある石川ハイテイク交流センターで、丘陵地にあり、積雪は30㌢ほどあった=写真=。それでも、参加登録者150人のうち、欠席はおよそ10人だった。これは歩留まりから考えて想定内の数字だ。つまり晴れていてもこの程度は欠席率があるものだ。タウンミーティングは、地域との対話を通じて連携を探るため、金沢大学が平成14年(2002)から石川県内で毎年連続して開催しており、今回で9回目。雪のタウンミーティングも始めての経験だった。
きのう(19日)、金沢大学と能美市が主催する「タウンミーティングin能美」が開催された。会場は同市辰口にある石川ハイテイク交流センターで、丘陵地にあり、積雪は30㌢ほどあった=写真=。それでも、参加登録者150人のうち、欠席はおよそ10人だった。これは歩留まりから考えて想定内の数字だ。つまり晴れていてもこの程度は欠席率があるものだ。タウンミーティングは、地域との対話を通じて連携を探るため、金沢大学が平成14年(2002)から石川県内で毎年連続して開催しており、今回で9回目。雪のタウンミーティングも始めての経験だった。 「ネギは雪が降ると糖度が増して甘くなる。ほら食べてごらん」。農場のスタッフが収穫したばかりのネギを差し出してくれた。ネギは切ると辛くなるが、剥いている分には甘い。白い部分をバナナでも食べるようにガブリと。確かに甘い。しかも、その甘みが不思議と口の中に残っている。そして喉あたりがいつまでも温かく感じる。初めての取材で緊張の面持ちだった福井出身の女子学生は「おろしそばに刻んで入れて食べてみたい」と相好を崩した。雪のネギ畑でひとしきり会話が弾んだ。
「ネギは雪が降ると糖度が増して甘くなる。ほら食べてごらん」。農場のスタッフが収穫したばかりのネギを差し出してくれた。ネギは切ると辛くなるが、剥いている分には甘い。白い部分をバナナでも食べるようにガブリと。確かに甘い。しかも、その甘みが不思議と口の中に残っている。そして喉あたりがいつまでも温かく感じる。初めての取材で緊張の面持ちだった福井出身の女子学生は「おろしそばに刻んで入れて食べてみたい」と相好を崩した。雪のネギ畑でひとしきり会話が弾んだ。