この「自在コラム」の2010年10月26日付「COP10の風~下~」で「里山SATOYAMAイニシアティブ」について紹介した。里山イニシアティブは生態系を守りながら漁業や農業の営みを続ける「持続可能な自然資源利用」という概念で、今後、生態系保全を考える上で世界共通の基本認識となりつつある。
 その背景には、国際条約への流れがある。2008年5月に神戸で開催されたG8環境大臣会合で里山イニシアティブの国際的な推進が合意され、ドイツ・ボンでの生物多様性条約COP9では日本がその促進を国際社会に表明し、2009年4月にイタリア・シチリアで開催されたG8環境大臣会合でもシラクサ宣言に盛り込まれた。そしてことし10月、名古屋で開催されたCOP10では、世界各地域の自然共生の事例をもとに、二次的な自然資源管理の考え方や具体的な方法を整理し、自然資源管理の国際モデルとして里山イニシアティブを促進する決議案が採択された。
その背景には、国際条約への流れがある。2008年5月に神戸で開催されたG8環境大臣会合で里山イニシアティブの国際的な推進が合意され、ドイツ・ボンでの生物多様性条約COP9では日本がその促進を国際社会に表明し、2009年4月にイタリア・シチリアで開催されたG8環境大臣会合でもシラクサ宣言に盛り込まれた。そしてことし10月、名古屋で開催されたCOP10では、世界各地域の自然共生の事例をもとに、二次的な自然資源管理の考え方や具体的な方法を整理し、自然資源管理の国際モデルとして里山イニシアティブを促進する決議案が採択された。
決議案の採択と並行して、COP10会場で国際組織「里山イニシアティブ国際パートナーシップ(IPSI)」が発足した。国際パートナーシップは、里山イニシアティブを提唱する日本政府が呼び掛けで、アジア・アフリカなど9ヵ国の政府や企業、非政府組織(NGO)や研究機関など51団体が参加した。その中には金沢大学も名を連ねる。その国際パートナーシップの第一弾とも言える「JICA研修プログラム」がさっそく実施され、JICA(国際協力機構)の招きでアジアやアフリカ、中南米13ヵ国の14人が今月17日から3週間の日程で石川県を訪れている。もちろん、金沢大学も協力している。
JICAの研修員はそれぞれの国の政府の自然保全や環境担当の専門官やマネージャー、生物資源研究所の研究員だ。石川プログラムのテーマは「持続可能な自然資源管理による生物多様性保全と地域振興~『SATOYAMA イニシアティブ』の推進~」。能登半島や白山ろくで、日本の里山や里海の伝統的知識や生物多様性に配慮した農林漁業の取り組みを学んでいる。25日は能登の炭焼きの窯場や塩田を訪ね、26日は実際に漁船に乗って、富山湾の定置網漁の現場に出た。雨降る早朝3時。網を引くとことろから、魚の選別、出荷までを見学し、定置網のどこが環境に優しく持続可能なのか、魚の品質管理とその経済性について、400年続く日本の漁業の知恵を学んだ。
そして、きのう27日は輪島市にある「石川県健康の森」交流センターでJICA主催のシンポジウムが開かれた。アカマツ林に囲まれたホール。シンポジウムのテーマは「世界は里山里海に何を学ぶのか」。国連大学高等研究所上席局員研究員の名執芳博氏、金沢大学教授・学長補佐の中村浩二氏が講演した。パネルディスカッションは壮観だった。先述の両氏のほか環境省自然環境局、石川県環境部、国際協力機構地球環境部の職員ほか、研修を受けれた製炭工場の経営者、製塩会社のスタッフ、これに研修生14人が加わり、総勢22人のパネリストが「SATOYAMA イニシアティブの実践に向けて~地域のそれぞれの立場から~」をテーマに報告や意見交換をした=写真=。
自身これまでシンポジウムを含め5つのプログラムに参加し、うち2つのプログラムでは講師やパネル討論のコーディネターとしてかかわった。彼らの質問が経済合理性や科学的論拠など多岐にわたる。「SATOYAMAイニシアティブの到達目標はどこにあるのか、そのイメージを示してほしい」と質問をされたとき、私自身がドキリとした。確かに、その解はまだ誰からも提示されていないのだ。「伝統的に磨かれた里山の知恵や技術を、21世紀型の持続可能な英知としてさらに磨きをかけていきましょう」と答えるのがせいぜいだった。以下は質疑応答のやり取りの一例だ。
イスタント氏 (インドネシア林業省国立公園長):SATOYAMAイニシアティブ(SI)というのはEcosystemの一つだと思う。里山における生物多様性を守るためのガイドラインのようなものはあるのか。
宇野:ガイドラインはないと思う。地域の人々の自然と共生しようという気があるかないかによって、生物多様性を守ることができる。
ジャイシャンカ氏(インド国立生物多様性局技術支援員):日本のSIは現在どの段階か。
宇野:能登は日本の産業化の影に隠れていた。石油の問題や地球温暖化などにより、今は持続可能な利用や人と自然が共生している能登のスタイルが見直されている。日本ではSIはまだイントロダクションの段階だと思う。
ジャイシャンカ氏:イニシアティブを始めるときに共通の課題はあるか。
宇野:現地の人の生活や考えを尊重する必要がある、SIという概念を押し付けてはいけない。
ジャイシャンカ氏:では、SIを市民にどう教えますか、具体的な行動は・・・。
上記のように里山イニシアティブへの具体論な質問がどんどんと投げかけられる。世界には里山と同じような地域(ランドスケープ)があり、フランスでは「テロワール」、スペインでは「デヘサ」、フィリピンでは「ムヨン」、韓国では「マウル」と呼ばれている。こうした地域には共通して、市場合理性の波や、若者が都市に流出するなどの現象が表れている。
シンポジウムでふと考えた。里山イニシアティブをこんな言葉で表現してみるとどうだろう。「里山イニシアティブは世界の地域興しだ」と。地域興しなら日本は長年やっている。地域興しの3つの条件がある。「若者」「よそ者」「バカ者」の3つの人的ファクターだ。若者は地域の担い手、よそ者は客観的な価値判断、バカ者は専門性が特徴だ。ならば、よそ者を外国人、バカ者を大学・研究機関の研究者に置き換えて、世界の人々と協力して里山イニシアティブ=世界の地域興しをやっていきましょう、と。
⇒28日(日)金沢の天気 くもり
 共産以外の各政党の支援を受け、県会議員と市会議員40人ほどが支える山出陣営は当初から「横綱相撲」と言われていた。候補者は79歳、6期目への挑戦だった。今回の選挙は「多選」というより、「高齢」の是非が大きな焦点となった。新人の山野之義氏(48)は「79歳の市長と古い政治を続けるか。48歳の私と一緒に新しい市をつくるか」と訴えていた。私が投票場(小学校)への道を歩いていると、前を歩いていた3人の中高年の女性たちから「コウキコウレイシャ(後期高齢者)やね・・・」という言葉が漏れていた。続く言葉は聞こえなかったが、後期高齢者はよいイメージで使われることはないので想像はついた。
共産以外の各政党の支援を受け、県会議員と市会議員40人ほどが支える山出陣営は当初から「横綱相撲」と言われていた。候補者は79歳、6期目への挑戦だった。今回の選挙は「多選」というより、「高齢」の是非が大きな焦点となった。新人の山野之義氏(48)は「79歳の市長と古い政治を続けるか。48歳の私と一緒に新しい市をつくるか」と訴えていた。私が投票場(小学校)への道を歩いていると、前を歩いていた3人の中高年の女性たちから「コウキコウレイシャ(後期高齢者)やね・・・」という言葉が漏れていた。続く言葉は聞こえなかったが、後期高齢者はよいイメージで使われることはないので想像はついた。 過日、能登半島・輪島市の公園を通りかかると、子供たちがフラフープに興じていた=写真=。腰を振って、実に楽しそうにこちらに手を振ってくれたので、思わずカメラに収めた。昔取った杵柄(きねづか)で、いまでも自分もできそうだと思うのが不思議だ。フラフープが再び日本でブームになっているようだ。
過日、能登半島・輪島市の公園を通りかかると、子供たちがフラフープに興じていた=写真=。腰を振って、実に楽しそうにこちらに手を振ってくれたので、思わずカメラに収めた。昔取った杵柄(きねづか)で、いまでも自分もできそうだと思うのが不思議だ。フラフープが再び日本でブームになっているようだ。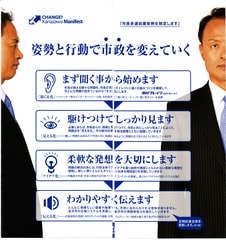 任期満了にともなう金沢市長選挙は28日投票が行われ、無所属の新人で元金沢市議会議員の山野之義氏(48)が初当選を果たした。5万8204票と5万6840票。現職で6選をめざす山出保氏(79)と1364票の僅差だった。投票率は前回に比べ8.5ポイント高い35.9%だった。
任期満了にともなう金沢市長選挙は28日投票が行われ、無所属の新人で元金沢市議会議員の山野之義氏(48)が初当選を果たした。5万8204票と5万6840票。現職で6選をめざす山出保氏(79)と1364票の僅差だった。投票率は前回に比べ8.5ポイント高い35.9%だった。 その背景には、国際条約への流れがある。2008年5月に神戸で開催されたG8環境大臣会合で里山イニシアティブの国際的な推進が合意され、ドイツ・ボンでの生物多様性条約COP9では日本がその促進を国際社会に表明し、2009年4月にイタリア・シチリアで開催されたG8環境大臣会合でもシラクサ宣言に盛り込まれた。そしてことし10月、名古屋で開催されたCOP10では、世界各地域の自然共生の事例をもとに、二次的な自然資源管理の考え方や具体的な方法を整理し、自然資源管理の国際モデルとして里山イニシアティブを促進する決議案が採択された。
その背景には、国際条約への流れがある。2008年5月に神戸で開催されたG8環境大臣会合で里山イニシアティブの国際的な推進が合意され、ドイツ・ボンでの生物多様性条約COP9では日本がその促進を国際社会に表明し、2009年4月にイタリア・シチリアで開催されたG8環境大臣会合でもシラクサ宣言に盛り込まれた。そしてことし10月、名古屋で開催されたCOP10では、世界各地域の自然共生の事例をもとに、二次的な自然資源管理の考え方や具体的な方法を整理し、自然資源管理の国際モデルとして里山イニシアティブを促進する決議案が採択された。 昭和29年(1954年)の合併時に3万8千人だった人口が半世紀余りで1万7千人と2万1千人も減った。そして高齢化も急テンポです進む。ことし7月に全国に先駆けて地上デジタル放送への完全移行を成功させたのも、高齢世帯の対策をどうするかということが市長自らを走らせた。6月に再選を果たした泉谷氏は「あと6年」と自ら到達年を設定して、手探りながら環境問題や財政建て直しなど次世代に引き継ぐ政策を打つ。市長だけではない。市職員からも切実感が伝わってくる。大学のプログラムに参加する都会からの移住者への対応も実に丁寧だ。
昭和29年(1954年)の合併時に3万8千人だった人口が半世紀余りで1万7千人と2万1千人も減った。そして高齢化も急テンポです進む。ことし7月に全国に先駆けて地上デジタル放送への完全移行を成功させたのも、高齢世帯の対策をどうするかということが市長自らを走らせた。6月に再選を果たした泉谷氏は「あと6年」と自ら到達年を設定して、手探りながら環境問題や財政建て直しなど次世代に引き継ぐ政策を打つ。市長だけではない。市職員からも切実感が伝わってくる。大学のプログラムに参加する都会からの移住者への対応も実に丁寧だ。 それにしても、「戦争」を伝えるメディアは内容もすさまじい。以下は、各紙の引用だ。
それにしても、「戦争」を伝えるメディアは内容もすさまじい。以下は、各紙の引用だ。 36歳のKさんは、神奈川県でIT企業に勤めていた。「歩くツーリズム」を自分で企画することが夢で能登のやってきた。昨年、パートナーといっしょにスペインのカミーノ・デ・サンティアゴという道を850㌔歩く旅をし、「豊かな自然、人、文化を歩いて旅をし、味わう道をつくりたい」と面接で熱く語った。4月に夫妻で能登に移住した。そのKさんは、ノルディックウォーキング「SUZUあるき」という企画を仲間たちとつくっている。珠洲市の自然資源を自分の足で感じつつ、地域の人々と参加者同士で交流し、汗を流したあとは季節の味覚を味わうという毎月開催のイベントだ。
36歳のKさんは、神奈川県でIT企業に勤めていた。「歩くツーリズム」を自分で企画することが夢で能登のやってきた。昨年、パートナーといっしょにスペインのカミーノ・デ・サンティアゴという道を850㌔歩く旅をし、「豊かな自然、人、文化を歩いて旅をし、味わう道をつくりたい」と面接で熱く語った。4月に夫妻で能登に移住した。そのKさんは、ノルディックウォーキング「SUZUあるき」という企画を仲間たちとつくっている。珠洲市の自然資源を自分の足で感じつつ、地域の人々と参加者同士で交流し、汗を流したあとは季節の味覚を味わうという毎月開催のイベントだ。 奥能登で生産された米の販売会が、20日と21日に金沢市にあるスーパー「どんたく金沢西南部店」であった。店頭に並んだ奥能登の米は、海洋深層水を利用したもの、鶏ふんなどの有機肥料を用いたり、棚田ではざ干し、女性たちが耕す棚田米などそれぞれ特徴を打ち出した「こだわり米」なのだ。NPOや農業法人、生産組合など10つの団体が出品した=写真=。
奥能登で生産された米の販売会が、20日と21日に金沢市にあるスーパー「どんたく金沢西南部店」であった。店頭に並んだ奥能登の米は、海洋深層水を利用したもの、鶏ふんなどの有機肥料を用いたり、棚田ではざ干し、女性たちが耕す棚田米などそれぞれ特徴を打ち出した「こだわり米」なのだ。NPOや農業法人、生産組合など10つの団体が出品した=写真=。 小田さんは、登山家の長谷川恒夫が「生きぬことが冒険」と語ったその生涯を紹介しながら話した。彼の登山人生は15歳のときにはじめて丹沢に登り、17歳で岩登りを知ることから始まる。26歳のとき、エベレスト登山隊に参加した。48人という大所帯での登山で、サミッター(登頂者)の生還を助けたが、自身の登頂はならならずに「組織登山」から、単独登山を志す。31歳で、アルプス三大北壁冬期単独登頂を果たし有名となる。その後も、アコンカグア南壁フランスルート冬期単独初登頂。その後、ダウラギリ、エベレストなどを目指したが敗退の連続で、ヒマラヤではサミッターにはなれなかった。1991年に未踏峰ウルタルIIに挑戦し、雪崩に巻き込まれ亡くなる。43歳だった。「挑戦し続ける人生こそ」と小田さんは言う。最後に、「好きこそものの上手なれ」という有名な言葉の説明をした。これには前文があり、「器用さ、稽古と好きのうち、好きこそものの上手なれ」だ。つまり、最初は下手でも、「好き」という人が最終的に名人になる。「好きなことに挑戦し続けよう、これが生きるセンス」と結んだ。
小田さんは、登山家の長谷川恒夫が「生きぬことが冒険」と語ったその生涯を紹介しながら話した。彼の登山人生は15歳のときにはじめて丹沢に登り、17歳で岩登りを知ることから始まる。26歳のとき、エベレスト登山隊に参加した。48人という大所帯での登山で、サミッター(登頂者)の生還を助けたが、自身の登頂はならならずに「組織登山」から、単独登山を志す。31歳で、アルプス三大北壁冬期単独登頂を果たし有名となる。その後も、アコンカグア南壁フランスルート冬期単独初登頂。その後、ダウラギリ、エベレストなどを目指したが敗退の連続で、ヒマラヤではサミッターにはなれなかった。1991年に未踏峰ウルタルIIに挑戦し、雪崩に巻き込まれ亡くなる。43歳だった。「挑戦し続ける人生こそ」と小田さんは言う。最後に、「好きこそものの上手なれ」という有名な言葉の説明をした。これには前文があり、「器用さ、稽古と好きのうち、好きこそものの上手なれ」だ。つまり、最初は下手でも、「好き」という人が最終的に名人になる。「好きなことに挑戦し続けよう、これが生きるセンス」と結んだ。 授業の冒頭に説明した。日本酒は欧米でちょっとしたブームだ。ワインやブランデー、ウイスキーなどの醸造方法より格段に人手をかけて醸す日本酒を世界が評価しているのだ、と。その後、農口氏を紹介するビデオを流し、「神技」とも評される酒造りの工程を学生に見せた。
授業の冒頭に説明した。日本酒は欧米でちょっとしたブームだ。ワインやブランデー、ウイスキーなどの醸造方法より格段に人手をかけて醸す日本酒を世界が評価しているのだ、と。その後、農口氏を紹介するビデオを流し、「神技」とも評される酒造りの工程を学生に見せた。