☆日本を洗濯-2-
情報発信に問題はないか、そのタイミングやネーミング
 「トモダチ作戦」と呼ばれる在日アメリカ軍による被災者の救援活動も印象に残る。沖縄の普天間基地から来たヘリコプターや貨物輸送機などが、物資を厚木基地から山形空港や東北沖にいる空母ロナルド・レーガンなどに輸送した。また、一時使用できなくなった仙台空港の瓦礫の撤去作業など行った。ロナルド・レーガンは原子力空母であり、平時だったらメディアでも問題視されいたことだろう。それを差し引いてもその迅速な救援活動は好印象で伝えられた。
「トモダチ作戦」と呼ばれる在日アメリカ軍による被災者の救援活動も印象に残る。沖縄の普天間基地から来たヘリコプターや貨物輸送機などが、物資を厚木基地から山形空港や東北沖にいる空母ロナルド・レーガンなどに輸送した。また、一時使用できなくなった仙台空港の瓦礫の撤去作業など行った。ロナルド・レーガンは原子力空母であり、平時だったらメディアでも問題視されいたことだろう。それを差し引いてもその迅速な救援活動は好印象で伝えられた。
それにしても不思議に思うこと。それは当然やっているだろと思いつく人が行動を起こしていないことだ。甚大な被害を受けた岩手県陸前高田市は民主党の小沢一郎元代表のかつての選挙地盤だった。その小沢氏が岩手入りしたのは3月28日だった。岩手県知事と会談した。それ以前もそれ以降も小沢氏の被災地にかかわる動きはメディアを通しては見えてこない。小沢氏の公式サイトをのぞいても、4月27日に予定していた「第62回小沢一郎政経フォーラム」の延期のお知らせ以外は、被災地での活動が記載されていない。
日本相撲協会は3月24日と25日に東京都内で街頭募金活動をした。25日に上野の松坂屋前で募金箱を首からぶらさげた高見盛が「首が重い」と善意に感謝した様子がテレビで映し出されていたが、それ以外、力士が被災地で炊き出しを行ったというような大相撲協会の救援活動が見えてこない。力士には東北出身者も多いはずである。そのくらいのことは当然していると思ったのだが。
物事にはタイミングというものがある。タイミングが悪いとあらぬ誤解を受けたりする。4月12日、日本政府は福島第1原子力発電所の事故評価をチェルノブイリと同等の「レベル7」に引き上げると発表した。当初は「レベル4」だと発表していた。ここに来て一気に「レベル7」に引き上げた。これが国内外に不信を招いた。「日本政府は原子炉について事実を公開していないのではないか」、「何らかの事故に対する隠蔽工作があったのではないか」・・・。結果的に、「やはり日本政府は隠していたのか」との不信を煽る結果になった。
もう一つ、ネーミングの問題がある。地震が発生した3月11日、気象庁はこの地震を「東北地方太平洋沖地震」と命名した。その後、日本政府は4月1日の閣議で震災の名称を「東日本大震災」とすることで了解した。新聞やテレビはこれ以降、「東日本大震災」の名称に統一した。政府とすれば、広範囲な名称で激甚災害の大きさを強調した方が今後復興に向けた取り組みで行いやすいと判断したようだ。ところが、これが海外からすると「日本の東半分は地震でやられた」との印象を与えている。今回の震災では原発事故とセットで被害を受けたとのイメージもあり、日本海側の東北地方や北海道などでも外国人旅行客が激減するなど風評被害が起きている。
震災をめぐる一連の動きで感じるのは、情報の発信力やコミュニケーション能力の落差である。発表のタイミングや、情報の伝え方は誤解や過剰反応を生む原因にもなる。逆に、うまく伝えれば評価を上げたり、汚名返上にもなりうる。野球賭博や八百長問題があったとしても、大相撲協会は力士を被災地に派遣して、避難所でちゃんこ鍋の炊き出しなどの救援活動をすると喜ばれるのではないだろうか。
⇒24日(日)朝・金沢の天気 はれ
 震災後から始まった外国人の帰国ラッシュ。身近でも、能登半島の観光施設で働いていたアメリカ人女性が最近タイに移った。両親から勧められたらしい。「日本にいては危ない」と。悲惨な津波の様子や原発事故は世界中のテレビで繰り返し流れている。それを視聴すれば、普通の親だった日本にいる娘や息子の身を案じるだろう。まして、政府が帰国を勧めれば、在日外国人の日本脱出は当然の成り行きだ。ただ、そこから浮き上がってくる問題がある。
震災後から始まった外国人の帰国ラッシュ。身近でも、能登半島の観光施設で働いていたアメリカ人女性が最近タイに移った。両親から勧められたらしい。「日本にいては危ない」と。悲惨な津波の様子や原発事故は世界中のテレビで繰り返し流れている。それを視聴すれば、普通の親だった日本にいる娘や息子の身を案じるだろう。まして、政府が帰国を勧めれば、在日外国人の日本脱出は当然の成り行きだ。ただ、そこから浮き上がってくる問題がある。 東北太平洋側のテレビ局記者・カメラマンはまさに「戦場のカメラマン」状態だと思う。おそらく毎日が「悲惨な事故現場」での取材の連続だろう。私自信も記者時代(新聞、テレビ)に自殺、交通死亡事故、水難事故など人が死ぬという現場を取材してきた。今回の東日本大震災の映像をテレビで見るたびに、遺体は映し出されてはいないものの、当時の現場がフラッシュバックで蘇ってくる。「現場」というのもはそれほど心に深く刻まれ、ときに連想で追いかけてくる。
東北太平洋側のテレビ局記者・カメラマンはまさに「戦場のカメラマン」状態だと思う。おそらく毎日が「悲惨な事故現場」での取材の連続だろう。私自信も記者時代(新聞、テレビ)に自殺、交通死亡事故、水難事故など人が死ぬという現場を取材してきた。今回の東日本大震災の映像をテレビで見るたびに、遺体は映し出されてはいないものの、当時の現場がフラッシュバックで蘇ってくる。「現場」というのもはそれほど心に深く刻まれ、ときに連想で追いかけてくる。 私が柏崎市を取材に訪れたのは震災から3ヵ月余りたった10月下旬だった。住宅街には倒壊したままの家屋が散見され、メインストリートの駅前の商店街の歩道はあちこちでひずみが残っていて歩きにくかった=写真=。復旧半ばという印象だった。能登半島地震の復旧に比べ、そのテンポの遅さを感じたのが正直な印象だった。事実、取材した被災者の人たちも「原発対応に追われ、復旧に行政の目が行き届いていない」と不満を述べていた。当時のニュースの露出も原発関連が先にあり、後に震災関連という順位だったと記憶している。
私が柏崎市を取材に訪れたのは震災から3ヵ月余りたった10月下旬だった。住宅街には倒壊したままの家屋が散見され、メインストリートの駅前の商店街の歩道はあちこちでひずみが残っていて歩きにくかった=写真=。復旧半ばという印象だった。能登半島地震の復旧に比べ、そのテンポの遅さを感じたのが正直な印象だった。事実、取材した被災者の人たちも「原発対応に追われ、復旧に行政の目が行き届いていない」と不満を述べていた。当時のニュースの露出も原発関連が先にあり、後に震災関連という順位だったと記憶している。 こうした被災者の声は誇張ではなく、感じたままを吐露したものだ。そして、阪神淡路大震災や新潟県中越地震など震災のたびに繰り返されてきた被災者の意見だろうと想像する。
こうした被災者の声は誇張ではなく、感じたままを吐露したものだ。そして、阪神淡路大震災や新潟県中越地震など震災のたびに繰り返されてきた被災者の意見だろうと想像する。 震災から3ヵ月後、被災地を取材に訪れた。住宅街には倒壊したままの家屋が散見され、柏崎駅前の商店街の歩道はあちこちでひずみが残っていて歩きにくかった。復旧半ばという印象だった。コミュニティー放送「FMピッカラ」はそうした商店街の一角にあった。祝日の午前の静けさを破る震度6強の揺れがあったのは午前10時13分ごろ。その1分45秒後には、「お聞きの放送は76.3メガヘルツ。ただいま大きな揺れを感じましたが、皆さんは大丈夫ですか」と緊急放送に入った。午前11時から始まるレギュラーの生番組の準備をしていたタイミングだったので立ち上がりは速かった。
震災から3ヵ月後、被災地を取材に訪れた。住宅街には倒壊したままの家屋が散見され、柏崎駅前の商店街の歩道はあちこちでひずみが残っていて歩きにくかった。復旧半ばという印象だった。コミュニティー放送「FMピッカラ」はそうした商店街の一角にあった。祝日の午前の静けさを破る震度6強の揺れがあったのは午前10時13分ごろ。その1分45秒後には、「お聞きの放送は76.3メガヘルツ。ただいま大きな揺れを感じましたが、皆さんは大丈夫ですか」と緊急放送に入った。午前11時から始まるレギュラーの生番組の準備をしていたタイミングだったので立ち上がりは速かった。 被災地に放送が果たす役割は大きいが、なんといってもインフラの整備だ。テレビを視聴できるようにすることだ。2007年3月25日、震度6強の能登半島地震では全体で避難住民は2100人余りに及んだ。多くの住民は避難所でテレビやラジオのメディアと接触することになった。注目すべきことがった、被害が大きかった輪島市門前町を含め45ヵ所の避難所すべてにテレビが完備されていたことだ=写真=。地震で屋根のテレビアンテナは傾き、壊れたテレビもあったはず。一体誰が。
被災地に放送が果たす役割は大きいが、なんといってもインフラの整備だ。テレビを視聴できるようにすることだ。2007年3月25日、震度6強の能登半島地震では全体で避難住民は2100人余りに及んだ。多くの住民は避難所でテレビやラジオのメディアと接触することになった。注目すべきことがった、被害が大きかった輪島市門前町を含め45ヵ所の避難所すべてにテレビが完備されていたことだ=写真=。地震で屋根のテレビアンテナは傾き、壊れたテレビもあったはず。一体誰が。 2007年3月25日の能登半島地震から4年になる。現地でのボンラティア活動でも上記と同じ思いをした。各地からさまざま善意が届けられる。しかし、それを受ける現地の状況が理解されていないために、返って混乱を招いている。私が目撃した一つの例を述べる。被災者の避難所には毎日、新聞各紙がどっさりと届けられる。ところが、避難所となっている地区の集会場は体育館のように大きくはない。被災者は肩を寄せ合っている状態だ。そこに新聞が山積みされても、まず新聞を広げて読むスペースが十分にない。しかも、新聞を広げても被災者が欲しい情報、たとえば回診や被災相談などの細かな情報は掲載されていない。読まれない新聞が日々どっさりとたまる。それを廃棄場所に持って行き始末するのはボランティアの役目だった。
2007年3月25日の能登半島地震から4年になる。現地でのボンラティア活動でも上記と同じ思いをした。各地からさまざま善意が届けられる。しかし、それを受ける現地の状況が理解されていないために、返って混乱を招いている。私が目撃した一つの例を述べる。被災者の避難所には毎日、新聞各紙がどっさりと届けられる。ところが、避難所となっている地区の集会場は体育館のように大きくはない。被災者は肩を寄せ合っている状態だ。そこに新聞が山積みされても、まず新聞を広げて読むスペースが十分にない。しかも、新聞を広げても被災者が欲しい情報、たとえば回診や被災相談などの細かな情報は掲載されていない。読まれない新聞が日々どっさりとたまる。それを廃棄場所に持って行き始末するのはボランティアの役目だった。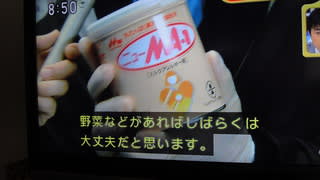 健常者でも障がい者で同じようにマスメディアから情報を得ることをユニバーサル・サービスという。内閣の、たとえば総理や官房長官の会見では、小画面に手話通訳者が出ている。会見場に手話通訳があることで、聴覚障がい者がリアルタイムでテレビから情報を得ることができる。今回の震災は原発事故と連動したため、メディアによるリアルタイムの放送に被災者の耳目が集まる。内閣の伝えようとする意志が見える。災害会見の手話放送はこれ以降、定番化するのではないだろうか。
健常者でも障がい者で同じようにマスメディアから情報を得ることをユニバーサル・サービスという。内閣の、たとえば総理や官房長官の会見では、小画面に手話通訳者が出ている。会見場に手話通訳があることで、聴覚障がい者がリアルタイムでテレビから情報を得ることができる。今回の震災は原発事故と連動したため、メディアによるリアルタイムの放送に被災者の耳目が集まる。内閣の伝えようとする意志が見える。災害会見の手話放送はこれ以降、定番化するのではないだろうか。 そのころ、能登半島の輪島市で記者活動をしていた。デスクから電話があり、輪島漁港に行ってみると、足元まで波が来て、危うく逃げ遅れるところだった。1枚だけ撮った、渦に飲み込まれる寸前の漁船の写真は翌日の一面を飾った。2004年にテレビ局を退職し、大学の地域連携コーディネーターという仕事をしている。2007年3月25日の能登半島地震(震度6強)、翌日26日に被害がもっとも大きかった輪島市門前町に現地入りした。そこで見たある光景がきっかけで、「震災とメディア」をテーマに調査研究を実施することになる。
そのころ、能登半島の輪島市で記者活動をしていた。デスクから電話があり、輪島漁港に行ってみると、足元まで波が来て、危うく逃げ遅れるところだった。1枚だけ撮った、渦に飲み込まれる寸前の漁船の写真は翌日の一面を飾った。2004年にテレビ局を退職し、大学の地域連携コーディネーターという仕事をしている。2007年3月25日の能登半島地震(震度6強)、翌日26日に被害がもっとも大きかった輪島市門前町に現地入りした。そこで見たある光景がきっかけで、「震災とメディア」をテーマに調査研究を実施することになる。