2月25日に福島市で開かれた三井物産環境基金交流会シンポジウムは、除染と復興、放射能と人の心情、安心と安全のパーセプションギャップなど問題が凝縮されていて、迫力のある内容だった。パネル討論が終わり、さらに分科会=写真=に出席した。テーマは「除染と健康、放射能と対峙するには」。放射能の土壌や健康への影響、そして除染の状況、今後の課題について、鈴木元・国際医療福祉大学教授、野中昌法教授が専門家の立場から口火を切った。
放射線リスクは「安全のお墨付き」より「値ごろ感」
 鈴木教授の専門は放射線病理、放射線疫学。最初に「低線量遷延被ばく、内部被ばくの健康リスクとどう付き合うか」と題して話した。「遷延被ばく」とは、福島第一原発の事故のように、環境中にばらまかれた放射性降下物からのゆっくりとした被ばくのこと。「内部被ばく」は放射性物質が含まれている飲み物や食べ物、空気体内に摂取したり吸ったりすることで起きる被ばくのこと。鈴木教授は、放射線リスクは「ある」「ない」で論じられるが、この世にゼロリスクはない。「リスクは低ければ低いほどよい」と一般的に認識されるているが、低めるに当たり失うものを考慮しないと、誤った価値判断に陥る。「低線量被ばく、内部被ばくは、急性被ばく(たとえば原爆による被ばく)よりリスクが何百倍も高い」との話が広まっているが、これを裏付ける疫学的なデータはない、と述べた。以上の点から、専門家としては「安全のお墨付き」というものを与えることはできないが、放射線リスクの「値ごろ感」というものを伝えることができる。そのために、「個々人、あるいは地域のみなさんに『受容レベル』を価値判断するための材料を提供できる」と慎重な言い回しで語った。
鈴木教授の専門は放射線病理、放射線疫学。最初に「低線量遷延被ばく、内部被ばくの健康リスクとどう付き合うか」と題して話した。「遷延被ばく」とは、福島第一原発の事故のように、環境中にばらまかれた放射性降下物からのゆっくりとした被ばくのこと。「内部被ばく」は放射性物質が含まれている飲み物や食べ物、空気体内に摂取したり吸ったりすることで起きる被ばくのこと。鈴木教授は、放射線リスクは「ある」「ない」で論じられるが、この世にゼロリスクはない。「リスクは低ければ低いほどよい」と一般的に認識されるているが、低めるに当たり失うものを考慮しないと、誤った価値判断に陥る。「低線量被ばく、内部被ばくは、急性被ばく(たとえば原爆による被ばく)よりリスクが何百倍も高い」との話が広まっているが、これを裏付ける疫学的なデータはない、と述べた。以上の点から、専門家としては「安全のお墨付き」というものを与えることはできないが、放射線リスクの「値ごろ感」というものを伝えることができる。そのために、「個々人、あるいは地域のみなさんに『受容レベル』を価値判断するための材料を提供できる」と慎重な言い回しで語った。
いくつかの事例が紹介された。原爆による人体への影響を調査している放射線影響研究所(広島市)による「原爆被爆生存者調査結果」によると、肺がんや消化器がんなどの固形がんは、被爆後15年ごろから増え始め、現在も続いている。被ばく線量とがんのリスクについてはこのようなデータがある。日本人男性ががんで死亡する確率は30%とされる、10歳の男の子が100ミリ・シーベルトの急性被ばくをしたとすると、30%だった生涯のがん死亡確率が32.1%、つまりプラス2.1%になる。女の子だと、20%だったのが22.2%になる。被曝量が10ミリ・シーベルトだと、その10分の1に減り、男の子は30%が30.2%、女の子は20%が20.2%になる。50歳の男性と10歳の男の子を比べると、7倍ぐらいの差になり、子供のほうがリスクが高いという評価が出ている。つまり、リスクを考えていくとき、どんなに小さい線量になっても、線量に応じてリスクは残ると考ええていると鈴木教授は述べた。
福島に関連して以下言及した。放射性セシウムのセシウム134、セシウム137は、それぞれの半減期が2年、30年と長いため、環境中に長くとどまる。ただ、雨風によりセシウムが表土から流出するので、実際の環境中から半減する期間は、30年よりはずっと短くなること。そのセシウムは体に入ると、カリウムと同じような動きをし、消化管から吸収され、細胞に取り込まれる。代謝によって排せつされる。尿中に90%ほどが排泄され、大人だと100日で半分が排泄される。子供の場合は早くて、2週から3週で半分が排泄されることがわかっている。
海外の事例が紹介示された。インドのケララ地方は、モナザイトという岩石から放射線が出て、高いガンマ線による被ばくがある地区。年間平均4ミリ・シーベルトぐらいで、多い人では1年間に70ミリ・シーベルトを被ばくする。ところが疫学調査が進められているが、ガンのリスクの上昇は認められていない。10年目の途中経過の報告なので、今後の報告が待たれる。
「悲しい現実」として紹介されたのが、チェルノブイリ事故後の精神健康に対する影響。旧ソ連では自殺が増加し、心因性疾患が増加したと報告されている。また、旧ソ連だけではなくて、ヨーロッパ各国で堕胎が増加したという報告(一説にポーランドだけで40万人)がある。放射線に対する過剰な不安が、国民を不合理な行動に走らせ、そして堕胎という生命損失を招いた。福島でそのようなことがないように情報を提供していきたい、と。
最後にキーワードは「リスクの認知と受容」だと述べた。年間5ミリ・シーベルトの被曝による健康への影響は、10歳の子供が生涯にがんで死亡するリスクが最大で0.1%上昇するといった大きさ。国際放射線防護委員会(ICRP)は、低線量の遷延被曝の場合、リスクは半分になると言っており、0.05%ということになる。そうなると、生涯がん死亡リスクは、10歳の男の子で、30%が30.05%になる、リスク上昇はそのくらい、と。むしろ、低線量被ばくのリスクを恐れて、園児に外遊びさせないということになれば、肥満によるガンのリスクが高まる。野菜不足も栄養面でマイナスだ。家にこもることも、心の健康を害したり、家族やコミュニティの崩壊を招く。リスクを自分なりに整理して、それをコントロールする知恵を身に付けてほしい。それが、環境中の放射線レベルを低減しながら、生活を守るということだ。あわてずに、計画的に生きよう、と。
土壌学が専門の野中教授は「福島の90%の農地は除染が必要ないと考える」と述べた。大切なのは、農家が自分の田畑の土壌を「測定すること」の重要性、そして直売所で農産物の放射線測定をして「消費者に伝えること」が大切だ、と。これ以上田畑を汚染させないために、稲わら、落ち葉などを入れて腐植土をつくり、作物への吸収を減じることが可能だと述べた。そして「何百年と引き継がれた肥沃な土づくりを、除染で表層土壌を取り除いたり、深耕したり、天地返しで20㌢より深い土壌と入れ替えることは、農業者が農業を続けられなくすることに等しい」と強調した。
野中教授は「除染よりむしろ大切なのは、事故前より、より良い農業・農村づくりを目指すことだ。それは可能であり、放射能を測って農村を守ること」と話し、「Man has lost the capacity to foresee and to forestall. He’ll end by destroying earth.(未来を見る目を失い現実に先んずるすべを忘れた人間。その行く先は自然の破壊だ)」と、医療と伝道に生きたアルベルト・シュヴァイツァーの言葉を引用して、会場を訪れた農業者を励ました。
⇒1日(金)朝・金沢の天気 はれ
 地震の被災地を訪れたのは2007年3月25日の能登半島地震、同年7月16日の新潟県中越沖地震以来だった。新潟は震度6強の激しい揺れに見舞われた。震源に近く、被害が大きかった柏崎市は原子力発電所の立地場所でもあり、地震と原発がメディアの取材のポイントとなっていた。そんな中で、「情報こそライフライン」と被災者向けの情報に徹底し、24時間の生放送を41日間続けたコミュニティー放送(FM)を取材した。それ以降、毎年、マスメディアの授業では、メディアが被災者と被災地に果たす役割とは何かをテーマに「震災とメディア」の講義を2コマないし3コマを組み入れている。震災から2ヵ月後に訪れた仙台市と気仙沼市は講義の取材のためだった。
地震の被災地を訪れたのは2007年3月25日の能登半島地震、同年7月16日の新潟県中越沖地震以来だった。新潟は震度6強の激しい揺れに見舞われた。震源に近く、被害が大きかった柏崎市は原子力発電所の立地場所でもあり、地震と原発がメディアの取材のポイントとなっていた。そんな中で、「情報こそライフライン」と被災者向けの情報に徹底し、24時間の生放送を41日間続けたコミュニティー放送(FM)を取材した。それ以降、毎年、マスメディアの授業では、メディアが被災者と被災地に果たす役割とは何かをテーマに「震災とメディア」の講義を2コマないし3コマを組み入れている。震災から2ヵ月後に訪れた仙台市と気仙沼市は講義の取材のためだった。 8日に能登半島の七尾市に所要で出かけた。金沢もそうだったが、どんよりと空がかすんでいた。一時雨が降ったが、雨が上がってもどんよりとした土色のかすみが空を覆い、晴れ上がることはなかった=写真=。黄砂がやってきた、と直感した。毎年この季節はかすむのである。ただ、ことしの黄砂は目と鼻に刺激が強いのだ。
8日に能登半島の七尾市に所要で出かけた。金沢もそうだったが、どんよりと空がかすんでいた。一時雨が降ったが、雨が上がってもどんよりとした土色のかすみが空を覆い、晴れ上がることはなかった=写真=。黄砂がやってきた、と直感した。毎年この季節はかすむのである。ただ、ことしの黄砂は目と鼻に刺激が強いのだ。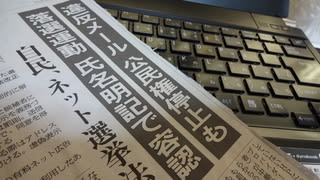 インターネットの活用を選挙で解禁するにあたり、ネックとなっていたのは、現行の公職選挙法は、公示・告示後の選挙期間中は、法律で定められたビラやはがきなどを除き、「文書図画(とが)」を不特定多数に配布することを禁じていたからである。候補者のホームページやツイッターなどソーシャルメディアの発信は、こうした文書図画に相当し、現行では認められていないのだ。
インターネットの活用を選挙で解禁するにあたり、ネックとなっていたのは、現行の公職選挙法は、公示・告示後の選挙期間中は、法律で定められたビラやはがきなどを除き、「文書図画(とが)」を不特定多数に配布することを禁じていたからである。候補者のホームページやツイッターなどソーシャルメディアの発信は、こうした文書図画に相当し、現行では認められていないのだ。 これに関して、現地で共同通信の記者のインタビューを受けた井上氏は「政治的に解決できないことが(両国間で)あるとしたら、僕らみたいなのが穴をあけ、互いの疎通を図ることが必要だ」「第九は平和を望む内容の曲。(演目として)僕から持ちかけ(北朝鮮側が)すんなり乗ってくれた」「音楽だけでなく、できることがある人は何とかつながりを持ち、この国にいろいろな情報を入れてあげないといけない」と話した(8日付・北陸中日新聞)。
これに関して、現地で共同通信の記者のインタビューを受けた井上氏は「政治的に解決できないことが(両国間で)あるとしたら、僕らみたいなのが穴をあけ、互いの疎通を図ることが必要だ」「第九は平和を望む内容の曲。(演目として)僕から持ちかけ(北朝鮮側が)すんなり乗ってくれた」「音楽だけでなく、できることがある人は何とかつながりを持ち、この国にいろいろな情報を入れてあげないといけない」と話した(8日付・北陸中日新聞)。 医薬品のネット販売は一見、選挙運動のネット解禁とイメージがだぶり、規制改革のシンボルのように思える。が、個人的な感想で言えば、「これ以上、国民を薬漬けにするな」との思いもわく。高血圧患者4千万人、高コレステロール血症(高脂血症)3千万人、糖尿病は予備軍含めて2300万人・・・と、日本にはすごい数の「病人」がいる(近藤誠著『医者に殺されない47の心得』より引用)。たとえば、高血圧の基準が、最高血圧の基準は160㎜Hgだったものが、2000年に140に、2008年のメタボ検診では130にまで引き下げられた。50歳を過ぎたら「上が130」というのは一般的な数値なので、たいい高血圧患者にされ、降圧剤を飲んで「治療」するハメになる(同)。その結果として、1988年には降圧剤の売上は2000億円だったものが、2008年には1兆円を超えて、20年間で売上が6倍に伸びた計算だ。
医薬品のネット販売は一見、選挙運動のネット解禁とイメージがだぶり、規制改革のシンボルのように思える。が、個人的な感想で言えば、「これ以上、国民を薬漬けにするな」との思いもわく。高血圧患者4千万人、高コレステロール血症(高脂血症)3千万人、糖尿病は予備軍含めて2300万人・・・と、日本にはすごい数の「病人」がいる(近藤誠著『医者に殺されない47の心得』より引用)。たとえば、高血圧の基準が、最高血圧の基準は160㎜Hgだったものが、2000年に140に、2008年のメタボ検診では130にまで引き下げられた。50歳を過ぎたら「上が130」というのは一般的な数値なので、たいい高血圧患者にされ、降圧剤を飲んで「治療」するハメになる(同)。その結果として、1988年には降圧剤の売上は2000億円だったものが、2008年には1兆円を超えて、20年間で売上が6倍に伸びた計算だ。 シェアにこだわること、それは、そこそこ品質がよいものを低価格で売り、市場の占有率を高めることだ。シェア1番でなければ存在意味がないと、ライバルが現れると価格競争でしのぎを削り、競り勝つ、それが勝利の方程式だった。ところが、2007年に起きたサブプライム問題に端を発したリーマンショック以降、世界的な金融不安が市場を覆い、リスク回避の流れからヨーロッパやアメリカのヘッジファンドなどが円買いに走った。円高にぶれてきて、日本の家電製品も自動車も価格競争という手を打てなくなった。もともと商品はそこそこの品質だったので、韓国や台湾、中国といったメーカーの追い上げを食らうようになる。日本のメーカーは、円高で価格競争ができない分、多機能化することで魅力をアップしようとした。ただ、多機能化の行き過ぎが製品の魅力を低下させることもある。
シェアにこだわること、それは、そこそこ品質がよいものを低価格で売り、市場の占有率を高めることだ。シェア1番でなければ存在意味がないと、ライバルが現れると価格競争でしのぎを削り、競り勝つ、それが勝利の方程式だった。ところが、2007年に起きたサブプライム問題に端を発したリーマンショック以降、世界的な金融不安が市場を覆い、リスク回避の流れからヨーロッパやアメリカのヘッジファンドなどが円買いに走った。円高にぶれてきて、日本の家電製品も自動車も価格競争という手を打てなくなった。もともと商品はそこそこの品質だったので、韓国や台湾、中国といったメーカーの追い上げを食らうようになる。日本のメーカーは、円高で価格競争ができない分、多機能化することで魅力をアップしようとした。ただ、多機能化の行き過ぎが製品の魅力を低下させることもある。 鈴木教授の専門は放射線病理、放射線疫学。最初に「低線量遷延被ばく、内部被ばくの健康リスクとどう付き合うか」と題して話した。「遷延被ばく」とは、福島第一原発の事故のように、環境中にばらまかれた放射性降下物からのゆっくりとした被ばくのこと。「内部被ばく」は放射性物質が含まれている飲み物や食べ物、空気体内に摂取したり吸ったりすることで起きる被ばくのこと。鈴木教授は、放射線リスクは「ある」「ない」で論じられるが、この世にゼロリスクはない。「リスクは低ければ低いほどよい」と一般的に認識されるているが、低めるに当たり失うものを考慮しないと、誤った価値判断に陥る。「低線量被ばく、内部被ばくは、急性被ばく(たとえば原爆による被ばく)よりリスクが何百倍も高い」との話が広まっているが、これを裏付ける疫学的なデータはない、と述べた。以上の点から、専門家としては「安全のお墨付き」というものを与えることはできないが、放射線リスクの「値ごろ感」というものを伝えることができる。そのために、「個々人、あるいは地域のみなさんに『受容レベル』を価値判断するための材料を提供できる」と慎重な言い回しで語った。
鈴木教授の専門は放射線病理、放射線疫学。最初に「低線量遷延被ばく、内部被ばくの健康リスクとどう付き合うか」と題して話した。「遷延被ばく」とは、福島第一原発の事故のように、環境中にばらまかれた放射性降下物からのゆっくりとした被ばくのこと。「内部被ばく」は放射性物質が含まれている飲み物や食べ物、空気体内に摂取したり吸ったりすることで起きる被ばくのこと。鈴木教授は、放射線リスクは「ある」「ない」で論じられるが、この世にゼロリスクはない。「リスクは低ければ低いほどよい」と一般的に認識されるているが、低めるに当たり失うものを考慮しないと、誤った価値判断に陥る。「低線量被ばく、内部被ばくは、急性被ばく(たとえば原爆による被ばく)よりリスクが何百倍も高い」との話が広まっているが、これを裏付ける疫学的なデータはない、と述べた。以上の点から、専門家としては「安全のお墨付き」というものを与えることはできないが、放射線リスクの「値ごろ感」というものを伝えることができる。そのために、「個々人、あるいは地域のみなさんに『受容レベル』を価値判断するための材料を提供できる」と慎重な言い回しで語った。 この地震速報の前後でパネルディカッションが熱気を帯びていた。そのキーワードは「徐前の費用対効果」だった。飯館村村長の菅野典雄氏は、放射能で汚染された土壌の改良、つまり除染に関しては、国家プロジェクトでやってほしいと述べた。つまり、避難している村民が戻ってきて、仕事や生活ができるような環境は、除染が大前提である、と。費用3200億円(20年間)をかけて除染を急いでいる。「放射能とは長い戦いになる。しかし、除染をすれば数値は下がる。これ(除染)をやらなければ避難している村民に戻ろうと言えない」、「それを『費用対効果』で語る政治家がいるのは残念だ」と述べた。
この地震速報の前後でパネルディカッションが熱気を帯びていた。そのキーワードは「徐前の費用対効果」だった。飯館村村長の菅野典雄氏は、放射能で汚染された土壌の改良、つまり除染に関しては、国家プロジェクトでやってほしいと述べた。つまり、避難している村民が戻ってきて、仕事や生活ができるような環境は、除染が大前提である、と。費用3200億円(20年間)をかけて除染を急いでいる。「放射能とは長い戦いになる。しかし、除染をすれば数値は下がる。これ(除染)をやらなければ避難している村民に戻ろうと言えない」、「それを『費用対効果』で語る政治家がいるのは残念だ」と述べた。 福島市に来ている。積雪はJR福島駅周辺で25㌢ほどだろうか=写真=。新聞やテレビのニュースを見ていると、地吹雪や視界不良で磐越自動車道が一時交通止めになったり、山形新幹線が一時立ち往生、南会津町でスキー大会が中止、きょう25日の国公立大学2次試験で会津大学の試験時間を2時間繰り下げたと報じている。
福島市に来ている。積雪はJR福島駅周辺で25㌢ほどだろうか=写真=。新聞やテレビのニュースを見ていると、地吹雪や視界不良で磐越自動車道が一時交通止めになったり、山形新幹線が一時立ち往生、南会津町でスキー大会が中止、きょう25日の国公立大学2次試験で会津大学の試験時間を2時間繰り下げたと報じている。
 「5大シャトー」は、1855年のパリ万国博覧会で、皇帝ナポレオン3世は世界中から集まる訪問客に向けて、フランスのボルドーワイン(赤)の展示に格付けが必要だと考えた。 そこで、ボルドー・メドック地区で、ワイン仲買人が評判や市場価格に従って、ワインをランク付けした。その格付けで4つのシャトーに「第一級」の称号を与えられた。それ以来、ボルドーワインの公式格付けとなった。その4つとは「Ch.Lafite-Rothschild(シャトー・ラフィット・ロートシルト)」、「Ch.Margaux(シャトー・マルゴー)」、「Ch.Latour(シャトー・ラトゥール)」、「Ch.Haut Brion(シャトー・オー・ブリオン)」のこと。これに、1973年の格付けで昇格した、「Ch.Mouton Rothschild(シャトー・ムートン・ロスシルド)」を加え、これら5つが世界トップクラス・シャトーといわれるようになった。インターネットで調べてみても、それぞれ1本5万円は下らない。ちなみの、今回の講座の会費は2万3千円。グラスに1杯ずつ5大シャトーが飲めるのだから。一生に一度のチャンスと思えば、案外お得かも知れない。
「5大シャトー」は、1855年のパリ万国博覧会で、皇帝ナポレオン3世は世界中から集まる訪問客に向けて、フランスのボルドーワイン(赤)の展示に格付けが必要だと考えた。 そこで、ボルドー・メドック地区で、ワイン仲買人が評判や市場価格に従って、ワインをランク付けした。その格付けで4つのシャトーに「第一級」の称号を与えられた。それ以来、ボルドーワインの公式格付けとなった。その4つとは「Ch.Lafite-Rothschild(シャトー・ラフィット・ロートシルト)」、「Ch.Margaux(シャトー・マルゴー)」、「Ch.Latour(シャトー・ラトゥール)」、「Ch.Haut Brion(シャトー・オー・ブリオン)」のこと。これに、1973年の格付けで昇格した、「Ch.Mouton Rothschild(シャトー・ムートン・ロスシルド)」を加え、これら5つが世界トップクラス・シャトーといわれるようになった。インターネットで調べてみても、それぞれ1本5万円は下らない。ちなみの、今回の講座の会費は2万3千円。グラスに1杯ずつ5大シャトーが飲めるのだから。一生に一度のチャンスと思えば、案外お得かも知れない。