「呪縛」とは、まじないをかけて動けなくすること。あるいは、心理的な強制によって、人の自由を束縛することの意味である。日本人ほど、シェア(市場占有率)にこだわり、自ら呪縛されている国民はないのではないかと最近考えている。
 シェアにこだわること、それは、そこそこ品質がよいものを低価格で売り、市場の占有率を高めることだ。シェア1番でなければ存在意味がないと、ライバルが現れると価格競争でしのぎを削り、競り勝つ、それが勝利の方程式だった。ところが、2007年に起きたサブプライム問題に端を発したリーマンショック以降、世界的な金融不安が市場を覆い、リスク回避の流れからヨーロッパやアメリカのヘッジファンドなどが円買いに走った。円高にぶれてきて、日本の家電製品も自動車も価格競争という手を打てなくなった。もともと商品はそこそこの品質だったので、韓国や台湾、中国といったメーカーの追い上げを食らうようになる。日本のメーカーは、円高で価格競争ができない分、多機能化することで魅力をアップしようとした。ただ、多機能化の行き過ぎが製品の魅力を低下させることもある。
シェアにこだわること、それは、そこそこ品質がよいものを低価格で売り、市場の占有率を高めることだ。シェア1番でなければ存在意味がないと、ライバルが現れると価格競争でしのぎを削り、競り勝つ、それが勝利の方程式だった。ところが、2007年に起きたサブプライム問題に端を発したリーマンショック以降、世界的な金融不安が市場を覆い、リスク回避の流れからヨーロッパやアメリカのヘッジファンドなどが円買いに走った。円高にぶれてきて、日本の家電製品も自動車も価格競争という手を打てなくなった。もともと商品はそこそこの品質だったので、韓国や台湾、中国といったメーカーの追い上げを食らうようになる。日本のメーカーは、円高で価格競争ができない分、多機能化することで魅力をアップしようとした。ただ、多機能化の行き過ぎが製品の魅力を低下させることもある。
むしろ、多機能より単純で使いやすい方がその機能のチカラというものを発揮させるものだ。海外が住む友人から、「日本製はやたらと多機能で値段が高い。韓国のサムスンなどは求められている、あるいは必要な機能に絞って販売している。結果、使いやすい」と聞いたことがある。世界の人々は日本人ほど器用でない。その日本人でさえ、地上デジタルテレビのリモコンに今でも辟易している。デジタルカメラもボタンが多く、静止画を撮ろうしして、動画撮影になったりすることがままある。日本企業にめぼしい技術革新もなかった。リーマンショックから5、6年が過ぎて、日本製品は海外で随分とシェアを落とした。
ここで最近、よく話題になるのが、日本製品とドイツ製品はどこで違いが出てきたのか、ということである。『日経ビジネス』(2013年2月25日)の記事が興味深かった。ドイツ人実業家ハーマン・サイモン氏の言葉を引用して、「日本企業はブランドや高級感の創出力に欠け、技術的な強みを活用しきれていない」と。つまり、「ソニーやパナソニックがなぜ10~20%上乗せの価格で売り、消費者を引きつけることができないのか」「市場シェアを追求する追及する限り、値下げによる価格競争に巻き込まれざるを得ない」と。シュアを落としてでもブランドイメージを創造すべきだというのだ。知名度の高さとブランドイメージを混同してはならない。ドイツの中小企業は高価格で売ることに努力を惜しまなかった。シェアより、利益にこだわったからだ。
シェアにこだわるのは何も工業製品だけと限らない。これは直観だが、国内ではマスメディアがこのシェアの罠に落ちている。部数というシェア争いを新聞社は演じている。かつて広告費はテレビに食われ、いまはインターネット広告に浸食されている。それでも、何とか各社が新聞を発行し続けることができているのは宅配制度という強固な販売システムに支えられているからだろう。では、紙面の中身はどうか。1面から社会面まで各紙ほとんど同じなのである。我先にセンセーショナリズムに走っている。しかも、うがった見方をすれば、発表を先取りすることを「スクープ」と称している。ここのところ、昨今の新しい日銀総裁の人事案件などはその典型だろう。数日経れば発表される記事を、各社血まなこになって先を争い追いかけた。
日経新聞はもともと別だが、全国紙のうちの1紙ぐらいは「クオリティペーパーを目指す」と宣言して、発表の先取り型から独自の調査報道に重心を置く新聞社が現れないものだろうか。ただ、報道現場は賛成しても、販売や広告の現場が反対するかもしれない。「シェアを落とす」と。「読者はテレビやネットに出たニュースを最終的に新聞で確認したいと思っている。新聞はニュースのアンカーだ」として、独自の調査報道路線には承服しないだろう。
シェア(視聴率)を取れる番組とは何かを追求しているテレビ局も同じだ。大衆迎合だと視聴者から言われても、子どもに見せたくない番組だと言われても、ゴールデン番組はお笑いタレントが占める。番組タイトルは違うが、どこもコンセプトはどこかよく似ている。短いキャッチフレーズでお笑いを取り、視聴者も満足している。そして、いま、日本国中がB級グルメ選手権ばやりだ。A級グルメを目指さない風潮になった。A級では人が集まらないからだ。
シェアには、市場に対する影響力や発言力の拡大や、顧客の囲い込みといったメリットがあるものの、世界的な競争の中でシェアは崩されやすく、消耗度が高い。ドイツ企業はシェアより利益をどう高めるかを模索した。
⇒2日(土)朝・金沢の天気 くもり
 きょう(25日)朝、自宅の庭の梅の木を見ると満開になっていた=写真=。金沢はすっかり春めいてきた。ただし、肌寒い。朝、青空駐車場の車のガラスは凍りついた状態になっていて、しばらく車を温めた。9時ごろだった。突然、ホーペケキョとウグイスの鳴き声が聞こえた。ぎこちない、初鳴きだ。
きょう(25日)朝、自宅の庭の梅の木を見ると満開になっていた=写真=。金沢はすっかり春めいてきた。ただし、肌寒い。朝、青空駐車場の車のガラスは凍りついた状態になっていて、しばらく車を温めた。9時ごろだった。突然、ホーペケキョとウグイスの鳴き声が聞こえた。ぎこちない、初鳴きだ。
 これに対して、18日のメディア各社のネットニュースでは、中国国防省報道事務局は18日、中国海軍艦艇による海上自衛隊護衛艦へのレーダー照射問題で、中国軍幹部が射撃管制用レーダー照射を認めたとする日本の一部メディアの報道について「事実に合致しない」と改めて否定する談話を発表した、とある。さらに、同局は「日本側がマスコミを使って大げさに宣伝し、中国軍の面目をつぶして、国際社会を誤解させるのは、下心があってのことだ」と非難。「日本側は深く反省し、無責任な言論の発表をやめ、実際の行動で両国関係の大局を守るべきだ」と求めた、というのだ。
これに対して、18日のメディア各社のネットニュースでは、中国国防省報道事務局は18日、中国海軍艦艇による海上自衛隊護衛艦へのレーダー照射問題で、中国軍幹部が射撃管制用レーダー照射を認めたとする日本の一部メディアの報道について「事実に合致しない」と改めて否定する談話を発表した、とある。さらに、同局は「日本側がマスコミを使って大げさに宣伝し、中国軍の面目をつぶして、国際社会を誤解させるのは、下心があってのことだ」と非難。「日本側は深く反省し、無責任な言論の発表をやめ、実際の行動で両国関係の大局を守るべきだ」と求めた、というのだ。 次に翌年10月、「里山マイスター」育成プログラムという社会人の人材養成カリキュラムをつくった。文部科学省の科学技術振興調整費という委託金をベースにした。これで、常駐するが教員スタッフ(博士研究員ら)が一気に5人増えた。対外的には、「地域づくりは人づくり」と言い、学内的には「フィールド研究」といい、地域貢献と学内研究のバランスを取った。当初予想しなかったのだが、このプログラム(5年間)の修了生62人を出すことで、大学は大きなチカラ=協力者を得たことになった。この62人は卒業課題論文を仕上げ、パワーポイントでの発表を通じて審査員の評価を得、またプレゼンテーション能力を磨いた若者たち(45歳以下)である。そして、その後もアクティブに活動している。
次に翌年10月、「里山マイスター」育成プログラムという社会人の人材養成カリキュラムをつくった。文部科学省の科学技術振興調整費という委託金をベースにした。これで、常駐するが教員スタッフ(博士研究員ら)が一気に5人増えた。対外的には、「地域づくりは人づくり」と言い、学内的には「フィールド研究」といい、地域貢献と学内研究のバランスを取った。当初予想しなかったのだが、このプログラム(5年間)の修了生62人を出すことで、大学は大きなチカラ=協力者を得たことになった。この62人は卒業課題論文を仕上げ、パワーポイントでの発表を通じて審査員の評価を得、またプレゼンテーション能力を磨いた若者たち(45歳以下)である。そして、その後もアクティブに活動している。 日本海に突き出た能登半島に金沢大学の能登学舎(石川県珠洲市)がある。しかも、地元の人たちが「サザエの尻尾の先」と呼ぶ、半島の先端である。ここに廃校となっていた小学校施設を市から無償で借り受けて、平成18年から研究交流拠点として活用している。学舎の窓からは、日によって海の向こうに立山連峰のパノラマが展開する。この絶好のロケーションで、環境に配慮した農林漁業をテーマに社会人のための人材育成が行われている。
日本海に突き出た能登半島に金沢大学の能登学舎(石川県珠洲市)がある。しかも、地元の人たちが「サザエの尻尾の先」と呼ぶ、半島の先端である。ここに廃校となっていた小学校施設を市から無償で借り受けて、平成18年から研究交流拠点として活用している。学舎の窓からは、日によって海の向こうに立山連峰のパノラマが展開する。この絶好のロケーションで、環境に配慮した農林漁業をテーマに社会人のための人材育成が行われている。 地震の被災地を訪れたのは2007年3月25日の能登半島地震、同年7月16日の新潟県中越沖地震以来だった。新潟は震度6強の激しい揺れに見舞われた。震源に近く、被害が大きかった柏崎市は原子力発電所の立地場所でもあり、地震と原発がメディアの取材のポイントとなっていた。そんな中で、「情報こそライフライン」と被災者向けの情報に徹底し、24時間の生放送を41日間続けたコミュニティー放送(FM)を取材した。それ以降、毎年、マスメディアの授業では、メディアが被災者と被災地に果たす役割とは何かをテーマに「震災とメディア」の講義を2コマないし3コマを組み入れている。震災から2ヵ月後に訪れた仙台市と気仙沼市は講義の取材のためだった。
地震の被災地を訪れたのは2007年3月25日の能登半島地震、同年7月16日の新潟県中越沖地震以来だった。新潟は震度6強の激しい揺れに見舞われた。震源に近く、被害が大きかった柏崎市は原子力発電所の立地場所でもあり、地震と原発がメディアの取材のポイントとなっていた。そんな中で、「情報こそライフライン」と被災者向けの情報に徹底し、24時間の生放送を41日間続けたコミュニティー放送(FM)を取材した。それ以降、毎年、マスメディアの授業では、メディアが被災者と被災地に果たす役割とは何かをテーマに「震災とメディア」の講義を2コマないし3コマを組み入れている。震災から2ヵ月後に訪れた仙台市と気仙沼市は講義の取材のためだった。 8日に能登半島の七尾市に所要で出かけた。金沢もそうだったが、どんよりと空がかすんでいた。一時雨が降ったが、雨が上がってもどんよりとした土色のかすみが空を覆い、晴れ上がることはなかった=写真=。黄砂がやってきた、と直感した。毎年この季節はかすむのである。ただ、ことしの黄砂は目と鼻に刺激が強いのだ。
8日に能登半島の七尾市に所要で出かけた。金沢もそうだったが、どんよりと空がかすんでいた。一時雨が降ったが、雨が上がってもどんよりとした土色のかすみが空を覆い、晴れ上がることはなかった=写真=。黄砂がやってきた、と直感した。毎年この季節はかすむのである。ただ、ことしの黄砂は目と鼻に刺激が強いのだ。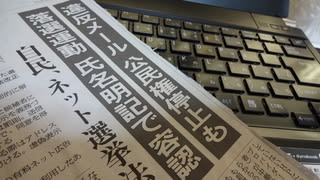 インターネットの活用を選挙で解禁するにあたり、ネックとなっていたのは、現行の公職選挙法は、公示・告示後の選挙期間中は、法律で定められたビラやはがきなどを除き、「文書図画(とが)」を不特定多数に配布することを禁じていたからである。候補者のホームページやツイッターなどソーシャルメディアの発信は、こうした文書図画に相当し、現行では認められていないのだ。
インターネットの活用を選挙で解禁するにあたり、ネックとなっていたのは、現行の公職選挙法は、公示・告示後の選挙期間中は、法律で定められたビラやはがきなどを除き、「文書図画(とが)」を不特定多数に配布することを禁じていたからである。候補者のホームページやツイッターなどソーシャルメディアの発信は、こうした文書図画に相当し、現行では認められていないのだ。 これに関して、現地で共同通信の記者のインタビューを受けた井上氏は「政治的に解決できないことが(両国間で)あるとしたら、僕らみたいなのが穴をあけ、互いの疎通を図ることが必要だ」「第九は平和を望む内容の曲。(演目として)僕から持ちかけ(北朝鮮側が)すんなり乗ってくれた」「音楽だけでなく、できることがある人は何とかつながりを持ち、この国にいろいろな情報を入れてあげないといけない」と話した(8日付・北陸中日新聞)。
これに関して、現地で共同通信の記者のインタビューを受けた井上氏は「政治的に解決できないことが(両国間で)あるとしたら、僕らみたいなのが穴をあけ、互いの疎通を図ることが必要だ」「第九は平和を望む内容の曲。(演目として)僕から持ちかけ(北朝鮮側が)すんなり乗ってくれた」「音楽だけでなく、できることがある人は何とかつながりを持ち、この国にいろいろな情報を入れてあげないといけない」と話した(8日付・北陸中日新聞)。 医薬品のネット販売は一見、選挙運動のネット解禁とイメージがだぶり、規制改革のシンボルのように思える。が、個人的な感想で言えば、「これ以上、国民を薬漬けにするな」との思いもわく。高血圧患者4千万人、高コレステロール血症(高脂血症)3千万人、糖尿病は予備軍含めて2300万人・・・と、日本にはすごい数の「病人」がいる(近藤誠著『医者に殺されない47の心得』より引用)。たとえば、高血圧の基準が、最高血圧の基準は160㎜Hgだったものが、2000年に140に、2008年のメタボ検診では130にまで引き下げられた。50歳を過ぎたら「上が130」というのは一般的な数値なので、たいい高血圧患者にされ、降圧剤を飲んで「治療」するハメになる(同)。その結果として、1988年には降圧剤の売上は2000億円だったものが、2008年には1兆円を超えて、20年間で売上が6倍に伸びた計算だ。
医薬品のネット販売は一見、選挙運動のネット解禁とイメージがだぶり、規制改革のシンボルのように思える。が、個人的な感想で言えば、「これ以上、国民を薬漬けにするな」との思いもわく。高血圧患者4千万人、高コレステロール血症(高脂血症)3千万人、糖尿病は予備軍含めて2300万人・・・と、日本にはすごい数の「病人」がいる(近藤誠著『医者に殺されない47の心得』より引用)。たとえば、高血圧の基準が、最高血圧の基準は160㎜Hgだったものが、2000年に140に、2008年のメタボ検診では130にまで引き下げられた。50歳を過ぎたら「上が130」というのは一般的な数値なので、たいい高血圧患者にされ、降圧剤を飲んで「治療」するハメになる(同)。その結果として、1988年には降圧剤の売上は2000億円だったものが、2008年には1兆円を超えて、20年間で売上が6倍に伸びた計算だ。 シェアにこだわること、それは、そこそこ品質がよいものを低価格で売り、市場の占有率を高めることだ。シェア1番でなければ存在意味がないと、ライバルが現れると価格競争でしのぎを削り、競り勝つ、それが勝利の方程式だった。ところが、2007年に起きたサブプライム問題に端を発したリーマンショック以降、世界的な金融不安が市場を覆い、リスク回避の流れからヨーロッパやアメリカのヘッジファンドなどが円買いに走った。円高にぶれてきて、日本の家電製品も自動車も価格競争という手を打てなくなった。もともと商品はそこそこの品質だったので、韓国や台湾、中国といったメーカーの追い上げを食らうようになる。日本のメーカーは、円高で価格競争ができない分、多機能化することで魅力をアップしようとした。ただ、多機能化の行き過ぎが製品の魅力を低下させることもある。
シェアにこだわること、それは、そこそこ品質がよいものを低価格で売り、市場の占有率を高めることだ。シェア1番でなければ存在意味がないと、ライバルが現れると価格競争でしのぎを削り、競り勝つ、それが勝利の方程式だった。ところが、2007年に起きたサブプライム問題に端を発したリーマンショック以降、世界的な金融不安が市場を覆い、リスク回避の流れからヨーロッパやアメリカのヘッジファンドなどが円買いに走った。円高にぶれてきて、日本の家電製品も自動車も価格競争という手を打てなくなった。もともと商品はそこそこの品質だったので、韓国や台湾、中国といったメーカーの追い上げを食らうようになる。日本のメーカーは、円高で価格競争ができない分、多機能化することで魅力をアップしようとした。ただ、多機能化の行き過ぎが製品の魅力を低下させることもある。