世界農業遺産国際会議(5月29日-6月1日)を終えた6月8日、金沢大学も関わっている能登の地域塾「ふるさと未来塾」で世界農業遺産(GIAHS)と能登のかかわりについて講義する機会があった。2011年6月、北京で開催されたGIAHS国際フォーラムで「能登の里山里海」と「トキと共生する佐渡の里山」が認定を受けた。講義では、あれから2年能登にはどのような変化起きたのか、社会人塾生たちと考えた。
クーハフカン氏が「幸せな農家だ」と称賛した能登の青年のこと
講義の流れは大まかに、1.能登における金沢大学の人材養成の取り組みとGIAHSについて、2.SatoyamaとNotoは国際的に通用する言葉、3.能登のどこが「国際評価」を受けているのか、4.「GIAHSの農業」で変わり始めた能登の人々、5.「能登コミュニケ」で読む、能登の未来可能性・・・の5ポイント。講義でとくに強調したのは、人材養成の取り組みである。
2010年6月4日、GIAHS事務局長のパルヴィス・クーハフカン氏(当時、FAO天然資源管理・環境局 土地・水資源部長)が能登を候補地視察に訪れた。先導役は当時国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット所長のあん・まくどなるど氏、ほか同大学サステイナビリティと平和研究所や同大学高等研究所のメンバー含め一行は10人ほどだった。農林水産省の審議官も同行予定だったが、同日は間に合わなかった。一行はこの日、能登空港から輪島市に入り、同市の千枚田、珠洲市にある金沢大学能登学舎、輪島市の金蔵集落(朝日新聞「にほんの里100選」)、能登町の農家民宿群「春蘭の里」を巡り、七尾市和倉温泉で宿泊した。
私はコースのうち、金沢大学能登学舎と金蔵集落を案内した。能登学舎では、金沢大学が廃校だった小学校施設を借り受け、地域の社会人に学びの場を提供する「能登里山マイスター養成プログラム」(現在の名称は「能登里山里海マイスター育成プログラ」)を実施している。プログラムの概要は小路晋作特任助教が説明した。
2007年10月スタートした人材養成プログラムでは、人材像として、3つのタイプ(農林漁業人材・ビジネス人材・地域リーダー人材)のセンスを兼ね備えた人材の育成を想定。人材を養成するため、受講生には「地域づくり支援講座」「自然共生型能登再生論」「ニューアグリビジネス創出論」での講義を通じて、地域づくり、起業のノウハウ、一次産業の仕組みや販売システムに関する知識を習得させるとともに、「新農法特論」「里山マイスター演・実習」等で環境・生物調査や栽培実習を実践し、当該技術や基本知識を習得。さらに卒業課題演習と卒業論文作成を通じ、実際の地域課題の解決、あるいは就農・起業へつながる取り組みを実践。単位換算で54単位(2年間)に相当する。単なる社会人の教養講座と異なる点は、卒業論文を課して、その発表を審査する点だろう。5年間で62人が修了し、うち52人が能登地区に定着して活動を広げている。
修了生の何人かを紹介すると。農林漁業人材では、水産加工会社社員(男性)が同社の新規農業参入(耕作面積26㌶)の中心的役割を果たし、耕作放棄地を減少させている。製炭業職人(男性)は高付加価値の茶道用の高級炭の産地化に向けて、地域住民らともに荒廃した山地に広葉樹の植林運動を毎年実施している。また農業関連企業社員(男性)は、自治体職員(女性)、NPO職員(女性)らと連携して地元住民らと「奥能登棚田ネットワーク協議会」を設立し、棚田米のブランド化や都市農村交流事業に取り組んでいる。ビジネス人材では、花卉小売店社員(男性)が農協職員(男性)と連携し、神棚に供える能登産サカキを金沢市場に出荷している。リーダー人材では、デザイナー(女性)が集落の伝統的知恵や自然について学ぶ「まるやま組」という企画を毎月実施し、地元住民と大学研究者や都市住民らを結び付ける役割を果たしている。
 クーハフカン氏が能登学舎でこの里山マイスター養成プログラムの説明を受けて、身を乗り出したのは、受講生たちが環境配慮の水稲栽培を実施する中で採取した昆虫標本とその分類データだった。クーハフカン氏は社会人の人材養成プログラムに昆虫標本の作製まで取り入れるプログラムを高く評価し、「能登の生物多様性と農業の取り組みはとても先進的だ」と標本に見入った=写真=。クーハフカン氏自身、フランス・モンペリエ第二大学で陸域生態学のドクターを取得しており、生物多様性と農業には詳しく、FAOの世界農業遺産の認定基準(1.食料と生計の保障、2.生物多様性と生態系機能、3.知識システムと適応技術、4.文化、価値観、社会組織、5.優れた景観と土地・水資源の管理の特徴など)にも盛り込んでいる。能登には、大学が関与する生物多様性に配慮した農業人材の養成システムがすでにあることがクーハフカン氏の脳裏に刻まれ、その後に能登GIAHS認定の大きなポイントとなったに違いない。
クーハフカン氏が能登学舎でこの里山マイスター養成プログラムの説明を受けて、身を乗り出したのは、受講生たちが環境配慮の水稲栽培を実施する中で採取した昆虫標本とその分類データだった。クーハフカン氏は社会人の人材養成プログラムに昆虫標本の作製まで取り入れるプログラムを高く評価し、「能登の生物多様性と農業の取り組みはとても先進的だ」と標本に見入った=写真=。クーハフカン氏自身、フランス・モンペリエ第二大学で陸域生態学のドクターを取得しており、生物多様性と農業には詳しく、FAOの世界農業遺産の認定基準(1.食料と生計の保障、2.生物多様性と生態系機能、3.知識システムと適応技術、4.文化、価値観、社会組織、5.優れた景観と土地・水資源の管理の特徴など)にも盛り込んでいる。能登には、大学が関与する生物多様性に配慮した農業人材の養成システムがすでにあることがクーハフカン氏の脳裏に刻まれ、その後に能登GIAHS認定の大きなポイントとなったに違いない。
事実、北京での国際フォーラムでは、能登里山マイスター養成プログラムの研究代表、中村浩二金沢大学教授がクーハフカン氏から依頼され、「Satoyamaand SatoumiInitiatives for Conservation of Biodiversity and Reactivation of Rural Areas in NotoPeninsula: Kanazawa University’s role in GIAHS」と題して、「Noto Satoyama Meister Training Program」の取り組み紹介した。生物多様性に配慮した農業人材の養成システムがすでにあることのインパクトは想像に難くない。その後、中村教授はGIAHSの科学委員に指名された。そして、今回の能登での国際フォーラムでも「Human Capacity Building in GIAHS sites: Role of Universities in the Revitalization and Sustainable Development of Satoyama and Satoumi」と題して、GIAHSサイトでは持続可能な里山里海の利用において人材養成は欠かせないと強調した。
感動的な場面がことし2月20日、能登であった。金沢大学の「マイスター養成」プログラムを修了し、活動を広げている若手の農業者ら6人とフクーハフカン氏の「直接対話」を中村教授がセットしたのである。その6人のうちの1人、無農薬・無肥料の自然農法で水稲栽培をしている33歳の青年のスピーチを聞いた後、クーハフカン氏はこのように質問した。
Dr. Koohafkan: Congratulations. Did the land that you have used was your own land or did you rent, borrow, or buy it? Do you think a family could live happily? I see you are a very happy farmer and do you think that many others would be able to live lik e you in the area that you are working? (クーハフカン:素晴らしいですね。賛辞を贈らせていただきたいと思います。今お使いの土地はもともと所有されていた土地ですか。それとも借りたり購入したりしたのでしょうか。また、家族が幸せに暮らすことができると思われますか。あなたは非常に幸せな農家だとお見受けしますが、今お仕事をされている地域で、他にも多くの人が同じように暮らしていけると思われますか。)
e you in the area that you are working? (クーハフカン:素晴らしいですね。賛辞を贈らせていただきたいと思います。今お使いの土地はもともと所有されていた土地ですか。それとも借りたり購入したりしたのでしょうか。また、家族が幸せに暮らすことができると思われますか。あなたは非常に幸せな農家だとお見受けしますが、今お仕事をされている地域で、他にも多くの人が同じように暮らしていけると思われますか。)
Mr. Arai: I am using all of the rice paddies free of charge. A lot of things are happening in my life, but I am living happily.
Urban consumers do not like pesticides. Abandoned agricultural land is on the increase in the Noto, but it means that Noto is an environment where organic rice can be cultivated. I feel that people living in cities would find farming in Noto interesting if the number of people who come to Noto from cities for inspection and other purposes continues to increase even by one or two. (田んぼは全部、ただで借りています。いろいろありますが、幸せに暮らしています(笑)。都会の消費者の方は農薬が嫌いです。能登は耕作放棄地が増えていますが、逆に考えると、無農薬米が作れる環境にあるということです。就農希望の都会の人が視察に来るので、その中から1~2 人ずつ仲間が増えていけば、さらに能登の農業は面白いと都会の人が思ってくれると感じています。)
埼玉県出身の青年はこれまで就農と移住の相談を国、県、14の市町村にしたが、「稲作だけで農業は無理」と断られ、最終的に輪島市役所だけが受け入れてくれた。2008年に移住し耕作放棄地だった田んぼを無償で借り受け、いまは4㌶に拡大している。無農薬・無肥料の自らの田んぼで生き物調査をして、生き物は84種、植物は311種を確認している。それをホームページを使って情報発信し、共感してくれた全国の支援者が田んぼを訪れている。生物多様性と農業について考え、果敢に取り組む青年に、クーハフカン氏は「あなたは非常に幸せな農家だ」とエールを送ったのである。
※下の写真は、積雪の中、「田の神」に感謝する農耕儀礼「あえのこと」を執り行う青年。それを仲間たちが見守った=2012年12月9日・輪島市三井町で
⇒13日(木)朝・金沢の天気 はれ
 先の授業で選挙公示以降の新聞・テレビのメディアの公平性をテーマに講義をした。候補者を紹介する写真と記事の量・スペースの平等性など、新聞・テレビとも結構気を使っている、との講義内容だった。学生から質問があった。公平・平等とは言え、4日の公示の各陣営の模様を伝える5日付の新聞紙面で、自民の党首(安倍氏)の写真が他党の党首の顔写真より6倍もサイズが大きな写真だった。学生から「これは政権与党だからの配慮ですか」と問われ、これをどう説明しようか迷った。
先の授業で選挙公示以降の新聞・テレビのメディアの公平性をテーマに講義をした。候補者を紹介する写真と記事の量・スペースの平等性など、新聞・テレビとも結構気を使っている、との講義内容だった。学生から質問があった。公平・平等とは言え、4日の公示の各陣営の模様を伝える5日付の新聞紙面で、自民の党首(安倍氏)の写真が他党の党首の顔写真より6倍もサイズが大きな写真だった。学生から「これは政権与党だからの配慮ですか」と問われ、これをどう説明しようか迷った。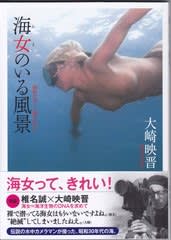 今回の旅程で個人的に楽しみにしているは、25日に訪れる「海女博物館」だ。自分自身も新聞記者時代に輪島市舳倉島(へぐらじま)の海女さんたちをルポールタージュ形式で取材した。1983年ごろ、今から30年も前の話になる。いまでも、輪島市では200人余りがいる。ウエットスーツを着用して、素潜りである。そのころ、18㍍の水深を潜ってアワビ漁をしていた海女さんたちがいた。このように深く潜る海女さんたちは「ジョウアマ」あるいは「オオアマ」と呼ばれていた。重りを身に付けているので、これだけ深く潜ると自力で浮上できない。そこで、夫が船上で、命綱からクイクイと引きの合図があるのを待って、妻でもある海女を引き上げるのだ。こうして夫婦2人でアワビ漁をすることを「夫婦船(めおとぶね)」と今でも呼ばれている。輪島の海女、済州島の海女の潜り方、使っている道具、漁の仕方などを済州島の海女博物館で見学したいと思っている。共通性と違いはどこにあるのか、比較もしてみたい。
今回の旅程で個人的に楽しみにしているは、25日に訪れる「海女博物館」だ。自分自身も新聞記者時代に輪島市舳倉島(へぐらじま)の海女さんたちをルポールタージュ形式で取材した。1983年ごろ、今から30年も前の話になる。いまでも、輪島市では200人余りがいる。ウエットスーツを着用して、素潜りである。そのころ、18㍍の水深を潜ってアワビ漁をしていた海女さんたちがいた。このように深く潜る海女さんたちは「ジョウアマ」あるいは「オオアマ」と呼ばれていた。重りを身に付けているので、これだけ深く潜ると自力で浮上できない。そこで、夫が船上で、命綱からクイクイと引きの合図があるのを待って、妻でもある海女を引き上げるのだ。こうして夫婦2人でアワビ漁をすることを「夫婦船(めおとぶね)」と今でも呼ばれている。輪島の海女、済州島の海女の潜り方、使っている道具、漁の仕方などを済州島の海女博物館で見学したいと思っている。共通性と違いはどこにあるのか、比較もしてみたい。 な道筋ができる。つまり、前向きな指標となる。二つ目に、たとえばTPP(環太平洋連携協定)が意識され、農地の集約などによる効率化やコスト競争力などの農業の体質強化が重視される余りに、GIAHS認定地でも、その理念である農文化や生物多様性の維持がおろそかになる恐れがある。とくに里山のような中山間地の棚田では耕作放棄地も進んでいる。そうした地域では同時に、洪水の防止や景観保全といった農業や農地が持つ多面的な機能が失われつつある。そこで、農地の変化や生物多様性、地域の生態系サービス、農業文化(収穫の祭りの開催など)、地域住民の意識などをモニタリングする。これらが、現実を見る指標となる。この前向きと現実の指標を定点観測しながら政策提言やビジネスチャンスを創り出していければ、との期待である。
な道筋ができる。つまり、前向きな指標となる。二つ目に、たとえばTPP(環太平洋連携協定)が意識され、農地の集約などによる効率化やコスト競争力などの農業の体質強化が重視される余りに、GIAHS認定地でも、その理念である農文化や生物多様性の維持がおろそかになる恐れがある。とくに里山のような中山間地の棚田では耕作放棄地も進んでいる。そうした地域では同時に、洪水の防止や景観保全といった農業や農地が持つ多面的な機能が失われつつある。そこで、農地の変化や生物多様性、地域の生態系サービス、農業文化(収穫の祭りの開催など)、地域住民の意識などをモニタリングする。これらが、現実を見る指標となる。この前向きと現実の指標を定点観測しながら政策提言やビジネスチャンスを創り出していければ、との期待である。 クーハフカン氏が能登学舎でこの里山マイスター養成プログラムの説明を受けて、身を乗り出したのは、受講生たちが環境配慮の水稲栽培を実施する中で採取した昆虫標本とその分類データだった。クーハフカン氏は社会人の人材養成プログラムに昆虫標本の作製まで取り入れるプログラムを高く評価し、「能登の生物多様性と農業の取り組みはとても先進的だ」と標本に見入った=写真=。クーハフカン氏自身、フランス・モンペリエ第二大学で陸域生態学のドクターを取得しており、生物多様性と農業には詳しく、FAOの世界農業遺産の認定基準(1.食料と生計の保障、2.生物多様性と生態系機能、3.知識システムと適応技術、4.文化、価値観、社会組織、5.優れた景観と土地・水資源の管理の特徴など)にも盛り込んでいる。能登には、大学が関与する生物多様性に配慮した農業人材の養成システムがすでにあることがクーハフカン氏の脳裏に刻まれ、その後に能登GIAHS認定の大きなポイントとなったに違いない。
クーハフカン氏が能登学舎でこの里山マイスター養成プログラムの説明を受けて、身を乗り出したのは、受講生たちが環境配慮の水稲栽培を実施する中で採取した昆虫標本とその分類データだった。クーハフカン氏は社会人の人材養成プログラムに昆虫標本の作製まで取り入れるプログラムを高く評価し、「能登の生物多様性と農業の取り組みはとても先進的だ」と標本に見入った=写真=。クーハフカン氏自身、フランス・モンペリエ第二大学で陸域生態学のドクターを取得しており、生物多様性と農業には詳しく、FAOの世界農業遺産の認定基準(1.食料と生計の保障、2.生物多様性と生態系機能、3.知識システムと適応技術、4.文化、価値観、社会組織、5.優れた景観と土地・水資源の管理の特徴など)にも盛り込んでいる。能登には、大学が関与する生物多様性に配慮した農業人材の養成システムがすでにあることがクーハフカン氏の脳裏に刻まれ、その後に能登GIAHS認定の大きなポイントとなったに違いない。 e you in the area that you are working? (クーハフカン:素晴らしいですね。賛辞を贈らせていただきたいと思います。今お使いの土地はもともと所有されていた土地ですか。それとも借りたり購入したりしたのでしょうか。また、家族が幸せに暮らすことができると思われますか。あなたは非常に幸せな農家だとお見受けしますが、今お仕事をされている地域で、他にも多くの人が同じように暮らしていけると思われますか。)
e you in the area that you are working? (クーハフカン:素晴らしいですね。賛辞を贈らせていただきたいと思います。今お使いの土地はもともと所有されていた土地ですか。それとも借りたり購入したりしたのでしょうか。また、家族が幸せに暮らすことができると思われますか。あなたは非常に幸せな農家だとお見受けしますが、今お仕事をされている地域で、他にも多くの人が同じように暮らしていけると思われますか。) 2011年6月、能登の里山里海は国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産(GIAHS=世界重要農業資産システム)に認定された。持続可能な、未来へと続く、里山里海での人々の生き方が高く評価されたからだ。自然と調和することの意味は、たとえば生物多様性に配慮して農業や漁業を営むことだ。そして伝統文化では、自然からの恵みに感謝する儀式がある、と前置きして、輪島の海女漁、ユネスコの無形文化遺産に登録された農耕儀礼「あえのこと」、そして、生物多様性条約事務局長、アフメド・ジョグラフ氏が2008年9月に能登を視察に訪れたときのエピドーソを紹介した。
2011年6月、能登の里山里海は国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産(GIAHS=世界重要農業資産システム)に認定された。持続可能な、未来へと続く、里山里海での人々の生き方が高く評価されたからだ。自然と調和することの意味は、たとえば生物多様性に配慮して農業や漁業を営むことだ。そして伝統文化では、自然からの恵みに感謝する儀式がある、と前置きして、輪島の海女漁、ユネスコの無形文化遺産に登録された農耕儀礼「あえのこと」、そして、生物多様性条約事務局長、アフメド・ジョグラフ氏が2008年9月に能登を視察に訪れたときのエピドーソを紹介した。 FAOのGIAHS認定の基準(食料と生計の保障、生物多様性と生態系機能、知識システムと適応技術など)があるが、それぞれの国で農林水産漁業の事情は異なる。日本の場合、稲作だけでなく、ため池や森林利用などもあり、さらに祭りなどの文化もあり農業の多様性は豊か。日本の村落の農業そのものが世界農業遺産と称してよいくらいだ。おそらく公募すれば、全国から手が上がるだろう。そこで、国内農業の特長や文化、生物多様性の取り組みなどを明確化するために基準が必要となる。もちろん、「世界農業遺産」の考えを広めることにもなる。つまり「日本農業遺産」創設という展開になるのかどうか、期待したいところだ。
FAOのGIAHS認定の基準(食料と生計の保障、生物多様性と生態系機能、知識システムと適応技術など)があるが、それぞれの国で農林水産漁業の事情は異なる。日本の場合、稲作だけでなく、ため池や森林利用などもあり、さらに祭りなどの文化もあり農業の多様性は豊か。日本の村落の農業そのものが世界農業遺産と称してよいくらいだ。おそらく公募すれば、全国から手が上がるだろう。そこで、国内農業の特長や文化、生物多様性の取り組みなどを明確化するために基準が必要となる。もちろん、「世界農業遺産」の考えを広めることにもなる。つまり「日本農業遺産」創設という展開になるのかどうか、期待したいところだ。  HSの大使になっていただきたい。GIAHSの概念的な枠組みを自分の環境に持ち込み、ビジネスに適用してください。もちろん政治家、政策決定者の皆さんも、子供たちや若い世代が、このような持続可能な暮らしや持続可能な発展の枠組みについて実際に考えるよう促してください」と。このとき、私は「大使」より「伝道者」の方が意味的に近いと思ったが、宗教と間違えられて困るので、国際的には「GIAHS大使」、これでよいのかもしれない。
HSの大使になっていただきたい。GIAHSの概念的な枠組みを自分の環境に持ち込み、ビジネスに適用してください。もちろん政治家、政策決定者の皆さんも、子供たちや若い世代が、このような持続可能な暮らしや持続可能な発展の枠組みについて実際に考えるよう促してください」と。このとき、私は「大使」より「伝道者」の方が意味的に近いと思ったが、宗教と間違えられて困るので、国際的には「GIAHS大使」、これでよいのかもしれない。 ん、能登で開催できたのは、農林水産省や石川県などが予算的、人的にバックアップしてのことだが、他国のGIAHSサイトでは伝統的な村落の集合体のようなところであり、国際会議を開催しようにも施設の収容力などの点で難しいだろう。ところが今回、首都に出向くのではなく、サイトで集まるという状況が能登で設定できたのである。採択されたコミュニケではそのことが盛り込まれた。「日本の石川県能登地域で開催された今回の世界農業遺産国際会議は、先進国での、またGIAHS認定サイトでの開催となった初の世界農業遺産国際会議であることに留意する(原文:Note further that the this Forum held in Noto region, Ishikawa Prefecture, 」apan, is the first GlAHS international Forum to take place at a GIAHS designated site in a developed country)」。さらに、この交流価値を結びつきの場として活かすべきだと、以下の勧告がなされた。「先進国と発展途上国の間のGIAHSサイトの結びつきを促進すること(原文:Promote the twinning of GIAHS sites between developed and developing countries)」
ん、能登で開催できたのは、農林水産省や石川県などが予算的、人的にバックアップしてのことだが、他国のGIAHSサイトでは伝統的な村落の集合体のようなところであり、国際会議を開催しようにも施設の収容力などの点で難しいだろう。ところが今回、首都に出向くのではなく、サイトで集まるという状況が能登で設定できたのである。採択されたコミュニケではそのことが盛り込まれた。「日本の石川県能登地域で開催された今回の世界農業遺産国際会議は、先進国での、またGIAHS認定サイトでの開催となった初の世界農業遺産国際会議であることに留意する(原文:Note further that the this Forum held in Noto region, Ishikawa Prefecture, 」apan, is the first GlAHS international Forum to take place at a GIAHS designated site in a developed country)」。さらに、この交流価値を結びつきの場として活かすべきだと、以下の勧告がなされた。「先進国と発展途上国の間のGIAHSサイトの結びつきを促進すること(原文:Promote the twinning of GIAHS sites between developed and developing countries)」 きょう30日午前は、政府関係者や国際機関幹部らが協議する、GIAHSでは初の「ハイレベルセッション」が20ヵ国から出席して行われた。角田豊農林水産省大臣官房審議官は、日本政府が今年度、世界農業遺産プロジェクトに初めて3000万円を資金協力するとし、GIAHSの理念に合致した地域は農業遺産に認定されるように支援する考えを示した。このために、認定地域を評価・観察し、日本独自の認定基準づくりを検討したいと話した。この後、認証式が行われた=写真=。
きょう30日午前は、政府関係者や国際機関幹部らが協議する、GIAHSでは初の「ハイレベルセッション」が20ヵ国から出席して行われた。角田豊農林水産省大臣官房審議官は、日本政府が今年度、世界農業遺産プロジェクトに初めて3000万円を資金協力するとし、GIAHSの理念に合致した地域は農業遺産に認定されるように支援する考えを示した。このために、認定地域を評価・観察し、日本独自の認定基準づくりを検討したいと話した。この後、認証式が行われた=写真=。 発表順に、日本の熊本県の「阿蘇の草原と持続可能な農業(Managing Aso Grasslands for Sustainable Agriculture)」、静岡県の「静岡の茶草場農法(Traditional tea (Chagusaba) of Shizuoka)」、中国の「会稽山の古代中国のトレヤ(Kuaijishan Ancient Chinese Toreya)」、中国の「宣化のブドウ栽培の都市農業遺産(Urban Agricultural Heritage of Xuanhua Grape Gardens)」、インドの「海抜以下でのクッタナド農業システム(Kuttanad Below Sea Level Farming System)」、イランの「カナード灌漑システム(Qanat Irrigation System)、最後が日本の大分県の「国東半島宇佐の農林漁業循環システム(Kunisaki Peninsula Usa Integrated Forestry, Agriculture and Fisheries System)」の7つの地域。
発表順に、日本の熊本県の「阿蘇の草原と持続可能な農業(Managing Aso Grasslands for Sustainable Agriculture)」、静岡県の「静岡の茶草場農法(Traditional tea (Chagusaba) of Shizuoka)」、中国の「会稽山の古代中国のトレヤ(Kuaijishan Ancient Chinese Toreya)」、中国の「宣化のブドウ栽培の都市農業遺産(Urban Agricultural Heritage of Xuanhua Grape Gardens)」、インドの「海抜以下でのクッタナド農業システム(Kuttanad Below Sea Level Farming System)」、イランの「カナード灌漑システム(Qanat Irrigation System)、最後が日本の大分県の「国東半島宇佐の農林漁業循環システム(Kunisaki Peninsula Usa Integrated Forestry, Agriculture and Fisheries System)」の7つの地域。 「日本におけるGIAHSの発展:大学の役割」と題して発表した国連大学サスティナビリティと平和研究所の永田明シニア・プログラム・コーディネーターの言葉だった。「欧州がユネスコの世界遺産をリードしたように、農業遺産はアジアがリードできるポジションにある」と述べ、とくに、日本、中国、韓国、日本の連携が重要で、国連大学は今後ともアジアの国々の世界農業遺産の連携に貢献したいと強調した。
「日本におけるGIAHSの発展:大学の役割」と題して発表した国連大学サスティナビリティと平和研究所の永田明シニア・プログラム・コーディネーターの言葉だった。「欧州がユネスコの世界遺産をリードしたように、農業遺産はアジアがリードできるポジションにある」と述べ、とくに、日本、中国、韓国、日本の連携が重要で、国連大学は今後ともアジアの国々の世界農業遺産の連携に貢献したいと強調した。