★トランプの赤ネクタイ-下-
 やはり、トランプ氏の赤ネクタイは「勝負ネクタイ」だったのか。71歳のトランプ氏が終始、34歳とされる金氏をリードしながら丁寧に対応する姿はまさに勝負師そのものだった。見方によっては、世間慣れしていない息子を諭すように教える老父という感じもした。ワーキングランチ前の記者に向かってのトランプ氏の言葉「Getting a good picture, everybody? So we look nice and handsome and thin? (みんな、いい写真を撮っているかい?かっこよく、細く見えてるだろう?)」。要は、金氏を細くかっこよく撮ってくれよと。ジョークではあるものの、金氏への気遣いだと見て取れた。
やはり、トランプ氏の赤ネクタイは「勝負ネクタイ」だったのか。71歳のトランプ氏が終始、34歳とされる金氏をリードしながら丁寧に対応する姿はまさに勝負師そのものだった。見方によっては、世間慣れしていない息子を諭すように教える老父という感じもした。ワーキングランチ前の記者に向かってのトランプ氏の言葉「Getting a good picture, everybody? So we look nice and handsome and thin? (みんな、いい写真を撮っているかい?かっこよく、細く見えてるだろう?)」。要は、金氏を細くかっこよく撮ってくれよと。ジョークではあるものの、金氏への気遣いだと見て取れた。
共同声明に盛り込まれなかった「IAEAの査察」の今後
両者が署名した共同声明にはCVID(完全かつ検証可能で不可逆的な非核化)の文言はなく、果たしてこれでよいのかと戸惑うものの、こうしたトランプ氏の振る舞いを見ていると、共同声明にある「Reaffirming the April 27, 2018 Panmunjom Declaration, the DPRK commits to work toward complete denuclearization of the Korean Peninsula.(2018年4月27日の板門店宣言を再確認し、北朝鮮は朝鮮半島の完全な非核化に向け取り組む)」の下りは期待できるようにも思えてくる。
トランプ氏の単独の記者会見でも「Chairman Kim has told me that North Korea is already destroying a major missile engine testing site that’s not in your signed document. (合意文書を調印した後に金氏から「北朝鮮は既に主要なミサイルエンジン実験場の破壊に取り掛かっている」と口頭で伝えられた)」と述べていた。金氏の非核化に向けたヤル気を察知したのかもしれない。
だとすると、金氏が非核化への準備をしているのであれば、IAEA(国際原子力機関)による査察を共同声明として提案すべきでなかったか。すなわち、核が保管されている施設を申告させて場所を明確にする「特定査察」、そこに監視カメラを設置して、平和目的かどうかを監視する「通常査察」、そして、監視によって疑惑が出た場合には「特別査察」を行うことだ。トランプ氏は「IAEAの査察を受け入れれば、アメリカだけでなく国際社会も歓迎するよ。君はあすからヒーローになれる」とアドバイスすべきではなかったか。
さらに、問題になると思ったのは、会談後の記者会見でトランプ氏がアメリカと韓国が行っている合同軍事演習を凍結すると発言したことだ。理由は「経費節減」のようだが、この会見を聞いて誰しもが、近い将来、朝鮮戦争の終結に合意し在韓米軍を撤収するのではないかと印象付けたに違いない。
前回ブログの繰り返しになるが、韓国の文在寅大統領は在韓米軍撤収の動きと連動して「一国二制度」の半島統一に素早く動くのではないだろうか。一方で非核化へのプロセスは4、5年の中長期にわたると言われている。その間、核弾頭が存在すれば「いつの間にか韓国と北は核を共有している」という事態にならないだろうか。国際政治の舞台はいろいろイメージを膨らませてくれる。(※米朝首脳会談後、トランプ氏の記者会見を伝えるNHKニュース=12日午後7時25分)
⇒13日(水)朝・金沢の天気 あめ




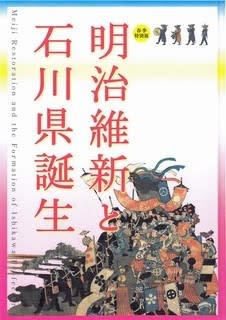

 係者全員を不起訴とした。きょう1日付の朝刊を読むと、各紙の論調は「まだ幕引きは許されぬ」(朝日新聞)といった感じで、私自身も何だか釈然としない=写真=。しかし、どこかでケジメをつけないといつまでも「モリカケ問題」が国会の論戦になっているのはいかがなものか、とも。
係者全員を不起訴とした。きょう1日付の朝刊を読むと、各紙の論調は「まだ幕引きは許されぬ」(朝日新聞)といった感じで、私自身も何だか釈然としない=写真=。しかし、どこかでケジメをつけないといつまでも「モリカケ問題」が国会の論戦になっているのはいかがなものか、とも。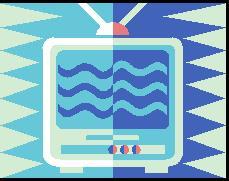 これはあくまでも「スポーツの世界」であり、審判員が試合を適切に判断できないのであればスポーツは成り立たなくなる。監督が「つぶせ」と指示したとしても、審判員がそれを見逃さずに早々と退場にしていれば、よかったのではないか。それがスポーツの世界だろう。単なる見逃しだったのか、その判断を聞きたい。審判員としての釈明がなければ、逆に日大と審判員の関係性を勘ぐってしまう。
これはあくまでも「スポーツの世界」であり、審判員が試合を適切に判断できないのであればスポーツは成り立たなくなる。監督が「つぶせ」と指示したとしても、審判員がそれを見逃さずに早々と退場にしていれば、よかったのではないか。それがスポーツの世界だろう。単なる見逃しだったのか、その判断を聞きたい。審判員としての釈明がなければ、逆に日大と審判員の関係性を勘ぐってしまう。 トランプ流交渉の「脅しのタックル」だ。すると金正恩氏は実にスピード感のある対応に出た。その日(26日)に韓国の文在寅大統領と板門店で会談。前回の首脳会談は4月27日だったので、1ヵ月足らずでの再会談は異例だろう。このニュースを視聴した人は誰しも「トランプの揺さぶりに金正恩はうろたえた」との印象を持ったことだろう。特に今回は板門店の北朝鮮側の施設での会談なので、金正恩氏からの一方的な要請によるものだったと推測できる。
トランプ流交渉の「脅しのタックル」だ。すると金正恩氏は実にスピード感のある対応に出た。その日(26日)に韓国の文在寅大統領と板門店で会談。前回の首脳会談は4月27日だったので、1ヵ月足らずでの再会談は異例だろう。このニュースを視聴した人は誰しも「トランプの揺さぶりに金正恩はうろたえた」との印象を持ったことだろう。特に今回は板門店の北朝鮮側の施設での会談なので、金正恩氏からの一方的な要請によるものだったと推測できる。