★世界農業遺産と持続可能な社会-下
和歌山県みなべ町で開催されている「第5回東アジア農業遺産学会(ERAHS)二日目のきょう28日はチャーターバスに乗ってのエクスカーション(視察)だった。日本や中国、韓国の参加者180人が4台のバスに分乗して、みなべ町の「県果樹試験場うめ研究所」「うめ振興館」、田辺市の「紀州石神(いしがみ)田辺梅林」「紀州備長炭記念公園」を巡った。
紀州備長炭と南高梅の「共生」関係
 和歌山県の梅生産量は5万3500㌧で全国の62%を占める(平成29年農林統計)。うめ研究所によれば、その和歌山県の生産量のうち、みなべ町41%と田辺市35%だ。和歌山の梅生産の品種別割合でいえば全国で知られる「南高梅」が85%を占める。ちなみに「南高」というネーミングは、戦後に地元の優良品種の絞り込みが行われた際、南部高校園芸科の生徒たちが5年間の調査研究に協力して「高田梅」という品種を選び出したことから「南高梅」と命名されたという。ローカルから発した全国ブランドだ。
和歌山県の梅生産量は5万3500㌧で全国の62%を占める(平成29年農林統計)。うめ研究所によれば、その和歌山県の生産量のうち、みなべ町41%と田辺市35%だ。和歌山の梅生産の品種別割合でいえば全国で知られる「南高梅」が85%を占める。ちなみに「南高」というネーミングは、戦後に地元の優良品種の絞り込みが行われた際、南部高校園芸科の生徒たちが5年間の調査研究に協力して「高田梅」という品種を選び出したことから「南高梅」と命名されたという。ローカルから発した全国ブランドだ。
 その生産現場である紀州石神田辺梅林を訪ねて驚いた。急傾斜ですり鉢状の地形の底の石神集落を取り囲むように梅林が広がる=写真・上=。「ひと目三十万本」。その広さを説明してくれたのは紀州田辺観梅協会の会長、石神忠夫氏だった=写真・中=。30度から40度の傾斜地を上り下りしながら400年の歳月をかけて創り上げた世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」のシンボル的な場所だ。坂道を速足で歩く石神氏は77歳。参加者の一人が「健康の秘訣は何ですか」と尋ねると、「暴飲暴食をしないこと。この土地の人は皆心がけていますよ」と即座に。条件不利地で伝統的な農業を受け継ぐには「体が資本」と言うことか。
その生産現場である紀州石神田辺梅林を訪ねて驚いた。急傾斜ですり鉢状の地形の底の石神集落を取り囲むように梅林が広がる=写真・上=。「ひと目三十万本」。その広さを説明してくれたのは紀州田辺観梅協会の会長、石神忠夫氏だった=写真・中=。30度から40度の傾斜地を上り下りしながら400年の歳月をかけて創り上げた世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」のシンボル的な場所だ。坂道を速足で歩く石神氏は77歳。参加者の一人が「健康の秘訣は何ですか」と尋ねると、「暴飲暴食をしないこと。この土地の人は皆心がけていますよ」と即座に。条件不利地で伝統的な農業を受け継ぐには「体が資本」と言うことか。
山並みの上部には水源涵養(かんよう)や崩落防止の役目を果たすウバメガシやカシ、クヌギなどの薪炭林が広がっている。薪炭林にはニホンミツバチが生息し、山の中腹に広がる梅林の花の受粉を手伝っている。システマチックに形成された自然環境と生物多様性はまさに里山、そのふもとに人里(集落)が広がる。ニホンミツバチの巣箱や梅の天日干しが行われているビニールハウスの現場を見る。梅の花が一斉に咲く2月の観梅期には地元に1万人ほどの来訪者がある。最近では台湾や中国からのバスツアーも増えた。「世界農業遺産のおかげですよ」と石神氏は目を細めた。
 ウバメガシを原料とする備長炭(びんちょうたん)もこの地域の主力産業の一つだ。紀州備長炭記念公園を訪れると、「炭琴」の演奏で歓迎してくれた=写真・下=。備長炭は鉄のように硬く、澄み切った音が響く。地元の女性たちで構成する「秋津川炭琴サークル」による 「上を向いて歩こう」「さくらさくら」の演奏に聴き入った。グループの中に20代の若さの女性がいた。演奏後に尋ねると、地域おこし協力隊のメンバーで去年3月に移住し、炭琴サークルに誘われて入った。「心に響く音色ですね」と水を向けると、「備長炭は湿気を吸って音程が変わるので、調律をしなければならないデリケートな楽器なんですよ」と。
ウバメガシを原料とする備長炭(びんちょうたん)もこの地域の主力産業の一つだ。紀州備長炭記念公園を訪れると、「炭琴」の演奏で歓迎してくれた=写真・下=。備長炭は鉄のように硬く、澄み切った音が響く。地元の女性たちで構成する「秋津川炭琴サークル」による 「上を向いて歩こう」「さくらさくら」の演奏に聴き入った。グループの中に20代の若さの女性がいた。演奏後に尋ねると、地域おこし協力隊のメンバーで去年3月に移住し、炭琴サークルに誘われて入った。「心に響く音色ですね」と水を向けると、「備長炭は湿気を吸って音程が変わるので、調律をしなければならないデリケートな楽器なんですよ」と。
炭焼き窯に行くと、若夫婦が炭の窯出し作業を行っていた。窯の中で高温で蒸し焼きにし、窯から出して、素灰と呼ぶ灰を掛けて消火する。このため「白炭」とも呼ばれる。今月12日にウバメガシの原木を窯に入れ、きょう窯出しなので17日間の作業だ。3㌧の原木を入れて、製炭量は350㌔ほどになる。
炭焼き業者は梅林の上にある薪炭林の中から太い幹だけを伐採する契約を梅栽培農家と結び原木を調達する。農家にとっても間伐は薪炭林の保全に必要だ。全国ブランドである紀州備長炭と南高梅はこうした「共生」関係にある。「梅システム」恐るべし。
⇒28日(火)夜・和歌山県みなべ町の天気 はれ

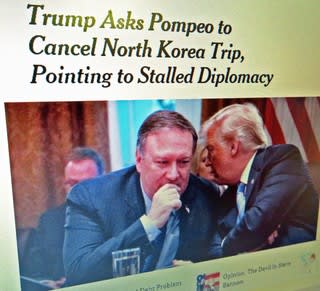

 きょうも金沢は35度を超える猛暑日だ。きのう小松市で観測史上最高の38.6度まで上がった。直射日光に焼け付くような痛さを感じる。1時間ほど駐車場に置いておいた自家用車のドアを開けると、車内から熱風が吹き出し、入れない。しばらく前後のドアを開けて待ち、それから運転席に着き、エアコンを最大限にしてようやく運転開始。それでも車内が熱い。「車は走るかまど」とはよく言ったものだ。県内のニュースによると、きのう県内で21人が熱中症の疑いで病院に搬送されている。
きょうも金沢は35度を超える猛暑日だ。きのう小松市で観測史上最高の38.6度まで上がった。直射日光に焼け付くような痛さを感じる。1時間ほど駐車場に置いておいた自家用車のドアを開けると、車内から熱風が吹き出し、入れない。しばらく前後のドアを開けて待ち、それから運転席に着き、エアコンを最大限にしてようやく運転開始。それでも車内が熱い。「車は走るかまど」とはよく言ったものだ。県内のニュースによると、きのう県内で21人が熱中症の疑いで病院に搬送されている。






