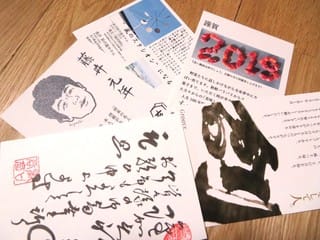★雪のない冬の兼六園で
このところの天気が異常に思える。例年ならば、周囲は雪景色なのだが積雪はゼロである。まったく降らなかったわけではない。12月30日朝は雪が4、5㌢積もっ ていて、30分ほど自宅周囲の雪すかしをした。この冬はそれ一回だけ。新調したスコップも手持ちぶさたで、出番を待っている=写真・上=。
ていて、30分ほど自宅周囲の雪すかしをした。この冬はそれ一回だけ。新調したスコップも手持ちぶさたで、出番を待っている=写真・上=。
きょう午前、所用で通りかかったので久しぶりに兼六園を歩いた。前を歩く家族連れらしき3人のうち女性が「せっかく兼六園に来たのに、雪がないと魅力がないよね」と。そうか、暖冬で一番ぼやいているのは観光客かもしれない。確かに、雪吊りの風景をパンフで見て、銀世界の兼六園のイメージを膨らませて金沢にやって来たのに、拍子抜けとはこのことか。
夕顔亭(ゆうがおてい)=写真・下=という古い茶亭の横を通った。もう14年も前のことだがエピドーソを思い出した。茶亭をハイビジョンカメラで撮影したことがある。撮影は、石川県の委託事業で兼六園を映像保存するもの。兼六園の数ある茶亭でもなぜ夕顔亭にこだわったのかというと、この茶室から滝を見ることができるので「滝見の御亭(おちん)」と呼ばれていて、茶室から見る風景がもっとも絵になるからだ。
この夕顔亭の見本となったといわれるのが、京都の茶道・藪内家の「燕庵(え んなん)」という茶亭。そこで、撮影では藪内家の若宗匠、藪内紹由氏(2015年に家元を継承)に夕顔亭まで起こし頂き、お点前を撮影させていただいた。そこで出た話だ。藪内家には、「利家、居眠りの柱」とういエピソードがある。京の薮内家を訪れた加賀藩祖の前田利家が燕庵に通された時、疲れがたまっていたのか、豪快な気風がそうさせたのか、柱にもたれかかって眠リこけてしまった。こうした逸話が残る燕庵を後に利家の子孫、11代の治脩(はるなが)が1774年に燕庵を模してつくった茶亭が夕顔亭だった。
んなん)」という茶亭。そこで、撮影では藪内家の若宗匠、藪内紹由氏(2015年に家元を継承)に夕顔亭まで起こし頂き、お点前を撮影させていただいた。そこで出た話だ。藪内家には、「利家、居眠りの柱」とういエピソードがある。京の薮内家を訪れた加賀藩祖の前田利家が燕庵に通された時、疲れがたまっていたのか、豪快な気風がそうさせたのか、柱にもたれかかって眠リこけてしまった。こうした逸話が残る燕庵を後に利家の子孫、11代の治脩(はるなが)が1774年に燕庵を模してつくった茶亭が夕顔亭だった。
この夕顔亭をつくる際、薮内家と加賀藩には一つの約束事があった。茶器で有名な古田織部が指導してつくったこの由緒ある茶亭を簡単に模倣させる訳にはいかない。そこで、もし燕庵が不慮の事故で焼失した場合は「京に戻す」という条件で建築が許された、との言い伝えだ。知的財産権の観点からいうと、広い意味での「使用権」だけを加賀藩に貸与したということになるかもしれない。その後、契約者である前田ファミリーは明治維新後この夕顔亭を手放し、今では石川県の所有になっている。その約束事は消滅しているのかもしれない。
知的財産権という法律は当時なかったにせよ、「知財を守る」という精神は脈々と日本の歴史の中に生きていたと、若宗匠のお点前を拝見しながら思ったものだ。暖冬の話がいつの間にか知財の話になってしまった。
⇒19日(土)午後・金沢の天気 はれ

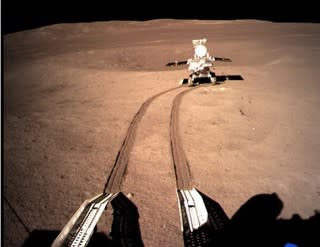

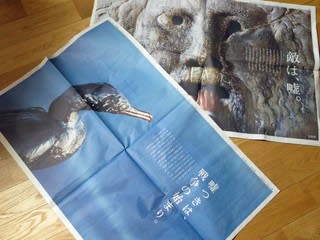
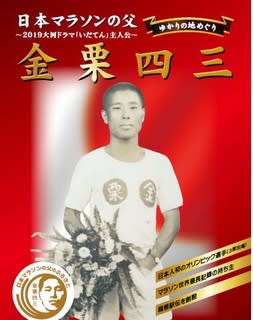




 や男性がバイクや軽トラックで次々と花の束を持ち込んで、とても活気があった。ベトナム航空のロゴマークは蓮(はす)の花をデザインしたもの。蓮は日本では仏花を代表する花だが、ベトナムでもシンボリックな花だ。ベトナムは社会主義の国だが仏教が主流だ。そして、ベトナムで仏教を信仰する多くの人々は月2回(1日と15日)に精進料理を食べることも習慣となっている。文化的な価値感を共有できる国ではないだろうか。
や男性がバイクや軽トラックで次々と花の束を持ち込んで、とても活気があった。ベトナム航空のロゴマークは蓮(はす)の花をデザインしたもの。蓮は日本では仏花を代表する花だが、ベトナムでもシンボリックな花だ。ベトナムは社会主義の国だが仏教が主流だ。そして、ベトナムで仏教を信仰する多くの人々は月2回(1日と15日)に精進料理を食べることも習慣となっている。文化的な価値感を共有できる国ではないだろうか。