★米朝首脳会談がダナンで、ならば
次なるアメリカと北朝鮮の首脳会談が気になるところ。トランプ大統領が5日の一般教書演説で再会談の日程や場所を発表する可能性があるとも報じられている。2日付の韓国の中央日報Web(日本版)は日朝首脳会談に関連する社説を掲載している。以下引用。
 「米国が韓半島(朝鮮半島)で戦争を終える終戦宣言の意志に言及した。ビーガン北朝鮮担当特別代表の言葉だ。ビーガン代表は一昨日、米カリフォルニア州スタンフォード大ウォルター・H・ ショレンスティン・アジア太平洋研究センターが主催した講演で『トランプ大統領は朝鮮戦争を終わらせる準備ができている』とし『北朝鮮侵攻や政権転覆を追求しないはず』と明らかにした。また『最後の核兵器が北朝鮮を離れて制裁が解除されれば、大使館に国旗が掲げられ、平和条約が締結されるだろう』と述べた。ビーガン代表が今月末に開かれる見通しの2回目の米朝首脳会談を控え、米国の立場を公開したとみられる。」
「米国が韓半島(朝鮮半島)で戦争を終える終戦宣言の意志に言及した。ビーガン北朝鮮担当特別代表の言葉だ。ビーガン代表は一昨日、米カリフォルニア州スタンフォード大ウォルター・H・ ショレンスティン・アジア太平洋研究センターが主催した講演で『トランプ大統領は朝鮮戦争を終わらせる準備ができている』とし『北朝鮮侵攻や政権転覆を追求しないはず』と明らかにした。また『最後の核兵器が北朝鮮を離れて制裁が解除されれば、大使館に国旗が掲げられ、平和条約が締結されるだろう』と述べた。ビーガン代表が今月末に開かれる見通しの2回目の米朝首脳会談を控え、米国の立場を公開したとみられる。」
北朝鮮の核兵器が撤廃されれば、アメリカと北朝鮮の間で平和条約が締結される可能性があるとの内容だ。この文脈は、米朝首脳会談ではトランプ大統領は金正恩委員長に対し核兵器廃絶と引き換えに平和条約を結ぶことを明言する。同紙はこうも述べている。
「しかし今回の交渉が失敗すれば『コンティンジェンシープラン(非常計画)』が避けられないとビーガン代表は警告した。コンティンジェンシープランとは軍事オプションを含む米国の積極的な対応を意味する。 敗すれば『コンティンジェンシープラン(非常計画)』が避けられないとビーガン代表は警告した。コンティンジェンシープランとは軍事オプションを含む米国の積極的な対応を意味する。」
そのまま読めば、トランプ大統領は軍事オプションをちらつかせながら、金委員長に対し核兵器廃絶を迫るのではないか、とイメージを膨らませてしまう。首脳会談の場所は、ベトナムのダナンで開かれることが有力視されていている(3日付・NHKニュース)。ダナンはハノイとサイゴンのちょうど中間地点にあり、2017年11月にアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議が開かれている=写真、外務省ホームページより=。ただ、「ベトナム戦争」の記憶が残る場所だけに、トランプ大統領は金委員長に対し高圧的に核兵器廃絶を迫ったりはできないのではないか、と考えたりもする。
⇒3日(日)夜・金沢の天気 あめ

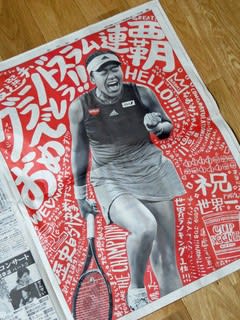





 トキが急激に減少したとされる1900年代、日本は食糧増産に励んでいた。レチェル・カーソンが1960年代に記した名著『サイレント・スプリング』で、「春になっても鳥は鳴かず、生きものが静かにいなくなってしまった」と記した。農業は豊かになったけれども春が静かになった。1970年1月、本州最後の1羽だったトキが能登半島で捕獲された。オスで「能里(ノリ)」の愛称があった。繁殖のため佐渡のトキ保護センターに送られたが、翌1971年に死んだ。解剖された能里の肝臓や筋肉からはDDTなどの有機塩素系農薬や水銀が高濃度で検出された。2003年10月、佐渡で捕獲されたメスの「キン」が死んで、日本のトキは絶滅した。その後、同じ遺伝子の中国産のトキの人工繁殖が始まった。
トキが急激に減少したとされる1900年代、日本は食糧増産に励んでいた。レチェル・カーソンが1960年代に記した名著『サイレント・スプリング』で、「春になっても鳥は鳴かず、生きものが静かにいなくなってしまった」と記した。農業は豊かになったけれども春が静かになった。1970年1月、本州最後の1羽だったトキが能登半島で捕獲された。オスで「能里(ノリ)」の愛称があった。繁殖のため佐渡のトキ保護センターに送られたが、翌1971年に死んだ。解剖された能里の肝臓や筋肉からはDDTなどの有機塩素系農薬や水銀が高濃度で検出された。2003年10月、佐渡で捕獲されたメスの「キン」が死んで、日本のトキは絶滅した。その後、同じ遺伝子の中国産のトキの人工繁殖が始まった。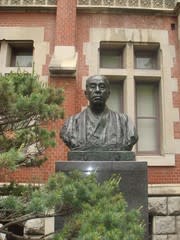 逆に、「信頼できない」トップが国会議員56%、次がマスコミ42%だ。ひとくくりにマスコミと言っても範囲は広いが、その一員でもある日経新聞社もショックな数字だったろう。私自身この数字には正直「困った」との印象だ。ネット上ではフェイクニュースが氾濫している。確かな取材手法で情報を世に投げるのがマスコミの使命だと解釈している。そのマスコミが「信頼できない」となるとファクトチェック(信憑性の検証)は誰が担うのか。
逆に、「信頼できない」トップが国会議員56%、次がマスコミ42%だ。ひとくくりにマスコミと言っても範囲は広いが、その一員でもある日経新聞社もショックな数字だったろう。私自身この数字には正直「困った」との印象だ。ネット上ではフェイクニュースが氾濫している。確かな取材手法で情報を世に投げるのがマスコミの使命だと解釈している。そのマスコミが「信頼できない」となるとファクトチェック(信憑性の検証)は誰が担うのか。 た。店のオーナーが男に問いただしたところ、男は「ボタンを押し間違えただけだ」と言い逃れようとしていた。警察の調べに対しては、容疑を認めているという。
た。店のオーナーが男に問いただしたところ、男は「ボタンを押し間違えただけだ」と言い逃れようとしていた。警察の調べに対しては、容疑を認めているという。