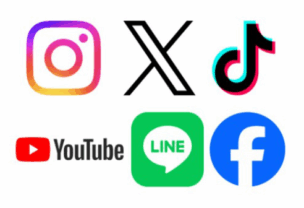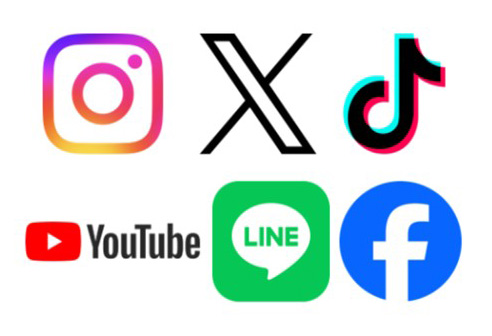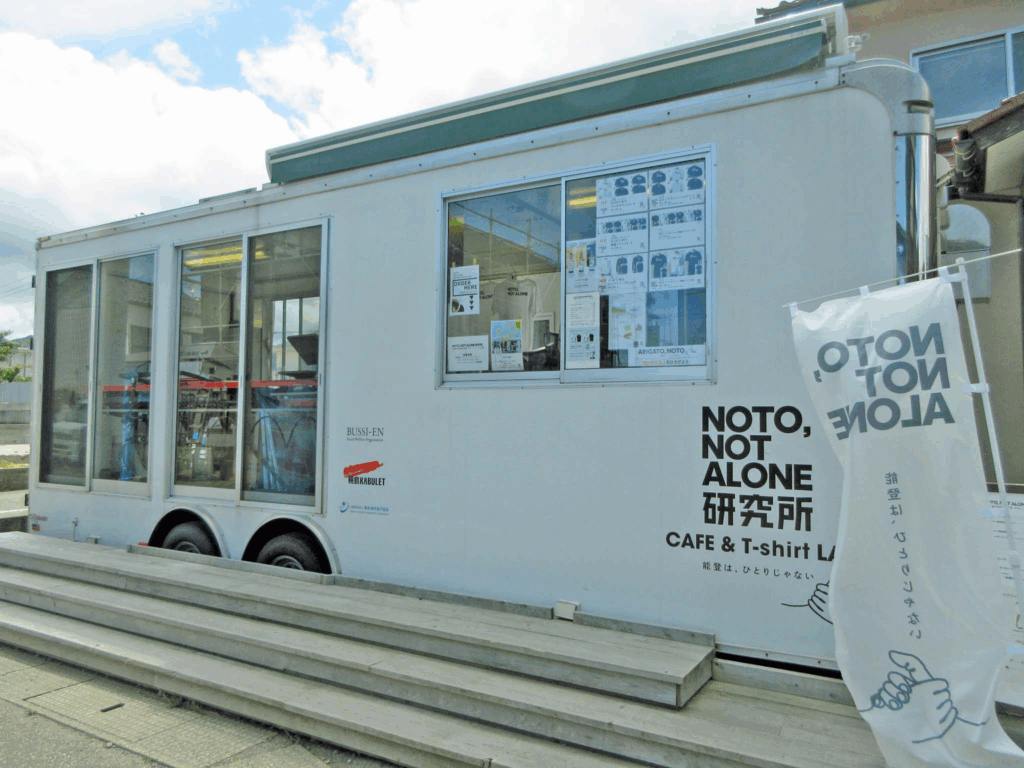★地元期待の大の里 千秋楽待たず優勝、横綱昇進へ
地元・石川県出身の郷土力士、大の里はきょう(23日)も勝って13勝目を上げ、千秋楽を待たずに優勝を果たした。2場所連続で4回目だ。自身を含めて県民はワクワクしている。何しろ、場所後の横綱昇進が見えてきた。

きょうの取り組みをNHKで視ていた。相手は同じ大関・琴櫻。立ち合い、両腕を固めて当たっていき、そのまま得意の右を差して左も使いながら一気に攻めて、寄り切りで負かした。13日目に優勝が決まるのは平成27年(2015)初場所の横綱・白鵬以来10年ぶり、と報じていた。残り2日を勝って全勝優勝で横綱昇進なのか、期待が高まる。
NHKの報道によると、横綱審議委員会には、横綱に推薦する条件として「大関で2場所連続の優勝か、これに準ずる成績」という内規があり、これまで2場所連続で優勝した力士が横綱に昇進できなかった例はないようだ。なので、大の里は場所後の横綱昇進がほぼ確定ということになる。(※写真は、JR金沢駅に設置されている郷土力士の等身大パネル)
石川出身の相撲界のトップはこれまで2人いる。江戸時代の第6代横綱の阿武松緑之助(1791‐1852)と、第54代横綱の輪島大士(1948- 2018)だ。大の里にとって輪島はスピード出席の先輩でもある。現在の年6場所制が整った1958年以降で、輪島は初土俵から21場所で横綱に昇進し、これまで最速記録だった。この記録を大の里が抜いて13場所で横綱となる見通しだ。
横綱審議委員会は千秋楽翌日の今月26日に開かれる。大の里が横綱に推薦されれば、日本相撲協会は今月28日に番付編成会議と臨時の理事会を開き、横綱昇進を正式に決定することになる。
⇒23日(金)夜・金沢の天気 はれ