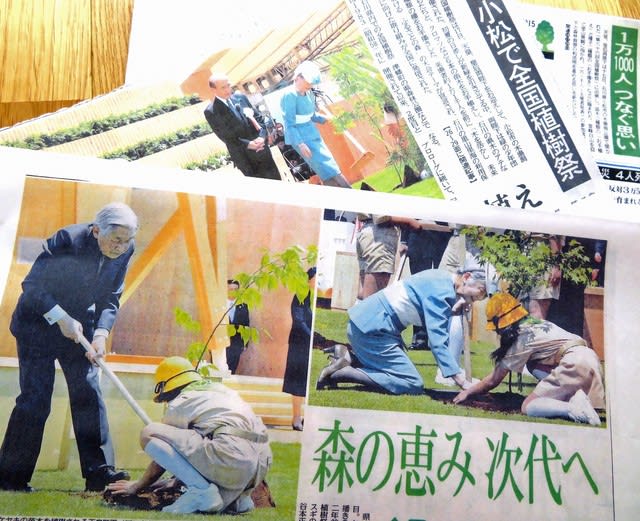☆北、きょうもミサイル発射
きょう(9日)午後5時ごろ、メディアのニュース速報が流れた。「午後4時30分ごろ、北朝鮮が飛翔体を日本海に発射した」。夕方のニュース番組では、韓国軍合同参謀本部は短距離ミサイルと推定される飛翔体を午後4時29分と同49分、北西部の亀城(クソン)付近から1発ずつ計2発を発射、それぞれ420㌔と270㌔飛行して日本海に落下したと発表したと伝えた。
 世界のメディアも速報で伝えている。イギリス公共放送「BBC」Web版は「North Korea fires two short-range missiles, South says(北朝鮮が2発の短距離ミサイルを放ったと、韓国発表)」と見出しで、金正恩朝鮮労働党委員長が双眼鏡を手にしている写真とともに掲載した。北は今月4日午前にも東部の元山(ウォンサン)から日本海に向けて飛翔体を数発を発射している。折しも、4日のミサイル発射をめぐってきょう日本、アメリカ、韓国の3ヵ国の防衛当局による実務者協議がソウルで開かれていた。きょうのミサイル発射はそのタイミングを狙って挑発的したのではないかとも受け取れる。
世界のメディアも速報で伝えている。イギリス公共放送「BBC」Web版は「North Korea fires two short-range missiles, South says(北朝鮮が2発の短距離ミサイルを放ったと、韓国発表)」と見出しで、金正恩朝鮮労働党委員長が双眼鏡を手にしている写真とともに掲載した。北は今月4日午前にも東部の元山(ウォンサン)から日本海に向けて飛翔体を数発を発射している。折しも、4日のミサイル発射をめぐってきょう日本、アメリカ、韓国の3ヵ国の防衛当局による実務者協議がソウルで開かれていた。きょうのミサイル発射はそのタイミングを狙って挑発的したのではないかとも受け取れる。
もう一つ、タイミングが重なった。韓国の文在寅大統領は就任2年を翌日に控えたきょう夜、韓国の公共放送局「KBS」の特集対談番組に生出演した。その様子をKBSのラジオニュースWeb版が伝えている。「President Moon Urges N. Korea to Stop Raising Tensions(文大統領は北に対し、緊張の高まりを止めるよう要請した)」との見出しで、夕方に発射された飛翔体について、文氏は「短距離ミサイルと推定している」「短距離だとしても、弾道ミサイルなら国連安保理決議に違反する可能性もある」「このような行為が繰り返されれば、対話と交渉の局面を難しくする」と述べたと伝えている。
特集対談番組は以前から組まれていた。その番組は生放送でのインタビューだった。このWeb版ニュースを読む限り、文氏の発言はもう北をかばいきれないと判断しているようにも思える。
⇒9日(木)夜・金沢の天気 はれ