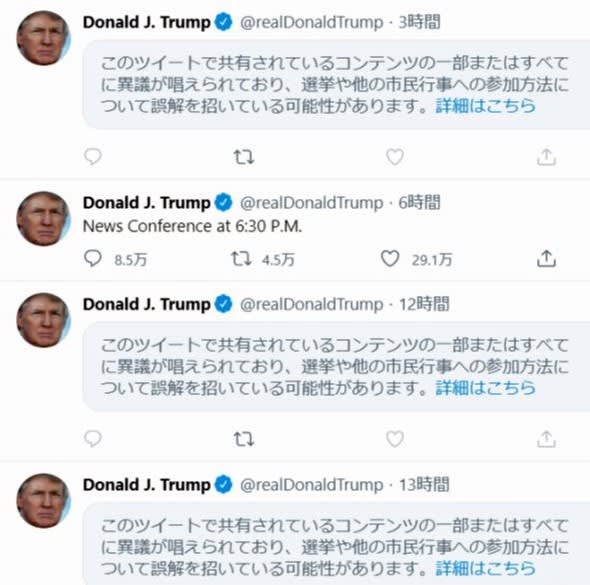★「困難に負けない」 ツワブキの花言葉
晩秋の気配を紅葉と落ち葉で感じるきょうこの頃だ。庭先の日陰でツワブキが黄色い花を咲かせていた。日陰ながら葉を茂らせ、花を咲かせることから「謙譲」「謙遜」「愛よ甦れ」「困難に負けない」と花言葉がある。そのツワブキを床の間に生けてみた=写真=。
 花もさることながら、葉はハスのように丸く、表面には艶がある。とても床の間に映える。ツワブキには「石蕗」と漢字が充てられている。確かに、石垣のすき間の中からささやかに花を咲かせ、つやつやとした葉を見せてくれるツワブキもある。日陰や石垣といった、ある意味での逆境にありながらも、植物の個性を見事に表現している。その日一日を粛々と生きる。ただひたすらに、ありのままに前向きな心境になれば、別の風景も見えてくるものだ。
花もさることながら、葉はハスのように丸く、表面には艶がある。とても床の間に映える。ツワブキには「石蕗」と漢字が充てられている。確かに、石垣のすき間の中からささやかに花を咲かせ、つやつやとした葉を見せてくれるツワブキもある。日陰や石垣といった、ある意味での逆境にありながらも、植物の個性を見事に表現している。その日一日を粛々と生きる。ただひたすらに、ありのままに前向きな心境になれば、別の風景も見えてくるものだ。
掛け軸には『閑坐聴松風』を出してみた。「かんざして しょうふうをきく」と読む。静かに心落ち着けて坐り、松林を通り抜ける風の音を聴く。茶席によくこの軸物が掛かる。釜の湯がシュン、シュンとたぎる音を「松風」と称したりする。日曜日の静かな午前のひとときを花と掛け軸で楽しんだ。
午後からはまるで爆音のようなメディアの騒ぎだ。IOCのバッハ会長が来日した。延期された東京オリ・パラ開催に向けて、現地・日本の様子を確認する狙いだろうが、本人の新型コロナウイルス対策はどうか最初に気になった。何しろ、ヨーロッパは新型コロナウイルスの感染拡大が猛烈な勢いだ。ニュースでは、訪日に備えてバッハ氏を含めてIOC関係者は事前に自主隔離し、さらに少人数でチャーター機を使って来日したというから気遣いを察した。
ただ、年末になってもコロナウイルスは衰えるどころか変異してさらにパワーアップしているようだ。ことし3月25日に当時の安倍総理とIOCのバッハ会長の電話会談で東京オリンピックを1年ほど延期すると表明があった時点で、大会の出場枠は全体の43%が確定していなかった。これから各国が予選を行い、代表選手を決めるとなると選手のモチベーションそのものが高まるだろうか。各種ランキングを用いて出場選手を決めることも検討されているようだ(11月12日付・時事通信Web版)。
逆境のただ中で東京オリ・パラ開催できるのかどうか。このリスクは日本にとって重過ぎるのではないだろうか。だからと言って菅政権は「諸事情に鑑みて中止」とは政治的には絶対に言えないだろう。世界史に刻まれる日本の難題がこれから始まる。ツワブキの花を眺めながらふとそんなことを考えた。
⇒15日(日)夜・金沢の天気 くもり
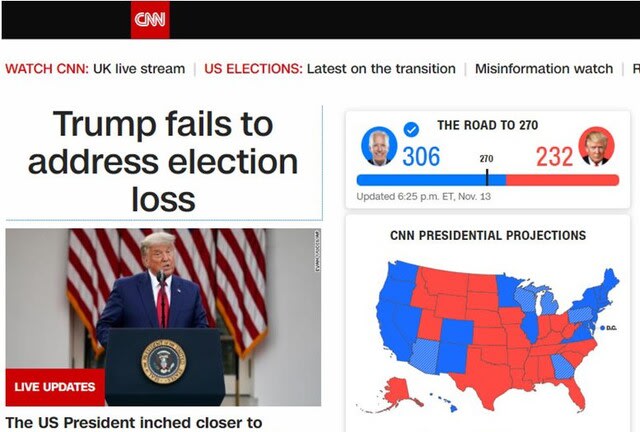
 動物たちの反乱は身近に起きている。きょう大学から一斉メールが届いた。「高病原性鳥インフルエンザに対する対策について」との文科省からの通知の転送だ。添付ファイルに「野鳥との接し方」がある。以下引用。「野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。 特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください」。自家用車を駐車場に停めておくと、鳥のフンがフロントガラスについていることがある。これまでテッシュペーパーで拭いて、水をかけて洗っていたが、触れないようさらに用心が必要だ。鳥たちの「フン爆撃」か。処置としては、ガソリンスタンドの洗車機で洗うのベストだろう。1回450円だ。
動物たちの反乱は身近に起きている。きょう大学から一斉メールが届いた。「高病原性鳥インフルエンザに対する対策について」との文科省からの通知の転送だ。添付ファイルに「野鳥との接し方」がある。以下引用。「野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。 特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください」。自家用車を駐車場に停めておくと、鳥のフンがフロントガラスについていることがある。これまでテッシュペーパーで拭いて、水をかけて洗っていたが、触れないようさらに用心が必要だ。鳥たちの「フン爆撃」か。処置としては、ガソリンスタンドの洗車機で洗うのベストだろう。1回450円だ。
 二人が話しているとラ-メンが出てきて、二人は黙々と食べて店を出て行った。さまざまな食味を追求したラーメン店が巷(ちまた)に看板を競っているが、この店は「自然派らーめん」と称している。無化調(無化学調味料のこと)を売りに、鶏をベースに鰹節、煮干、コンブの海産物からとった薄味のスープ。インパクトはなく優しい味わいで美味。ちじれ麺は足踏みだから腰がある。ちじれ麺にスープが絡んでいるのでのど越しがいい。
二人が話しているとラ-メンが出てきて、二人は黙々と食べて店を出て行った。さまざまな食味を追求したラーメン店が巷(ちまた)に看板を競っているが、この店は「自然派らーめん」と称している。無化調(無化学調味料のこと)を売りに、鶏をベースに鰹節、煮干、コンブの海産物からとった薄味のスープ。インパクトはなく優しい味わいで美味。ちじれ麺は足踏みだから腰がある。ちじれ麺にスープが絡んでいるのでのど越しがいい。

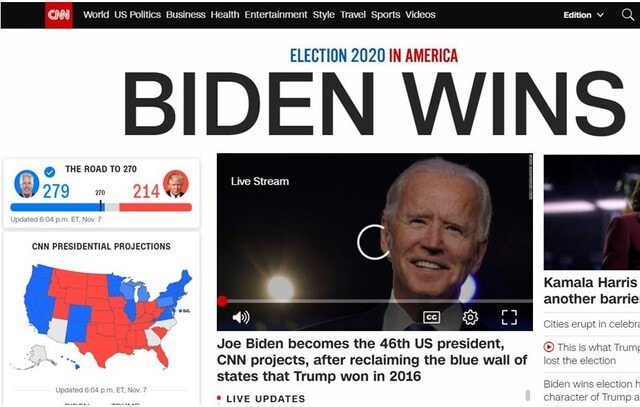
 上回る40万円で競り落とされた。いよいよカニのシーズン到来だ。
上回る40万円で競り落とされた。いよいよカニのシーズン到来だ。