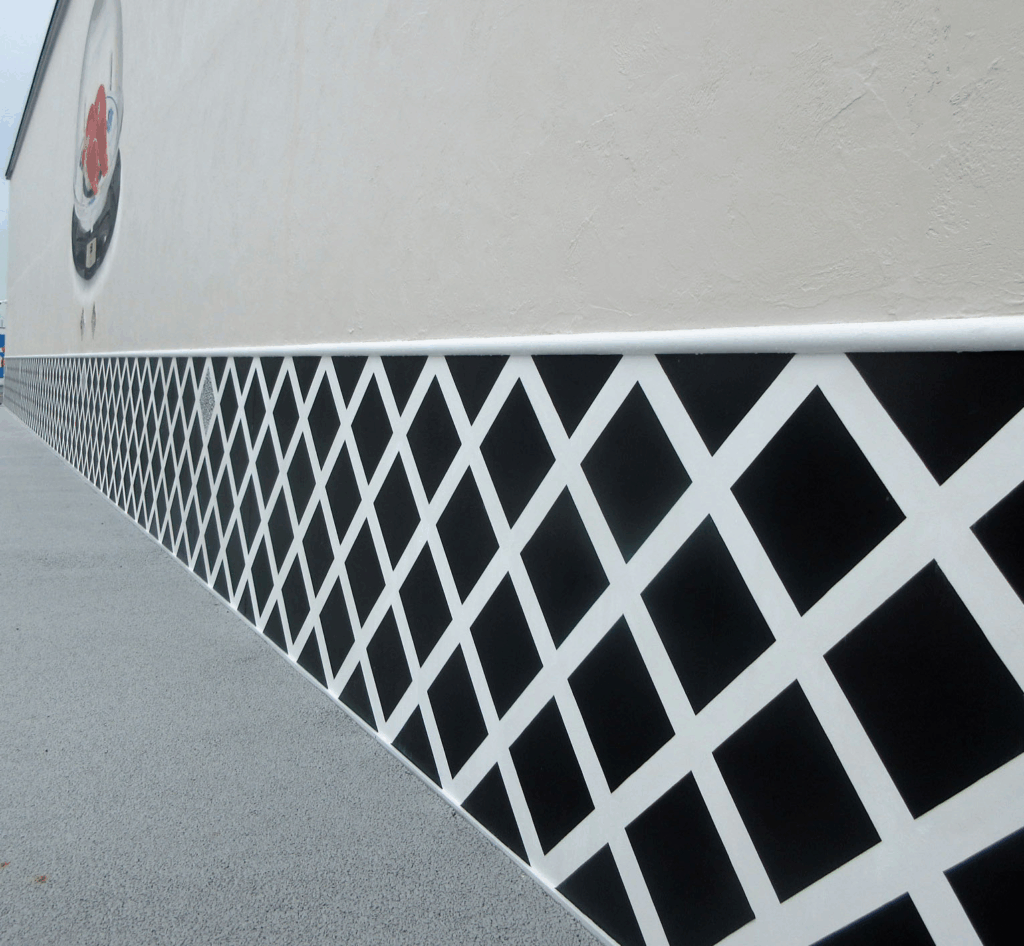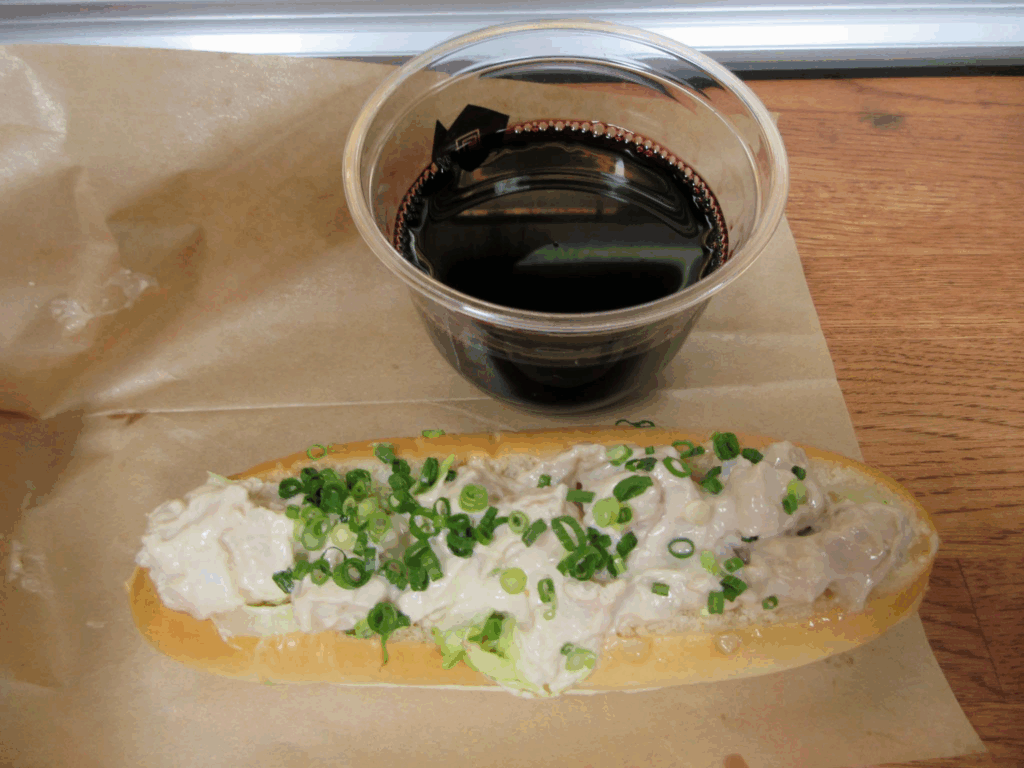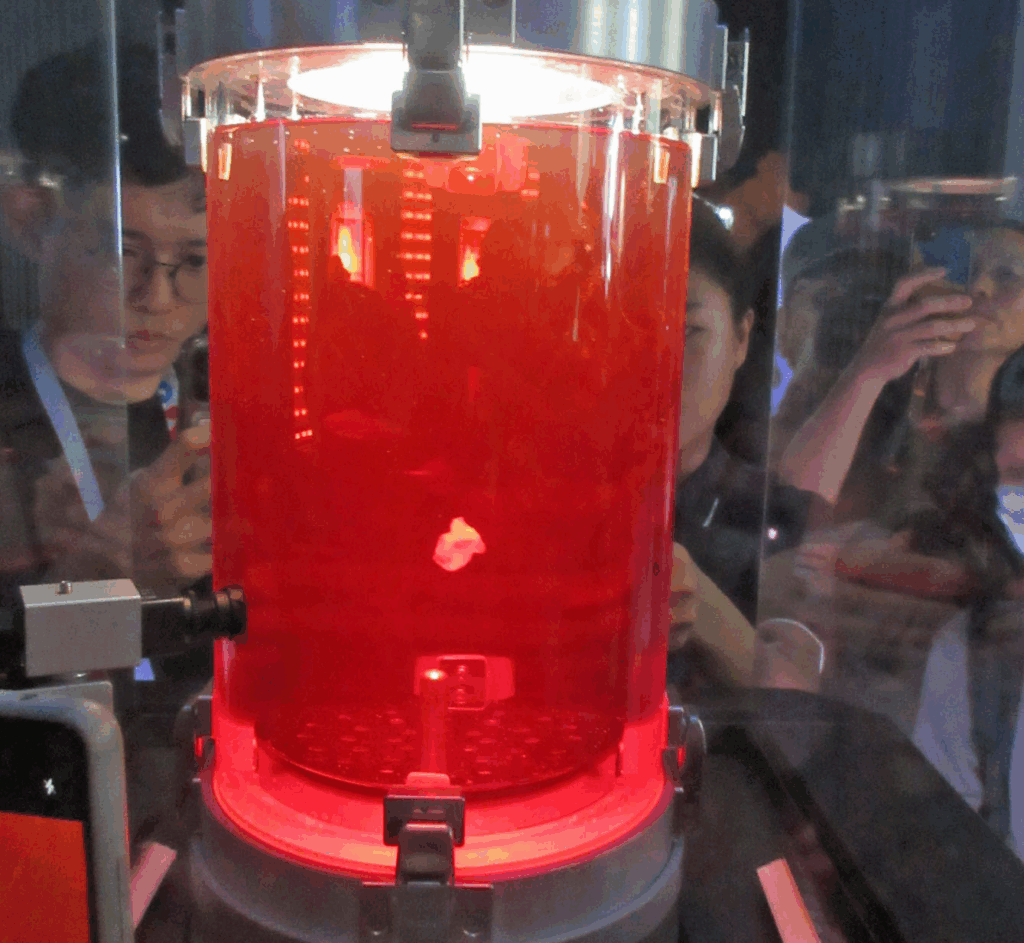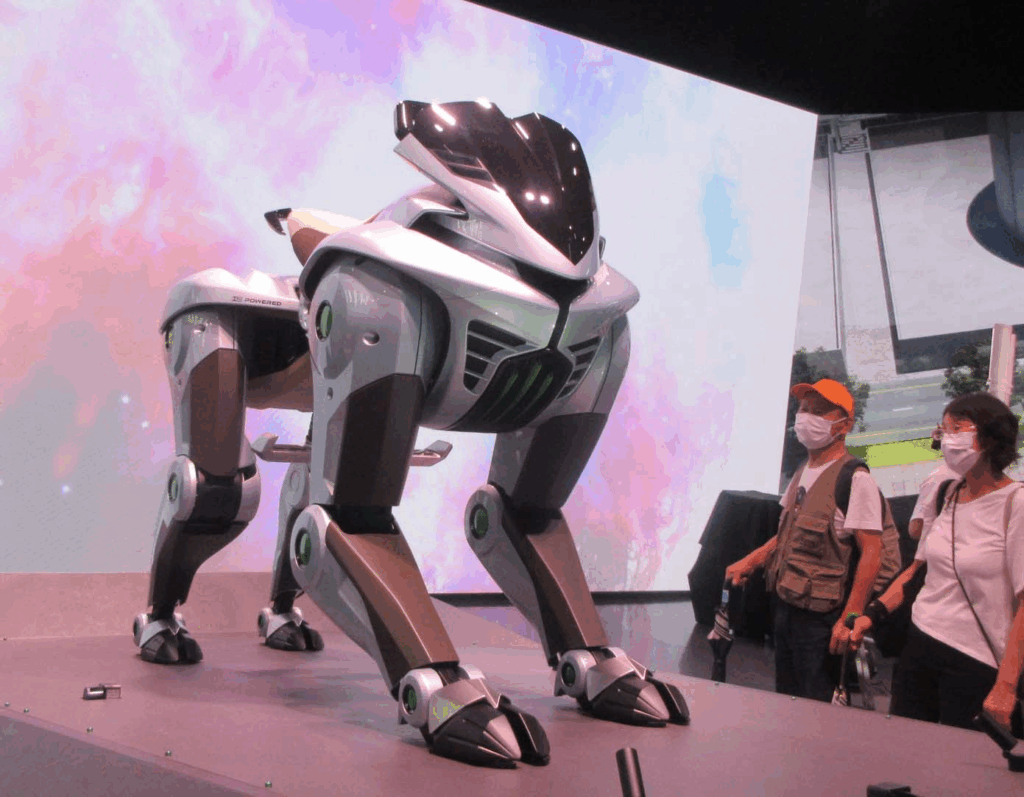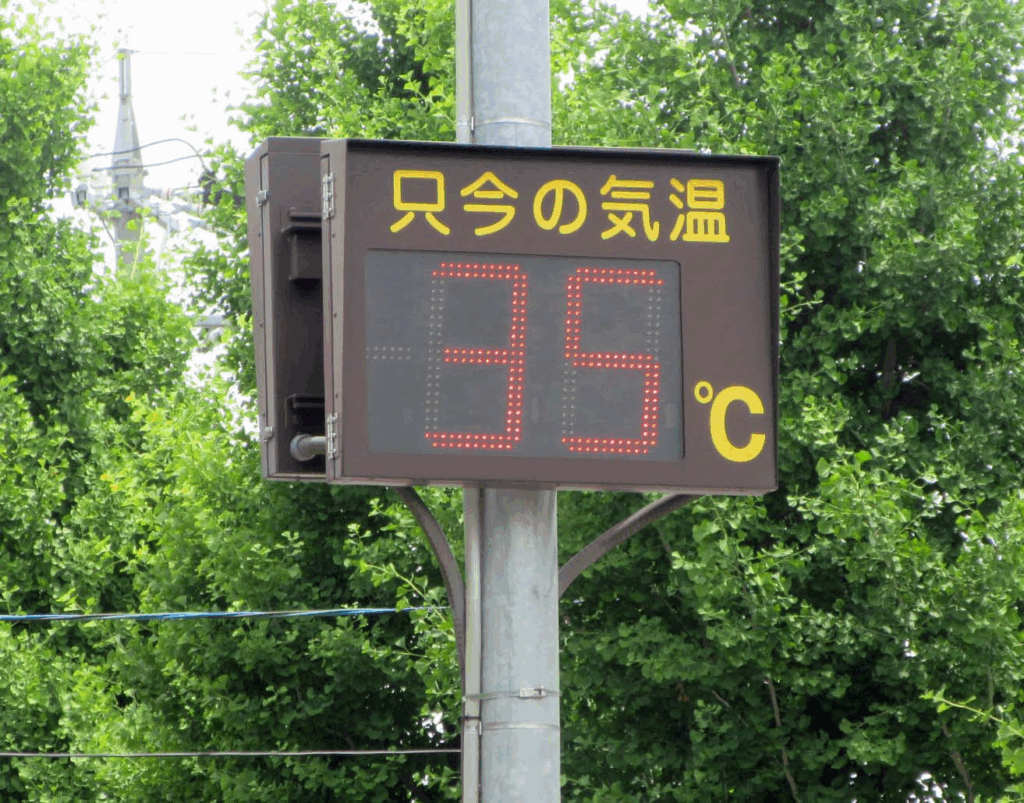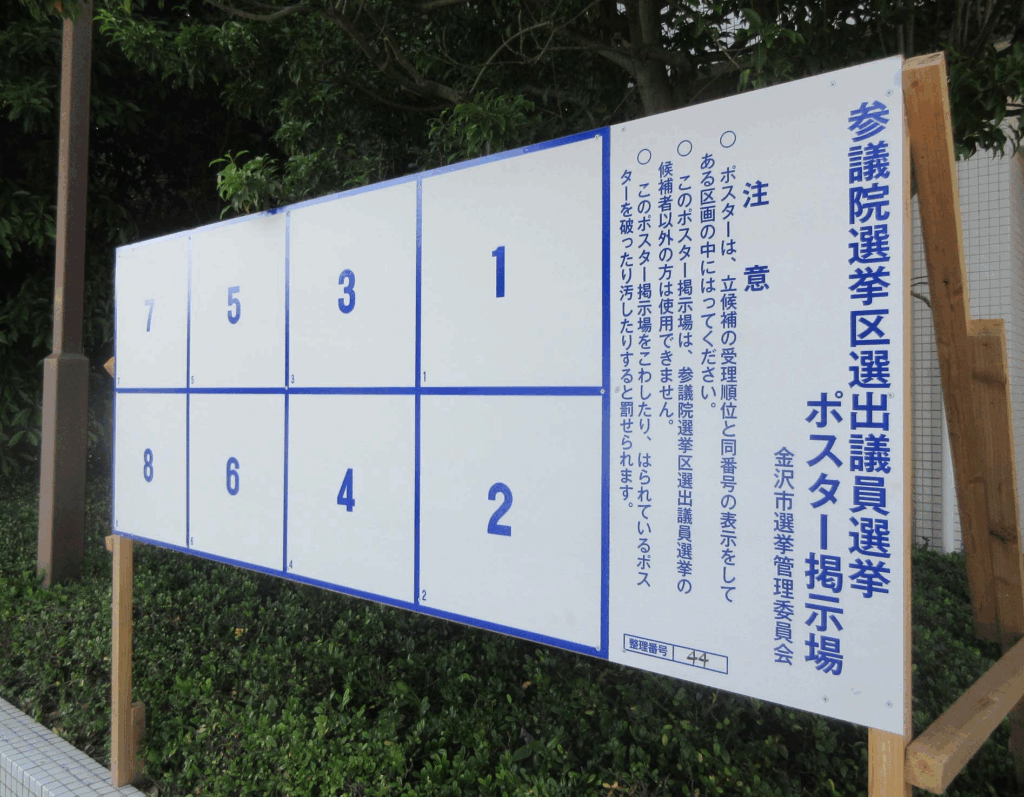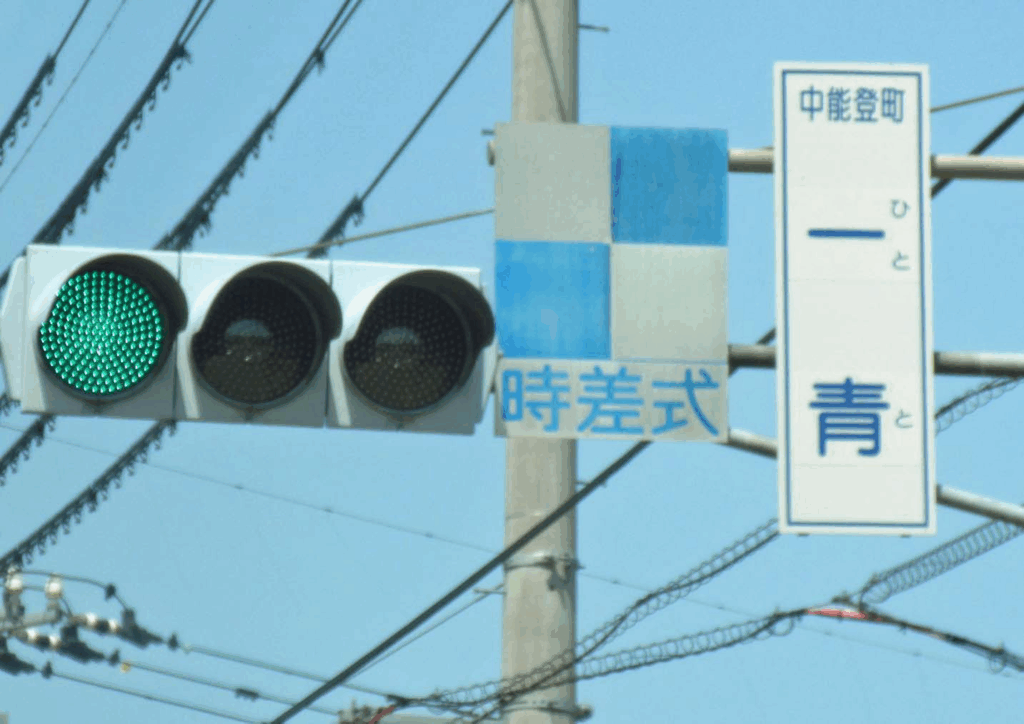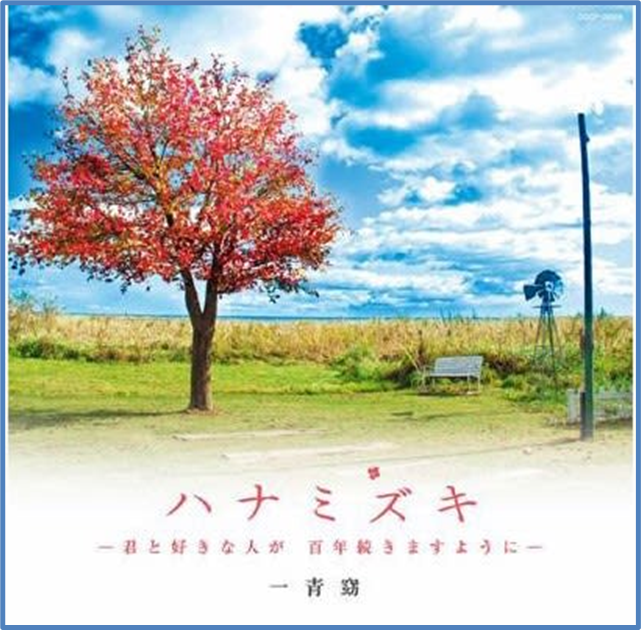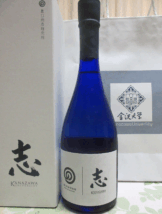☆万博そぞろ歩き(続)・・万博のシンボルは巨大な大屋根リング

万博の作品はパビリオンの中だけではなく、外にも飾られている。中でも、「インド」パビリオンの前にある大きな手のオブジェが目立つ。合掌する青色と肌色の手だ=写真・上=。「ナマステハンド」と呼ばれている。インド人は会ったとき、そして別れの挨拶に合掌して、「ナマステ」と言葉を発する。ナマスは敬礼・服従するという意味で、テは「あなたに」の意味がある(Wikipedia「ナマステ」)。インドのお国柄を象徴するような作品だ。

外から大屋根リングを眺めると、大勢が歩いている。エスカレーターで高さ12㍍の屋上「スカイウォーク」に行き、楽しそうに歩いている様子が見える=写真・中=。リングの全長は2025㍍なので、1㌔をゆっくりめの15分で歩いたとして、30分ほどで一周する。来月7月28日夕方には、スカイウォークで7000人が参加して盆踊り大会が開かれるようだ。

そして、大屋根リングは巨大な休憩所のような雰囲気が漂う=写真・下= 。リングの下は歩ける交通空間であると同時に、雨風や日差しなどを遮る快適な滞留空間として利用されている。EXPO2025公式サイトによると、リングは「多様でありながら、ひとつ」という会場デザインの理念を表すシンボルとなる建築物、と評されている。そして、構造が神社仏閣などの建築に使用されてきた伝統的な貫(ぬき)接合の工法を加えた建築で、和の風格がある。
大屋根リングは、最大の木造建築物としてことし3月4日にギネス世界記録に認定された。正式な英語記録名は「The largest wooden architectural structure」。万博会場を回っていて、万博のシンボルと言われるものはなんだろうかと考えると、やはり大屋根リングだろう。1970年の万博では、芸術家の岡本太郎氏がデザインした、あの「太陽の塔」がシンボルだった。ただし、大屋根リングは万博終了後に一部を残して解体されることになっている(EXPO2025公式サイト)。つかの間の万博のシンボル、そしてギネス世界記録の建築物はさっと姿を消すことになる。個人的には、心に残ればそれでよい。
⇒27日(金)夜・金沢の天気 くもり