★能登の旋風(かぜ)-3-
奥能登の農家には「あえのこと」という田の神を迎える年中行事がある。稲の生育と豊作を願い、田の神をまつる農家の儀礼で、毎年12月と2月に行われる。儀礼は家の主人が中心となり、家内に迎え入れ、風呂や食事でもてなす。いまではわずかな農家でしか伝承されておらず、国の重要無形民俗文化財でもある。この儀礼の特徴は田の神があたかも実在するかのように振る舞う主人の仕草にある。
ホスピタリティの「大学」
 というのも、田の神は目が不自由とされ、迎え入れる主人は想像力をたくましくしながら、「田の神さま、廊下の段差がありますのでお気をつけください」「料理は向かって左がお頭つきのタイでございます」などとリテールにこだわった丁寧な案内と説明をすることになる。これはある意味で高度なホスピタリティ(もてなし)である。招き入れる家の構造、料理の内容はその家によって異なり、自ら目が不自由だと仮定して、どのように案内すれば田の神が転ばずに済むか、居心地がよいか(満足か)とイマジネーションを膨らませトレーニングする。これがホスピタリティ(もてなし)の原点となる。万人に通用するように工夫された外食産業の店員対応マニュアルとは対極にある。
というのも、田の神は目が不自由とされ、迎え入れる主人は想像力をたくましくしながら、「田の神さま、廊下の段差がありますのでお気をつけください」「料理は向かって左がお頭つきのタイでございます」などとリテールにこだわった丁寧な案内と説明をすることになる。これはある意味で高度なホスピタリティ(もてなし)である。招き入れる家の構造、料理の内容はその家によって異なり、自ら目が不自由だと仮定して、どのように案内すれば田の神が転ばずに済むか、居心地がよいか(満足か)とイマジネーションを膨らませトレーニングする。これがホスピタリティ(もてなし)の原点となる。万人に通用するように工夫された外食産業の店員対応マニュアルとは対極にある。
文化庁は7月30日、能登の「あえのこと」を国連教育科学文化機関(ユネスコ)が来年から作成する無形文化遺産のリストに、日本からは第一弾として登録を提案すると発表した。日本から登録を目指すのは、能楽や人形浄瑠璃文楽、歌舞伎と合わせ17件。後世に伝えるべき文化財として国際的に知名度が高まれば、観光面などへの波及効果は大きい。ちなみに「あえ」とは「餐」の字を当てる。
能登にはヨバレという風習がある。夏祭り、秋祭りが集落単位で行われ、神輿(みこし)や山車(だし)、キリコ(奉灯)が繰り出してにぎやか。自宅に親戚、友人、知人を招き入れる。招かれることをヨバレという。その家の祭り料理をヨバレゴッツォという。酒も入る。家族全員がホスト役となった、年に一度の盛大なホームパーティーである。ヨバレた側は今度、自らの集落のお祭りの際には呼んでくれた人を招くことになる。招き、招かれる。この祭りを通じて能登の人たちは幼いころからホスト、ゲストの振る舞いの所作を身に着けることになる。3歳の子供が客人に座布団を出し、中学生ならば熱燗の加減が分るといったふうにである。
能登エコ・スタジアム2008では、能登の祭りをテーマに「キリコ祭りフォーラム」(9月16日・珠洲市)を開催した。フォーラムのオプションとしてヨバレ体験をした。民家の座敷に上げてもらい、赤ご膳でもてなしを受けた。ここで感じたことだが、もてなしを受ける側(ゲスト)ともてなす側(ホスト)とでは同じ座敷でも見える風景が異なるものだ。ただ、2つの立場を理解することは人の素養としては必要なことだ。
日本の温泉観光は「ホスピタリティ産業」とも呼ばれる。中でも、能登の和倉温泉の加賀屋は「プロが選ぶ日本のホテル旅館百選」(主催:旅行新聞新社)で28年連続日本一に選ばれた名旅館だ。加賀屋だけではない。一客一亭でもてなす、レベルの高い旅館や民宿も能登には数多くある。加賀屋の小田禎彦会長から聞いた話(7月11日)だ。「能登は人をもてなす人材の宝庫です」と。
祭りでもてなしを受ける側(ゲスト)ともてなす側(ホスト)を小さいころから体験し、トレーニングを積んでいる。つまり、意識をしなくても能登の人たちはホスピタリティの高度な実践教育を受けている。これをプロ人材として生かしているのが和倉温泉でもある。その権化(オーソリティ)が加賀屋ということになる。まさに能登は「ホスピタリティの大学」なのだ。しかも、小中高と一貫の。その原点は、目の不自由な田の神をもてなす「あえのこと」だと考えている。さしずめ建学の精神といったところか。(※写真:能登エコ・スタジアム2008「祭りヨバレ体験」=9月16日、珠洲市)
⇒22日(月)夜・神戸の天気 くもり
 実は今回のイベント「能登エコ・スタジアム2008」もその関連会議のシュミレーションとしての意味合いで金沢セッション、能登エクスカーションが構成された。ジョグラフ氏の能登訪問は2010年の能登エクスカーションの「下見」との意義付けもある。もし、ジョグラフ氏がここで「能登で見るべきもの、学ぶべきものはない」と感じれば、2010年の能登エクスカーションは沙汰やみになる。迎えるスタッフもプラン段階から気を遣った。では、ジョグラフ氏の反応はどうだったのか。
実は今回のイベント「能登エコ・スタジアム2008」もその関連会議のシュミレーションとしての意味合いで金沢セッション、能登エクスカーションが構成された。ジョグラフ氏の能登訪問は2010年の能登エクスカーションの「下見」との意義付けもある。もし、ジョグラフ氏がここで「能登で見るべきもの、学ぶべきものはない」と感じれば、2010年の能登エクスカーションは沙汰やみになる。迎えるスタッフもプラン段階から気を遣った。では、ジョグラフ氏の反応はどうだったのか。 まず、「能登エコ・スタジアム2008」の概要を説明しよう。金沢大学などが企画し,地域自治体と連携して開催した初めての大型イベント。4日間で3つのシンポジウム、6つのイベント、1つのツアーを実施した。生物多様性などの環境問題を理解するとともに、海や山を活用した地域振興策を探ろうという内容。13日に開催したキックオフシポジウム「里山里海から地球へ」=写真=には市民ら280人が参加し、国連大学の武内和彦副学長(東京大学教授)や生物多様性ASEANセンターのG.W.ロザリアストコ部長、女子美術大学の北川フラム教授が講演した。
まず、「能登エコ・スタジアム2008」の概要を説明しよう。金沢大学などが企画し,地域自治体と連携して開催した初めての大型イベント。4日間で3つのシンポジウム、6つのイベント、1つのツアーを実施した。生物多様性などの環境問題を理解するとともに、海や山を活用した地域振興策を探ろうという内容。13日に開催したキックオフシポジウム「里山里海から地球へ」=写真=には市民ら280人が参加し、国連大学の武内和彦副学長(東京大学教授)や生物多様性ASEANセンターのG.W.ロザリアストコ部長、女子美術大学の北川フラム教授が講演した。 この文を書いていたとき、実は念頭に石川県の谷本正憲知事のことがあった。失礼な言い方になるかもしれないが、谷本氏はことし春ごろまで、それほど里山や里海といった言葉に深い造詣を抱いてはおられなかったと思う。ところが、この4月に金沢で設置された国連大学の研究所(いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット)が里山里海を研究テーマにしていること、さらにドイツでの環境視察(5月22日-29日)、その視察の最中で生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)の関連会議でスピーチをきっかけとして猛勉強され、いまではおそらく「里山知事」を自認するまでになった。そして、環境への取り組みとして、里山里海をテーマに行政施策に反映させてもいる。谷本知事には里山里海の風景がこれまでとまったく違って見えているのだ。
この文を書いていたとき、実は念頭に石川県の谷本正憲知事のことがあった。失礼な言い方になるかもしれないが、谷本氏はことし春ごろまで、それほど里山や里海といった言葉に深い造詣を抱いてはおられなかったと思う。ところが、この4月に金沢で設置された国連大学の研究所(いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット)が里山里海を研究テーマにしていること、さらにドイツでの環境視察(5月22日-29日)、その視察の最中で生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)の関連会議でスピーチをきっかけとして猛勉強され、いまではおそらく「里山知事」を自認するまでになった。そして、環境への取り組みとして、里山里海をテーマに行政施策に反映させてもいる。谷本知事には里山里海の風景がこれまでとまったく違って見えているのだ。 ~里山里海(さとやまさとうみ)という言葉が最近よく使われるようになってきました。日本ではちょっと郊外に足を運べば里山があり里海が広がります。実はそこは多様な生物を育む生態系(エコシステム)であるとことを、私たち日本人は忘れてしまっていたようです。二酸化炭素の吸収、生物多様性、持続可能な社会など、環境を考えるさまざまなキーワードが里山里海に潜んでいます。「能登エコ・スタジアム2008」ではこれらのキーワードを探す旅をします。それを発見したとき、あなたが見える里山里海の風景は一変するはずです。~
~里山里海(さとやまさとうみ)という言葉が最近よく使われるようになってきました。日本ではちょっと郊外に足を運べば里山があり里海が広がります。実はそこは多様な生物を育む生態系(エコシステム)であるとことを、私たち日本人は忘れてしまっていたようです。二酸化炭素の吸収、生物多様性、持続可能な社会など、環境を考えるさまざまなキーワードが里山里海に潜んでいます。「能登エコ・スタジアム2008」ではこれらのキーワードを探す旅をします。それを発見したとき、あなたが見える里山里海の風景は一変するはずです。~ 先月(7月)28日に金沢市を襲った豪雨は午前5時から8時までの3時間で254㍉だった。報道によると、県が「百年に一度」と想定している規模の雨量は2日間で260㍉なので、まさに「想定外」の降りだった。金沢市災害対策本部が2万世帯5万人に避難指示をした。27日から日本海から北陸地方にかけて東西に前線が停滞し、28日に南からの暖かい湿った空気が流れ込んできた。このため、大気が不安定となり、雲が急速に発達し、短時間で激しい雨をもたらしたというの金沢地方気象台の見解だ。
先月(7月)28日に金沢市を襲った豪雨は午前5時から8時までの3時間で254㍉だった。報道によると、県が「百年に一度」と想定している規模の雨量は2日間で260㍉なので、まさに「想定外」の降りだった。金沢市災害対策本部が2万世帯5万人に避難指示をした。27日から日本海から北陸地方にかけて東西に前線が停滞し、28日に南からの暖かい湿った空気が流れ込んできた。このため、大気が不安定となり、雲が急速に発達し、短時間で激しい雨をもたらしたというの金沢地方気象台の見解だ。 国連世界食糧計画(WFP)と国連食糧農業機関(FAO)は毎年、緊急の食料援助を必要とする国をリストアップしている。2007年5月にリストアップされたのは33カ国。このうち17カ国は内戦と紛争で、食料援助しようにも、その活動が阻まれるところ多い。つまり、援助部隊が襲撃されることもある。そんな国は間違いなく破綻に向かう。
国連世界食糧計画(WFP)と国連食糧農業機関(FAO)は毎年、緊急の食料援助を必要とする国をリストアップしている。2007年5月にリストアップされたのは33カ国。このうち17カ国は内戦と紛争で、食料援助しようにも、その活動が阻まれるところ多い。つまり、援助部隊が襲撃されることもある。そんな国は間違いなく破綻に向かう。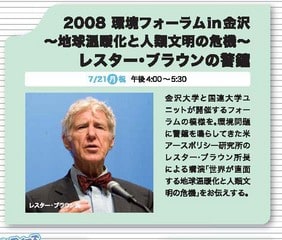 その講演会でのこぼれ話。レスター氏はペットボトルの水を嫌がった。水をわざわざペットボトルに入れなくても、水差しでよい、石油を原材料にする経済の仕組みはもう転換すべきだとはレスター氏の主張だ。そして講演20分前には瞑想に入り、スニーカーで登壇した。
その講演会でのこぼれ話。レスター氏はペットボトルの水を嫌がった。水をわざわざペットボトルに入れなくても、水差しでよい、石油を原材料にする経済の仕組みはもう転換すべきだとはレスター氏の主張だ。そして講演20分前には瞑想に入り、スニーカーで登壇した。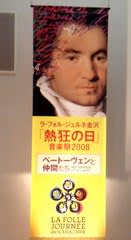 この「自在コラム」でも何度か取り上げたベートーベンの話を再度。昨年10月から、金沢大学が運営する「能登里山マイスター」養成プログラムに携わっていて、能登通いが続いている。車で大学から片道2時間30分(休憩込み)をみている。何しろ能登学舎があるのは能登半島の先端、距離にしてざっと160㌔にもなる。早朝もあれば、深夜もある。体調がすぐれないときや、疲れたときもある。運転にはリスクがつきまとう。同乗者がいればまだよいが、怖いのは一人での運転である。眠気が襲う。
この「自在コラム」でも何度か取り上げたベートーベンの話を再度。昨年10月から、金沢大学が運営する「能登里山マイスター」養成プログラムに携わっていて、能登通いが続いている。車で大学から片道2時間30分(休憩込み)をみている。何しろ能登学舎があるのは能登半島の先端、距離にしてざっと160㌔にもなる。早朝もあれば、深夜もある。体調がすぐれないときや、疲れたときもある。運転にはリスクがつきまとう。同乗者がいればまだよいが、怖いのは一人での運転である。眠気が襲う。 3年前の冬だった。金沢の行きつけのスナックに入ると、珍しくジャズピアノのキース・ジャレット(Keith・Jarrett)のCDがかかっていた。キース・ジャレットは1975年に初めて、当時のPLで「ケルン・コンツェルト」を聴き、すっかりファンになった。鍵盤を回すような軽快な旋律、そして興に乗って発せられるキース・ジャレット自身の呟きが、いかにも即興ライブという感じで、心に響く。
3年前の冬だった。金沢の行きつけのスナックに入ると、珍しくジャズピアノのキース・ジャレット(Keith・Jarrett)のCDがかかっていた。キース・ジャレットは1975年に初めて、当時のPLで「ケルン・コンツェルト」を聴き、すっかりファンになった。鍵盤を回すような軽快な旋律、そして興に乗って発せられるキース・ジャレット自身の呟きが、いかにも即興ライブという感じで、心に響く。