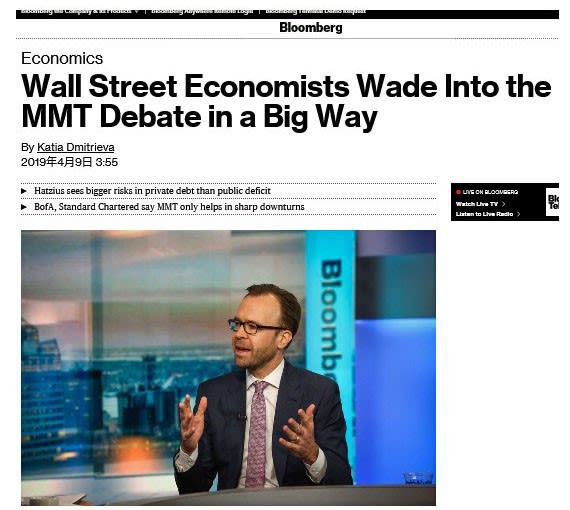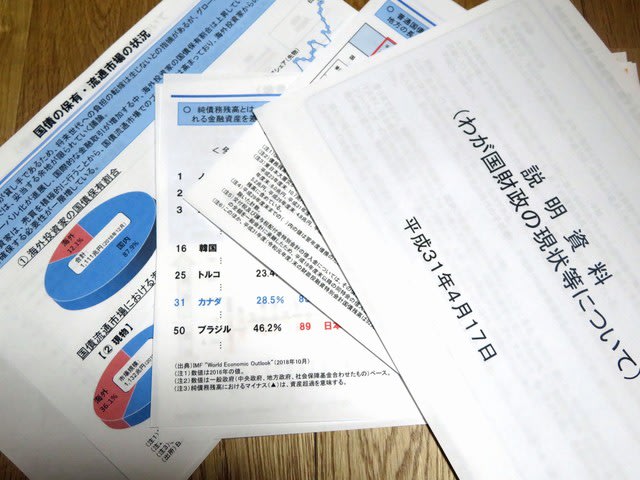☆計算された「拡大自殺」
きのう28日朝、ブログを書いているときにニュースが流れた。川崎市多摩区の路上でスクールバスを待っていた小学生や大人が51歳の男に次々と包丁で刺され、女子児童と30代の男性の2人が死亡、17人がけがを負った、と。男は身柄を確保されたが、自ら首を刺して搬送先の病院で死亡した。目撃情報では、「ぶっ殺すぞ」と男は叫び、子どもたちを襲った。
 ニュースで知る限り、犯人と犠牲者との間に接点はない。現場には使われたとみられる包丁2本が落ちていたほか、男のリュックサックの中には使用されていない包丁がさらに2本があった。包丁4本で犯行に及んだと推測される。推測だが、落ちていた2本は他殺用に、リュックの2本は自殺用だったのではないだろうか。保険証があったので身元がすぐに割れた。逃走する意思もなかったのだろう。
ニュースで知る限り、犯人と犠牲者との間に接点はない。現場には使われたとみられる包丁2本が落ちていたほか、男のリュックサックの中には使用されていない包丁がさらに2本があった。包丁4本で犯行に及んだと推測される。推測だが、落ちていた2本は他殺用に、リュックの2本は自殺用だったのではないだろうか。保険証があったので身元がすぐに割れた。逃走する意思もなかったのだろう。
この事件で浮かんだのは「拡大自殺」という言葉だ。この聞き慣れない言葉は、ウイキペディアなどによると、その定義として、1)本人に死の意志 2)1名以上の他者を相手の同意なく自殺行為に巻き込む 3)犯罪と、他殺の結果でない自殺とが同時に行われること。道連れ殺人ともいえる。アメリカでは学校でライフル銃を乱射した後に自殺するケースが多いが、典型的な拡大自殺だろう。
身近に事件があった。2017年3月10日、石川県能登町で帰宅するためバス停で待っていた高校1年の女子生徒が連れ去られ、バス停から5㌔離れた山あいの集落の空き家で頭から血を流して死亡しているのが見つかった。殺害したとされる男子大学生21歳は同日午後7時40分ごろ、空き家から16㌔離れた道路に飛び出して乗用車にはねられ死亡した。2人は顔見知りではなく、死亡した男子学生は一人でバス停で待っていた女子高生を角材で殴り、車で連れ去って、空き家(祖父の家)で殺害した。その殺害動機は解明されていない。
男子学生が自殺を図った現場の能越自動車道穴水道路は能登との往復でよく利用する。上下それぞれ1車線で部分的に両脇がコンクリート壁になっていて狭く感じる。ここで急に道路に飛び込んでくる人影があっても、それを避けようにも車体を横に切ることはできない場所だ。まして夜である。他殺、自殺、死亡事故。計算し尽された死の演出ではなかったか。拡大自殺の巻き添えになった女子高生が痛ましい。(写真は、川崎の殺傷事件を伝える28日付の夕刊各紙)
⇒29日(水)朝・金沢の天気 くもり