☆「光で再生した古い家」と「金継ぎの皿」
能登半島の珠洲市で開催された「創造都市ネットワーク日本(CCNJ)現代芸術の国際展部会シンポジウム」の続き。2日目(最終日)はバスで常設作品を見学するエクスカーションだった。印象的だったのは中島伽耶子作『あかるい家 Bright house』。珠洲は珪藻土で屋根瓦や七輪などを生産する工場がいまもある。 使われなくなった相当古い戸建ての事務所に入ると、まるで銀河の世界のようだった=写真・上=。外壁や屋根に無数の穴が開けられていて、穴から太陽光が差し込んでくる。
使われなくなった相当古い戸建ての事務所に入ると、まるで銀河の世界のようだった=写真・上=。外壁や屋根に無数の穴が開けられていて、穴から太陽光が差し込んでくる。
よく見ると、穴の一つ一つには穴と同じ直径の透明の円柱のプラスチックが埋め込まれていて、雨や風などが入ってこないように工夫されている。それにしても、星空のごとく無数の穴を創るだけで相当の労力だ。柱や梁がしっかりと造られているものの、古いこの家をアートとして再生させた作家のモチベーションを聴きたくなった。
6作品をめぐるエクスカーションの最後は「スズ・シアター・ミュージアム『光の方舟』」。このミュージアムのコンセプトは「大蔵ざらえプロジェクト」。半島の尖端にある珠洲は古来より農業や漁業、商いが盛んだったが、当時の民具などは時代とともに使われなくなり、その多くが家の蔵や納屋に保管されたまま忘れ去れていた。市民の協力を得て蔵ざらえした1500点を活用し、8組のアーティスト と専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館としてミュージアムがオープンした。日本海を見下ろす高台にある廃校となった小学校の体育館だ。
と専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館としてミュージアムがオープンした。日本海を見下ろす高台にある廃校となった小学校の体育館だ。
奥能登は「キリコ祭り」という伝統的な祭り行事がいまでも盛んで、人を料理でもてなすことを「ヨバレ」と言う。そのヨバレで使われたであろう古い食器などが展示されているコーナーを見学した。目に止まったのが「金継ぎ」の大皿だった=写真・下=。松の木とツルとカメの絵が描かれ、めでたい席で使われたのだろう。それを、うっかり落としたか、何かに当てたのだろうか。中心から4方に金継ぎの線が延びている。
東京パラリンピックの閉会式でアンドリュー・パーソンズ会長が発した言葉を思い出した。器のひび割れを漆と金粉を使って器として再生する日本の金継ぎの技術について、「不完全さを受け入れ、隠すのではなく、大切にしようという発想であり素晴らしい」と述べて、金継ぎという言葉が世界でもトレンドになった。
この家の大正か昭和の初めのころの皿だろうか。金継ぎの皿からその家のにぎわいやもてなし、そして「もったいない」の気持ちが伝わる家風まで見えてきたような思いだった。
⇒23日(日)夜・金沢の天気 くもり
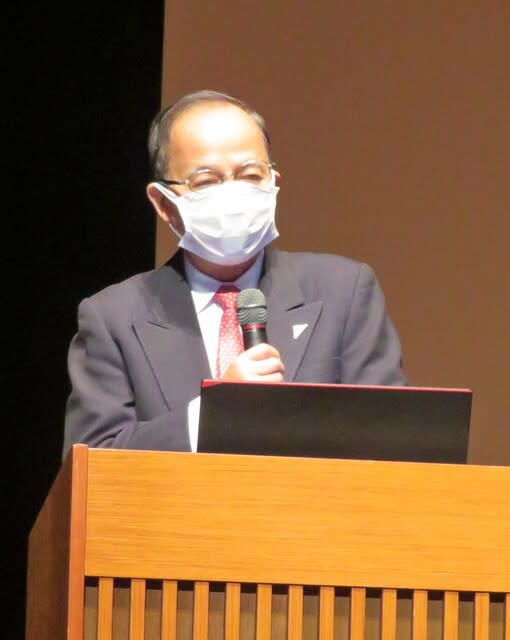 珠洲市で昨年秋に開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の総合ディレクターの北川フラム氏=写真・上=が「持続可能な地域社会と国際芸術祭」と題して基調講演。「厳しい地域ほど魅力的で、珠洲は地政学的にも特異点がある。芸術祭で大いに変わる可能性がある。ぜひ10年で最低3回の芸術祭をやってほしい」と述べた。珠洲の特異点として、「この地には日本で失われた生活が残っている。そして、国と人がつながる日本海を望む『さいはての地』であり、鉄道の消滅点でもある。地域コミュニティーの絆が強く、里山里海の自然環境に恵まれている。アートはこうした特異点に迫っていく」とアーチスト目線で珠洲の魅力と可能性を強調した。
珠洲市で昨年秋に開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の総合ディレクターの北川フラム氏=写真・上=が「持続可能な地域社会と国際芸術祭」と題して基調講演。「厳しい地域ほど魅力的で、珠洲は地政学的にも特異点がある。芸術祭で大いに変わる可能性がある。ぜひ10年で最低3回の芸術祭をやってほしい」と述べた。珠洲の特異点として、「この地には日本で失われた生活が残っている。そして、国と人がつながる日本海を望む『さいはての地』であり、鉄道の消滅点でもある。地域コミュニティーの絆が強く、里山里海の自然環境に恵まれている。アートはこうした特異点に迫っていく」とアーチスト目線で珠洲の魅力と可能性を強調した。 か。北川フラム氏が述べたように、半島の先端という地理的な条件や過疎化といったハンディはアーチストにとって「厳しい地域こそ魅力的」に感じ、移住者も共感するという現象なのか。
か。北川フラム氏が述べたように、半島の先端という地理的な条件や過疎化といったハンディはアーチストにとって「厳しい地域こそ魅力的」に感じ、移住者も共感するという現象なのか。 