★「金継ぎ」の発想で能登復興の10年先、20年先をつなぐ
輪島市や珠洲市など能登半島地震の被災地をめぐると、これまで行き来した能登での思い出などが蘇って来る。輪島で倒壊した7階建ての建物は、輪島塗の製造販売(塗師屋)の大手「五島屋」のビルだ=写真・上=。倒壊した内部の様子を外から見ると、グランドピアノが横倒しになっている。展示場で飾られてあった、輪島塗のピアノだろうと察した。
 もう40年も前の話だが、当時、新聞記者として輪島支局に赴いた。そのとき、当時の社長の五島耕太郎氏(1938-2014)と取材を通じて知り合った。チャレンジ精神が旺盛で、「ジャパン(japan)は漆器のことなんだよ」と言い、海外での展示販売などに積極的だった。また、「輪島塗は器や盆だけじゃない。ピアノも輪島塗でできる」と話していたことを覚えている。バブル景気の走りのころで、輪島塗業界には勢いがあった。その後、五島氏は1986年に輪島市長に就き、3期12年つとめた。そして漆器業界はバルブ経済絶頂には年間生産額が180億円(1991年)に達した。横倒しになったグランドピアノはそんなころに作られたものかと憶測した。
もう40年も前の話だが、当時、新聞記者として輪島支局に赴いた。そのとき、当時の社長の五島耕太郎氏(1938-2014)と取材を通じて知り合った。チャレンジ精神が旺盛で、「ジャパン(japan)は漆器のことなんだよ」と言い、海外での展示販売などに積極的だった。また、「輪島塗は器や盆だけじゃない。ピアノも輪島塗でできる」と話していたことを覚えている。バブル景気の走りのころで、輪島塗業界には勢いがあった。その後、五島氏は1986年に輪島市長に就き、3期12年つとめた。そして漆器業界はバルブ経済絶頂には年間生産額が180億円(1991年)に達した。横倒しになったグランドピアノはそんなころに作られたものかと憶測した。
話は変わるが、輪島塗は塗り物だが、焼き物との接点もある。「金継ぎ」と呼ばれる、陶器の割れを漆と金粉を使って器として再生する技術のこと。2022年1月に珠洲市の国際芸術祭の会場の一つ「スズ・シアター・ミュージアム『光の 方舟』」にある大皿にも金継ぎが施されていた。松の木とツルとカメの絵が描かれ、めでたい席で使われたのだろう。それを、うっかり落としたか、何かに当てたのだろうか。中心から4方に金継ぎの線が延びている=写真・下=。大正か昭和の初めのころの作か。金継ぎの皿からその家のにぎわいやもてなし、そして「もったいない」の気持ちが伝わってくる。
方舟』」にある大皿にも金継ぎが施されていた。松の木とツルとカメの絵が描かれ、めでたい席で使われたのだろう。それを、うっかり落としたか、何かに当てたのだろうか。中心から4方に金継ぎの線が延びている=写真・下=。大正か昭和の初めのころの作か。金継ぎの皿からその家のにぎわいやもてなし、そして「もったいない」の気持ちが伝わってくる。
「kintsugi」という言葉が世間に、そして世界に広がったきっかけは、東京パラリンピックの閉会式(国立競技場・2021年9月5日)でアンドリュー・パーソンズ会長が発した言葉だった。日本の金継ぎの技術について、「不完全さを受け入れ、隠すのではなく、大切にしようという発想であり素晴らしい」と述べた。その背景には、サステナビリティやサーキュラーエコノミー(循環型経済)を各国が推し進めていることもある。
輪島で受け継がれている金継ぎ技術から連想するのは、震災で壊れた能登の復興だ。壊れた皿に漆と金箔を使うことでアートを施して芸術的価値を高める。能登の復興も単なる復興ではなく、不完全さを受け入れながらも住み易さや、未来への可能性を確信させる街づくりに向っていく。金継ぎの発想で能登の復興の10年先、20年先をつなぐ。そうあってほしい。
⇒13日(土)午後・金沢の天気 はれ
 2020年にユネスコ無形文化遺産にも登録されている。
2020年にユネスコ無形文化遺産にも登録されている。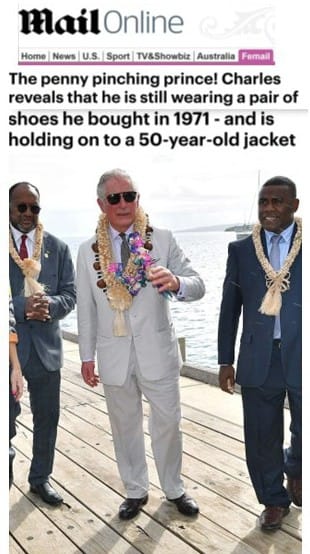 ら、この言葉が広がったようだ。丁寧な修繕という意味だろうか。靴の場合、ただの革のパッチではなく、張り合わせた革を縫いつけ固定することで、ひび割れなどを隠して補強するという丁寧な補修を指す。
ら、この言葉が広がったようだ。丁寧な修繕という意味だろうか。靴の場合、ただの革のパッチではなく、張り合わせた革を縫いつけ固定することで、ひび割れなどを隠して補強するという丁寧な補修を指す。 金継ぎという言葉が世界に広がったきっかけがあった。東京パラリンピックの閉会式(国立競技場・2021年9月5日)でアンドリュー・パーソンズ会長が発した言葉だった。日本の金継ぎの技術について、「不完全さを受け入れ、隠すのではなく、大切にしようという発想であり素晴らしい」と述べて、金継ぎという言葉が世界でもトレンドになった。さらに、金継ぎは一度は壊れてしまった製品を修復するだけでなく、金箔を使うことでアートを施し、芸術的価値を高める。
金継ぎという言葉が世界に広がったきっかけがあった。東京パラリンピックの閉会式(国立競技場・2021年9月5日)でアンドリュー・パーソンズ会長が発した言葉だった。日本の金継ぎの技術について、「不完全さを受け入れ、隠すのではなく、大切にしようという発想であり素晴らしい」と述べて、金継ぎという言葉が世界でもトレンドになった。さらに、金継ぎは一度は壊れてしまった製品を修復するだけでなく、金箔を使うことでアートを施し、芸術的価値を高める。 使われなくなった相当古い戸建ての事務所に入ると、まるで銀河の世界のようだった=写真・上=。外壁や屋根に無数の穴が開けられていて、穴から太陽光が差し込んでくる。
使われなくなった相当古い戸建ての事務所に入ると、まるで銀河の世界のようだった=写真・上=。外壁や屋根に無数の穴が開けられていて、穴から太陽光が差し込んでくる。