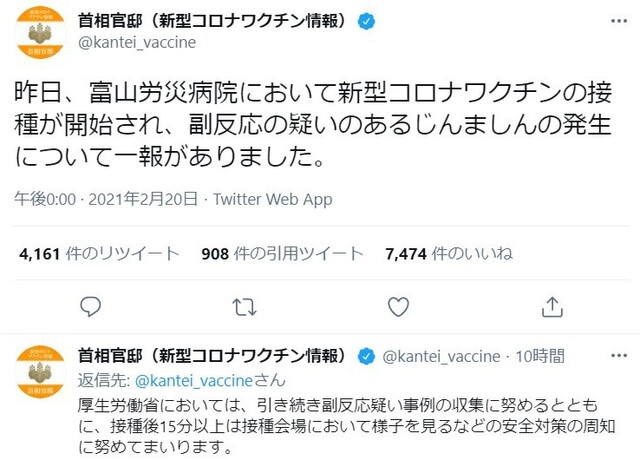DX(デジタル・トランスフォーメーション)が叫ばれているが、一番出遅れているのか民放ではないかと考えることがある。なぜなら、放送と通信(ネット)の同時配信がいまだに進んでいないからだ。そのネックの一つとなっていた著作権問題では道筋が見えてきたようだ。放送番組のインターネット同時配信の著作権問題について、文化庁著作権分科会のワーキングチームはきのう(11月30日)、ネット配信の著作権の処理については放送と同等に扱うべきとする報告書案をまとめた。
現状、著作権は放送と通信(ネット)では「平等」ではないという現実がある。たとえば、テレビ局が番組に曲を使う場合、実演家(演奏者・歌手・俳優)やレコード会社に事後報告でよいが、ネットでの使用の場合は事前許諾が必要となる。ただし、作詞家や作曲家には双方とも事前許諾が必要だ。このため、NHKは民放に先行してことし4月から1日18時間の同時配信の運用を始めているが、番組をネットに同時送信するため、わざわざ事前許諾を求めている。その権利処理が行えない場合には曲をカットしたり、差し替えをする、業界用語で「ふたかぶせ」の対応を迫られている。
 事前の著作権許諾の作業だけでもスタッフの配置が必要なためにコストもかさむことは想像に難くない。さらに、出演料なども地上波のみから、ネット配信もということになれば、値上げが必然となるだろう。NHKの2020年度インターネット活用業務実施計画(1月15日付)によると、今年度から同時配信を進めるために設備費や放送権料などにかかわる費用として54億円を計上している。
事前の著作権許諾の作業だけでもスタッフの配置が必要なためにコストもかさむことは想像に難くない。さらに、出演料なども地上波のみから、ネット配信もということになれば、値上げが必然となるだろう。NHKの2020年度インターネット活用業務実施計画(1月15日付)によると、今年度から同時配信を進めるために設備費や放送権料などにかかわる費用として54億円を計上している。
仮に著作権問題がある程度軽減されたとして、民放の同時配信が進むかと問えば、さらに、別の大きな問題もある。一つはCMだ。テレビ離れが進んでいるといわれる若者たちがスマホやタブレットでテレビを視聴できる環境をつくったとして、局側がスポンサーにCM料を地上波に上乗せして払ってくれと言えるだろうか。地上波でのCM料は視聴率という目安があるが、同時配信でのネット上のCM料の目安はいまだ確立されてはいない。スマホやタブレット上の競争相手はテレビ局ではない、動画コンテンツは無限にある。
もう一つは県域問題だ。ローカル局には放送法で「県域」というものがあり、放送免許は基本的に県単位で1波、あるいは数県で1波が割り与えられている。1波とは、東京キー局(日本テレビ、テレビ朝日、TBS、フジテレビ、テレビ東京)の系列ローカル局のこと。逆に言うと、スマホやタブレットで東京キー局の番組を視聴できれば、同じ系列局のローカル局の番組は視聴されなくなるかもしれない。
このように書くと、民放、とくにロ-カル局には夢も希望もないような表現になる。が、個人的には同時配信に踏み切ることでローカル局にはチャンスが生まれると言いたい。ここからは持論だ。ローカル局が自社制作番組をネット配信をすることで、首都圏や遠方の他県に住む出身者など新たな視聴者層を開拓できるのではないだろうか。「ふるさと」をアピールできる。出身者でなくても、金沢・能登・加賀ファンをつかむことができる。
できれば、金沢からリアルな情報を発信する動画配信サービスのサイトを石川県内の民放4局が共同出資でつくってほしい。それも、日本語と英語で構築できないだろうか。能登、金沢、加賀の県内各地のケーブルテレビ局も巻き込んで、「KANAZAWAチャンネル」をつくり、観光・ツーリズムを発信する。これまでの規制にとらわれない、新たなパラダイムがテレビ局に求められているのではないだろうか。今回の著作権の緩和はそのスタートだと解釈している。
⇒1日(火)夜・金沢の天気 はれ時々くもり
 ー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすようだ。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。
ー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすようだ。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。