☆能登大雨で熊木川の氾濫 大伴家持が詠んだ「熊来」伝説
きょうから7月、その初日は能登半島は大雨に見舞われた。とくに中能登と呼ばれている七尾市中島地区の熊木川の一部流域では、氾濫危険水位を超えて農地や道路が冠水し、住宅では床下浸水の被害があった。中島地区など5800世帯・1万4100人を対象に避難指示が発令された=写真、1日付・夕刊各紙=。
 このニュースが気になったもの、中島地区で激しい雨を自身も経験したことがあるからだ。ちょうど6年前、2017年7月1日だ。能登へ乗用車で出かけ、自動車専用道「のと里山海道」の中島地区で、大雨に巻き込まれた。雨がたたきつけるようにフロントガラスに当たり、ワイパーの回転を一番速くしても前方が見えず、しばらく車を停車し小降りになるのを待った。再び出発すると、たたきつけるような雨に再び見舞われた。3度運転を見合わせた。波状的な激しい雨は初めてだった。このとき能登では1時間で53㍉の非常に激しい雨が観測され、七尾市の崎山川や熊木川などが一部氾濫した。
このニュースが気になったもの、中島地区で激しい雨を自身も経験したことがあるからだ。ちょうど6年前、2017年7月1日だ。能登へ乗用車で出かけ、自動車専用道「のと里山海道」の中島地区で、大雨に巻き込まれた。雨がたたきつけるようにフロントガラスに当たり、ワイパーの回転を一番速くしても前方が見えず、しばらく車を停車し小降りになるのを待った。再び出発すると、たたきつけるような雨に再び見舞われた。3度運転を見合わせた。波状的な激しい雨は初めてだった。このとき能登では1時間で53㍉の非常に激しい雨が観測され、七尾市の崎山川や熊木川などが一部氾濫した。
話は変わるが、熊木川にはちょっとした思い入れもある。川の河口の七尾西湾は「能登かき」で知られる養殖カキの産地でもある。里山の栄養分が熊木川を伝って流れ、湾に注ぎこむ。その栄養分が植物プランクトンや海藻を育み、海域の食物連鎖へと広がり、カキもよく育つとされる。とくに、里山の腐葉土に蓄えられた栄養分「フルボ酸鉄」が豊富にあると現地で学んだことがある(2010年5月・金沢大学「里山里海環境調査」)。学習的なことは別として、能登かきのファンにとっては気になる場所なのだ。
和歌をたしなむ人々にとっても気にかかるのが「熊来」(のちに熊木村、現在の中島地区)かもしれない。天平20年(748)に越中国の国司だった大伴家持が能登を巡行している。そのときに詠んだ歌が万葉集におさめられている。「香島より熊来をさして漕ぐ舟の梶取る間なく都し思ほゆ」。以下、自己解釈で。(七尾の)香島から熊来の在所に向かって舟を漕いでいく。舟舵を取るのも忙しいが、それ以上に都のことがひっきりなしに思い浮かんでくる。
作者は不詳だが、万葉集にはさらに2つの「熊来」が出て来る。「梯立の熊来のやらに新羅斧堕入れわし懸けて懸けて勿泣なかしそね浮き出づるやと見むわし」「梯立の熊来酒屋に真罵らる奴わし誘い立て率て来なましを真罵らる奴わし」(※七尾市「能登国府」パンフより)
ある愚か者が鉄斧を熊来の河口の海底にうっかり落とした。海に沈んでしまえばもう浮かび上がることはないのに泣いてばかりいるので、しかたなく「そのうち浮かんで来るよ」とみんなでなだめた。熊木の在所の酒蔵でえらく怒鳴られている従業員がいたので、誘って連れ出そうかと思ったが、「怒鳴られているあんたはどうする」と。
8世紀に成立した日本最古の和歌集に、おそらく当時の最先端の言葉であったであろう「酒屋」と「新羅斧」が出てくる能登はどのような風景だったのか。豪雨の熊木川から連想した。
⇒1日(土)夜・金沢の天気 あめ
 えり、周囲の山水古木と調和して大本山の面影をしのばせる(総持寺パンフ)。2007年3月の能登半島地震でも大きな被害を受け、開創700年の2021年4月には修復工事が完了し落慶法要が営まれている。
えり、周囲の山水古木と調和して大本山の面影をしのばせる(総持寺パンフ)。2007年3月の能登半島地震でも大きな被害を受け、開創700年の2021年4月には修復工事が完了し落慶法要が営まれている。 葉の一つ一つが重く、そして心に透き通る。最後に、ドイツに戻っての布教は考えているのかと質問すると、「結婚し、子どもにも恵まれた。能登でさらに修行を積みたい」との返事だった。
葉の一つ一つが重く、そして心に透き通る。最後に、ドイツに戻っての布教は考えているのかと質問すると、「結婚し、子どもにも恵まれた。能登でさらに修行を積みたい」との返事だった。 その火様を今でも守っているお宅があることを聞いたのは10年前のこと。2014年8月、教えていただいた方に連れられてお宅を訪れた。能登半島の中ほどにある七尾市中島町河内の集落。かつて林業が盛んだった集落で、里山の風景が広がる。訪れたお宅の居間の大きな囲炉裏には、300年余り受け継がれてきたという火様があった。囲炉裏の真ん中に炭火があり、その一部が赤く燃えていた=写真=。訪れたのは夕方だったので、これから灰を被せるところだった。この集落でも火様を守っているのはこの一軒だけになったとのことだった。このお宅の火様を守っているのは、一人暮らしのお年寄りだった。
その火様を今でも守っているお宅があることを聞いたのは10年前のこと。2014年8月、教えていただいた方に連れられてお宅を訪れた。能登半島の中ほどにある七尾市中島町河内の集落。かつて林業が盛んだった集落で、里山の風景が広がる。訪れたお宅の居間の大きな囲炉裏には、300年余り受け継がれてきたという火様があった。囲炉裏の真ん中に炭火があり、その一部が赤く燃えていた=写真=。訪れたのは夕方だったので、これから灰を被せるところだった。この集落でも火様を守っているのはこの一軒だけになったとのことだった。このお宅の火様を守っているのは、一人暮らしのお年寄りだった。 のうち、審査で1本が認定された。「煌」第1号は重さ15.5㌔で体長94㌢の大物だ。例年、寒ブリは比較的高値がついても15万円から20万円なので、ブランド化によって今回は20倍ほど値が上がったことになる。
のうち、審査で1本が認定された。「煌」第1号は重さ15.5㌔で体長94㌢の大物だ。例年、寒ブリは比較的高値がついても15万円から20万円なので、ブランド化によって今回は20倍ほど値が上がったことになる。 資源保護政策で香箱ガニの漁期は11月6日から12月29日に短縮された。そこで、値段は徐々に上がってはいたものの、それが急騰したのは2015年3月の北陸新幹線の金沢開業だった。金沢おでんが観光客の評判を呼び、季節メニューのかに面は人気の的となり、おでんの店には行列ができるようになった。
資源保護政策で香箱ガニの漁期は11月6日から12月29日に短縮された。そこで、値段は徐々に上がってはいたものの、それが急騰したのは2015年3月の北陸新幹線の金沢開業だった。金沢おでんが観光客の評判を呼び、季節メニューのかに面は人気の的となり、おでんの店には行列ができるようになった。 能登の祭りは派手でにぎやかだ。大学教員のときに、留学生たちを何度か能登の祭りに連れて行った。中国の留学生が「能登はアジアですね」と目を輝かせた。キリコは収穫を神様に感謝する祭礼用の奉灯を巨大化したもので、大きなものは高さ16㍍にもなる=写真=。輪島塗の本体を蒔(まき)絵で装飾した何基ものキリコが地区の神社に集う。集落によっては、若者たちがドテラと呼ばれる派手な衣装まとってキリコ担ぎに参加する。もともと女性の和服用の襦袢(じゅばん)を祭りのときに粋に羽織ったのがルーツとされ、花鳥風月の柄が入る。インドネシアの留学生は「少数民族も祭りのときには多彩でキラキラとした衣装を着ますよ」と。留学生たちは興味津々だった。
能登の祭りは派手でにぎやかだ。大学教員のときに、留学生たちを何度か能登の祭りに連れて行った。中国の留学生が「能登はアジアですね」と目を輝かせた。キリコは収穫を神様に感謝する祭礼用の奉灯を巨大化したもので、大きなものは高さ16㍍にもなる=写真=。輪島塗の本体を蒔(まき)絵で装飾した何基ものキリコが地区の神社に集う。集落によっては、若者たちがドテラと呼ばれる派手な衣装まとってキリコ担ぎに参加する。もともと女性の和服用の襦袢(じゅばん)を祭りのときに粋に羽織ったのがルーツとされ、花鳥風月の柄が入る。インドネシアの留学生は「少数民族も祭りのときには多彩でキラキラとした衣装を着ますよ」と。留学生たちは興味津々だった。 環境省の候補地選定の動きをとらえて、石川県と能登の4市5町、関係団体は今月6日、「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を設置し初会合を開いた。馳知事は「放鳥によって石川県の世界農業遺産に登録されている地域の農業に一層の付加価値を与える」と述べ、放鳥実現を目指していく考えを強調した(7日付・読売新聞石川県版)。
環境省の候補地選定の動きをとらえて、石川県と能登の4市5町、関係団体は今月6日、「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を設置し初会合を開いた。馳知事は「放鳥によって石川県の世界農業遺産に登録されている地域の農業に一層の付加価値を与える」と述べ、放鳥実現を目指していく考えを強調した(7日付・読売新聞石川県版)。
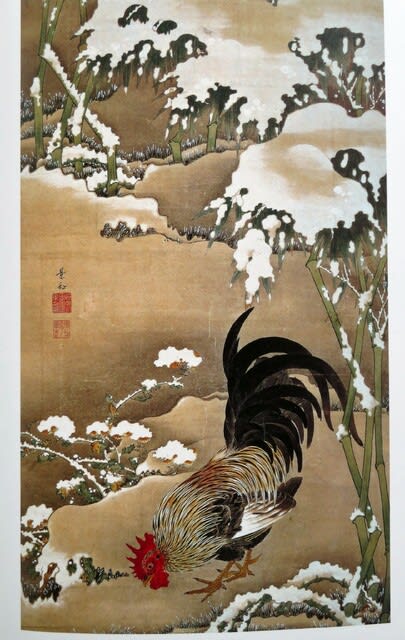 ど。これからが本番なのだろう。庭を眺めるとロウバイの黄色い花にうっすらと雪がかぶっていた=写真・上=。ロウバイは大寒から立春の時節に咲く。ロウバイの木に近づこうとすると、雪面から野鳥が1羽、驚いたように飛び立っていった。よく見えなかったが、目のふちが黒っぽく、尾羽が長めだったので、セキレイではなかったか。
ど。これからが本番なのだろう。庭を眺めるとロウバイの黄色い花にうっすらと雪がかぶっていた=写真・上=。ロウバイは大寒から立春の時節に咲く。ロウバイの木に近づこうとすると、雪面から野鳥が1羽、驚いたように飛び立っていった。よく見えなかったが、目のふちが黒っぽく、尾羽が長めだったので、セキレイではなかったか。 下=。金沢には古くから「一里一尺」という言葉がある。金沢地方気象台が発表する積雪量は、海側に近いところにある同気象台での観測であり、山側にある自宅周辺とでは積雪の数値が異なる。山側へ一里(4㌔)行けば、雪は一尺(30㌢)多くなる。
下=。金沢には古くから「一里一尺」という言葉がある。金沢地方気象台が発表する積雪量は、海側に近いところにある同気象台での観測であり、山側にある自宅周辺とでは積雪の数値が異なる。山側へ一里(4㌔)行けば、雪は一尺(30㌢)多くなる。 これは人為的な原因によって誘発される「誘発地震」か、と考え込んでしまった。というのも、北朝鮮が同じ9月の15日正午過ぎに弾道ミサイル2発を発射、その1発が能登半島沖の舳倉島の北約300㌔のEEZに落下した(同月15日・防衛大臣臨時会見「北朝鮮による弾道ミサイル発射事案」)。この落下地点と29日の震源が近かった。不気味だ。
これは人為的な原因によって誘発される「誘発地震」か、と考え込んでしまった。というのも、北朝鮮が同じ9月の15日正午過ぎに弾道ミサイル2発を発射、その1発が能登半島沖の舳倉島の北約300㌔のEEZに落下した(同月15日・防衛大臣臨時会見「北朝鮮による弾道ミサイル発射事案」)。この落下地点と29日の震源が近かった。不気味だ。 申請の翌年2011年6月10日、中国・北京で開催されたFAO主催のGIAHS国際フォーラムで、能登と当時に申請していた佐渡市の申請などが審査された。自身も北京に同行しその成り行きを見守った。審査会では、能登を代表して七尾市長の武元文平氏と佐渡市長の高野宏一郎氏がそれぞれ農業を中心とした歴史や文化、将来展望を英語で紹介した。質疑もあったが、足を引っ張るような意見ではなく、GIAHSサイトの連携についてどう考えるかといった内容だった。申請案件は科学評価委員20人の拍手で採択された。日本の2件のほか、インド・カシミールの「サフラン農業」など合わせて4件が採択された。日本では初、そして先進国では初めてのGIAHS認定だった。
申請の翌年2011年6月10日、中国・北京で開催されたFAO主催のGIAHS国際フォーラムで、能登と当時に申請していた佐渡市の申請などが審査された。自身も北京に同行しその成り行きを見守った。審査会では、能登を代表して七尾市長の武元文平氏と佐渡市長の高野宏一郎氏がそれぞれ農業を中心とした歴史や文化、将来展望を英語で紹介した。質疑もあったが、足を引っ張るような意見ではなく、GIAHSサイトの連携についてどう考えるかといった内容だった。申請案件は科学評価委員20人の拍手で採択された。日本の2件のほか、インド・カシミールの「サフラン農業」など合わせて4件が採択された。日本では初、そして先進国では初めてのGIAHS認定だった。