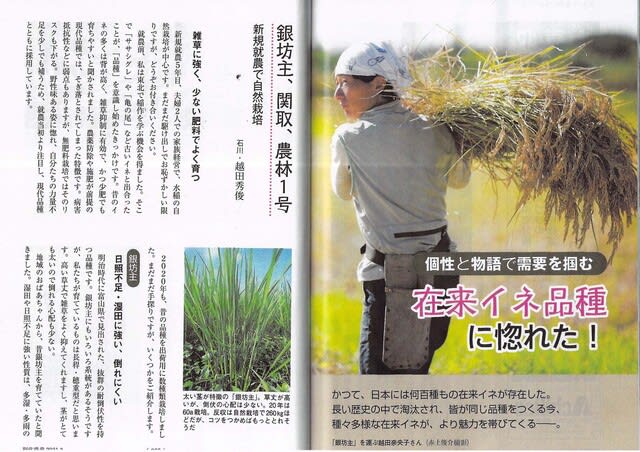★「必要は発明の神さま」で祭り復活
「必要は発明の母」と言われる。この場合は「必要は発明の神さま」かもしれない。新型コロナウイルスの感染拡大で、昨年に引き続きことしも各地域の祭礼や神事などの恒例行事の中止が相次いでいる。インターネット調査で、コロナ禍で失われる可能性が⾼い⽇本⽂化として、「祭り」がもっとく高く42.3%、「花⽕⼤会」32.8%、「屋形船」29.0%、「花⾒」24.3%と続く(⼀般社団法⼈マツリズム、有効回答:男女400人、調査:2021年02月27日-3月1日)。祭りについては以前から高齢化や少子化で担い手不足が指摘されていたが、コロナ禍が拍車がかけたとも言える。
多くの祭りは、神輿を担ぎ、その先導に獅子舞などがいて、それを見学する人々がいる。いわゆる「3密」の状態になることから、祭りが中止となるケースが多い。このような中、伝統の祭りを絶やしてはいけないと、神様を神社から外にお連れする神輿の代わりにミニ台車を手作りした神社の宮司がいる。きょう神社を訪れる機会に恵まれ、その想いを聞いた。
 石川県羽咋(はくい)市にある深江八幡神社。羽咋は祭礼の獅子舞が盛んな土地柄だが、昨年ほとんど中止となった。宮司の宮谷敬哉氏は3密を避けるために神輿を出せないとなれば、一人で押せる台車を作れないかとホームセンターに何度も通い、高さ150㌢ほどのものを完成させた=写真=。みこしに欠かせない鳳凰(ほうおう)は手作りが難しかったので、通販で小型のものを購入し飾り付けた。「神座(みくら)台車」と名付けた。
石川県羽咋(はくい)市にある深江八幡神社。羽咋は祭礼の獅子舞が盛んな土地柄だが、昨年ほとんど中止となった。宮司の宮谷敬哉氏は3密を避けるために神輿を出せないとなれば、一人で押せる台車を作れないかとホームセンターに何度も通い、高さ150㌢ほどのものを完成させた=写真=。みこしに欠かせない鳳凰(ほうおう)は手作りが難しかったので、通販で小型のものを購入し飾り付けた。「神座(みくら)台車」と名付けた。
昨年7月12日の例祭「祇園祭」では、神のより代である御霊代(みたましろ)を台車に収め、獅子頭だけを乗せた手押しワゴンが先導した。宮谷宮司が神輿の代わりに1人で台車を押して後に続いた。各家を1軒1軒回った。例年ならば神輿と獅子舞でにぎやか祭礼だが、簡素ではあるものの中止することなく続けることができた。
この地区は500年ほど前に疫病が流行したことから、京都の八坂神社から神を招いて七日七夜祈祷したところ疫病が収まり、それを機に祇園祭が始まったと伝わる。宮谷宮司は「苦労して疫病を鎮めた歴史が地元にあり、『できない』ではなく、『どうしたらできるか』と考えた末にアイデアが浮かんだ」と。
この神座台車と獅子頭の手押しワゴンが意外な展開を見せる。1965年(昭和40)年前後に神輿の渡御が途絶えていた集落から復活させたいと申し出があった。10月18日に地元の子どもたち6人が中心となって、神座台車と獅子頭の手押しワゴンで町内を歩いて回った。少子高齢化で担い手が少なくなり中止していたが、実に55年ぶりに祭りが復活したのだ。
宮司は「祭りの復活で地域の様子が活き活きとしていることを一番感じたのは地域の人たちだと思う」と。この秋も神座台車と獅子頭の手押しワゴンの出番となる。
⇒17日(木)夜・金沢の天気 くもり