☆「トキが舞う能登」を震災復興のシンボルに 環境省が本州で初の放鳥へ
きょうの金沢は朝から晴天。予報だと、気温は10度まで上がった。そして、あす16日はさらに12度まで。雪国に住んでいるとうれしくなる数値だ。雪が溶けるから。朝8時ごろ、近所の人が一人、二人と出てきて、「積み雪くずし」が始まった。玄関の前などの除雪で積み上げた雪を今度は崩す作業だ。気温が10度に上がっても、積み上げた雪はそう簡単に溶けない。なので、スコップを入れてカタチを崩すことで、空気の熱が雪の表面に広く伝わり、溶けるのを加速させる。あるいは、太陽光で熱を帯びたコンクリートやアスファルトの表面に崩した雪を散らす。雪を溶かす作業は意外と楽しめる。
 話は変わる。環境省はきのうトキ野生復帰検討会を開催し、国の特別天然記念物のトキの放鳥を2026年度上半期をめどに能登地域で行うことを決めた(14日付・環境省公式サイト「報道発表資料」)。本州でのトキの放鳥は初めてとなる。環境省は本州における「トキと共生する里地づくり取組地域」にを目指す自治体を2022年度に公募し、能登と島根県出雲市の2地域を選定していた。今回のトキ野生復帰検討会で能登が野生復帰をするに足るだけの自然的、社会的環境と地域体制が着実に整備されていると認め、来年度の放鳥が正式に決まった。(※写真は、輪島市三井町洲衛の空を舞うトキ=1957年、岩田秀男氏撮影)
話は変わる。環境省はきのうトキ野生復帰検討会を開催し、国の特別天然記念物のトキの放鳥を2026年度上半期をめどに能登地域で行うことを決めた(14日付・環境省公式サイト「報道発表資料」)。本州でのトキの放鳥は初めてとなる。環境省は本州における「トキと共生する里地づくり取組地域」にを目指す自治体を2022年度に公募し、能登と島根県出雲市の2地域を選定していた。今回のトキ野生復帰検討会で能登が野生復帰をするに足るだけの自然的、社会的環境と地域体制が着実に整備されていると認め、来年度の放鳥が正式に決まった。(※写真は、輪島市三井町洲衛の空を舞うトキ=1957年、岩田秀男氏撮影)
能登でのトキ放鳥は深いつながりがある。かつて、「本州で最後の一羽」と呼ばれたトキが能登にいた。「能里(のり)」という愛称で呼ばれていた。オス鳥だった。能登には大きな河川がなく、山の中腹にため池をつくり、田んぼの水を蓄えていた。そのため池にはトキが大好物のドジョウやカエルなどなどが豊富にいた。能登半島の中ほどにある眉丈山では、1961年に5羽のトキが確認されている。そのころ、田んぼでついばむエサが農薬にまみれていた。このため、1970年に能里が本州で最後の一羽となる。当時、新潟県佐渡には環境省のトキ保護センターが設置させていて、能里は人工繁殖のために佐渡に送られた。ところが、翌年1971年3月、鳥かごのケージの金網で口ばしを損傷したことが原因で死んでしまう。
こうしたいきさつから能登ではトキへの思い入れがあり、石川県と能登9市町は環境省の本州でのトキ放鳥に熱心に動いてきた。国連が定める「国際生物多様性の日」である5月22日を「いしかわトキの日」と決め、県民のモチベーションを盛り上げている、県は能登でのトキの放鳥に向けた「ロードマップ」案を独自に作成。トキが生息できる環境整備として700㌶の餌場を確保するため、化学肥料や農薬を使わない水田など「モデル地区」を設けて生き物調査を行い、拡充を図っている。こうした取り組みが環境省で評価され、能登での放鳥の段取りがスムーズに進んだようだ。
能登半島地震の災害からの復興のために石川県が提示した『創造的復興リーディングプロジェクト』の13の取り組みの中に、「トキが舞う能登の実現」が盛り込まれている。トキが舞う能登を震災復興のシンボルとしたい。その思いが動き出す。
⇒15日(土)夜・金沢の天気 はれ
 本州最後の1羽だったトキが1970年に能登半島で捕獲され、繁殖のため佐渡のトキ保護センターに送られた実績があることから、石川県と能登の4市5町、JAなど関係団体は5月6日に「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を結成。環境省に受け入れを申請していた。
本州最後の1羽だったトキが1970年に能登半島で捕獲され、繁殖のため佐渡のトキ保護センターに送られた実績があることから、石川県と能登の4市5町、JAなど関係団体は5月6日に「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を結成。環境省に受け入れを申請していた。 ひなを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと、福井県越前市生まれのメスで、ことし4月中旬に志賀町の山の中の電柱の上に巣をつくり、5月下旬には親鳥がひなに餌を与える様子が確認された。初めて見た1ヵ月前より、相当大きくなっていて、時折羽を広げて飛び立とうとしている様子だった=写真・下=。この場所はコウノトリのひなが育った日本での最北の地とされていて、これからの定着と繁殖を期待しながら巣を見上げていた。
ひなを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと、福井県越前市生まれのメスで、ことし4月中旬に志賀町の山の中の電柱の上に巣をつくり、5月下旬には親鳥がひなに餌を与える様子が確認された。初めて見た1ヵ月前より、相当大きくなっていて、時折羽を広げて飛び立とうとしている様子だった=写真・下=。この場所はコウノトリのひなが育った日本での最北の地とされていて、これからの定着と繁殖を期待しながら巣を見上げていた。 入ると「内浦」と呼ばれる波風が静かな、見附島や九十九湾、穴水湾、七尾湾、氷見海岸と連なる。まさに動と静が織りなすリアス式海岸の絶景だ。
入ると「内浦」と呼ばれる波風が静かな、見附島や九十九湾、穴水湾、七尾湾、氷見海岸と連なる。まさに動と静が織りなすリアス式海岸の絶景だ。 「既存の国定公園周辺には、棚田や谷地田、塩田、まがき集落景観がみられ、気候や地形といった自然条件に適応した人の営みが里山の風景を形作っている。こうした人と自然との関わりが評価され、国内初の世界農業遺産に登録されている」「地域は昆虫類が豊富で、シャープゲンゴロウモドキをはじめとした二次的自然環境に依存する希少種も生息・生育し、生物多様性が高く、トキの本州最後の生息地であった」「これらの里山域は、隣接する既存の国定公園の風景を成す一体の要素と考えられる」
「既存の国定公園周辺には、棚田や谷地田、塩田、まがき集落景観がみられ、気候や地形といった自然条件に適応した人の営みが里山の風景を形作っている。こうした人と自然との関わりが評価され、国内初の世界農業遺産に登録されている」「地域は昆虫類が豊富で、シャープゲンゴロウモドキをはじめとした二次的自然環境に依存する希少種も生息・生育し、生物多様性が高く、トキの本州最後の生息地であった」「これらの里山域は、隣接する既存の国定公園の風景を成す一体の要素と考えられる」 環境省の候補地選定の動きをとらえて、石川県と能登の4市5町、関係団体は今月6日、「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を設置し初会合を開いた。馳知事は「放鳥によって石川県の世界農業遺産に登録されている地域の農業に一層の付加価値を与える」と述べ、放鳥実現を目指していく考えを強調した(7日付・読売新聞石川県版)。
環境省の候補地選定の動きをとらえて、石川県と能登の4市5町、関係団体は今月6日、「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を設置し初会合を開いた。馳知事は「放鳥によって石川県の世界農業遺産に登録されている地域の農業に一層の付加価値を与える」と述べ、放鳥実現を目指していく考えを強調した(7日付・読売新聞石川県版)。 二日目(30日)の基調講演で、公益財団法人「地球環境戦略研究機関」の理事長、武内和彦氏が「日本の持続可能な農業とは~佐渡GIAHSの農村文化から考える~」と題して、「世界農業遺産は過去の遺産ではなく、生き続ける遺産」と説明した。「朱鷺と暮らす郷づくり」認証農家は現在407戸に。佐渡の積極的なトキの米づくりを目指す新規就農者は2019年度実績で67人に。学校ではトキとコメ作りをテーマに環境教育や食育教育が行われている。佐渡は多様な価値観を持った人たちが集う「コモンズ」共同体へと進化している。農業だけでなく観光や自然環境、コミュニティーの人々が連携することで横つながり、そして世代を超えるという新たなステージに入っている。武内氏が強調したのは「佐渡GIAHSにおける新たな農村文化の展開」という言葉だった。
二日目(30日)の基調講演で、公益財団法人「地球環境戦略研究機関」の理事長、武内和彦氏が「日本の持続可能な農業とは~佐渡GIAHSの農村文化から考える~」と題して、「世界農業遺産は過去の遺産ではなく、生き続ける遺産」と説明した。「朱鷺と暮らす郷づくり」認証農家は現在407戸に。佐渡の積極的なトキの米づくりを目指す新規就農者は2019年度実績で67人に。学校ではトキとコメ作りをテーマに環境教育や食育教育が行われている。佐渡は多様な価値観を持った人たちが集う「コモンズ」共同体へと進化している。農業だけでなく観光や自然環境、コミュニティーの人々が連携することで横つながり、そして世代を超えるという新たなステージに入っている。武内氏が強調したのは「佐渡GIAHSにおける新たな農村文化の展開」という言葉だった。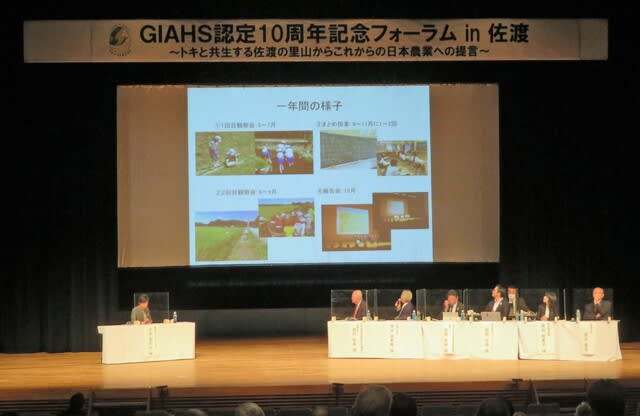 きょうパネルディスカッション=写真・下=では「これからの日本農業への提言」をテーマに話し合った。能登GIAHSから参加した珠洲市長の泉谷満寿裕氏から意外な発言があった。「トキを能登で放鳥してほしい」と。この発言には背景がある。環境省は今後のトキの放鳥について、2025年までのロードマップをことし6月に作成し、トキの受け入れに意欲的な地域(自治体)を中心に、トキの生息に適した環境の保全や再生、住民理解などの社会環境の整備に取り組む(6月22日付・読売新聞Web版)。トキは感染症の影響を受けやすい。さらに、佐渡で野生生息が484羽に増えており、今後エサ場の確保などを考慮すると、佐渡以外での複数の生息地を準備することが不可欠との判断されたのだろう。泉谷氏の発言は地元佐渡で受け入れの名乗りを上げたことになる。
きょうパネルディスカッション=写真・下=では「これからの日本農業への提言」をテーマに話し合った。能登GIAHSから参加した珠洲市長の泉谷満寿裕氏から意外な発言があった。「トキを能登で放鳥してほしい」と。この発言には背景がある。環境省は今後のトキの放鳥について、2025年までのロードマップをことし6月に作成し、トキの受け入れに意欲的な地域(自治体)を中心に、トキの生息に適した環境の保全や再生、住民理解などの社会環境の整備に取り組む(6月22日付・読売新聞Web版)。トキは感染症の影響を受けやすい。さらに、佐渡で野生生息が484羽に増えており、今後エサ場の確保などを考慮すると、佐渡以外での複数の生息地を準備することが不可欠との判断されたのだろう。泉谷氏の発言は地元佐渡で受け入れの名乗りを上げたことになる。 では、どこで放鳥が始まるのか。やはり、本州最後の一羽が生息していた能登ではないだろうか。奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)には大小1000ヵ所ともいわれる水稲用の溜め池がある。溜め池は中山間地にあり、上流に汚染源がないため水質が保たれている。ゲンゴロウやサンショウウオ、ドジョウなどの水生生物が量、種類とも豊富である。これらの水生生物は疏水を伝って水田へと流れていく。
では、どこで放鳥が始まるのか。やはり、本州最後の一羽が生息していた能登ではないだろうか。奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)には大小1000ヵ所ともいわれる水稲用の溜め池がある。溜め池は中山間地にあり、上流に汚染源がないため水質が保たれている。ゲンゴロウやサンショウウオ、ドジョウなどの水生生物が量、種類とも豊富である。これらの水生生物は疏水を伝って水田へと流れていく。