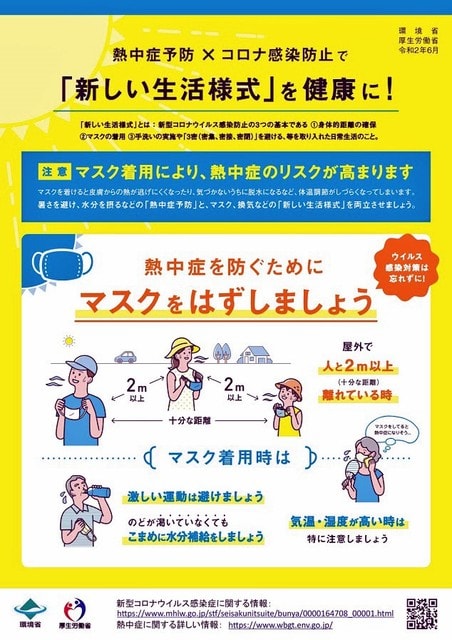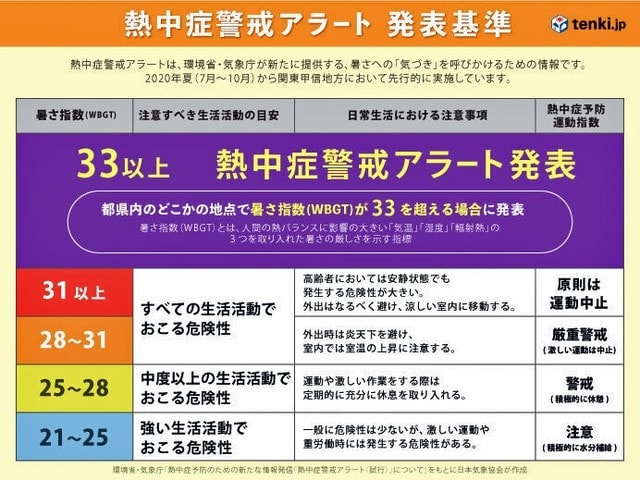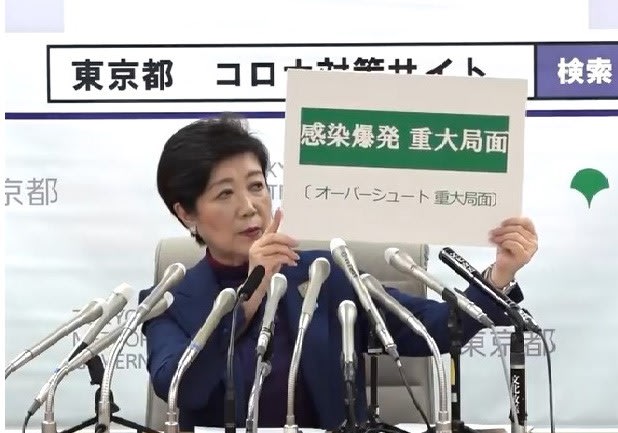★CMガタ落ちテレビ業界、同時配信のチャンス
新型コロナウイルスの感染拡大でさまざまな産業に影響が及んでいる。最近、テレビを視聴していても、自社の番組宣伝や通販のCMが多い。4月7日に東京など7都府県で緊急事態宣言が発令されたころは、「ACジャパン(公共広告機構)」が目立った。公共広告はスポンサーの都合でCMを降りた場合に使われるが、番宣や通販CMが目立つということはCM枠そのものがガラガラになっている、ということでもある。では、CM収入がどの程度落ち込んでいるのか、日本テレビホールディングスがホームページで掲載している今年度の有価証券報告書(第1四半期、4‐6月)と決算説明資料をチェックしてみた。
まず、視聴率である。日本テレビは独自に「男女13-49歳」の個人視聴率を「コアターゲット」として設定して他社と比較した数字を出している。そのコアターゲット視聴率(関東地区、ビデオリサーチ調べ)は「4月クール」(2020年3月30日-6月28日)の調査で、全日(6-24時)が4.7%、プライム(19-23時)7.7%、ゴールデン(19-22時)8.0%と2位以下を大きく離して「3冠」となっている。3冠は2013年7月期から28クール連続。視聴率そのものも、「ステイホーム」など在宅率と連動して伸びている。では、CMはどうなのか。
 テレビ局の放送収入(CM)には2つの枠がある。番組に提供する「タイム」枠と、番組と番組の間で流す「スポット」枠である。第1四半期(4‐6月)の日本テレビの放送収入はタイムが290憶円、スポットが196憶円と、前年同期比でそれぞれマイナス1.1%、同36.6%となっている。とくにスポットの落ち込みが大きい。さらに、スポットを月別で見ると、4月が前年同月比でマイナス24.7%、5月が同40.2%、6月が47.5%と相当な落ち込みだ。民放キーをリードしている日本テレビがこの落ち込みである。
テレビ局の放送収入(CM)には2つの枠がある。番組に提供する「タイム」枠と、番組と番組の間で流す「スポット」枠である。第1四半期(4‐6月)の日本テレビの放送収入はタイムが290憶円、スポットが196憶円と、前年同期比でそれぞれマイナス1.1%、同36.6%となっている。とくにスポットの落ち込みが大きい。さらに、スポットを月別で見ると、4月が前年同月比でマイナス24.7%、5月が同40.2%、6月が47.5%と相当な落ち込みだ。民放キーをリードしている日本テレビがこの落ち込みである。
とはいえ、放送収入の主力であるタイムがマイナス1.1%なのだから、そう案じることもないのではと考えてしまうのだが、むしろ、問題はこれからかもしれない。タイム枠はほとんどが半年契約である。4月に契約したスポンサーが、10月以降も継続するかどうか。提供を降りるスポンサーが、スポット並みに続出するかもしれない。
放送収入の減少傾向は、コロナ禍とは別次元でも危惧されている。電通がまとめた「2019年 日本の広告費」によると、広告費は6兆9381億円で8年連続のプラス成長だった。中でも、インターネット広告費が初めて2兆円超え、テレビ広告費を上回りトップの座に躍り出た。テレビ広告費(1兆8612億円)は対前年比97.3%と減少した。テレビ広告費の減少要因は、この年の台風などの自然災害や、消費税増税に伴う出稿控えやアメリカと中国の貿易摩擦の経済的影響などで3年連続の減少だった。ことしはコロナ禍が拍車をかけ、線状降水帯など自然災害、さらに米中の対立が貿易にとどまらず安全保障にまで拡大する気配を見せている。第2四半期(7-9月)の決算が気になる。
テレビ業界も生き残り戦略に特化していくだろう。先に述べた、日本テレビの「男女13-49歳」の個人視聴率を「コアターゲット」とする戦略はその代表ではないだろうか。従来の世帯視聴率は不特定多数の量的な数字だ。ではなく、個人視聴率を用いて若い層や就業・就学者にどれだけ番組のニーズがあるのかを調査しなければ、クライアント(スポンサー)の満足度を最大化することはできない。視聴率にも質的な転換が求められている。
と同時に、デジタル化への戦略だろう。番組のネット配信を進めなければ、さらなる番組の価値を生み出すことはできない。日本テレビ社長の定例会見(7月27日)の内容がHPで掲載されていて、同時配信について述べている。「今年10月から12月にトライアルを実施する方向で作業を進めている。私どもが考える意義は、視聴環境が大きく変化する中、テレビを持っていない、あるいはテレビを見る機会が少ないデジタルデバイスのユーザーの皆さんに対して、地上波のコンテンツとの接触機会をとにかく促進する、ということ。プライムタイムの番組で、特に権利者の許諾等々、ネットワークのコンディションにかなうものを配信する予定」
アフターコロナではテレビ業界も大打撃を受けての再出発となるだろう。放送と通信の同時配信のチャンスではないだろうか。そして、これまでの視聴率を取ればなんとかなるという発想ではおそらく生き残れない。テレビ業界そのものが「ポツンと一軒家」化してしまうかもしれない。
⇒16日(日)午後・金沢の天気 はれ