★アートとSDGs
前回の能登半島の珠洲市で開催された「創造都市ネットワーク日本(CCNJ)現代芸術の国際展部会シンポジウム」の続き。シンポジウムの前半は奥能登国際芸術祭の総合ディレクター、北川フラム氏の基調講演。後半は「里山里海×アート×SDGsの融合と新しいコモンズの視点から」をテーマにパネル討論だった。このテーマのキーワードは「里山里海×アート×SDGs」。能登半島は2011年に国連食糧農業機関(FAO)から世界農業遺産(GIAHS)に認定された。そのタイトルが「能登の里山里海」だった。さらに市は独自に2017年に奥能登国際芸術祭を開催し、2018年には内閣府の「SDGs未来都市」に登録されるなど、「持続可能な地域社会」を先取りする政策を次々と打ち出している。
討論会のファシリテーターは自身が務め、パネリストは泉谷満寿裕珠洲市長、国連大学サスティナビリティ高等研究所OUIK事務局長の永井三岐子氏、金沢21世紀美術館学芸部長チーフ・キュレーターの黒澤浩美氏、金沢市都市政策局SDGs推進担当の笠間彩氏の4人。前回のブログの冒頭でも述べた、「アートとSDGsは果たしてリンクできるのか」とパネリストに投げかけた。里山里海とアートはこれまでもこのブログで紹介してきたようにインスタレーション(空間芸術)でつながる。SDGsは貧困に終止符を打ち、地球の環境を保護して、すべての人 が平和と豊かさを享受できるようにすることを呼びかける国連の目標だが、SDGsの17の目標の中に「アート」「芸術」という文字はない。
が平和と豊かさを享受できるようにすることを呼びかける国連の目標だが、SDGsの17の目標の中に「アート」「芸術」という文字はない。
アートとSDGsは果たしてつながるのか。すると、討論の中で「アーチストもSDGsをどう創作・表現するか迷っている」という言葉が出た。ハタと気がついた。アーチストもSDGsを表現しようと試行錯誤している。珠洲市は「SDGs未来都市」に登録されている、作家もそのコンセプトを表現しようとするはずだ。思い当たる作品が浮かんだ。
インドの作家スボード・グプタ氏の作品「Think about me(私のこと考えて)」がある。大きなバケツがひっくり返され、海の漂着物がどっと捨てられるというイメージだ=写真=。プラスチック製浮子(うき)や魚網などの漁具のほか、ポリタンク、プラスチック製容器など生活用品、自然災害で出たと思われる木材などさまざまな海洋ゴミだ。ガイドブックによると、これらの漂着ごみのほとんどが実際にこの地域に流れ着いたものだ。地域の人たちの協力で作品が完成した。グプタ氏の創作の想いが海洋ゴミを無くして海の自然と豊かさを守ろうという意味と解釈すれば、まさにSDGsだ。
奥能登国際芸術祭ではインスタレーションの視点で楽しんだが、SDGsの視線で作品を見たことはなかった。アートには無限の可能性や、社会を豊かに変えていくことができる芸術の力があるのではないか、と今さらながら感じ入った次第だ。
⇒22日(土)夜・金沢の天気 くもり
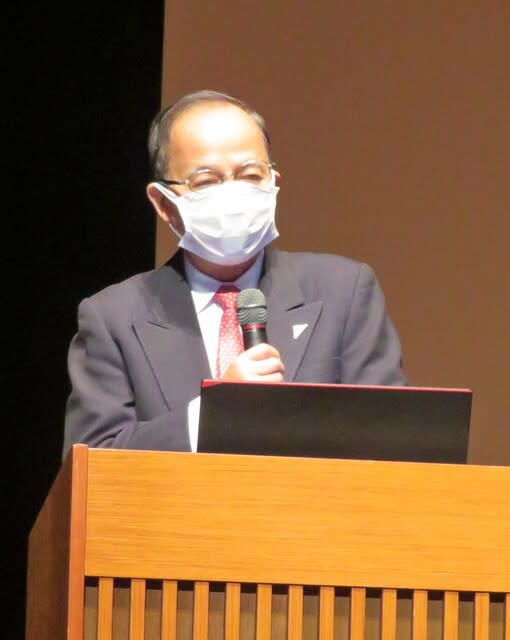 珠洲市で昨年秋に開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の総合ディレクターの北川フラム氏=写真・上=が「持続可能な地域社会と国際芸術祭」と題して基調講演。「厳しい地域ほど魅力的で、珠洲は地政学的にも特異点がある。芸術祭で大いに変わる可能性がある。ぜひ10年で最低3回の芸術祭をやってほしい」と述べた。珠洲の特異点として、「この地には日本で失われた生活が残っている。そして、国と人がつながる日本海を望む『さいはての地』であり、鉄道の消滅点でもある。地域コミュニティーの絆が強く、里山里海の自然環境に恵まれている。アートはこうした特異点に迫っていく」とアーチスト目線で珠洲の魅力と可能性を強調した。
珠洲市で昨年秋に開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の総合ディレクターの北川フラム氏=写真・上=が「持続可能な地域社会と国際芸術祭」と題して基調講演。「厳しい地域ほど魅力的で、珠洲は地政学的にも特異点がある。芸術祭で大いに変わる可能性がある。ぜひ10年で最低3回の芸術祭をやってほしい」と述べた。珠洲の特異点として、「この地には日本で失われた生活が残っている。そして、国と人がつながる日本海を望む『さいはての地』であり、鉄道の消滅点でもある。地域コミュニティーの絆が強く、里山里海の自然環境に恵まれている。アートはこうした特異点に迫っていく」とアーチスト目線で珠洲の魅力と可能性を強調した。 か。北川フラム氏が述べたように、半島の先端という地理的な条件や過疎化といったハンディはアーチストにとって「厳しい地域こそ魅力的」に感じ、移住者も共感するという現象なのか。
か。北川フラム氏が述べたように、半島の先端という地理的な条件や過疎化といったハンディはアーチストにとって「厳しい地域こそ魅力的」に感じ、移住者も共感するという現象なのか。  採択された後、同市は「能登SDGsラボ」を開設した。市民や企業の参加を得て、経済・社会・環境の3つの側面の課題を解決しながら、統合的な取り組みで相乗効果と好循環を生み出す工夫を重ねるというもの。簡単に言えば、経済・社会・環境をミックス(=ごちゃまぜ)しながら手厚い地域づくりをしていく。そのために、金沢大学、国連大学サスティナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわ・オペレーティングユニット(OUIK)、石川県立大学、石川県産業創出支援機構(ISICO)、地元の経済界や環境団体(NPOなど)、地域づくり団体などがラボに参画している。
採択された後、同市は「能登SDGsラボ」を開設した。市民や企業の参加を得て、経済・社会・環境の3つの側面の課題を解決しながら、統合的な取り組みで相乗効果と好循環を生み出す工夫を重ねるというもの。簡単に言えば、経済・社会・環境をミックス(=ごちゃまぜ)しながら手厚い地域づくりをしていく。そのために、金沢大学、国連大学サスティナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわ・オペレーティングユニット(OUIK)、石川県立大学、石川県産業創出支援機構(ISICO)、地元の経済界や環境団体(NPOなど)、地域づくり団体などがラボに参画している。 能登半島の尖端、珠洲市で開催されている奥能登国際芸術祭(9月4日-11月5日)の最終日に鑑賞してきた。名残惜しさと芸術の秋が相まって楽しむことができた。
能登半島の尖端、珠洲市で開催されている奥能登国際芸術祭(9月4日-11月5日)の最終日に鑑賞してきた。名残惜しさと芸術の秋が相まって楽しむことができた。 境を感じさせる。
境を感じさせる。 たまま忘れ去れていた。市民の協力を得て蔵ざらえしたこれらの道具や用具を用いて、アーティストと専門家が関わり、民族博物館と劇場が一体化したシアター・ミュージアムが創られた。芸術祭終了後も常設施設として残される。
たまま忘れ去れていた。市民の協力を得て蔵ざらえしたこれらの道具や用具を用いて、アーティストと専門家が関わり、民族博物館と劇場が一体化したシアター・ミュージアムが創られた。芸術祭終了後も常設施設として残される。  実際にひびのこずえ氏は能登の海を潜って得た感性で作品づくりをしている。寄せては返す潮の満ち引き、それは出会いと別れでもあり、移り変わりでもある。ここから作品名を「Come and Go」と名付けられたとボランティアガイドから説明を受けた。
実際にひびのこずえ氏は能登の海を潜って得た感性で作品づくりをしている。寄せては返す潮の満ち引き、それは出会いと別れでもあり、移り変わりでもある。ここから作品名を「Come and Go」と名付けられたとボランティアガイドから説明を受けた。 敷を借りて、5つの作品を展示している。スズプロは2017年の芸術祭から参加しているが、今回は新作として『いのりを漕ぐ』という大作を展示している。客間に能登産材の「アテ」(能登ヒバ)を持ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ。
敷を借りて、5つの作品を展示している。スズプロは2017年の芸術祭から参加しているが、今回は新作として『いのりを漕ぐ』という大作を展示している。客間に能登産材の「アテ」(能登ヒバ)を持ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ。 「場のアート」という言葉は、庭師の仕事にも当てはまるのではないかと思っている。先月末に庭木の刈り込み(剪定)を造園業者にお願いした。ベテランや若手の庭師4人が作業をしてくれた。庭木は放っておくと、枝葉が繁り放題になる。庭として形状を保つためには、剪定によって樹木を整える。
「場のアート」という言葉は、庭師の仕事にも当てはまるのではないかと思っている。先月末に庭木の刈り込み(剪定)を造園業者にお願いした。ベテランや若手の庭師4人が作業をしてくれた。庭木は放っておくと、枝葉が繁り放題になる。庭として形状を保つためには、剪定によって樹木を整える。 道路で断ち切られた線路跡に設置されている、ドイツのトビアス・レーベルガー氏の作品「Something Else is Possible(なにか他にできる)」は前回(2017年)の作品=写真・上=だが、今でも寒色から暖色へのグラデーションが青空に映える。渦を巻くような内部には双眼鏡が置かれている。のぞいてみると、線路の200㍍ほど先にあるかつての終着駅、「蛸島駅」の近くに少し派手なメッセージ看板が見える。「something ELSE is POSSIBLE」と記されている。「ELSE」と「POSSIBLE」が大文字で強調されている。線路も駅もここで終わっているが、この先の未来には可能性はいくらだってある、と解釈する。レーベルガー氏が珠洲の人々に贈ったメッセージではないだろうか。
道路で断ち切られた線路跡に設置されている、ドイツのトビアス・レーベルガー氏の作品「Something Else is Possible(なにか他にできる)」は前回(2017年)の作品=写真・上=だが、今でも寒色から暖色へのグラデーションが青空に映える。渦を巻くような内部には双眼鏡が置かれている。のぞいてみると、線路の200㍍ほど先にあるかつての終着駅、「蛸島駅」の近くに少し派手なメッセージ看板が見える。「something ELSE is POSSIBLE」と記されている。「ELSE」と「POSSIBLE」が大文字で強調されている。線路も駅もここで終わっているが、この先の未来には可能性はいくらだってある、と解釈する。レーベルガー氏が珠洲の人々に贈ったメッセージではないだろうか。 旧・鵜飼駅にあるのが、香港の作家、郭達麟(ディラン・カク)氏の作品「😂」だ。絵文字なので、使う人や読む人にとって少々意味がずれてくるかもしれない。ネットで検索すると、「うれし泣き」「泣けるほど感動」「深く感謝」といった意味だ。作品は、2つある。旧駅舎を郵便局に見立てて、絵葉書などを展示している。せっかく能登半島に来たのだから、ゆったりとした気持ちで葉書でも書いて送りましょう、とのメッセージのようも思える。そして、線路では、スマホに没頭するサルのオブジェがある=写真・中=。作者は香港から奥能登に来て、東京など大都会とはまったく異なる風景や時間の流れを感じたに違いない。スマホが象徴する気ぜわしい現代、そして時間がゆったりと流れる能登。「😂」の絵文字はその能登に感動したという意味を込めているのだろうか。
旧・鵜飼駅にあるのが、香港の作家、郭達麟(ディラン・カク)氏の作品「😂」だ。絵文字なので、使う人や読む人にとって少々意味がずれてくるかもしれない。ネットで検索すると、「うれし泣き」「泣けるほど感動」「深く感謝」といった意味だ。作品は、2つある。旧駅舎を郵便局に見立てて、絵葉書などを展示している。せっかく能登半島に来たのだから、ゆったりとした気持ちで葉書でも書いて送りましょう、とのメッセージのようも思える。そして、線路では、スマホに没頭するサルのオブジェがある=写真・中=。作者は香港から奥能登に来て、東京など大都会とはまったく異なる風景や時間の流れを感じたに違いない。スマホが象徴する気ぜわしい現代、そして時間がゆったりと流れる能登。「😂」の絵文字はその能登に感動したという意味を込めているのだろうか。 旧・正院駅には「植木鉢」を巨大化した「植林鉢」という作品が並ぶ=写真・下=。サンパウロに生まれ、ニューヨークに拠点を構えて、建築家、そしてアーティストとして活躍する大岩オスカール氏の作品だ。駅舎を囲むように植えられているのはソメイヨシノ。作者はおそらく春に現地にやって来た。そこで見たサクラのきれいなこの場所に感動し、秋は紅葉の名所にしたいと考えたのではないだろうか。ガイドブックによると、植林の材料のタンクは、地元の焼酎蒸留会社の不要になったタンクをリサイクルしたもの。巨大な植木鉢の側面には、能登で見た海の波、そして海を赤く染める夕日が描かれている。
旧・正院駅には「植木鉢」を巨大化した「植林鉢」という作品が並ぶ=写真・下=。サンパウロに生まれ、ニューヨークに拠点を構えて、建築家、そしてアーティストとして活躍する大岩オスカール氏の作品だ。駅舎を囲むように植えられているのはソメイヨシノ。作者はおそらく春に現地にやって来た。そこで見たサクラのきれいなこの場所に感動し、秋は紅葉の名所にしたいと考えたのではないだろうか。ガイドブックによると、植林の材料のタンクは、地元の焼酎蒸留会社の不要になったタンクをリサイクルしたもの。巨大な植木鉢の側面には、能登で見た海の波、そして海を赤く染める夕日が描かれている。 前回(2017年)の奥能登国際芸術祭でも同じ海岸で、深澤孝史氏が「神話の続き」と題する作品=で、この地域に流れ着いた海洋ごみを用いて、神社の鳥居を模倣して創作した=写真・下=。古来より、強い偏西風と荒波に見舞われる外浦の海岸には、大陸から流れ出たものを含めさまざまな漂流物が流れ着く。大昔は仏像なども流れてきて、「寄り神」として祀られたこともあるが、現在ではそのほとんどが対岸の国で発生したプラスチックごみや漁船から投棄された漁具類だ。
前回(2017年)の奥能登国際芸術祭でも同じ海岸で、深澤孝史氏が「神話の続き」と題する作品=で、この地域に流れ着いた海洋ごみを用いて、神社の鳥居を模倣して創作した=写真・下=。古来より、強い偏西風と荒波に見舞われる外浦の海岸には、大陸から流れ出たものを含めさまざまな漂流物が流れ着く。大昔は仏像なども流れてきて、「寄り神」として祀られたこともあるが、現在ではそのほとんどが対岸の国で発生したプラスチックごみや漁船から投棄された漁具類だ。 は英語、10個は中国語、日本語は3個だった。ポリタンクだけではない。医療系廃棄物(注射器、薬瓶、プラスチック容器など)の漂着もすさまじい。環境省が2007年3月にまとめた1年間の医療系廃棄の漂着は日本海沿岸地域を中心に2万6千点以上あった。
は英語、10個は中国語、日本語は3個だった。ポリタンクだけではない。医療系廃棄物(注射器、薬瓶、プラスチック容器など)の漂着もすさまじい。環境省が2007年3月にまとめた1年間の医療系廃棄の漂着は日本海沿岸地域を中心に2万6千点以上あった。 「奥能登国際芸術祭2020+」が開催されている石川県珠洲市は能登半島の尖端に位置する。さらに海に突き出た最尖端に「禄剛崎(ろっこうざき)灯台」がある。灯台の近くには、「ウラジオストック 772㎞」「東京 302㎞」などと記された方向看板がある=写真・上=。この看板を見ただけでも、最果ての地に来たという旅情が沸いてくる。別の石碑を見ると、「日本列島ここが中心」と記されている。確かに地図で眺めても能登半島は本州のほぼ中央に位置する。最果てでありながら、列島の中心分に位置するという不思議な感覚が今回のアートでも表現されている。
「奥能登国際芸術祭2020+」が開催されている石川県珠洲市は能登半島の尖端に位置する。さらに海に突き出た最尖端に「禄剛崎(ろっこうざき)灯台」がある。灯台の近くには、「ウラジオストック 772㎞」「東京 302㎞」などと記された方向看板がある=写真・上=。この看板を見ただけでも、最果ての地に来たという旅情が沸いてくる。別の石碑を見ると、「日本列島ここが中心」と記されている。確かに地図で眺めても能登半島は本州のほぼ中央に位置する。最果てでありながら、列島の中心分に位置するという不思議な感覚が今回のアートでも表現されている。 れている=写真・中=。アクリル板を使って日本列島と島々を表現し、天井から逆さでつるすことで、周辺の海域や能登半島と大陸の位置関係などを示している。背景の壁面にはユーラシア大陸が描かれ、周辺海域や日本列島の特性、大陸と能登半島の歴史などもゆらゆらと揺れながら浮かび上がる。
れている=写真・中=。アクリル板を使って日本列島と島々を表現し、天井から逆さでつるすことで、周辺の海域や能登半島と大陸の位置関係などを示している。背景の壁面にはユーラシア大陸が描かれ、周辺海域や日本列島の特性、大陸と能登半島の歴史などもゆらゆらと揺れながら浮かび上がる。 崎詣(まり)り」と呼んで、その姿に合掌する習わしがある。また、同市馬緤(まつなぎ)の海岸には、「巨鯨慰霊碑」がある。明治から昭和にかけて、シロナガスクジラなどが岩場に漂着し、地域の人たちに恵みをもたらした。それに感謝する碑である。こうした海の生き物に感謝する歴史と伝説を調査し、土地の人々からの聞き取りを基に、台湾出身の作家、涂維政(トゥ・ウィチェン)氏は「クジラ伝説遺跡」を創作した。
崎詣(まり)り」と呼んで、その姿に合掌する習わしがある。また、同市馬緤(まつなぎ)の海岸には、「巨鯨慰霊碑」がある。明治から昭和にかけて、シロナガスクジラなどが岩場に漂着し、地域の人たちに恵みをもたらした。それに感謝する碑である。こうした海の生き物に感謝する歴史と伝説を調査し、土地の人々からの聞き取りを基に、台湾出身の作家、涂維政(トゥ・ウィチェン)氏は「クジラ伝説遺跡」を創作した。 なぜこの海をのぞむ児童公園を創作の場に選んだのか。上記のガイドブックを読んでなんとなくイメージが浮かんできた。この公園の入り口には、万葉の歌人として知られる大伴家持が珠洲を訪れたときの歌碑=写真・中=がある。「珠洲の海に 朝開きして 漕ぎ来れば 長浜の浦に 月照りにけり」。748年、越中国司だった大伴家持が能登へ巡行し、最後の訪問地だった珠洲で朝から船に乗って越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。当時は大陸の渤海(698-926年)からの使節団が能登をルートに奈良朝廷を訪れており、大伴家持が乗った船はまさに月面探査機をイメージさせるような使節団の船ではなかったか。ヴェガ氏もこの話を地元の人たちからこの話を聞いて発想し、ここでルナークルーザーを創ったとすれば、歴史の場を意識した作品ではないのか。こうした勝手解釈ができるところが作品鑑賞の楽しみでもある。
なぜこの海をのぞむ児童公園を創作の場に選んだのか。上記のガイドブックを読んでなんとなくイメージが浮かんできた。この公園の入り口には、万葉の歌人として知られる大伴家持が珠洲を訪れたときの歌碑=写真・中=がある。「珠洲の海に 朝開きして 漕ぎ来れば 長浜の浦に 月照りにけり」。748年、越中国司だった大伴家持が能登へ巡行し、最後の訪問地だった珠洲で朝から船に乗って越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。当時は大陸の渤海(698-926年)からの使節団が能登をルートに奈良朝廷を訪れており、大伴家持が乗った船はまさに月面探査機をイメージさせるような使節団の船ではなかったか。ヴェガ氏もこの話を地元の人たちからこの話を聞いて発想し、ここでルナークルーザーを創ったとすれば、歴史の場を意識した作品ではないのか。こうした勝手解釈ができるところが作品鑑賞の楽しみでもある。 所」=写真・下=。製材所の海側の壁は透明なアクリル壁に手直しされ、ベンチに座ると海の水平線を望むことができる。
所」=写真・下=。製材所の海側の壁は透明なアクリル壁に手直しされ、ベンチに座ると海の水平線を望むことができる。