★大阪都構想 票に滲むコロナ禍と報道と共感と
「反対50.6%、賛成49.4%」の僅差で否決された大阪都構想。その後の新聞・テレビ各社の報じる論評を読めば読むほど分からないことが増えてくる。同時に票にはさまざま思いや時のタイミングが滲んでいると思えてくる。
大阪・朝日放送(ABC)の世論調査によると、10月24-25日調査では賛成46.9%、反対41.2%だった。ABCは9月19-20日から世論調査を始めているが、それまでの賛成が6回続けてリードしていた。7回目となる10月30-31日の調査で初めて反対46.6%、賛成45.0%と逆転した。これまで「未定・不明」と答えた人の割合が、3.5ポイント減って反対側に流れたようだ。そして、この7回目の調査結果がそのまま11月1日の住民投票の結果に反映されたかっこうだ。
ABC調査で気になったデータがある。「新型コロナの拡大下でも住民投票を行うべきか」(10月3-4日調査)の問い。年代でもバラツキがあるが、全年代通しでは「予定通り行うべき」37.8%を「中止もしくは延期するべき」42.0%が上回っている。大阪市では、10月は第3波ともいえる新規感染者数が増加を始めたころだった。とくに終盤の27日から11月1日の投票日にかけては連日50人から70人の新規陽性者が出ていた(大阪市役所公式ホームページ)。
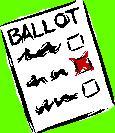 実際にコロナ禍は投票行動に影響を与えたのではないだろうか。投票率が66.8%だった前回(2015年)より世論の関心度も高く盛り上がったにもかかわらず、今回投票率が62.4%と4.4ポイントもダウンしたのも、コロナ禍で投票場へ行くのを控えた人も多かったせいだろう。期日前投票が前回35万9千、今回41万8千と率にして16%も増えているのも、「3密」を避けた投票行動と読めるのではないか。
実際にコロナ禍は投票行動に影響を与えたのではないだろうか。投票率が66.8%だった前回(2015年)より世論の関心度も高く盛り上がったにもかかわらず、今回投票率が62.4%と4.4ポイントもダウンしたのも、コロナ禍で投票場へ行くのを控えた人も多かったせいだろう。期日前投票が前回35万9千、今回41万8千と率にして16%も増えているのも、「3密」を避けた投票行動と読めるのではないか。
ABC調査のデータが現実になったともいえる。「中止もしくは延期するべき」が声が上がっていたにもかかわらず、それを実施したことに対する、松井市長、大阪維新の会への批判が「反対」票となって表れたのではないだろうか。大阪都構想を推進する側にとっては、コロナ禍はタイミングが悪かった。
さらにもう一つ「反対」票につながったと思われる数字がある。大阪市を4つの特別区に分割した場合、標準的な行政サービスを実施するために毎年必要なコスト「基準財政需要額」の合計が、現在よりも約218億円増えることが市財政局の試算で明らかになったと報道された(10月26日付・毎日新聞Web版)。市財政局の担当者は29日に緊急記者会見で、この試算を撤回した(10月29日付・同)。が、この数字が都構想のデメリットとして独り歩きを始めたのではないだろうか。
きょう大阪維新の会のツイッターをチェックすると、吉村知事の囲み会見(11月2日)が動画で紹介されている。支持者のコメントが出ていた。「燃え尽き症候群のようになってしまわないか心配です。今はなかなか切り替えができないと思いますけど、違うやり方で少しづつ改革を進めることはできます。60万人以上の市民が賛成したのも事実です、これで都構想を諦めるなんて言わないでください!まずは一休みして」。やさしい励ましの言葉だ。都構想はある意味で市民の共感を得ていた政策だったのだ、と理解もできた。
⇒3日(祝)朝・金沢の天気 はれ

