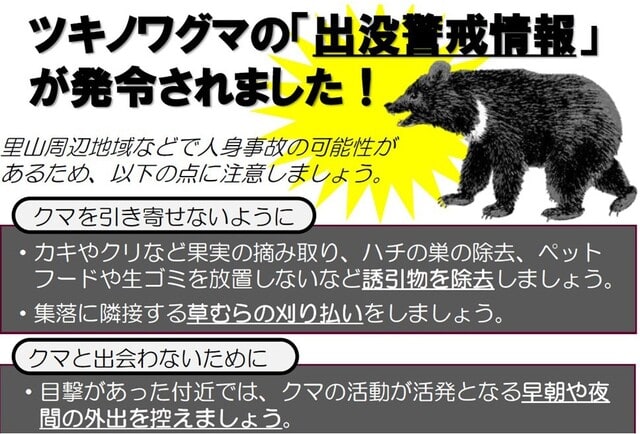☆目の当たりの『戦』この一年 ~その3~
「オール・オア・ナッシング」の驚きの事態が中国で顕著になっている。メディア各社の報道によると、ゼロコロナ政策を掲げてきた中国政府が今月7日に大転換し、新型コロナウイルスの感染者数と死者数が急増しているようだ。緩和政策は、それまでの「白紙」抗議デモによる妥協との見方もあるが、変異ウイルスにより感染力が強まって、ゼロコロナ政策そのものが機能しなくなったことや、工場の生産停止などで「世界の工場」の地位が失墜するという経済的な不安の高まりなどが指摘されている。
~大気汚染とコロナ感染、中国の『戦』い~
 そもそも中国はゼロコロナ政策になぜこだわってきたのか。2019年暮れに発生した武漢市での新型コロナウイルス感染が、2020年1月の中国の春節の大移動で、日本を含め世界各地にコロナ感染者が拡大したとされる。さらに、その発生源について「2020年2月6日、華南理工大学の肖波涛教授は、このウイルスについて『恐らく武漢の研究所が発生源だろう』と結論付けた論文を発表した。しかし中国政府はコロナの発生源に関する研究を厳しく制限しており、同教授は論文を撤回した」(2021年5月27日付・ウォールストリート・ジャーナルWeb版日本語)。こうした流れから読めることは、ゼロコロナという独自の防疫政策の優位性を誇示し、発生源は中国ではないと言い逃れしたかったのではないか。
そもそも中国はゼロコロナ政策になぜこだわってきたのか。2019年暮れに発生した武漢市での新型コロナウイルス感染が、2020年1月の中国の春節の大移動で、日本を含め世界各地にコロナ感染者が拡大したとされる。さらに、その発生源について「2020年2月6日、華南理工大学の肖波涛教授は、このウイルスについて『恐らく武漢の研究所が発生源だろう』と結論付けた論文を発表した。しかし中国政府はコロナの発生源に関する研究を厳しく制限しており、同教授は論文を撤回した」(2021年5月27日付・ウォールストリート・ジャーナルWeb版日本語)。こうした流れから読めることは、ゼロコロナという独自の防疫政策の優位性を誇示し、発生源は中国ではないと言い逃れしたかったのではないか。
それにしても、中国当局の発表では、政策を転換した今月7日以降の死者数は10人、2020年のパンデミック発生以降の公式な死者数は今月28日時点で5246人、という。メディアの報道によれば、基礎疾患があり死亡した場合はコロナによる死者数にカウントしないようだ。
以下は、あくまでも憶測だ。コロナ感染で中国で死者が多数出ているとされる、その基礎疾患とは何か。気になる言葉がある。中国のコロナ患者が死亡でキーワードに上がっているが「白肺」だ。肺炎になると、レントゲンでは肺が白く写る。コロナ感染で呼吸系疾患が重症化し、機能不全に陥り死亡するケースだ。中国は大気汚染が深刻で、呼吸器系疾患の患者が多いと聞いたことがある。2012年8月に浙江省杭州市での国際ワークショップに訪れた折、ガイドの女性から聞いた話だ。(※写真は、2008年1月に上海を訪れたときに撮影したもの)
中国の大気汚染の原因の一つは、石炭火力発電所に先進国では当たり前の脱硫装置をつけるが、中国では発電施設の増強が優先され設置が遅れている。発電施設の増強が優先され、その結果、上海などの大都市やその周辺では、肺がんやぜんそくなどを引き起こす微小粒子状物質「PM2・5」の大気中濃度が高まっているとされる。
中国では大気汚染でもともと呼吸器系疾患が広まっている上に、新型コロナウイルスの感染で肺炎症状などが悪化、重症化するケースが増えているのだろうか。現在ではPM2・5を排出する工場の稼働率も下がっていることだろう。ただ、呼吸器系疾患を以前から持ち続けている人々にとっては気の抜けない日々と察する。
⇒30日(金)午後・金沢の天気 くもり時々あめ