☆アフガン政変で見えたアメリカのドライなリセット
アフガニスタンにおける政変で、クローズアップされているのが「自主防衛」という言葉ではないだろうか。アメリカにとって、アフガンは「保護国」であって同盟国ではない。なので、アメリカはトランプ政権下の2020年2月、タリバンとの和平交渉で「アメリカは駐留軍撤退」「タリバンは武力行使を縮小」で合意。そして、バイデン大統領は今年4月に同時多発テロ事件から20年の節目にあたる「9月11日」まで完全撤退すると表明していた(4月14日付・BBCニュースWeb版日本語)。
では、タリバンが一方的に合意を破って首都カブールに進攻したのであれば、アメリカは駐留軍撤退の合意を破棄すべきではないか、との世界の論調も高まるだろう。現に、アメリカ世論は揺れている。ロイター通信はタリバンが首都カブールを制圧した後の16日に実施した世論調査を17日に公表した。バイデン大統領への支持率は46%で、先週の53%から7ポイント低下し、1月の就任後で最低を記録した(8月18日付・時事通信Web版)。一方で、アメリカのイプソス社が16日に行った世論調査では、アフガン駐留軍の完全撤収の判断には、61%が支持すると回答した。野党・共和党支持者に限っても支持(48%)が不支持(39%)を上回った(同・読売新聞Web版)。
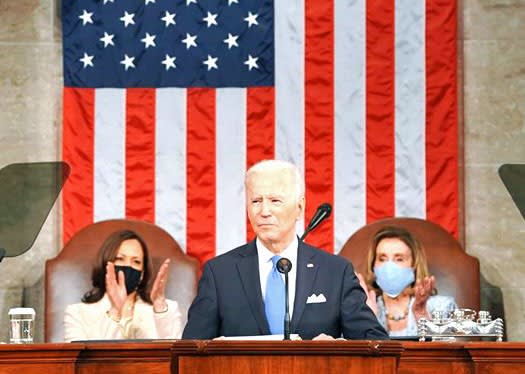 アメリカの世論がこれほど動くのも、歴代政権が支援してきたアフガンの民主政権を守れなかったのではないかとの国民の評価が分かれ、一方で、アメリカ軍と協力するはずの民主政権の「自主防衛」の有り様が問われた。このニュースは世界中に流れた。ロシア通信は16日、アフガンのガニ大統領が、車4台とヘリコプターに現金を詰め込んで同国を脱出したと伝えた。在アフガニスタンのロシア大使館広報官の話としている(同・共同通信Web版)。多額の現金に関してはフェイクニュースとの見方があるものの、軍の総司令官でもある大統領が抵抗勢力と戦わずして高跳びしたことは事実である。言うならば「無血開城」。これでは、アメリカ軍も手出しようがない。
アメリカの世論がこれほど動くのも、歴代政権が支援してきたアフガンの民主政権を守れなかったのではないかとの国民の評価が分かれ、一方で、アメリカ軍と協力するはずの民主政権の「自主防衛」の有り様が問われた。このニュースは世界中に流れた。ロシア通信は16日、アフガンのガニ大統領が、車4台とヘリコプターに現金を詰め込んで同国を脱出したと伝えた。在アフガニスタンのロシア大使館広報官の話としている(同・共同通信Web版)。多額の現金に関してはフェイクニュースとの見方があるものの、軍の総司令官でもある大統領が抵抗勢力と戦わずして高跳びしたことは事実である。言うならば「無血開城」。これでは、アメリカ軍も手出しようがない。
このアフガンの事態を見て、緊張しているのは台湾だろう。アメリカと台湾は1954年に「相互防衛条約」を締結し強固な同盟関係を結んだ。しかし、1979年のアメリカと中国の国交樹立を機に翌年1980年に条約は失効し、アメリカ軍の司令部や駐留軍は台湾から撤退した。ただ、アメリカは中国との軍事バランスの見地から、1979年にアメリカの国内法である「台湾関係法」を制定し、有事の際は日本やフィリピンのアメリカ軍基地からの軍隊の派遣を定めている。その代わりに台湾はアメリカから武器を購入するという、「柔らかな同盟」だ。
今回のアフガンの政変で台湾側は危機感を持った。NHKニュースWeb版(8月18日付)によると、蔡英文総統は18日、与党・民進党のオンライン会議で「台湾の唯一の選択肢は、より強大になり、より団結し、よりしっかりと自主防衛することだ。自分が何もせず、ただ人に頼ることを選んではいけない」と述べた。そして、民主と自由の価値を堅持し、国際社会で台湾の存在意義を高めることが重要だと強調した。
蔡氏があえて「自主防衛」を持ち出したのは、台湾をアフガンの二の舞にしてはならないという確固たる決意の表れだ。一方で、中国は今回のアフガンのように民主政権ならば何が何でも守るというスタンスではないアメリカのドライな一面を理解した。今後、中国は台湾海峡での海上封鎖といった緊張状態を仕掛けて、あるいは融和策を台湾に持ち掛けて、アメリカの出方をうかがうのではないか。その上で、アメリカ世論の動向も読みながら、「柔らかな同盟」を踏みつぶしにかかってくる。裏読みではある。 (※写真は、The White House公式ホームページより)
⇒19日(木)午後・金沢の天気 くもり時々あめ
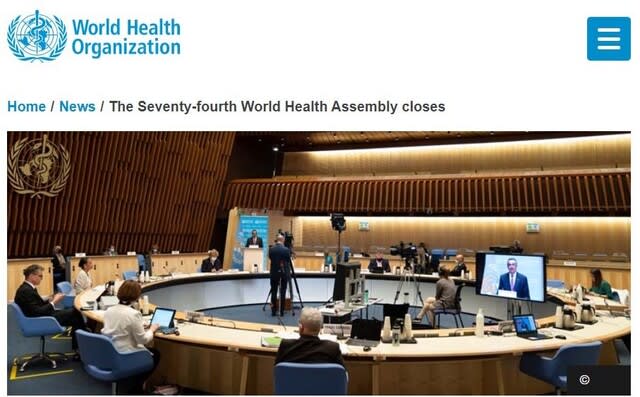 台湾はWHOに非加盟であるものの、2009年から2016年までは年次総会にオブザーバーとして参加していた。2017年以降は、中国と台湾は一つの国に属するという「一つの中国」を認めない蔡英文氏が台湾総統に就いたことで、「一つの中国」を原則を掲げる中国が反対し、オブザーバー参加が認められなくなった。
台湾はWHOに非加盟であるものの、2009年から2016年までは年次総会にオブザーバーとして参加していた。2017年以降は、中国と台湾は一つの国に属するという「一つの中国」を認めない蔡英文氏が台湾総統に就いたことで、「一つの中国」を原則を掲げる中国が反対し、オブザーバー参加が認められなくなった。 認めるよう各国に求める決議を全会一致で可決した(6月11日付・NHKニュースWeb版)。決議文は超党派の議員がまとめたもので、「検疫体制の強化などに先駆的に取り組んできた台湾が会議に参加できないことが、国際防疫上、世界的な損失であることは、各国の共通認識になっている」との内容で、政府にも今後、台湾が会議に参加する機会が保障されるよう各国に働きかけることを求めている(同)。
認めるよう各国に求める決議を全会一致で可決した(6月11日付・NHKニュースWeb版)。決議文は超党派の議員がまとめたもので、「検疫体制の強化などに先駆的に取り組んできた台湾が会議に参加できないことが、国際防疫上、世界的な損失であることは、各国の共通認識になっている」との内容で、政府にも今後、台湾が会議に参加する機会が保障されるよう各国に働きかけることを求めている(同)。
