☆遅咲きの梅の花 震災の倒壊ビルは片付くも、待たれる原因究明
けさから金沢は晴れて、午前中の気温が16度と春の陽気を感じる天気となっている。そして、自宅庭の梅の木の花がようやく咲き始めた=写真・上=。金沢地方気象台の生物季節観測表によると、金沢の梅の開花は平年2月23日となっているので、まさに1ヵ月遅れだ。ちなみに観測表によると、これまでの早咲きは1月28日(1998年)、遅咲きは4月6日(1957年)とある。予報によると、気温はあす24日は22度、27日は25度の夏日となり、これから一気に開花 するのだろう。そして気になるのは桜の開花。観測表の金沢の平年の開花は4月3日、ウェザーニュースの開花予想日だと4月2日だ。梅の散り際とソメイヨシノの咲き始めが同時に楽しめるかもしれない。
するのだろう。そして気になるのは桜の開花。観測表の金沢の平年の開花は4月3日、ウェザーニュースの開花予想日だと4月2日だ。梅の散り際とソメイヨシノの咲き始めが同時に楽しめるかもしれない。
話は変わる。おととい(21日)輪島市の豪雨被災地と併せて震災地をめぐった。言葉は適切ではないかもしれないが、ある意味で震災のシンボル的な光景されてきたのが、240棟余りの商店や民家が全焼し焦土と化した朝市通り、そして、倒壊した輪島塗製造販売会社「五島屋」の7階建てビルだった。倒壊によってビルに隣接していた3階建ての住居兼居酒屋が下敷きとなり、母子2人が犠牲となった。倒壊現場を初めて見たのは2月5日だった。その倒れ方は壮絶だった。地面下に打ち込んで固定されていたビルの根っこ部分にあたる コンクリートと鉄による杭(くい)の基礎部分がまるでゴボウ抜きしたようにむき出しになっていた。まったくの素人目線なのだが、バランスを崩して根っこから倒れた、そんなように見えた。(※写真・中は2024年2月5日撮影、写真・下は今月21日撮影)
コンクリートと鉄による杭(くい)の基礎部分がまるでゴボウ抜きしたようにむき出しになっていた。まったくの素人目線なのだが、バランスを崩して根っこから倒れた、そんなように見えた。(※写真・中は2024年2月5日撮影、写真・下は今月21日撮影)
おととい現場を訪れると、倒壊したビルの公費解体はほとんど終わっているように見えた。解体作業が始まったのは10月初旬だったので、半年ほどかけてひと区切りが付いたように見えた。むしろ問題視されているのはビル倒壊の原因が何なのかという点ではないだろうか。一部報道によると、2007年3月25日の能登半島地震でビルが大きく揺れたことから、五島屋の社長はビルの耐震性を懸念して、地下を埋めて基礎を強化する工事を行っていた。それが倒壊したとなると、社長自身もビル倒壊に納得していないようだ。ビルの築年数は50年ほど。基礎部の一部が地面にめり込んでおり、くいの破損や地盤が原因ではないかとも指摘されている。
国土交通省が基礎部を中心に倒壊の原因を調べている。なぜ、震度6強の揺れに耐えきれずに根元から倒れたのか。ビル倒壊の原因が分かってくれば、責任の所在もおのずと明らかになるだろう。倒壊原因についてはいまだ公表されていない。
⇒23日(日)午後・金沢の天気 はれ
 最強寒波の影響で大雪となっている能登では、震災で全半壊した家屋の公費解体が一時ストップしていると前回ブログで述べた。では、公費解体そのものはどこまで進んでいるのだろうか。今月6日発表した石川県のまとめによると、去年元日の能登地震と9月の豪雨で被災した家屋のうち公費解体が見込まれる家屋は3万9235棟、そのうち1月末時点で1万7112棟で解体作業を終えていて、43.6%が完了したことなる。公費解体は持ち主の申請によるもので、申請数は1月末時点で3万6304棟に上る。半壊と判定されても修繕すれば住み続けられるも家屋もあり、県では解体を申請しても申し出があれば留保し取り消しもできるとしている。
最強寒波の影響で大雪となっている能登では、震災で全半壊した家屋の公費解体が一時ストップしていると前回ブログで述べた。では、公費解体そのものはどこまで進んでいるのだろうか。今月6日発表した石川県のまとめによると、去年元日の能登地震と9月の豪雨で被災した家屋のうち公費解体が見込まれる家屋は3万9235棟、そのうち1月末時点で1万7112棟で解体作業を終えていて、43.6%が完了したことなる。公費解体は持ち主の申請によるもので、申請数は1月末時点で3万6304棟に上る。半壊と判定されても修繕すれば住み続けられるも家屋もあり、県では解体を申請しても申し出があれば留保し取り消しもできるとしている。 ㍍)の大きな家だ。黒瓦と白壁、威風堂々としたたたずまい。九六を建てるのが男の甲斐性(かいしょう)とする風土もあり、「九六の意地」とも称される。今回の大雪で九六はどうなっているのか、能登町に向かった。
㍍)の大きな家だ。黒瓦と白壁、威風堂々としたたたずまい。九六を建てるのが男の甲斐性(かいしょう)とする風土もあり、「九六の意地」とも称される。今回の大雪で九六はどうなっているのか、能登町に向かった。 ンを使わないのですか」と尋ねると、「夏は風が通るので使わない。冬は石油ストーブがあればそれで十分。エアコンはいらない」とのことだった。それにしても大きい。初めての人は大寺院と見間違えするかもしれない。
ンを使わないのですか」と尋ねると、「夏は風が通るので使わない。冬は石油ストーブがあればそれで十分。エアコンはいらない」とのことだった。それにしても大きい。初めての人は大寺院と見間違えするかもしれない。 衆の拍手にまったく気づかず、背を向けていた。見かねたかアルト歌手がベートーベンの手を取って、聴衆の方に向かわせて初めて熱狂的な反応に気が付いたという話だ。そんなリーフレットの説明も目を通していると、演奏が始まった。(※写真は、第九交響曲コンサートのチラシ)
衆の拍手にまったく気づかず、背を向けていた。見かねたかアルト歌手がベートーベンの手を取って、聴衆の方に向かわせて初めて熱狂的な反応に気が付いたという話だ。そんなリーフレットの説明も目を通していると、演奏が始まった。(※写真は、第九交響曲コンサートのチラシ) 現地では、パワーショベルなど重機が3台が動いていた=写真・上=。行政による公費解体で、2棟ある五島屋ビルのうち倒壊を免れた3階建てのビルは解体が終わり、市道にはみ出している7階建てビルの解体が始まっていた。解体と合わせて、国交省は倒壊原因について基礎部分の調査を現在行っている。解体は当初、上部から段階的に輪切りにして解体していく予定だったが、周囲への安全面に配慮して側面から崩すように作業を変更した。3階以上は年内に、ビル全体は年度内に作業を終えるようだ(17日付・地元メディア各社の報道)。
現地では、パワーショベルなど重機が3台が動いていた=写真・上=。行政による公費解体で、2棟ある五島屋ビルのうち倒壊を免れた3階建てのビルは解体が終わり、市道にはみ出している7階建てビルの解体が始まっていた。解体と合わせて、国交省は倒壊原因について基礎部分の調査を現在行っている。解体は当初、上部から段階的に輪切りにして解体していく予定だったが、周囲への安全面に配慮して側面から崩すように作業を変更した。3階以上は年内に、ビル全体は年度内に作業を終えるようだ(17日付・地元メディア各社の報道)。 どで出張朝市などを続けてきたが、最近では「カムバック朝市」を目指して、朝市通りの近くにある輪島市マリンタウンの特設会場で1日限定のイベントを催したり、地元での屋外開催を増やしている。
どで出張朝市などを続けてきたが、最近では「カムバック朝市」を目指して、朝市通りの近くにある輪島市マリンタウンの特設会場で1日限定のイベントを催したり、地元での屋外開催を増やしている。 ルなどはほぼ解体され、更地に戻りつつある。今月5日に輪島市の現場を視察した石破総理に対し、同市の坂口市長は新たな建物を建てるため、土地区画整理を行うなどと説明していた(5日付・地元メディア各社の報道)。地域の再開発が動き出すのだろう。
ルなどはほぼ解体され、更地に戻りつつある。今月5日に輪島市の現場を視察した石破総理に対し、同市の坂口市長は新たな建物を建てるため、土地区画整理を行うなどと説明していた(5日付・地元メディア各社の報道)。地域の再開発が動き出すのだろう。 このブログの8月9日付で紹介した珠洲市の「3Dプリンター住宅」が完成したとニュースになっていたので見に行った。同市上戸町にことし7月にオープンしたホテルの別室。ホテルの支配人が兵庫県西宮市のスタートアップ企業である建築会社に発注して造った建物。2人世帯向け平屋タイプで、ダイニングや寝室、バスルームなどがある。石川県では初めての「3D住宅」という。中には入れなかったが、日本海が一望できる。そもそもが何が3Dなのかと言うと、3Dプリンターが設計データを読み込み、ロボットがコンクリートを塗り重ねて、壁や屋根を成形する仕組みのようだ。
このブログの8月9日付で紹介した珠洲市の「3Dプリンター住宅」が完成したとニュースになっていたので見に行った。同市上戸町にことし7月にオープンしたホテルの別室。ホテルの支配人が兵庫県西宮市のスタートアップ企業である建築会社に発注して造った建物。2人世帯向け平屋タイプで、ダイニングや寝室、バスルームなどがある。石川県では初めての「3D住宅」という。中には入れなかったが、日本海が一望できる。そもそもが何が3Dなのかと言うと、3Dプリンターが設計データを読み込み、ロボットがコンクリートを塗り重ねて、壁や屋根を成形する仕組みのようだ。 では、なぜ倒壊した民家などが手つかずの状態になっているのか。考えうるのは、能登には空き家が多くあることだ。今回の地震では石川県全体で全半壊・一部損壊が7万3500棟に及んでいて(3月15日現在)、このうち全半壊の2万3700棟については自治体が費用を負担して解体ならびに撤去する。政府が能登半島地震を特定非常災害に指定したことから、いわゆる「公費解体」が可能となった。県ではこの作業を来年秋の2025年10月までに終える計画だ。ただ、問題がある。公費解体は所有者の申請、あるいは同意に基づいて行われるが、空き家の場合は所有者と連絡がつかない、あるいは所有者が誰なのか不明というケースが多いのだ。
では、なぜ倒壊した民家などが手つかずの状態になっているのか。考えうるのは、能登には空き家が多くあることだ。今回の地震では石川県全体で全半壊・一部損壊が7万3500棟に及んでいて(3月15日現在)、このうち全半壊の2万3700棟については自治体が費用を負担して解体ならびに撤去する。政府が能登半島地震を特定非常災害に指定したことから、いわゆる「公費解体」が可能となった。県ではこの作業を来年秋の2025年10月までに終える計画だ。ただ、問題がある。公費解体は所有者の申請、あるいは同意に基づいて行われるが、空き家の場合は所有者と連絡がつかない、あるいは所有者が誰なのか不明というケースが多いのだ。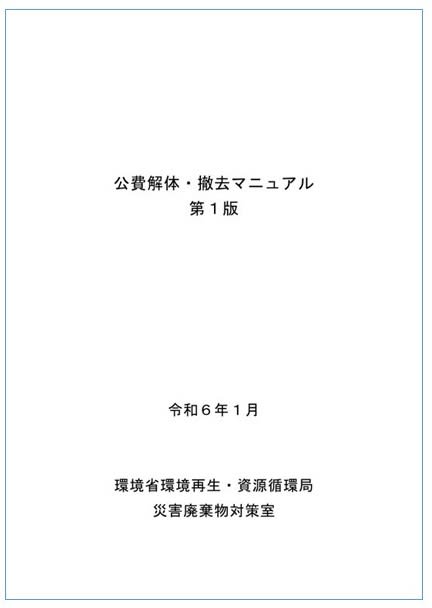 23.5%、珠洲市は20.6%、能登町は24.3%となっている。ちなみに県内で空き家率がもっとも高いのは、原発が立地する志賀町の28.1%だ。
23.5%、珠洲市は20.6%、能登町は24.3%となっている。ちなみに県内で空き家率がもっとも高いのは、原発が立地する志賀町の28.1%だ。