★本州最後の一羽のトキ「能里」が残した教訓
本州最後の一羽のトキは愛称「能里(のり)」と呼ばれていた。能登半島で生息していたが、国の指示で1970年1月に捕獲され、繁殖のために佐渡トキ保護センターに移された。しかし、翌71年3月13日にケージの金網でくちばしを折ったことが原因で死んでしまった。もう半世紀も前のことだが、能登の人たちの中には、「昔ここには能里が飛んで来とった」と今でも懐かしそうに話すシニアの人たちもいる。
 こうした能登のトキへの想いが伝わったのだろう、環境省は去年8月、佐渡市で野生復帰の取り組みが進むトキについて、本州で放鳥を行う候補地として能登半島と島根県出雲市を選定し、能登での放鳥は2026年以降と発表した。これを受けて、石川県は先月15日に発表した2023年度の当初予算案で、放鳥のための生息の環境づくり関連費として1億360万円の「トキ予算」を盛り込んだ。また、国連が定める「国際生物多様性の日」である5月22日を「いしかわトキの日」と決め、県民のモチベーションを盛り上げる。(※写真は石川県歴史博物館で展示されている「能里」のはく製)
こうした能登のトキへの想いが伝わったのだろう、環境省は去年8月、佐渡市で野生復帰の取り組みが進むトキについて、本州で放鳥を行う候補地として能登半島と島根県出雲市を選定し、能登での放鳥は2026年以降と発表した。これを受けて、石川県は先月15日に発表した2023年度の当初予算案で、放鳥のための生息の環境づくり関連費として1億360万円の「トキ予算」を盛り込んだ。また、国連が定める「国際生物多様性の日」である5月22日を「いしかわトキの日」と決め、県民のモチベーションを盛り上げる。(※写真は石川県歴史博物館で展示されている「能里」のはく製)
トキ放鳥のムードが盛り上がる中で、懸念も増している。このブログでも何度か取り上げた、能登半島で進む風力発電の増設計画についてだ。長さ30㍍クラスのブレイド(羽根)の風車が能登には現在73基あるが、新たに12事業・171基が計画されている。
自然保護の観点から懸念されるのはバードストライク問題であり、景観上もふさわしくない。そして、地域住民への影響もある。去年7月で開催された「能登地域トキ放鳥推進シンポジウム」(七尾市田鶴浜)で、地元の環境保護団体の代表と立ち話で意見交換をした。代表が住む地域の周囲には10基の風車が回り、「風が強い日の風車の風切り音はとてもうるさく、滝の下にいるような騒音だよ」「これ以上、増設する必要はない」と強調していた。
石川県は今月5日、能登でのトキの放鳥に向けた「ロードマップ」案を作成。それによると、能登の9つの自治体などと連携し、トキが生息できる環境整備として700㌶の餌場を確保する方針で、化学肥料や農薬を使わない水田など「モデル地区」を設けて生き物調査を行い、拡充していく。
能登はトキが営巣するのに必要なアカマツ林が豊富だ。そして、リアス式海岸で知られる能登は平地より谷間が多い。警戒心が強いとされるトキは谷間の棚田で左右を警戒しながらドジョウやタニシなどの採餌行動をとる。豊富な餌を担保する溜め池と水田、営巣に必要なアカマツ林、そしてコロニーを形成する谷という条件が能登にはある。佐渡に次ぎ、能登半島が本州のトキの繁殖地となることを期待したい。
⇒12日(日)午後・金沢の天気 はれ
 本州最後の1羽だったトキが1970年に能登半島で捕獲され、繁殖のため佐渡のトキ保護センターに送られた実績があることから、石川県と能登の4市5町、JAなど関係団体は5月6日に「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を結成。環境省に受け入れを申請していた。
本州最後の1羽だったトキが1970年に能登半島で捕獲され、繁殖のため佐渡のトキ保護センターに送られた実績があることから、石川県と能登の4市5町、JAなど関係団体は5月6日に「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を結成。環境省に受け入れを申請していた。 ひなを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと、福井県越前市生まれのメスで、ことし4月中旬に志賀町の山の中の電柱の上に巣をつくり、5月下旬には親鳥がひなに餌を与える様子が確認された。初めて見た1ヵ月前より、相当大きくなっていて、時折羽を広げて飛び立とうとしている様子だった=写真・下=。この場所はコウノトリのひなが育った日本での最北の地とされていて、これからの定着と繁殖を期待しながら巣を見上げていた。
ひなを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと、福井県越前市生まれのメスで、ことし4月中旬に志賀町の山の中の電柱の上に巣をつくり、5月下旬には親鳥がひなに餌を与える様子が確認された。初めて見た1ヵ月前より、相当大きくなっていて、時折羽を広げて飛び立とうとしている様子だった=写真・下=。この場所はコウノトリのひなが育った日本での最北の地とされていて、これからの定着と繁殖を期待しながら巣を見上げていた。 ツアーのテーマは「佐渡GIAHSを形成したジオパークと佐渡金銀山、そして農村の営み」。佐渡の金山跡に入ると、ガイドの女性が詳しく説明してくれた。島内には55の鉱山があり、江戸時代から約390年間に産出された金は78㌧、銀は2330㌧に上った。佐渡金山は幕府直轄の天領として奉行所が置かれ、金銀の採掘のほか小判の製造も行われた。鉱山開発の拠点となった佐渡には国内各地から山師や測量技術者、労働者が集まった。最前線で鉱石を掘ったのは、「金穿大工(かなほりだいく)」と呼ばれた採掘のプロだった。
ツアーのテーマは「佐渡GIAHSを形成したジオパークと佐渡金銀山、そして農村の営み」。佐渡の金山跡に入ると、ガイドの女性が詳しく説明してくれた。島内には55の鉱山があり、江戸時代から約390年間に産出された金は78㌧、銀は2330㌧に上った。佐渡金山は幕府直轄の天領として奉行所が置かれ、金銀の採掘のほか小判の製造も行われた。鉱山開発の拠点となった佐渡には国内各地から山師や測量技術者、労働者が集まった。最前線で鉱石を掘ったのは、「金穿大工(かなほりだいく)」と呼ばれた採掘のプロだった。 水上輪は坑道の安全を守るために必要だった。地下に向かって鉱石を掘れば掘るほど水が湧き出るため、放っておけば坑道が水没する恐れがあった。そこで、手動のポンプである水上輪を導入し、水を汲み上げて排水溝に注いだ。ただ、ハンドルを回すのは相当な力仕事だった。水上輪だけでなく、桶でくみ上げる作業と合わせて坑道の排水作業は「水替人足(みずかえにんそく)」の仕事だった。
水上輪は坑道の安全を守るために必要だった。地下に向かって鉱石を掘れば掘るほど水が湧き出るため、放っておけば坑道が水没する恐れがあった。そこで、手動のポンプである水上輪を導入し、水を汲み上げて排水溝に注いだ。ただ、ハンドルを回すのは相当な力仕事だった。水上輪だけでなく、桶でくみ上げる作業と合わせて坑道の排水作業は「水替人足(みずかえにんそく)」の仕事だった。 GIAHS認定をステップにして、翌2012年7月に「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)が開催された。この会議には日本のほか中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。国際会議が開かれるきっかけとなったのが、2010年10月に生物多様性第10回締約国会議(COP10)だった。湿地における生物多様性に配慮するラムサール条約の「水田決議」をCOP10でも推進することが決まった。この決議で佐渡の認証米制度が世界各国から注目されることになる。
GIAHS認定をステップにして、翌2012年7月に「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)が開催された。この会議には日本のほか中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。国際会議が開かれるきっかけとなったのが、2010年10月に生物多様性第10回締約国会議(COP10)だった。湿地における生物多様性に配慮するラムサール条約の「水田決議」をCOP10でも推進することが決まった。この決議で佐渡の認証米制度が世界各国から注目されることになる。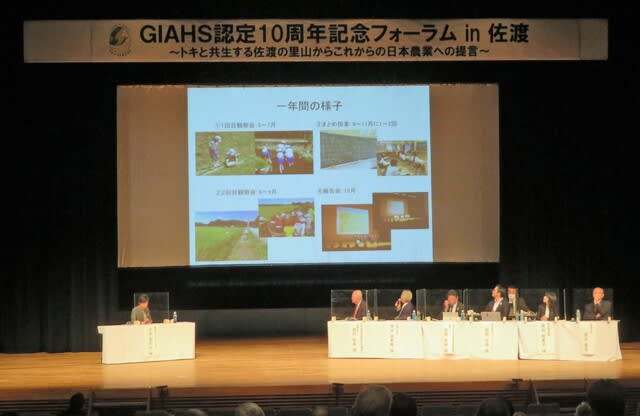 きょうパネルディスカッション=写真・下=では「これからの日本農業への提言」をテーマに話し合った。能登GIAHSから参加した珠洲市長の泉谷満寿裕氏から意外な発言があった。「トキを能登で放鳥してほしい」と。この発言には背景がある。環境省は今後のトキの放鳥について、2025年までのロードマップをことし6月に作成し、トキの受け入れに意欲的な地域(自治体)を中心に、トキの生息に適した環境の保全や再生、住民理解などの社会環境の整備に取り組む(6月22日付・読売新聞Web版)。トキは感染症の影響を受けやすい。さらに、佐渡で野生生息が484羽に増えており、今後エサ場の確保などを考慮すると、佐渡以外での複数の生息地を準備することが不可欠との判断されたのだろう。泉谷氏の発言は地元佐渡で受け入れの名乗りを上げたことになる。
きょうパネルディスカッション=写真・下=では「これからの日本農業への提言」をテーマに話し合った。能登GIAHSから参加した珠洲市長の泉谷満寿裕氏から意外な発言があった。「トキを能登で放鳥してほしい」と。この発言には背景がある。環境省は今後のトキの放鳥について、2025年までのロードマップをことし6月に作成し、トキの受け入れに意欲的な地域(自治体)を中心に、トキの生息に適した環境の保全や再生、住民理解などの社会環境の整備に取り組む(6月22日付・読売新聞Web版)。トキは感染症の影響を受けやすい。さらに、佐渡で野生生息が484羽に増えており、今後エサ場の確保などを考慮すると、佐渡以外での複数の生息地を準備することが不可欠との判断されたのだろう。泉谷氏の発言は地元佐渡で受け入れの名乗りを上げたことになる。 では、どこで放鳥が始まるのか。やはり、本州最後の一羽が生息していた能登ではないだろうか。奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)には大小1000ヵ所ともいわれる水稲用の溜め池がある。溜め池は中山間地にあり、上流に汚染源がないため水質が保たれている。ゲンゴロウやサンショウウオ、ドジョウなどの水生生物が量、種類とも豊富である。これらの水生生物は疏水を伝って水田へと流れていく。
では、どこで放鳥が始まるのか。やはり、本州最後の一羽が生息していた能登ではないだろうか。奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)には大小1000ヵ所ともいわれる水稲用の溜め池がある。溜め池は中山間地にあり、上流に汚染源がないため水質が保たれている。ゲンゴロウやサンショウウオ、ドジョウなどの水生生物が量、種類とも豊富である。これらの水生生物は疏水を伝って水田へと流れていく。
