☆能登半島地震 マイナス金利解除、そして過疎化に拍車
日銀がマイナス金利の解除を決めた。これが被災地にどのような影響を及ぼすのか。地震の激しい揺れや土砂災害、液状化、火災、津波などで住宅に大きな被害が出ている。石川県のまとめ(3月15日現在)で、全壊が8500棟、半壊が1万5200棟、一部破損が4万9700棟あまりとなる。全半壊の解体・撤去は自治体が公費で行うが、新築して再建する際に住宅ローンはどうなるのか。
武見厚労大臣は2月27日の記者会見で、能登半島地震で被災した世帯が住宅ローンを組んで自宅を再建する場合、石川県事業として最大300万円の金利助成を実施すると発表した。また、北國銀行(金沢市)はきょう19日付のニュースリリースで、「住宅ローンを今月22日以降に新規でお借入される際に、特約固定2年、3年を選択されるお客さまのお借入時および初回金利更新時の割引幅を拡大します」と発表している。さらに、能登半島地震の住宅再建のため、一部の優遇金利をさらに引き下げる考えも示している。確かに、金融機関にとっては、復旧・復興にこれから着手する地域での貸出金利の引き上げはそう簡単な話ではないだろう。
 元旦ということもあって自宅でくつろいでいるときの地震だった。被災地をめぐると、住宅だけでなくガレージも車ごと押しつぶされたような状態になっているケースが目につく。住宅再建のほかに車も新規に購入するなど、対応に迫られるだろう。そして、被災した中小企業や個人事業主にとっては住宅のほかに店舗や工場の再建もあり、負担はさらに重くなることは想像に難くない。(※写真は、七尾市の老舗商店街「一本杉通り」で倒壊した和ろうそくの店舗=2月3日撮影)
元旦ということもあって自宅でくつろいでいるときの地震だった。被災地をめぐると、住宅だけでなくガレージも車ごと押しつぶされたような状態になっているケースが目につく。住宅再建のほかに車も新規に購入するなど、対応に迫られるだろう。そして、被災した中小企業や個人事業主にとっては住宅のほかに店舗や工場の再建もあり、負担はさらに重くなることは想像に難くない。(※写真は、七尾市の老舗商店街「一本杉通り」で倒壊した和ろうそくの店舗=2月3日撮影)
被災地のさらなる難題は過疎化の進行かも知れない。もともと能登は人口減少が急ピッチで進んでいた。65歳以上の高齢化率が50%以上の自治体もある。震災を機に、金沢など都市で暮らす息子や娘たちとの同居、あるいはアパートやマンション住まいが加速するだろう。共同通信Web版(3月3日付)によると、今回の地震で甚大な被害を受けた輪島市や珠洲市など奥能登2市2町の今年1月の転出者数が計397人となり、前年1月の93人の4.27倍に上ることが、石川県がまとめた2月1日時点の人口推計で判明した。4市町の1月の転出者数は被害が大きかった輪島市が180人で、前年1月の29人の6.2倍、そして珠洲市は112人で同20人の5.6倍に上っている。
これは一時的な現象ではない。2007年3月25日の能登半島地震(震度6強)で家屋被害が大きかった輪島市と穴水町では、10年間で人口減少が輪島市で17%、穴水町で19%も進んだ(2017年・石川県の人口統計)。今回の地震は2007年に比べて広範囲で桁違いに被害が大きい。今後、強烈に過疎化が進むのではないか。
⇒19日(火)夜・金沢の天気 あめ
 ョ現象で暖冬と長期予報が出ていたが、季節感が失われるのではないかと、妙な胸騒ぎがする。
ョ現象で暖冬と長期予報が出ていたが、季節感が失われるのではないかと、妙な胸騒ぎがする。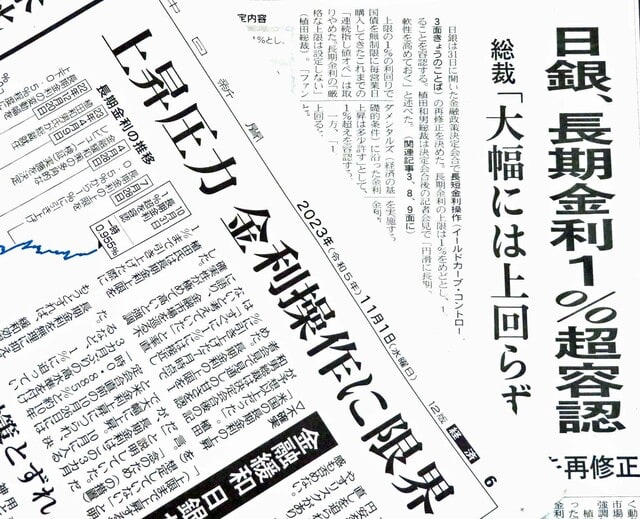 そしてきょうの株式は午前中、前日比600円余り高くなっている。外国為替市場で1㌦=151円台まで円安にシフトしていて、輸出関連企業への買いが広がっているようだ。
そしてきょうの株式は午前中、前日比600円余り高くなっている。外国為替市場で1㌦=151円台まで円安にシフトしていて、輸出関連企業への買いが広がっているようだ。 一つ注目しているのが、市場金利の上昇と住宅ローン金利、そして住宅価格だ。すでに建築資材などの価格が一斉に上がっている。当然、
一つ注目しているのが、市場金利の上昇と住宅ローン金利、そして住宅価格だ。すでに建築資材などの価格が一斉に上がっている。当然、