☆タリバンの容赦ないジャーナリスト狩り
実にいたましい記事だ。そして、この記事の写真を見るとタリバンは獲物を狙う「山賊」のようにも見える。ドイツ国際放送「Deutsche Welle」(DW)は19日、アフガニスタン国籍の同社記者の家族がタリバンによって射殺されたと報じている=写真=。記事は、「Journalists and their families are in grave danger in Afghanistan. The Taliban have no compunction about carrying out targeted killings as the case of a DW journalist shows.」(意訳:アフガンではジャーナリストとその家族が重大な危険にさらされている。DWのジャーナリストのケースが示すように、タリバンは標的を絞って殺害を実行し、そこには何らの妥協もない)と報じている。
 DW記事によると、射殺されたのは「ストリンガー」と呼ばれる、アフガンで採用された現地記者の家族だ。記者はドイツの本社に来ていた。タリバンはその記者を探して家から家へ捜索を行っていた。家族を探し出して、射殺した。以下憶測だが、記者がドイツの本社にいることを家族から聞いて、見せしめに家族を射殺したのだろう。もともと記者本人を殺害するために探していた。
DW記事によると、射殺されたのは「ストリンガー」と呼ばれる、アフガンで採用された現地記者の家族だ。記者はドイツの本社に来ていた。タリバンはその記者を探して家から家へ捜索を行っていた。家族を探し出して、射殺した。以下憶測だが、記者がドイツの本社にいることを家族から聞いて、見せしめに家族を射殺したのだろう。もともと記者本人を殺害するために探していた。
タリバンによる「ジャーナリスト狩り」はこれだけではない。記事によると、アフガンの民間テレビ局ガルガシュトテレビの記者はタリバンに誘拐され、民間ラジオ局パクティア・ガグラジオの責任者は射殺されている。ドイツの週刊ニュース紙「Die Zeit」に投稿していた翻訳者が今月に入って射殺されている。そして、世界的にも有名なインドの写真家のデニッシュ・シディキ氏(ピューリッツァー賞受賞者、ロイター通信写真記者)が7月16日にカンダハルで武装勢力によって殺害されている。
ドイツジャーナリスト協会(DJV)は、欧米のメディアで働いているストリンガーの家族が殺害されたことを受けて、「同僚が迫害され、殺害されている間、ドイツはぼんやりと立っていてはならない」と声明を発表して、ドイツ政府に迅速な行動を取るように求めている。また、国際ジャーナリストのNGO「国境なき記者団(RSF)」は国連安全保障理事会に対し、アフガンにおけるジャーナリストへの危険な状況に対処するための非公式の特別セッションを開催するよう要請した。
では、なぜ、タリバンがジャーナリスト狩りを行っているのか。イスラム原理主義のタリバンが目指すところは、最高意思決定機関を据えた政教一致の体制だろう。ところが、世界のジャーナリストは権力への監視という重要な役割を担っていると自負している。タリバンにとっては、政権批判は忌み嫌う欧米の文化と映るのだろう。「山狩り」のように徹底したジャーナリストの排除を狙っているのではないだろうか。
⇒21日(土)午後・金沢の天気 くもり時々あめ
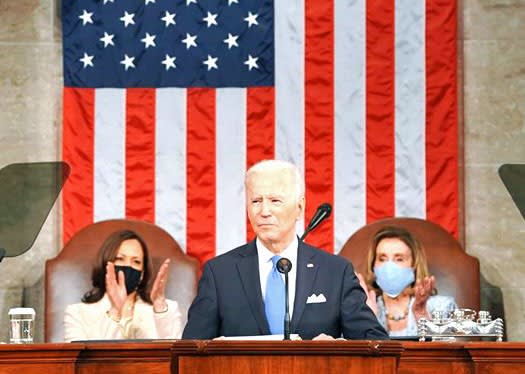 アメリカの世論がこれほど動くのも、歴代政権が支援してきたアフガンの民主政権を守れなかったのではないかとの国民の評価が分かれ、一方で、アメリカ軍と協力するはずの民主政権の「自主防衛」の有り様が問われた。このニュースは世界中に流れた。ロシア通信は16日、アフガンのガニ大統領が、車4台とヘリコプターに現金を詰め込んで同国を脱出したと伝えた。在アフガニスタンのロシア大使館広報官の話としている(同・共同通信Web版)。多額の現金に関してはフェイクニュースとの見方があるものの、軍の総司令官でもある大統領が抵抗勢力と戦わずして高跳びしたことは事実である。言うならば「無血開城」。これでは、アメリカ軍も手出しようがない。
アメリカの世論がこれほど動くのも、歴代政権が支援してきたアフガンの民主政権を守れなかったのではないかとの国民の評価が分かれ、一方で、アメリカ軍と協力するはずの民主政権の「自主防衛」の有り様が問われた。このニュースは世界中に流れた。ロシア通信は16日、アフガンのガニ大統領が、車4台とヘリコプターに現金を詰め込んで同国を脱出したと伝えた。在アフガニスタンのロシア大使館広報官の話としている(同・共同通信Web版)。多額の現金に関してはフェイクニュースとの見方があるものの、軍の総司令官でもある大統領が抵抗勢力と戦わずして高跳びしたことは事実である。言うならば「無血開城」。これでは、アメリカ軍も手出しようがない。 ニューヨークでの同時多発テロ事件で、ブッシュ大統領はタリバンが首謀者のオサマ・ビン・ラディンをかくまっていると非難して、アフガンへの空爆を始めた。アメリカにとって、「テロの温床」タリバンのイメージは20年経った今も変わっていないのだろう。
ニューヨークでの同時多発テロ事件で、ブッシュ大統領はタリバンが首謀者のオサマ・ビン・ラディンをかくまっていると非難して、アフガンへの空爆を始めた。アメリカにとって、「テロの温床」タリバンのイメージは20年経った今も変わっていないのだろう。 連合軍がアフガンへの空爆を始め、タリバン政権は崩壊。大規模な捜索にもかかわらず、ビン・ラディンを捕捉できなかった。10年後の2011年5月2日、隣国パキスタンに逃げ込んでいたビン・ラディンの潜伏先をアメリカ軍特殊部隊が探し出して殺害している。
連合軍がアフガンへの空爆を始め、タリバン政権は崩壊。大規模な捜索にもかかわらず、ビン・ラディンを捕捉できなかった。10年後の2011年5月2日、隣国パキスタンに逃げ込んでいたビン・ラディンの潜伏先をアメリカ軍特殊部隊が探し出して殺害している。