★フェイクニュースをどう司法判断するのか
前回のブログに続き、今回も「ジャーナリスト狩り」をテーマに取り上げる。韓国の朝鮮日報Web版日本語(8月21日付)の記事は「韓国与党・共に民主党がいわゆる『言論懲罰法』と呼ばれる言論仲裁法の改正を強行採決しようとする中、各国の言論団体など海外のジャーナリストたちも批判の声を上げ始めた」と報じている。ネットでこれまで韓国の言論仲裁法については何度か読んだが、海外のジャーナリストを巻き込んで事が大きくなっている。
この言論仲裁法は正式には「言論仲裁および被害救済等に関する法律」と呼ばれ、報道被害の救済を大義名分につくられた法律だ。今回の改正法案は、新聞・テレビのマスメディアやネットニュースで、取り上げられた個人や団体側がいわゆる「フェイクニュース」として捏造・虚偽、誤報を訴え、裁判所が故意や重過失がある虚偽報道と判断すれば、報道による被害額の最大5倍まで懲罰的損害賠償を請求することができる。つまり、メディアの賠償責任を重くすることで、報道被害の救済に充てる改正法案だ。国会で3分の2以上の議席を占める与党系が今月25日にも強行採決する見通し。
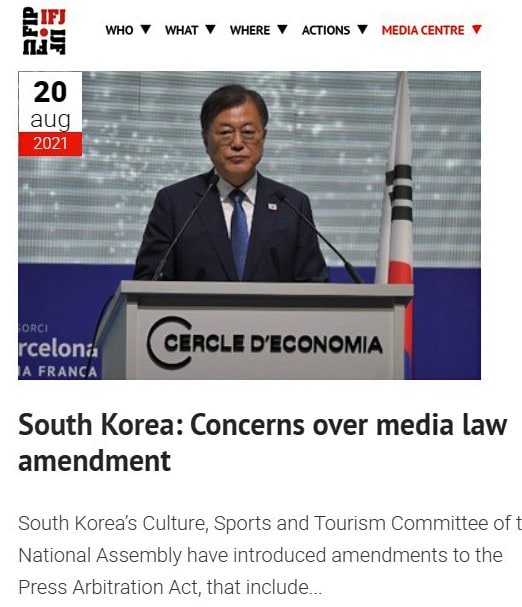 改正法案を急ぐ理由には、韓国のネット事情もあるのではないか。「ネット大国」といわれる韓国では中小メディアが乱立し、臆測に基づくニュースが目に付く。フェイクニュースではなかったが、先の東京オリンピックでは2つの金メダルを獲得した韓国のアーチェリー選手が、短くした髪型が理由で、国内のネット上で中傷が相次いでいると報道されていた(7月30日付・日テレNEWS24Web版)。韓国ではSNSによる誹謗中傷で芸能人の自死が相次ぐなど社会問題化している。当事者に対して強烈な批判が沸き起こる社会的な風土があるのかもしれない。日本でも同様に、番組に出演していた女子プロレスラーがSNSの誹謗中傷を苦に自死した事件(2020年5月)があったように、他人事ではない。
改正法案を急ぐ理由には、韓国のネット事情もあるのではないか。「ネット大国」といわれる韓国では中小メディアが乱立し、臆測に基づくニュースが目に付く。フェイクニュースではなかったが、先の東京オリンピックでは2つの金メダルを獲得した韓国のアーチェリー選手が、短くした髪型が理由で、国内のネット上で中傷が相次いでいると報道されていた(7月30日付・日テレNEWS24Web版)。韓国ではSNSによる誹謗中傷で芸能人の自死が相次ぐなど社会問題化している。当事者に対して強烈な批判が沸き起こる社会的な風土があるのかもしれない。日本でも同様に、番組に出演していた女子プロレスラーがSNSの誹謗中傷を苦に自死した事件(2020年5月)があったように、他人事ではない。
こうした韓国政府の言論仲裁法の改正の動きに対して、国際ジャーナリスト連盟(IFJ、本部ブリュッセル)は公式ホームページ(8月21日付)で「South Korea: Concerns over media law amendment」との見出しで韓国政府への懸念を表明している=写真=。また、朝鮮日報Web版日本語(8月21日付)によると、韓国に拠点を置く外国メディアの組織「ソウル外信記者クラブ(SFCC)」は20日、「『フェイクニュースの被害から救済する制度が必要』との大義名分には共感するが、民主社会における基本権を制約する恐れがある」と声明を出した。
以下は持論。記事に目を通して、改正法案に矛盾点があるように思える。記事がフェイクニュースであるかどうかを判断するのは裁判所だ。先に述べたネット上の中小メディアが流した記事ならば、記事の入手方法や取材過程などについて裁判官がメディア側に尋問すれば記事の信ぴょう性を判断できるかもしれない。
問題はマスメディアの記者、あるいはフリーランスのジャーナリストの場合だ。率直に自らの取材上のミスだったと認める良心的な記者ならば何ら問題はない。しかし、ミスを認めたくない記者の場合、そう簡単ではない。「情報源の秘匿」をタテに口をつぐむだろう。秘匿している限り、取材過程が明らかにされることはない。それを強制的に吐かせるとなれば、裁判所側が報道の自由の侵害とそしりを受けることになる。おそらく、裁判所側は状況証拠を積み上げて最終的に判断するしかない。これはそう簡単ではない。
懲罰的損害賠償をもくろんであえて訴える人も出てくるだろう。「取材で答えたことと記事の内容が違う。名誉が棄損された、損害を被った」と。記者は「確かにそう言った」、訴えた側は「言ってない。捏造だ」と展開し、「言った・言わない」に審理は終始する。こうなると、裁判官が悩むことになる。むしろ、裁判官たちがこの改正法案を忌避しているのではないだろうか。
⇒22日(日)夜・金沢の天気 あめ時々くもり
 DW記事によると、射殺されたのは「ストリンガー」と呼ばれる、アフガンで採用された現地記者の家族だ。記者はドイツの本社に来ていた。タリバンはその記者を探して家から家へ捜索を行っていた。家族を探し出して、射殺した。以下憶測だが、記者がドイツの本社にいることを家族から聞いて、見せしめに家族を射殺したのだろう。もともと記者本人を殺害するために探していた。
DW記事によると、射殺されたのは「ストリンガー」と呼ばれる、アフガンで採用された現地記者の家族だ。記者はドイツの本社に来ていた。タリバンはその記者を探して家から家へ捜索を行っていた。家族を探し出して、射殺した。以下憶測だが、記者がドイツの本社にいることを家族から聞いて、見せしめに家族を射殺したのだろう。もともと記者本人を殺害するために探していた。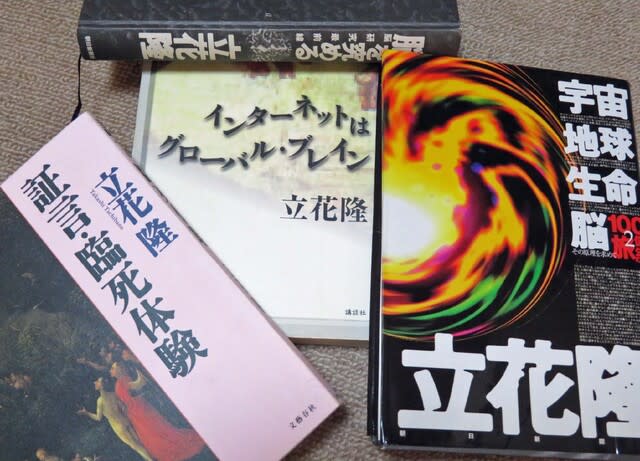 書棚を眺めて立花氏の本を手に取る=写真=。権力者の不正を追及するだけではなく、「科学する心」を持ったジャーナリストだった。宇宙や医療、脳、インターネットといった分野でも数々の著書を残している。科学・技術の最前線に立った人間がその体験を精神世界でどう受容し、その後の人生にどう影響したのか人物像も追っている。
書棚を眺めて立花氏の本を手に取る=写真=。権力者の不正を追及するだけではなく、「科学する心」を持ったジャーナリストだった。宇宙や医療、脳、インターネットといった分野でも数々の著書を残している。科学・技術の最前線に立った人間がその体験を精神世界でどう受容し、その後の人生にどう影響したのか人物像も追っている。


