★北朝鮮の発射体は「はりぼて衛星」だったのか
5月31日朝、沖縄県にJアラート=全国瞬時警報システムが鳴り響いた。「北朝鮮からミサイルが発射されたものとみられます。建物の中や地下に避難して下さい」と。間もなくして、「先ほどのミサイルは我が国には飛来しないものとみられます。避難の呼びかけを解除します」に切り替わった。Jアラートを報じるNHKニュースをチェックしていたが、スピード感のある速報だった。緊張が走ったのも、これに先立って北朝鮮が4月29日に「31日から来月11日までの間に『人工衛星』を打ち上げる」と日本に通告していたからだ。
その後に韓国メディアのWeb版に切り替えた。すると、通信社の「聯合ニュース」は、韓国軍の消息筋の話として、北の宇宙発射体が予告された落下地点に行かず、レーダーから消失したと伝えていた。
さらに北朝鮮の国営メディア「朝鮮中央通信」Web版をチェックすると、「午前6時27分に西海衛星発射場から軍事衛星『万里鏡1号』を新型ロケット『千里馬1型』に搭載・発射した」「1段目の分離後、2段目のエンジン始動に異常があり推進力を失って朝鮮西海(黄海)に落ちた」。失敗の原因を「千里馬1型に導入された新型エンジンシステムの信頼性と安定性が低く、使用された燃料の特性が不安定であることに事故の原因 があった」とした上で、「国家宇宙開発局は衛星発射で現れた重大な欠陥を具体的に調査、解明し、可能な限り早期に2回目の発射を断行する」と報じていた。
があった」とした上で、「国家宇宙開発局は衛星発射で現れた重大な欠陥を具体的に調査、解明し、可能な限り早期に2回目の発射を断行する」と報じていた。
北朝鮮の衛星発射の失敗から36日。きょう6日付の韓国メディア「中央日報」のWeb版をチェックすると、その結末が報じられている。韓国軍合同参謀本部は黄海に落下した北朝鮮の衛星の残骸を引き上げて分析した結果をきのう5日に発表した。米韓が共同分析した結果では、搭載されていたカメラは横・縦1㍍が1個の点で表示されることを意味する「解像度1㍍級」よりはるかに解像度が落ちるもので、偵察を目的とした軍事的効用はまったくないことが分かった。(※写真、先月16日に引き揚げられた発射体の残骸の一部=撮影:韓国軍合同参謀本部)
その上で、ミサイル防衛に詳しいマサチューセッツ工科大学の専門家のコメントとして、「技術的に発展した国というこ学を見せるためのもの」と紹介し、いわゆる「はりぼて衛星」をあたかも全世界を偵察できる能力があるように見せかける意図があったのではないかと指摘した。
ただ、北朝鮮は再度の衛星打ち上げを断行すると表明している。必要な技術と部品、装備を調達するとなれば、ロシアの支援を受けるしかないのではないか。
⇒6日(木)午後・金沢の天気 はれ
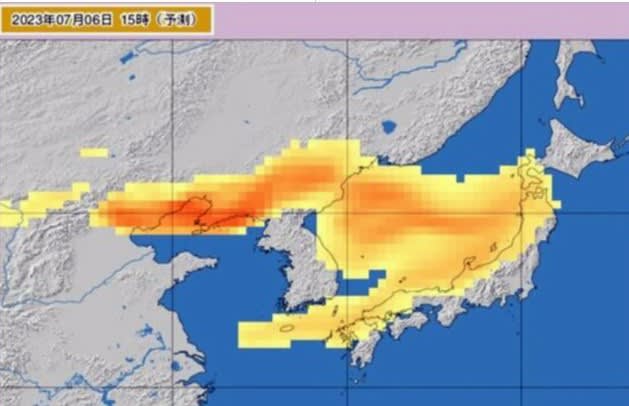 初めて6月に3日連続で40度を超え、22日には過去最高の41度を記録したと報じれらている(6月25日付・AFP通信Web版日本語)。
初めて6月に3日連続で40度を超え、22日には過去最高の41度を記録したと報じれらている(6月25日付・AFP通信Web版日本語)。 追悼の辞で、友人代表として菅前総理が興味深いエピソードを紹介していた。平成12年(2000年)、日本政府は北朝鮮にコメを送ろうとしていた。当選2回目だった菅氏は「草の根の国民に届くのならよいが、その保証がない限り、軍部を肥やすようなことはすべきでない」と自民党総務会で反対意見を述べた。これが紙面で掲載され、記事を見た安倍氏が「会いたい」と電話をかけてきた。このことが、安倍氏と菅氏が北朝鮮の拉致問題にタッグを組んで取り組むきっかけとなった。当時の森喜朗内閣や外務省は日朝正常化交渉を優先していて、拉致問題はむしろ交渉の阻害要因というスタンスだった。
追悼の辞で、友人代表として菅前総理が興味深いエピソードを紹介していた。平成12年(2000年)、日本政府は北朝鮮にコメを送ろうとしていた。当選2回目だった菅氏は「草の根の国民に届くのならよいが、その保証がない限り、軍部を肥やすようなことはすべきでない」と自民党総務会で反対意見を述べた。これが紙面で掲載され、記事を見た安倍氏が「会いたい」と電話をかけてきた。このことが、安倍氏と菅氏が北朝鮮の拉致問題にタッグを組んで取り組むきっかけとなった。当時の森喜朗内閣や外務省は日朝正常化交渉を優先していて、拉致問題はむしろ交渉の阻害要因というスタンスだった。 あれから間もなく1年になる。2022年7月8日、奈良市で街頭演説中の安倍元総理が銃で殺害された。同市に住む山上徹也容疑者が殺人と銃刀法違反の罪で逮捕された。これから裁判員裁判で審理されることになるが、殺害の動機とされるのが、母親が旧統一教会へ高額な献金をしたことから家庭が崩壊し、恨みを募らせたことが事件の発端とされる。安倍氏は祖父・岸信介の代から三代にわたって旧統一教会と深いつながりがあり、山上被告は安倍氏にも恨みを抱いていた。
あれから間もなく1年になる。2022年7月8日、奈良市で街頭演説中の安倍元総理が銃で殺害された。同市に住む山上徹也容疑者が殺人と銃刀法違反の罪で逮捕された。これから裁判員裁判で審理されることになるが、殺害の動機とされるのが、母親が旧統一教会へ高額な献金をしたことから家庭が崩壊し、恨みを募らせたことが事件の発端とされる。安倍氏は祖父・岸信介の代から三代にわたって旧統一教会と深いつながりがあり、山上被告は安倍氏にも恨みを抱いていた。  国民のマイナンバーカードへの不安や不満が、返納というカタチで表れている。 共同通信が都道府県所在地と政令指定都市の計52市区を対象に行った調査で、マイナンバーカードの自主返納について集計していたのは29市で、その合計は4月は21件だったものが、5月以降で少なくとも318件に上っていることが分かった(2日付・共同通信Web版)。最多は堺市の44件だった。金沢市では5月以降で21件の返納があった。返納届の記載には「信用できない」「問題が多い」があったという(同)。
国民のマイナンバーカードへの不安や不満が、返納というカタチで表れている。 共同通信が都道府県所在地と政令指定都市の計52市区を対象に行った調査で、マイナンバーカードの自主返納について集計していたのは29市で、その合計は4月は21件だったものが、5月以降で少なくとも318件に上っていることが分かった(2日付・共同通信Web版)。最多は堺市の44件だった。金沢市では5月以降で21件の返納があった。返納届の記載には「信用できない」「問題が多い」があったという(同)。 このニュースが気になったもの、中島地区で激しい雨を自身も経験したことがあるからだ。ちょうど6年前、2017年7月1日だ。能登へ乗用車で出かけ、自動車専用道「のと里山海道」の中島地区で、大雨に巻き込まれた。雨がたたきつけるようにフロントガラスに当たり、ワイパーの回転を一番速くしても前方が見えず、しばらく車を停車し小降りになるのを待った。再び出発すると、たたきつけるような雨に再び見舞われた。3度運転を見合わせた。波状的な激しい雨は初めてだった。このとき能登では1時間で53㍉の非常に激しい雨が観測され、七尾市の崎山川や熊木川などが一部氾濫した。
このニュースが気になったもの、中島地区で激しい雨を自身も経験したことがあるからだ。ちょうど6年前、2017年7月1日だ。能登へ乗用車で出かけ、自動車専用道「のと里山海道」の中島地区で、大雨に巻き込まれた。雨がたたきつけるようにフロントガラスに当たり、ワイパーの回転を一番速くしても前方が見えず、しばらく車を停車し小降りになるのを待った。再び出発すると、たたきつけるような雨に再び見舞われた。3度運転を見合わせた。波状的な激しい雨は初めてだった。このとき能登では1時間で53㍉の非常に激しい雨が観測され、七尾市の崎山川や熊木川などが一部氾濫した。  て、人に危害を与えないが食べ物を取っていくという事例が目立っているという。これまでも、サンドイッチやおにぎりなどが狙われた被害があったそうだ。確かに、注意書きの下には、「食べ物をねらって、空から急降下してくることがあります」と記してある。
て、人に危害を与えないが食べ物を取っていくという事例が目立っているという。これまでも、サンドイッチやおにぎりなどが狙われた被害があったそうだ。確かに、注意書きの下には、「食べ物をねらって、空から急降下してくることがあります」と記してある。 たとえは適切でないかもしれないが、ロシアにはもう一つの粛清の方法がある。それは墓などをつくらず、地上に存在したことを消去することだ。第二次世界大戦で、ヒトラー率いるドイツ軍は1945 年5月 8 日に無条件降伏したが、ヒトラーは降伏前の4月30日に自決する。遺体はヒトラーの遺言によって焼却されたものの、焼け残った遺体は当時ベルリンを占領していたソ連軍によって東ドイツのマクデブルクに運ばれ、ソ連諜報機関の事務所前の舗装の下に埋められた。1970年になって、ネオナチの崇拝目的になることを怖れ、遺体を再び焼却して遺灰をエルベ川に流したとされる(Wikipedia「
たとえは適切でないかもしれないが、ロシアにはもう一つの粛清の方法がある。それは墓などをつくらず、地上に存在したことを消去することだ。第二次世界大戦で、ヒトラー率いるドイツ軍は1945 年5月 8 日に無条件降伏したが、ヒトラーは降伏前の4月30日に自決する。遺体はヒトラーの遺言によって焼却されたものの、焼け残った遺体は当時ベルリンを占領していたソ連軍によって東ドイツのマクデブルクに運ばれ、ソ連諜報機関の事務所前の舗装の下に埋められた。1970年になって、ネオナチの崇拝目的になることを怖れ、遺体を再び焼却して遺灰をエルベ川に流したとされる(Wikipedia「 宗教画は「イコン(Icon)」と称され、聖三位一体のイコンは15世紀初頭に描かれたもので、旧約聖書の一場面でとされる。16世紀にモスクワ教会はこれをイコンと定めて保管してきたが、ロシア革命の後は宗教活動が認められなくなったため、1929年から国立トレチャコフ美術館で所蔵されていた。それをプーチン大統領がロシア正教の総本山であるモスクワ大聖堂に強制的に移設し、6月4日から一般公開している。
宗教画は「イコン(Icon)」と称され、聖三位一体のイコンは15世紀初頭に描かれたもので、旧約聖書の一場面でとされる。16世紀にモスクワ教会はこれをイコンと定めて保管してきたが、ロシア革命の後は宗教活動が認められなくなったため、1929年から国立トレチャコフ美術館で所蔵されていた。それをプーチン大統領がロシア正教の総本山であるモスクワ大聖堂に強制的に移設し、6月4日から一般公開している。 誘ってくれたのは稲作専業農家の大田豊氏74歳。先祖代々からの里山の田んぼを受け継ぐ。標高220㍍の棚田に無農薬、そして無化学肥料のコメづくりに取り組み、2011年に「渡津蛍米」を商標登録した。いわゆる「生き物ブランド米」だ。兵庫県但馬地域の「コウノトリ米」や新潟県佐渡の「トキ米」が有名だが、大田氏も「生き物は田んぼの豊かさを示すバロメーター」が持論で、独学で田んぼと生物多様性について学んでいる。多彩なゲストを招いての勉強会もその一環。
誘ってくれたのは稲作専業農家の大田豊氏74歳。先祖代々からの里山の田んぼを受け継ぐ。標高220㍍の棚田に無農薬、そして無化学肥料のコメづくりに取り組み、2011年に「渡津蛍米」を商標登録した。いわゆる「生き物ブランド米」だ。兵庫県但馬地域の「コウノトリ米」や新潟県佐渡の「トキ米」が有名だが、大田氏も「生き物は田んぼの豊かさを示すバロメーター」が持論で、独学で田んぼと生物多様性について学んでいる。多彩なゲストを招いての勉強会もその一環。 秒間隔との内容だ。ゲンジボタルのミトコンドリア遺伝子につながる塩基配列を用い、全国108地域の個体間の遺伝的類縁関係を調べるなど調査した。その結果、進化の過程で遺伝的変異とともに、発光パターンが変化したとの解説だった。
秒間隔との内容だ。ゲンジボタルのミトコンドリア遺伝子につながる塩基配列を用い、全国108地域の個体間の遺伝的類縁関係を調べるなど調査した。その結果、進化の過程で遺伝的変異とともに、発光パターンが変化したとの解説だった。