☆ブログの技術⑱
街角を歩いていると、面白い、あるいは微笑ましい被写体があり、ついデジカメや携帯電話カメラのレンズを向けてしまう。そんな街角のスナップショットをまとめてブログにアップロードしてみる。著作権や肖像権にちょっとだけ注意を払えばそう難しい話ではない。
テーマ「写真グラフを作る」
 実際に写真グラフを作ってみる。タイトルは<街角ショット3題>としよう。まずはことしのエトにちなんで。一番上の写真は、04年夏に神戸市内のオモチャ店で撮影したもの。イヌのオモチャが入った箱に「飼主募集中、エサは単3電池2本です」のキャッチコピーが面白い。気の利いたキャッチコピーが付いているとそれ自体が完結して、写真そのものが一枚の広告ポスターのようだ。
実際に写真グラフを作ってみる。タイトルは<街角ショット3題>としよう。まずはことしのエトにちなんで。一番上の写真は、04年夏に神戸市内のオモチャ店で撮影したもの。イヌのオモチャが入った箱に「飼主募集中、エサは単3電池2本です」のキャッチコピーが面白い。気の利いたキャッチコピーが付いているとそれ自体が完結して、写真そのものが一枚の広告ポスターのようだ。
 真ん中は、先日12月31日に東京のJR浜松町駅で撮った企業広告のスナップ写真。ニューヨークヤンキースの松井秀喜選手とニックネームでもあるゴジラと並べてデザインされた東芝のデジタル対応テレビのPRポスターだ。このポスターはどこにでもあるわけではない。JR浜松町駅近くに東芝の本社があり、ここでしか見れない、いわば「ご当地ポスター」のようなもの。
真ん中は、先日12月31日に東京のJR浜松町駅で撮った企業広告のスナップ写真。ニューヨークヤンキースの松井秀喜選手とニックネームでもあるゴジラと並べてデザインされた東芝のデジタル対応テレビのPRポスターだ。このポスターはどこにでもあるわけではない。JR浜松町駅近くに東芝の本社があり、ここでしか見れない、いわば「ご当地ポスター」のようなもの。
 下の写真は、きのう2日にドライブ先の富山県福光町で見つけた雪に凍える獅子(しし)の石像だ。バックは中国の唐宋時代の建築様式で建てられたという寺院風の平屋建て。寺院風なので狛犬(こまいぬ)と言ってもよいかもしれない。何しろ大屋根から落ちる雪でご覧の通り。さすがの獅子もちょっと情けない顔に見える。
下の写真は、きのう2日にドライブ先の富山県福光町で見つけた雪に凍える獅子(しし)の石像だ。バックは中国の唐宋時代の建築様式で建てられたという寺院風の平屋建て。寺院風なので狛犬(こまいぬ)と言ってもよいかもしれない。何しろ大屋根から落ちる雪でご覧の通り。さすがの獅子もちょっと情けない顔に見える。
◇
写真の配列は左右で分け、大小のメリハリをつけると見やすい。説明文はできるだけ省き、写真に語らせる。ただ、写真では見えない周囲の状況やエピソードは簡潔に入れたい。
著作・肖像権の問題では、基本的に公道に面して、あるいは人々の公衆の面前に置かれた広告物などに関しては、著作権者が「撮影を控えてください」と要請がない限り、それを撮影し、インターネットなどで掲載しても多くの場合問題とはならない。ただ、上記のポスターで松井選手の顔だけをアップにして撮影し、それをネットで掲載した場合などは肖像権が絡む。著作権者はポスターのデザイン全体を見てほしいから貼り出したのである。それを一部だけクローズアップしてネットで掲載するのは「著作意図に反する」ことになる。
ポスターなどの著作物は、著作権者の意図をちょっとだけ尊重するセンスを身につければ、臨機応変に撮影ができ、ブログでも掲載ができる。万が一、クレームが来た場合、「不快な思いさせて申し訳ありません。著作権を侵害する意図はまったくありませんので、すぐ外します」と応じればよいのである。ブロガーはそれで利益を得ているのはないのだから。
⇒3日(火)朝・金沢の天気 くもり
 いた。「日本の現代音楽作品を幅広く紹介した功績」というのがその受賞理由だ。
いた。「日本の現代音楽作品を幅広く紹介した功績」というのがその受賞理由だ。 ベートーベンの交響曲を1番から9番まで聴くだけでも随分勇気がいる。そのオーケストラを指揮するとなるとどれだけの体力と精神を消耗することか。休憩を入れるとはいえ9時間40分の演奏である。指揮者の岩城宏之さんがまたその快挙をやってのけた。東京芸術劇場で行われた2005年12月31日から2006年1月1日の越年コンサートである。
ベートーベンの交響曲を1番から9番まで聴くだけでも随分勇気がいる。そのオーケストラを指揮するとなるとどれだけの体力と精神を消耗することか。休憩を入れるとはいえ9時間40分の演奏である。指揮者の岩城宏之さんがまたその快挙をやってのけた。東京芸術劇場で行われた2005年12月31日から2006年1月1日の越年コンサートである。

 してこまめに顔を出している。
してこまめに顔を出している。 雪のまぶしさを久しぶりに感じた朝だった。雪原の純白さと、空の青さがなんとも言えぬ透明感があった。透明に近いブルーなのだ。この光景が目にしみて涙が出た。
雪のまぶしさを久しぶりに感じた朝だった。雪原の純白さと、空の青さがなんとも言えぬ透明感があった。透明に近いブルーなのだ。この光景が目にしみて涙が出た。 昨夜、深々と雪が降る中、この「角間の里」であるセミナーが開かれた。テーマは「新技術コグニティブ無線とアメリカの取り組み」。端末が自分で空いている周波数帯を探し出して通信を始めることから、ユビキタスネットやブロードバンドで広く応用が期待される「コグニティブ無線」について、電波の規制改革が進むアメリカの実情を知るのがその内容だ。講師は、米FCC(連邦通信委員会)法律顧問のジェームス・ミラー弁護士。冷え込んだ外とは対照的に、古民家の中は随分と参加者の熱気にあふれていた。
昨夜、深々と雪が降る中、この「角間の里」であるセミナーが開かれた。テーマは「新技術コグニティブ無線とアメリカの取り組み」。端末が自分で空いている周波数帯を探し出して通信を始めることから、ユビキタスネットやブロードバンドで広く応用が期待される「コグニティブ無線」について、電波の規制改革が進むアメリカの実情を知るのがその内容だ。講師は、米FCC(連邦通信委員会)法律顧問のジェームス・ミラー弁護士。冷え込んだ外とは対照的に、古民家の中は随分と参加者の熱気にあふれていた。
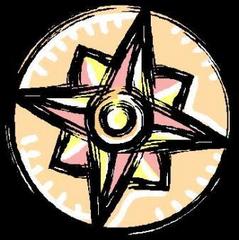 ブログのタイトルは通常、向かって右、あるいは左の縦の列の「RECENT ENTRY」でラインナップされる。横文字で表記で、「goo」の場合だと文字数は全角14文字分である。つまり、15文字だと下に1文字落ちて2行にわたってしまう。私にはこれが何となくだらしなく、野放図なように感じられ、タイトルは一行で納まるように工夫している。従って、私の場合は★か☆を入れて14字なので、全角で13字である。もちろんタイトルは2行分と決めて、28字での表記でもよい。要は、日々のブログの核心を表現する部分なので、自らの考えを整然と表記するよう心がけたい。上記のように言うとなんだか「ブログ道」のように精神が入ってくるのだが…。
ブログのタイトルは通常、向かって右、あるいは左の縦の列の「RECENT ENTRY」でラインナップされる。横文字で表記で、「goo」の場合だと文字数は全角14文字分である。つまり、15文字だと下に1文字落ちて2行にわたってしまう。私にはこれが何となくだらしなく、野放図なように感じられ、タイトルは一行で納まるように工夫している。従って、私の場合は★か☆を入れて14字なので、全角で13字である。もちろんタイトルは2行分と決めて、28字での表記でもよい。要は、日々のブログの核心を表現する部分なので、自らの考えを整然と表記するよう心がけたい。上記のように言うとなんだか「ブログ道」のように精神が入ってくるのだが…。

 なった。
なった。
