☆「総合学習」の新人類
私のオフィスがある金沢大学創立五十周年記念館「角間の里」は昨年4月に完成した。この建物は白山ろくの旧・白峰村の文化財だったものを大学を譲り受けて、この地に再生した。築300年の養蚕農家の建物構造だ。建て坪が110坪 (360平方㍍)もある。黒光りする柱や梁(はり)は歴史や家の風格というものを感じさせてくれる。金沢大学の「里山自 然学校」の拠点でもある。
然学校」の拠点でもある。
古民家を再生したということで、ここを訪ねてくる人の中には建築家や、古い民家のたたずまいを懐かしがってくる市民が多い。最近は学生もやってくる。その学生のタイプはこれまでの学生と違ってちょっと味がある。「こんな古い家、とても落ちつくんですよ」と言いながら2時間余りもスタッフとおしゃべりをしていた新入の女子学生。お昼になると弁当を持ってやってくる男子学生。「ボクとても盆栽に興味があって山を歩くのが好きなんです」という同じく新入の男子学生。今月初め、いっしょにタケノコ掘りに行かないかと誘うと、「タケノコ掘り、ワーッ楽しい」とはしゃぐ2人組の女子学生がいた。いずれも新入生である。
「学生が来てくれない」と嘆いた去年とは違って、ことしは手ごたえがある。この現象をどう分析するか。同僚の研究員は「総合学習の子らですね」と。総合学習とは、2002年度4月から導入された文部科学省の新学習指導要領の基本に据えられた「ゆとり教育」と「総合的な学習の時間(総合学習)」のこと。子どもたちの「生きる力」を育みたいと、週休2日制の移行にともない、教科書の学習時間を削減し、野外活動や地域住民と連携した学習時間が設定された。その新指導要領の恩恵にあずかった中学生や高校生が大学に入ってくる年代になったのである。
当時、批判のあった画一教育の反動で設けられた総合時間だが、その後、「ゆとり」という言葉が独り歩きし「ゆるみ」と言われ、総合学習も「遊び」と酷評されたこともあった。しかし、私が接した上記の「総合学習の子ら」は実に自然になじんでいるし、「ぜひ炭焼きにも挑戦したい」と汗をかくことをいとわない若者たちである。そして、動植物の名前をよく知っていて、何より人懐っこい。それは新指導要領が目指していた「生きる力」のある若者であるように思える。
もちろん、新入生のすべてがそうであるとは言わない。今後、金沢大学の広大な自然や里山に親しみを感じてくれる若者たちが増えることを期待して、数少ない事例だが紹介した。
⇒24日(水)朝・金沢の天気 くもり
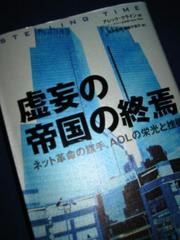 アメリカのネット革命の旗手とまでいわれたAOLがタイムワーナー社との合併に踏み込んだものの、その後に放逐されるまでの栄光と挫折を描いたルポルタージュ、「虚妄の帝国の終焉」(アレック・クライン著、ディスカヴァー・トゥエンティワン社刊)を読んでいる。実はまだ第3章「世紀の取引」を読んでいる途中で、茂みの中である。それでも、アメリカのメディアとインターネット産業をめぐる大事件として記憶に新しい。370㌻の出だしの3分の1ほどしか読み進んだあたりから、人間の相克と葛藤が次ぎ次ぎと展開されていく。このブログを書いている時点で私も読んでいる途中だが、それでも書評をしたためたくなるほどのボリユーム感がすでにある。
アメリカのネット革命の旗手とまでいわれたAOLがタイムワーナー社との合併に踏み込んだものの、その後に放逐されるまでの栄光と挫折を描いたルポルタージュ、「虚妄の帝国の終焉」(アレック・クライン著、ディスカヴァー・トゥエンティワン社刊)を読んでいる。実はまだ第3章「世紀の取引」を読んでいる途中で、茂みの中である。それでも、アメリカのメディアとインターネット産業をめぐる大事件として記憶に新しい。370㌻の出だしの3分の1ほどしか読み進んだあたりから、人間の相克と葛藤が次ぎ次ぎと展開されていく。このブログを書いている時点で私も読んでいる途中だが、それでも書評をしたためたくなるほどのボリユーム感がすでにある。 ると伝えている。
ると伝えている。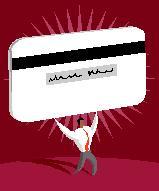 17日付の記事。見出しは「アジア太平洋地域諸国のうち、ゴールドカードを最もたくさん使っているのは韓国人」。ビザカード・コリアによると、今年3月現在、韓国人が保有しているビザ・ゴールドカードは1400万枚で、アジア太平洋地域全体のビザ・ゴールドカードの34%を占め、日本(480万枚)より3倍も多い。ゴールドカードよりワンランク上のプラチナカードの場合、韓国は260万枚(日本5万枚)になる。この数字を見る限り、4600万人の国民の3人に1人がゴールドカードを持つ、アジアでもっとも裕福でエクセレンな国が韓国となる。
17日付の記事。見出しは「アジア太平洋地域諸国のうち、ゴールドカードを最もたくさん使っているのは韓国人」。ビザカード・コリアによると、今年3月現在、韓国人が保有しているビザ・ゴールドカードは1400万枚で、アジア太平洋地域全体のビザ・ゴールドカードの34%を占め、日本(480万枚)より3倍も多い。ゴールドカードよりワンランク上のプラチナカードの場合、韓国は260万枚(日本5万枚)になる。この数字を見る限り、4600万人の国民の3人に1人がゴールドカードを持つ、アジアでもっとも裕福でエクセレンな国が韓国となる。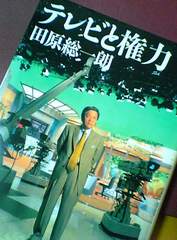 田原氏の近著、「テレビと権力」(講談社)を読んだ。内容は、権力の内幕をさらけ出すというより、田原氏がテレビや活字メディアに出演させた人物列伝とその取材の内幕といった印象だ。岩波映画の時代から始まって、テレビ東京のこと、現在の「サンデープロジェクト」まで、それこそ桃井かおりや小沢一郎、小泉純一郎まで、学生運動家や芸能人、財界人、政治家の名前が次々と出てくる。
田原氏の近著、「テレビと権力」(講談社)を読んだ。内容は、権力の内幕をさらけ出すというより、田原氏がテレビや活字メディアに出演させた人物列伝とその取材の内幕といった印象だ。岩波映画の時代から始まって、テレビ東京のこと、現在の「サンデープロジェクト」まで、それこそ桃井かおりや小沢一郎、小泉純一郎まで、学生運動家や芸能人、財界人、政治家の名前が次々と出てくる。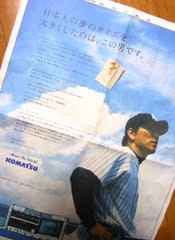 コピーの続き。「松井は野球の天才ではない。努力の天才なのだ」と言い、「コマツは、どうだろう。自分たちの技術に誇りを持ち、よりよい商品づくり心がけているだろうか。」と問う。そして、最後に小さく、「松井選手の今回のケガに際し、一日も早い復帰をお祈りしております」と締めている。松井の出身地である石川県能美市に近い小松市に主力工場を持つコマツは、ヤンキース入りした直後から松井選手のスポンサーになった。嫌みのない、実にタイムリーな広告企画ではある。
コピーの続き。「松井は野球の天才ではない。努力の天才なのだ」と言い、「コマツは、どうだろう。自分たちの技術に誇りを持ち、よりよい商品づくり心がけているだろうか。」と問う。そして、最後に小さく、「松井選手の今回のケガに際し、一日も早い復帰をお祈りしております」と締めている。松井の出身地である石川県能美市に近い小松市に主力工場を持つコマツは、ヤンキース入りした直後から松井選手のスポンサーになった。嫌みのない、実にタイムリーな広告企画ではある。 確かに、同研究所は板橋区加賀1丁目9番10号が所在地だ。加賀といえば加賀藩、つまり金沢なのである。加賀という地名は偶然ではない。かつて、加賀藩の江戸の下屋敷があったエリアなのである。それが今でも地名として残っている。
確かに、同研究所は板橋区加賀1丁目9番10号が所在地だ。加賀といえば加賀藩、つまり金沢なのである。加賀という地名は偶然ではない。かつて、加賀藩の江戸の下屋敷があったエリアなのである。それが今でも地名として残っている。 を想定したのだ。
を想定したのだ。 あの松井秀喜選手はどうなっているのか、楽しみにしていた。きょう(9日)、久しぶりに東京のJR浜松町駅にきた。なんと、松井選手はサッカーボールを持っていた。駅構内の広告のことである。なぜ松井がサッカーボールをと思うだろう。答えは簡単。松井のスポンサーになっている東芝はFIFAワールドカップ・ドイツ大会のスポンサーでもある。その大会に東芝は2000台以上のノートパソコンを提供するそうだ。理由はどうあれ、サッカーボールを持った松井選手というのは珍しいので、その広告をカメラで撮影した。
あの松井秀喜選手はどうなっているのか、楽しみにしていた。きょう(9日)、久しぶりに東京のJR浜松町駅にきた。なんと、松井選手はサッカーボールを持っていた。駅構内の広告のことである。なぜ松井がサッカーボールをと思うだろう。答えは簡単。松井のスポンサーになっている東芝はFIFAワールドカップ・ドイツ大会のスポンサーでもある。その大会に東芝は2000台以上のノートパソコンを提供するそうだ。理由はどうあれ、サッカーボールを持った松井選手というのは珍しいので、その広告をカメラで撮影した。
 JR浜松町駅近くに東芝の本社があり、ここでしか見れない、いわば「ご当地ポスター」のようなもの。去年の大晦日に見た松井選手の広告は本物のゴジラと顔を並べていた。
JR浜松町駅近くに東芝の本社があり、ここでしか見れない、いわば「ご当地ポスター」のようなもの。去年の大晦日に見た松井選手の広告は本物のゴジラと顔を並べていた。 マ「季節の変わり目を撮る」
マ「季節の変わり目を撮る」 