☆メディアのツボ-06-
先日、年齢がひと回りも上のテレビ業界の先輩と話す機会があった。年齢にして64歳、テレビの成長期、一番よい時代を経験したといわれる世代である。その先輩が言う。「われわれの現役のときはテレビ局は時代の寵児(ちょうじ)といわれた。しかし、いまは『テレビ局という会社もある』といった普通の存在になったね」
米紙ダウンサイジングの衝撃
確かに、アナ ウンサー職を除けば、テレビ局に応募者が殺到するという現象は見られなくなったという話を最近、ある局の人事担当者から聞いた。これは何もテレビ局に限った話ではない。春の選考で予定していた人数を採りきれず、秋にも引き続き採用活動を行う新聞社などマスコミ企業が増えている。マスメディアのダウンサイジング現象である。
ウンサー職を除けば、テレビ局に応募者が殺到するという現象は見られなくなったという話を最近、ある局の人事担当者から聞いた。これは何もテレビ局に限った話ではない。春の選考で予定していた人数を採りきれず、秋にも引き続き採用活動を行う新聞社などマスコミ企業が増えている。マスメディアのダウンサイジング現象である。
読んで字の如く「縮小する」動きも現れてきた。アメリカの大手紙ニューヨーク・タイムズが紙面の幅を2008年4月から3.8㌢縮小すると発表したニュースだ(7月18日)。紙面の縮小により、記事スペースは11%減るが、増ページも行って減少を5%に抑えるという。紙面サイズの縮小とともに、印刷工場も統合する。アメリカを代表する大手紙の紙面のリストラだけに、そのインパクトは内外の新聞業界に他人事ではない衝撃を与えたはずである。
この紙面縮小の背景には、新聞部数の減少がある。アメリカでは新聞発行部数が去年、全米で5300万部だった。これはピークだった1984年に比べ15%も落ちている。その原因はといえば、インターネットの普及による購読者数や広告収入の減少に尽きる。もう少し詳しく説明すると、新聞のビジネスモデルがインターネット企業によって侵食されているからである。情報を掲載して読む人の数の多さに比例して広告単価を上げるというネット広告の手法は、新聞の発行部数で広告単価を決めてきた従来の手法と重なる。こうして経営基盤が揺らぎ、傘下に32紙を持つ全米第2位の新聞グループ「ナイトリッダー」が身売りするという事態も起きた。
日本の新聞業界は宅配制度によって部数(5252万部・05年10月の日本新聞協会調べ)を維持しているものの、それでもピークだった1999年(5375万部)に比べ減少傾向にある。また、日本の新聞社は株式を公開していないので、アメリカのように株主がその経営実態に不安を抱いて経営改善を要求するといった実態が表に現れない。表面化した時は、倒産か身売りというせっぱ詰まった状態になってからだろう。
テレビのビジネスモデルもネット企業によって侵食されつつある。USENのブロードバンド放送「Gyao」(ギャオ)はユーザーが好きな時にネットを通じて番組が無料で視聴できるビデオオンデマンド方式を採用している。収益はサイトの広告収入がメインである。そのギャオの視聴登録者がすでに1000万人に達した。映画やアニメなど常時1500番組をそろえ、サービスを開始したのは去年4月である。すさまじい勢いで登録者を増やしたことになる。まだ黒字化はしていないものの、登録する際に入力する属性情報で、性別や年齢に応じた効果的な広告配信を試みている。また、7月からは地域・県別の広告配信も行っている。こうした小回りの効いた広告対応は既存の民放テレビ局ではできない。
ネット企業が情報メディアを目指して台頭すれば、それだけ既存のマスメディアの存在感が薄れる。そんな構造なのである。それはかつて圧倒的な存在感を誇っていた新聞メディアが高度成長期に乗って台頭してきた放送メディアによって影が薄くなったプロセスと重なる。
⇒4日(金)朝・金沢の天気 はれ
 実はこれは放送でいうクローズアップの手法なのである。普段見ない小さなもの、肉眼では見えないもの大きく拡大することで新鮮さを演出したり、人々を驚かせたり、ひきつけたりする。科学番組などでよく使う手法だ。NHKには「クローズアップ現代」という番組もある。
実はこれは放送でいうクローズアップの手法なのである。普段見ない小さなもの、肉眼では見えないもの大きく拡大することで新鮮さを演出したり、人々を驚かせたり、ひきつけたりする。科学番組などでよく使う手法だ。NHKには「クローズアップ現代」という番組もある。 いきさつはこうだった。05年6月10日、北朝鮮への経済制裁を検討する参院拉致問題特別委員会で、参考人として呼んだ拉致被害者の家族代表の横田滋さん夫妻に、岡田氏は「聞くに忍びないことをお聞きしますけれども」と前置きし、北朝鮮に経済制裁をすれば、めぐみさんが本当に殺されるかもしれない、その覚悟のほどはどうですか、とたずねた。それに対し、横田氏は「それを恐れていれば結局このままの状況が続く」と経済制裁を強く求めた。岡田氏とすれば、「家族はリスクを覚悟して経済制裁を求めている。だから、政府もやるべきだ」というセオリーで、慎重な言い回しだった。これには、横田夫妻も、参考人として発言の機会が与えられたことに対して、岡田氏に感謝をしていた(05年6月16日付「救う会全国協議会ニュース」)。
いきさつはこうだった。05年6月10日、北朝鮮への経済制裁を検討する参院拉致問題特別委員会で、参考人として呼んだ拉致被害者の家族代表の横田滋さん夫妻に、岡田氏は「聞くに忍びないことをお聞きしますけれども」と前置きし、北朝鮮に経済制裁をすれば、めぐみさんが本当に殺されるかもしれない、その覚悟のほどはどうですか、とたずねた。それに対し、横田氏は「それを恐れていれば結局このままの状況が続く」と経済制裁を強く求めた。岡田氏とすれば、「家族はリスクを覚悟して経済制裁を求めている。だから、政府もやるべきだ」というセオリーで、慎重な言い回しだった。これには、横田夫妻も、参考人として発言の機会が与えられたことに対して、岡田氏に感謝をしていた(05年6月16日付「救う会全国協議会ニュース」)。 に根を下ろしている。ブログ率はおおよそ60%、5日に3日は書いている計算になる。
に根を下ろしている。ブログ率はおおよそ60%、5日に3日は書いている計算になる。 実際に「イブニング5」の問題シーン(当日午後6時13分ごろ)を見ると、池田裕行キャスターが「旧日本軍の731部隊の石井隊長の日記の中に、終戦直後、上陸するアメリカ軍を細菌兵器で攻撃しようと計画していた記述があったことが分かった」と前ふりをしてVTRがスタートする。カメラマンがドーリー撮影をしながら、小道具置き場から数㍍離れて電話取材をする記者がいるブースまでの数秒間を移動する途中で、床にある安倍晋三官房長官の写真パネルが映っている。1秒間も映ってはいないが、安倍氏とはっきり認識できる。
実際に「イブニング5」の問題シーン(当日午後6時13分ごろ)を見ると、池田裕行キャスターが「旧日本軍の731部隊の石井隊長の日記の中に、終戦直後、上陸するアメリカ軍を細菌兵器で攻撃しようと計画していた記述があったことが分かった」と前ふりをしてVTRがスタートする。カメラマンがドーリー撮影をしながら、小道具置き場から数㍍離れて電話取材をする記者がいるブースまでの数秒間を移動する途中で、床にある安倍晋三官房長官の写真パネルが映っている。1秒間も映ってはいないが、安倍氏とはっきり認識できる。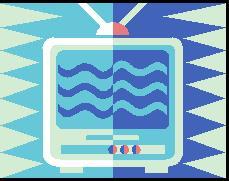 日本の世帯数は4600万以上といわれる。世帯数の4分の3近くを占める「2人以上世帯」のテレビ所有台数は1台と2台がほぼ3割ずつで、3台以上がほぼ4割を占める。以上を計算すると、家庭分だけで少なくとも8000万台から1億台以上のテレビが存在することになる。家庭以外の事業所、公共施設などの分も数えれば1億数千万台になるだろう。前回記したようにことし6月末時点での地デジ対応受信機の普及台数は1190万台だ。あと1億台ぐらいのテレビを5年間で普及させなければならない。経済的に余裕ある家庭は買い替えに積極的かもしれない。
日本の世帯数は4600万以上といわれる。世帯数の4分の3近くを占める「2人以上世帯」のテレビ所有台数は1台と2台がほぼ3割ずつで、3台以上がほぼ4割を占める。以上を計算すると、家庭分だけで少なくとも8000万台から1億台以上のテレビが存在することになる。家庭以外の事業所、公共施設などの分も数えれば1億数千万台になるだろう。前回記したようにことし6月末時点での地デジ対応受信機の普及台数は1190万台だ。あと1億台ぐらいのテレビを5年間で普及させなければならない。経済的に余裕ある家庭は買い替えに積極的かもしれない。 きょう7月24日、東京・霞ヶ関の総務省では総務大臣の竹中平蔵氏をテレビキー局(NHKを含む)の6人の女子アナたちが囲んで「地上デジタル移行まであと5年! カウントダウンセレモニー」を行われた。2011年7月24日に地上アナログ放送が終了するちょうど5年前ということで、銀座数寄屋交差点付近の「モザイク銀座阪急ビル」の広告スペースに「カウントダウンボード」が設置され、そのボードのスタートのボタンを押すというのがセレモニーの内容だった。竹中大臣らのスイッチオンで、カウントダウンボードには「あと1826日」と現れた。この様子は今夜、各テレビ局がニュースで報じていた。
きょう7月24日、東京・霞ヶ関の総務省では総務大臣の竹中平蔵氏をテレビキー局(NHKを含む)の6人の女子アナたちが囲んで「地上デジタル移行まであと5年! カウントダウンセレモニー」を行われた。2011年7月24日に地上アナログ放送が終了するちょうど5年前ということで、銀座数寄屋交差点付近の「モザイク銀座阪急ビル」の広告スペースに「カウントダウンボード」が設置され、そのボードのスタートのボタンを押すというのがセレモニーの内容だった。竹中大臣らのスイッチオンで、カウントダウンボードには「あと1826日」と現れた。この様子は今夜、各テレビ局がニュースで報じていた。  はとっさにそのタイトルが浮かんだ。「人質の論理」である。
はとっさにそのタイトルが浮かんだ。「人質の論理」である。 に10件の事故が起こり5人の死亡者が出ていたと、同社は18日になって発表した。判明した事故は合計27件、死者数は20人に上る。
に10件の事故が起こり5人の死亡者が出ていたと、同社は18日になって発表した。判明した事故は合計27件、死者数は20人に上る。 後4時から本番とあって、リハーサルにもかかわらず、上条恒彦のボリューム感のある声が園内に響き渡っていた。人のにぎわいと音で騒然としていた、と表現した方が分かりやすいかもしれない。
後4時から本番とあって、リハーサルにもかかわらず、上条恒彦のボリューム感のある声が園内に響き渡っていた。人のにぎわいと音で騒然としていた、と表現した方が分かりやすいかもしれない。 (おもむき)があった。
(おもむき)があった。