ことしのテレビの年間視聴率(1月1日-12月24日)のランキングが30日付の北陸中日新聞で掲載されていた。サッカー・ワールドカップやトリノオリンピックなど大型のスポーツイベントがあり、総合ベスト10のうち、スポーツが9つも占めるという結果になった。そこから何が見えるのか。視聴率の調査会社「ビデオリサーチ社」が公開している視聴率データ(関東地区)をもとに振り返る。
 ことしの総合トップは52.7%で「サッカー・2006FIFAワールドカップ 日本VSクロアチア」(6月18日・テレビ朝日)だった。試合はドローだったが、175分の緊張感はこのゼロの試合展開で保たれ、高視聴率に結びついた。以下8位まで「ワールド・ベースボール・クラシック」「ボクシング・亀田兄弟ダブルメイン」「トリノオリンピック」と続く。9位にようやくドラマ「HERO」31.8%(7月3日・フジテレビ)がランキングされてくる。そして、10位で「ボクシング・世界ライトフライ級 亀田興毅VSファン・ランダエタ」となる。つまり、年間の高視聴率10番組のうち、9つもスポーツものがランキングされた。
ことしの総合トップは52.7%で「サッカー・2006FIFAワールドカップ 日本VSクロアチア」(6月18日・テレビ朝日)だった。試合はドローだったが、175分の緊張感はこのゼロの試合展開で保たれ、高視聴率に結びついた。以下8位まで「ワールド・ベースボール・クラシック」「ボクシング・亀田兄弟ダブルメイン」「トリノオリンピック」と続く。9位にようやくドラマ「HERO」31.8%(7月3日・フジテレビ)がランキングされてくる。そして、10位で「ボクシング・世界ライトフライ級 亀田興毅VSファン・ランダエタ」となる。つまり、年間の高視聴率10番組のうち、9つもスポーツものがランキングされた。
数字だけを眺めれば、日本のテレビ局はスポーツコンテンツに頼らざるを得ないのか、という気分になってくる。が、つぶさに数字を追っていくとスポーツ番組の中で異変が生じているのが分かる。
3月21日の「ワールド・ベースボール・クラシック」43.4%は、キューバとの決勝に勝ち日本が世界一となったため。しかし、これを除けば、日本のプロ野球コンテンツは上位にランキングされていないのである。序盤に巨人が首位を快走しながら数字が伸び悩み、巨人の負けがこみ出すとさらに低下した。そして、7月の巨人戦ナイターの月間平均視聴率が7.2%に落ち込むと、フジテレビが8月以降の地上波での中継をやめるという事態になった。
さらに、読売グループの日本テレビは来季の巨人戦の主催試合(72試合)について、地上波は40試合しか放送しないと発表した(12月14日)。系列のCS放送では全試合を放送する。つまり、もう地上波の放送コンテンツとして営業的に限界線を超えているとの判断だろう。
ちょうど10年前の1996年の視聴率ランキングでは、日本シリーズ第2戦・巨人VSオリックスと総選挙開票スペシャル番組を同一画面で見せた日本テレビが43.3%を稼ぎ、年間ランキングで2位。ほかにもベスト10のうち、巨人戦がらみの3つの中継番組が入った。こうした数字とことしを比較すると、日本テレビの危機感は相当のものだろう。民放キー局の9月中間決算でも、日本テレビの売上高は対前年同期比でマイナス5.5%となり他キー局に比べ際立った。
スポーツ以外の番組視聴率はどうか。世界で起きていることを事実に基づき検証するといった報道番組となると、「教育・教養」のジャンルで10位にランキングされてる「筑紫哲也・安住紳一郎NYテロ5年目の真実」17.4%(9月11日・TBS)ぐらいである。それではエンターテイメントの娯楽番組はいうと、これは1位が「SMAP×SMAP」26.6%(3月13日・フジテレビ)。視聴率とすると悪くはない。「面白くなければテレビではない」のフジテレビは健在だ。
そこで注目が集まるのは、きょう31日夜のNHK紅白歌合戦の視聴率だ。かつて大晦日の風物詩、あるいは国民的行事とまでいわれた番組も2000年以降、一度も視聴率50%を超えていない。面白いのは、フジテレビはきょうの紅白歌合戦に最近人気のフィギュアスケートをぶつけてくる。全日本選手権を制した浅田真央ら大会上位選手が顔をそろえる華やかなアイスショーの収録もの。さらにNHKはこれを意識して、紅白歌合戦の特別ゲストにトリノオリンピックのフィギュアスケート金メダリスト、荒川静香を起用している。
不祥事が続き、受信料不払い、命令放送などなど、この1年も揺れに揺れたNHKはこの番組だけは死守したい。あやかれる人気にすべてあやかりたい、そんな思いが滲む。おそらくNHKの目標は1部40%(前回35.4%)、2部45%(同42.9%)だろう。しかし、他のマスメディアの関心事は2部が40%を切るかどうか、その一点に違いない。NHKを見る目線はいまだに厳しい。
⇒31日(日)午後・金沢の天気 はれ
 の里山自然学校からは研究員と、キャンパスでの炭焼きを目指す学生サークル 「CLUB炭焼き」の代表が出演する。NHK金沢放送局の夕方のワイド番組「デジタル百万石」 で午後6時30分ごろ放送だ。
の里山自然学校からは研究員と、キャンパスでの炭焼きを目指す学生サークル 「CLUB炭焼き」の代表が出演する。NHK金沢放送局の夕方のワイド番組「デジタル百万石」 で午後6時30分ごろ放送だ。 小学校にあった石炭ストーブではなく、炭を燃料としている。仕組みは ストーブに取り付けたタンク内で温まった水が、設置された配管内を循環し、部屋を暖めるというもの。当初、2005年8月ごろに、 金沢大学のOBで、バイオマス燃料の研究に取り組む北野滋さん(55)=明和工業社長(石川県能美市)=が炭ストーブの開発を大学へ提案。築300年の「角間の里」の木造の雰囲気と、そこを拠点に活動する「角間の里山自然学校」 のコンセプトとマッチしていたので、「角間の里」に設置が決まった。05年初頭の設置予定だったが、防災設備やスチームの配管、煙突の構造、 建物の外観とのすりあわせなどの問題をクリアーするのに遅れ、ようやく完成にこぎつけた。
小学校にあった石炭ストーブではなく、炭を燃料としている。仕組みは ストーブに取り付けたタンク内で温まった水が、設置された配管内を循環し、部屋を暖めるというもの。当初、2005年8月ごろに、 金沢大学のOBで、バイオマス燃料の研究に取り組む北野滋さん(55)=明和工業社長(石川県能美市)=が炭ストーブの開発を大学へ提案。築300年の「角間の里」の木造の雰囲気と、そこを拠点に活動する「角間の里山自然学校」 のコンセプトとマッチしていたので、「角間の里」に設置が決まった。05年初頭の設置予定だったが、防災設備やスチームの配管、煙突の構造、 建物の外観とのすりあわせなどの問題をクリアーするのに遅れ、ようやく完成にこぎつけた。 表格の番組がテレビ朝日系・火曜日夜9時の「ロンドンハーツ」かもしれない。何しろ、系列内部では「平均14%を超える高い視聴率をマークした」と評判がすこぶるいい。中でも05年10月に放送された「青木さやかパリコレへ!」は19.2%を獲得して、裏番組のガリバー「踊る!さんま御殿!!」を9.8%と1ケタに落とすというテレ朝にとっては「快挙」も成し遂げた。
表格の番組がテレビ朝日系・火曜日夜9時の「ロンドンハーツ」かもしれない。何しろ、系列内部では「平均14%を超える高い視聴率をマークした」と評判がすこぶるいい。中でも05年10月に放送された「青木さやかパリコレへ!」は19.2%を獲得して、裏番組のガリバー「踊る!さんま御殿!!」を9.8%と1ケタに落とすというテレ朝にとっては「快挙」も成し遂げた。 法案を出す出さないは内閣が今夏の参院選挙をにらんだり、各種の経済指標と照らし合わせてを決定することで論評する気はない。ただ、私自身、この残業問題というのは、この言葉を聞いただけでも正直うんざりするくらい憂鬱な気分になる。この問題で2年間苦しんだことがある。
法案を出す出さないは内閣が今夏の参院選挙をにらんだり、各種の経済指標と照らし合わせてを決定することで論評する気はない。ただ、私自身、この残業問題というのは、この言葉を聞いただけでも正直うんざりするくらい憂鬱な気分になる。この問題で2年間苦しんだことがある。 す」と好印象を述べてくれる。その記念館に先日、ストーブの煙突が立った。
す」と好印象を述べてくれる。その記念館に先日、ストーブの煙突が立った。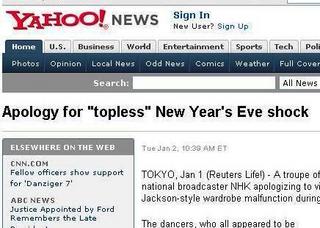 NHKホームページの紅白歌合戦のページでお詫びが出た。3日午後11時ごろにチェックした。文面は以下だった。「DJ OZMAのバックダンサーが裸と見間違いかねないボディスーツを着用して出演した件について、NHKではこのような姿になるということは放送まで知りませんでした。衣装の最終チェックであるリハーサルでは放送のような衣装ではありませんでした。今回の紅白のテーマにふさわしくないパフォーマンスだったと考えます。視聴者の皆様に深いな思いをおかけして誠に申し訳なく考えております」
NHKホームページの紅白歌合戦のページでお詫びが出た。3日午後11時ごろにチェックした。文面は以下だった。「DJ OZMAのバックダンサーが裸と見間違いかねないボディスーツを着用して出演した件について、NHKではこのような姿になるということは放送まで知りませんでした。衣装の最終チェックであるリハーサルでは放送のような衣装ではありませんでした。今回の紅白のテーマにふさわしくないパフォーマンスだったと考えます。視聴者の皆様に深いな思いをおかけして誠に申し訳なく考えております」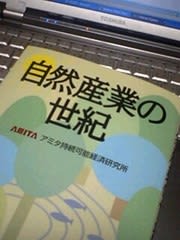 「人類はどこから来て、どこに行くのだろうか」という壮大なテーマを掲げて、持続可能な社会とは何かを徹底して論理的に実践的に追求する、そんなドゥタンクなのだ。設立は2005年7月、京都市上京区室町道にある築150年の京町屋に研究所を構えている。
「人類はどこから来て、どこに行くのだろうか」という壮大なテーマを掲げて、持続可能な社会とは何かを徹底して論理的に実践的に追求する、そんなドゥタンクなのだ。設立は2005年7月、京都市上京区室町道にある築150年の京町屋に研究所を構えている。 家人を列につけさせ、私は無料開放された兼六園にカメラのアングルを求めて入った。お目当ては兼六園の中でも見栄えがする、唐崎(からさき)の松の雪つりである。ごらんの通り、青空に映える幾何学模様の雪つりである。このほか、冬桜を撮影して列に戻った。思ったほど列は進んでいない。
家人を列につけさせ、私は無料開放された兼六園にカメラのアングルを求めて入った。お目当ては兼六園の中でも見栄えがする、唐崎(からさき)の松の雪つりである。ごらんの通り、青空に映える幾何学模様の雪つりである。このほか、冬桜を撮影して列に戻った。思ったほど列は進んでいない。 ことしの総合トップは52.7%で「サッカー・2006FIFAワールドカップ 日本VSクロアチア」(6月18日・テレビ朝日)だった。試合はドローだったが、175分の緊張感はこのゼロの試合展開で保たれ、高視聴率に結びついた。以下8位まで「ワールド・ベースボール・クラシック」「ボクシング・亀田兄弟ダブルメイン」「トリノオリンピック」と続く。9位にようやくドラマ「HERO」31.8%(7月3日・フジテレビ)がランキングされてくる。そして、10位で「ボクシング・世界ライトフライ級 亀田興毅VSファン・ランダエタ」となる。つまり、年間の高視聴率10番組のうち、9つもスポーツものがランキングされた。
ことしの総合トップは52.7%で「サッカー・2006FIFAワールドカップ 日本VSクロアチア」(6月18日・テレビ朝日)だった。試合はドローだったが、175分の緊張感はこのゼロの試合展開で保たれ、高視聴率に結びついた。以下8位まで「ワールド・ベースボール・クラシック」「ボクシング・亀田兄弟ダブルメイン」「トリノオリンピック」と続く。9位にようやくドラマ「HERO」31.8%(7月3日・フジテレビ)がランキングされてくる。そして、10位で「ボクシング・世界ライトフライ級 亀田興毅VSファン・ランダエタ」となる。つまり、年間の高視聴率10番組のうち、9つもスポーツものがランキングされた。 このニュースを読んで、去年7月、金沢大学で講演いただいたイギリスの大英博物館名誉日本部長、ヴィクター・ハリス氏=写真=の言葉を思い出した。ハリス氏は日本の刀剣に造詣が深く、宮本武蔵の「五輪書」を初めて英訳した人物だ。ハリス氏はヨーロッパ剣道連盟の副会長の要職にあった。そのハリス氏が講演の最後の方に以下のような苦言を呈した。
このニュースを読んで、去年7月、金沢大学で講演いただいたイギリスの大英博物館名誉日本部長、ヴィクター・ハリス氏=写真=の言葉を思い出した。ハリス氏は日本の刀剣に造詣が深く、宮本武蔵の「五輪書」を初めて英訳した人物だ。ハリス氏はヨーロッパ剣道連盟の副会長の要職にあった。そのハリス氏が講演の最後の方に以下のような苦言を呈した。