☆メディアのツボ-44-
情報番組「発掘!あるある大事典2」の捏造問題は随分と面白い展開になってきた。きょう21日、関西テレビの千草社長が自民党通信・放送産業高度化小委員会に出席した後、記者団に対し、番組を制作した番組制作会社に損害賠償を請求する可能性を示唆したという(日経新聞インターネット版)。
「賠償請求」の意味を考える
 記事を引用する。関テレの社長は、自らの責任問題を尋ねた記者の質問には直接答えず、「責任は重く受け止めている。再発防止、原因究明に努め信頼回復を図る」と話し、さらに「制作会社との契約では賠償責任があり、検討する」と語った。これが「賠償請求の可能性」として報道された。
記事を引用する。関テレの社長は、自らの責任問題を尋ねた記者の質問には直接答えず、「責任は重く受け止めている。再発防止、原因究明に努め信頼回復を図る」と話し、さらに「制作会社との契約では賠償責任があり、検討する」と語った。これが「賠償請求の可能性」として報道された。
今回の問題の一連の報道で見えてこないのは、関テレ自身が番組の欺瞞性に気づいていたのかどうかという点である。放送法第四条(訂正放送)の2項に「放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも」、訂正放送をしなけらばならないと記している。要は、当事者から指摘を受けなくても、常日ごろから放送の内容に留意し、事実の誤りや人権侵害などは自ら見つけ、糾(ただ)すよう求めているのである。このため、各テレビ局は「考査」というセクションを置いている。
この考査セクションでは、編成あるいは業務局に置かれ、CMや番組の表現内容をチェックして、時に営業から持ち込まれた誇大表現が含まれるCMなどをストップさせたりする。問題視したいのは、このセクションが520回にも及ぶ番組でいささか疑問を感じなかったのだろうか。あるいは、番組づくりの手の内を知り尽くしている制作部からは何の疑問の声も上がらなかったのだろうか。このテレビ局内のいわば自浄機能を伏して、制作会社の責任だけを問うのは無理がある。放送の最終的な責任はテレビ局にある。
社長が述べた「制作会社との契約では賠償責任があり」云々は本来、納品が間に合わず番組にアナを開けた場合などであって、番組の構成やつくりにはテレビ局のプロデューサーやディレクターが参加し、チェックしゴーサインを出しているのだから、これも話の筋が間違っている。日本語の吹き替え捏造などはオリジナルのVTRをチェックすれば簡単に分かる。
それでも関テレが制作会社の賠償を問うのであれば、相当の返り血を浴びる覚悟でやらなければならない。裁判の過程では「関テレ側の黙認」あるいは「暗黙の了解」という、番組の「闇」の部分があぶりだされるはずである。ウミを出し切るためにはむしろ裁判をやったほうがよいのかもしれない。
⇒21日(水)午後・金沢の天気 はれ
 「テレビ難民」問題化に国の先手
「テレビ難民」問題化に国の先手 関西テレビの番組「発掘!あるある大事典Ⅱ」で捏造問題が発覚して以来、テレビ業界全体の信頼度が落ちたように思える。そしてついにというか、きょう13日の閣議後の記者会見で、菅義偉総務相は「捏造再発防止法案」なるものを国会に提出すると述べたそうだ。その理由は「公の電波で事実と違うことが報道されるのは極めて深刻。再発防止策につながる、報道の自由を侵さない形で何らかのもの(法律)ができればいい」と。放送法第三条と第四条は、放送上の間違いがあった場合は総務省に報告し、自ら訂正放送をするとした内容の適正化の手順をテレビ局に義務付けている。さらにこれ以上の防止策となると、罰則規定の強化しかないのではないか。個別の不祥事イコール業界全体の規制の構図は繰り返されてきた負のスパイラルではある。
関西テレビの番組「発掘!あるある大事典Ⅱ」で捏造問題が発覚して以来、テレビ業界全体の信頼度が落ちたように思える。そしてついにというか、きょう13日の閣議後の記者会見で、菅義偉総務相は「捏造再発防止法案」なるものを国会に提出すると述べたそうだ。その理由は「公の電波で事実と違うことが報道されるのは極めて深刻。再発防止策につながる、報道の自由を侵さない形で何らかのもの(法律)ができればいい」と。放送法第三条と第四条は、放送上の間違いがあった場合は総務省に報告し、自ら訂正放送をするとした内容の適正化の手順をテレビ局に義務付けている。さらにこれ以上の防止策となると、罰則規定の強化しかないのではないか。個別の不祥事イコール業界全体の規制の構図は繰り返されてきた負のスパイラルではある。 捏造問題で、関テレの社長が2月7日、総務省近畿総合通信局を訪れ、捏造についてまとめた報告書を提出した。ところが、近畿総合通信局側は納得しなかったと、報じられている。なぜか。疑惑が次から次と出てきて、7日の説明は説明にならなかったからである。どとのつまり、「520回すべてを調査し報告しなければ、調査したことにはならない。これはあくまでも途中経過説ある」と監督官庁である近畿総合通信局側から灸を据えられたに違いない。こんなことは素人でも想像がつく。
捏造問題で、関テレの社長が2月7日、総務省近畿総合通信局を訪れ、捏造についてまとめた報告書を提出した。ところが、近畿総合通信局側は納得しなかったと、報じられている。なぜか。疑惑が次から次と出てきて、7日の説明は説明にならなかったからである。どとのつまり、「520回すべてを調査し報告しなければ、調査したことにはならない。これはあくまでも途中経過説ある」と監督官庁である近畿総合通信局側から灸を据えられたに違いない。こんなことは素人でも想像がつく。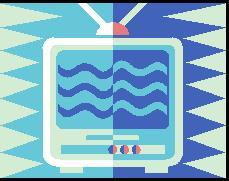 先日、あるテレビ局から金沢大学に取材の申し込みが電話あった。ニュースリリースなどの詳細をメールで送る旨を伝え、教えてもらったメールアドレスに送り、届いたら返信をくださいとお願いしたが、それがない。果たして送信できたのかとこちらが心配になって電話で確認すると、相手は「受け取りました」と。それだったら、受け取った旨の返信をくれればよいのにと思うことはしばしばある。その点、地元紙と呼ばれる新聞社は割とこまめに返信をくれる。
先日、あるテレビ局から金沢大学に取材の申し込みが電話あった。ニュースリリースなどの詳細をメールで送る旨を伝え、教えてもらったメールアドレスに送り、届いたら返信をくださいとお願いしたが、それがない。果たして送信できたのかとこちらが心配になって電話で確認すると、相手は「受け取りました」と。それだったら、受け取った旨の返信をくれればよいのにと思うことはしばしばある。その点、地元紙と呼ばれる新聞社は割とこまめに返信をくれる。 比べれば、ほぼ奇跡に近い。
比べれば、ほぼ奇跡に近い。 列記すると、各社一面を飾ったのが、NHKの番組が放送直前に改変されたとして、取材を受けた市民団体がNHKなどに総額4000万円の賠償を求めた控訴審判決で、東京高裁が取材された側の「期待権」を認めてNHKに200万円の賠償命令を命じたニュース。さらに同じ一面で、裁判員制度フォーラムを共催した産経新聞社などが謝礼を払ってサクラ(参加者)を集めていたこと。
列記すると、各社一面を飾ったのが、NHKの番組が放送直前に改変されたとして、取材を受けた市民団体がNHKなどに総額4000万円の賠償を求めた控訴審判決で、東京高裁が取材された側の「期待権」を認めてNHKに200万円の賠償命令を命じたニュース。さらに同じ一面で、裁判員制度フォーラムを共催した産経新聞社などが謝礼を払ってサクラ(参加者)を集めていたこと。 0日にホームページで公表した内容によると、捏造は3パターンである。一つは「データの捏造」。今回、被験者のコレステロール値、中性脂肪値、血糖値の測定せず、また、比較実験での血中イソフラボンの測定せず、さらに血液は採集をするも実際は検査せず、数字はすべて架空だった。二つ目が「コメントの捏造」である。米国テンプル大学アーサー・ショーツ教授の日本語訳コメントは内容は本人の話したものとはまったく違っていた。三つ目が「写真の捏造」である。やせたことを示す3枚は被験者とは無関係の写真だった。
0日にホームページで公表した内容によると、捏造は3パターンである。一つは「データの捏造」。今回、被験者のコレステロール値、中性脂肪値、血糖値の測定せず、また、比較実験での血中イソフラボンの測定せず、さらに血液は採集をするも実際は検査せず、数字はすべて架空だった。二つ目が「コメントの捏造」である。米国テンプル大学アーサー・ショーツ教授の日本語訳コメントは内容は本人の話したものとはまったく違っていた。三つ目が「写真の捏造」である。やせたことを示す3枚は被験者とは無関係の写真だった。 当初、「泡沫候補」とも言われていた元タレント候補が激戦を制したとあって、各新聞やテレビはトップニュースの扱いで報じた。ところが、このニュースを朝日新聞大阪本社はトップ扱いにしなかった。同じ朝日新聞でも、東京本社はトップだったのにである。大阪本社の一面トップは生活福祉資金の貸付金の272億円が未回収であることを報じたものだ。ホットなニュースである「そのまんま東氏当選」は準トップだった。なぜか、である。
当初、「泡沫候補」とも言われていた元タレント候補が激戦を制したとあって、各新聞やテレビはトップニュースの扱いで報じた。ところが、このニュースを朝日新聞大阪本社はトップ扱いにしなかった。同じ朝日新聞でも、東京本社はトップだったのにである。大阪本社の一面トップは生活福祉資金の貸付金の272億円が未回収であることを報じたものだ。ホットなニュースである「そのまんま東氏当選」は準トップだった。なぜか、である。 「単なる物販サイトではない。地域おこしの心意気でやっている」。北陸朝日放送(HAB)業務部、能田剛志部長は力を込めた。講演タイトルは「ECサイト『金沢屋』の6年で得たローカル独自のコマース展開とは」。放送エリアである石川県の地場産品にこだわり、この6年で生産者とともに100余りの商品を開発した。商品の採用が決まると、プロの写真家とライターが現地に入り、取材する。生産者の人となりや商品ができるまでの物語がテキストベースで紹介される。単に商品の画像を並べただけのショッピングモールとは異なり、手間ひま(コスト)をかけている。そのせいもあり、売上は緩やかな右肩上がりであるものの、単年度の黒字決算には至っていない。「(単年度黒字は)08年を目標にしている」と。今年5月、姉妹サイトとして「山形屋」(山形テレビ)が誕生した。システムと運営ノウハウを系列局にのれん分けするほどになったのである。
「単なる物販サイトではない。地域おこしの心意気でやっている」。北陸朝日放送(HAB)業務部、能田剛志部長は力を込めた。講演タイトルは「ECサイト『金沢屋』の6年で得たローカル独自のコマース展開とは」。放送エリアである石川県の地場産品にこだわり、この6年で生産者とともに100余りの商品を開発した。商品の採用が決まると、プロの写真家とライターが現地に入り、取材する。生産者の人となりや商品ができるまでの物語がテキストベースで紹介される。単に商品の画像を並べただけのショッピングモールとは異なり、手間ひま(コスト)をかけている。そのせいもあり、売上は緩やかな右肩上がりであるものの、単年度の黒字決算には至っていない。「(単年度黒字は)08年を目標にしている」と。今年5月、姉妹サイトとして「山形屋」(山形テレビ)が誕生した。システムと運営ノウハウを系列局にのれん分けするほどになったのである。