★「能登の花ヨメ」の完成度
 この映画制作にはまったく関わりがないが、ちょっとした縁がある。去年秋、私は大学コンソーシアム石川の事業「地域課題ゼミナール」で能登半島の珠洲市をテーマにケーブルテレビ向けの番組をつくった。お祭りのシーンの撮影は同市三崎町小泊地区のキリコ祭り=写真=だった。その撮影が終わった1ヵ月後、今度は、「能登の花ヨメ」の撮影が始まり、小泊地区では映画撮影用のお祭りが行なわれた。小泊の住人のひとたちは「年に2度、まっつり(祭り)が来た。こんなうれしいことはない」ととても喜んでいたのを思い出す。
この映画制作にはまったく関わりがないが、ちょっとした縁がある。去年秋、私は大学コンソーシアム石川の事業「地域課題ゼミナール」で能登半島の珠洲市をテーマにケーブルテレビ向けの番組をつくった。お祭りのシーンの撮影は同市三崎町小泊地区のキリコ祭り=写真=だった。その撮影が終わった1ヵ月後、今度は、「能登の花ヨメ」の撮影が始まり、小泊地区では映画撮影用のお祭りが行なわれた。小泊の住人のひとたちは「年に2度、まっつり(祭り)が来た。こんなうれしいことはない」ととても喜んでいたのを思い出す。
先行上映の封切りの日、きのうさっそく「能登の花ヨメ」を鑑賞に行った。そのストーリーを簡単に説明する。映画は女性の人間模様と能登の祭りがテーマ。ヒロイン役の田中美里が演じるのは東京のキャリアウーマン。結婚式を前に、泉ピン子が演じる婚約者の母が交通事故でけがをする。あいにく、海外出張でフィアンセは母がいる能登には行けない。そこで、代わりに看病のために能登へ行くというところから物語は始まる。都会育ちの女性にとって能登は刺激がなく、しかも慣れない人づき合い、大きな田舎造りの家の掃除、ヤギの世話…。しかも、姑(しゅうとめ)となる母親はつっけんどん。でも、能登には震災にもめげず、心根が優しい、自然をいつくしむ人たちがいて、都会にはない豊かさがあると気付く。
親しくなって、キノコ採りを教わった近所のおばあちゃん(内海桂子)からキリコ祭りを楽しみにしているという話を聞かされた。その数日後、おばあちゃんは急逝する。季節は秋へと移り、お祭りのシーズンがやってくる。地震で仮設住宅の人たちもいるのにお祭りはできるのか…。しかも、キリコは担ぎ手が不足していて、ここ数年は出していない。土地の人たちはキリコ祭りを楽しみにしているのにどこか遠慮している。そこで、都会からきた花嫁がキリコ祭りの復活を呼びかけて立ち上がる。
監督は白羽弥仁(しらは・みつひと)氏。3年も前から能登に通って、映画の構想を温めてきたという。そして撮影を始めようとする矢先に能登半島地震(07年3月25日)が起きた。神戸出身で自ら被災経験がある白羽監督はその2日後に被災地に駆けつけた。そして、映画づくりを続行すべきかどうか迷っていたときに、これまで協力してきた能登の人たちから「こんなときにこそ映画を撮って」と要望され、撮影を決断したという。映画が完成するまでの経緯がまるでストーリー仕立てのようだ。
冒頭でご当地映画には気恥ずかしさがあると述べた。それは方言のことである。方言は内々の言葉で、ほかの地域の人が聞けば野暮ったいものだ。「能登の花ヨメ」では能登弁を上手にさらけ出している。それが映画の味にもなっているのだが、能登出身者とするとちょっと気恥ずかしい。逆に言えば、能登人の言葉と心の襞(ひだ)までが映像表現されて完成度は高い。
⇒11日(日)朝・金沢の天気 くもり
 こいのぼりが揚がらなくなった理由として、住宅が狭くこいのぼりを揚げるスペースがないとよくいわれる。でも、能登や加賀の広々とした家並みでも見かけるのは稀だ。それは少子化で揚がらなくなったのでは、という人もいるだろう。能登地区は確かに少子高齢化だが、地域をつぶさに眺めると、公園などで遊んでいる小さな男の子たちは案外多い。まして、加賀地区で少子高齢化の現象は顕著ではない。でも不思議とこいのぼりを揚げる家は極少ないのだ。
こいのぼりが揚がらなくなった理由として、住宅が狭くこいのぼりを揚げるスペースがないとよくいわれる。でも、能登や加賀の広々とした家並みでも見かけるのは稀だ。それは少子化で揚がらなくなったのでは、という人もいるだろう。能登地区は確かに少子高齢化だが、地域をつぶさに眺めると、公園などで遊んでいる小さな男の子たちは案外多い。まして、加賀地区で少子高齢化の現象は顕著ではない。でも不思議とこいのぼりを揚げる家は極少ないのだ。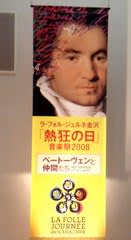 どこが「クラシックの民主化」なのかというと、①短時間で聴くクラシック②低料金で聴くクラシック③子どもも参加するクラシック・・・の3点に特徴があるそうだ。民主化というより、クラシックの裾野を広げるための音楽祭ともいえる。1995年にフランスのナント市で始まった音楽祭。この音楽祭の開催は世界で6番目、日本では東京に次いで2番目とか。
どこが「クラシックの民主化」なのかというと、①短時間で聴くクラシック②低料金で聴くクラシック③子どもも参加するクラシック・・・の3点に特徴があるそうだ。民主化というより、クラシックの裾野を広げるための音楽祭ともいえる。1995年にフランスのナント市で始まった音楽祭。この音楽祭の開催は世界で6番目、日本では東京に次いで2番目とか。 朝の日課なので、青空に映えるこいのぼりを見るとすがすがしい。通りがかりの学生たちが「こいのぼりをこんなに間近に見るのは初めて」とか「大学でこいのぼりを揚げているのは金大だけとちがうか…」などと言いながら見上げている。聖火リレーをめぐる騒ぎに比べれば、実にのどかな光景ではある。
朝の日課なので、青空に映えるこいのぼりを見るとすがすがしい。通りがかりの学生たちが「こいのぼりをこんなに間近に見るのは初めて」とか「大学でこいのぼりを揚げているのは金大だけとちがうか…」などと言いながら見上げている。聖火リレーをめぐる騒ぎに比べれば、実にのどかな光景ではある。 その法隆寺で、日本工芸のルーツといわれるのが「国宝 玉虫厨子(たまむしのずし)」。日本史では飛鳥美術の代表作とされる。が、現在のわれわれが目にするは黒光り、古色蒼然とした造作物という印象しかない。すでに描かれていたであろう仏教画や装飾などは、イメージをほうふつさせるほどに残されてはいない。歴史の時空の中で剥離し劣化した。
その法隆寺で、日本工芸のルーツといわれるのが「国宝 玉虫厨子(たまむしのずし)」。日本史では飛鳥美術の代表作とされる。が、現在のわれわれが目にするは黒光り、古色蒼然とした造作物という印象しかない。すでに描かれていたであろう仏教画や装飾などは、イメージをほうふつさせるほどに残されてはいない。歴史の時空の中で剥離し劣化した。 奥能登・珠洲市に古民家レストランと銘打っている店がある。確かに築110年という古民家には土蔵があり、その座敷で土地の郷土料理を味わう。過日訪れると、中庭で野点が催されていて、ご相伴にあずかった。
奥能登・珠洲市に古民家レストランと銘打っている店がある。確かに築110年という古民家には土蔵があり、その座敷で土地の郷土料理を味わう。過日訪れると、中庭で野点が催されていて、ご相伴にあずかった。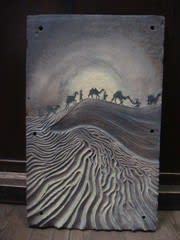 節を重んじ、相和すことを重んじる。そんな凛(りん)とした雰囲気が感じられる野点だった。
節を重んじ、相和すことを重んじる。そんな凛(りん)とした雰囲気が感じられる野点だった。
 ミシュランガイド東京に掲載されているレストランは150軒で、最も卓越した料理と評価される「三つ星」は8軒。「二つ星」は25軒、「一つ星」は117軒選ばれている。フランスやイタリア料理が多いのかと思いきや、ガイド全体では日本料理が6割を占めている。和食への評価が世界的に高まっていることがベースにあるのだろう。ちなみに、一つ星は「カテゴリーで特に美味しい料理」、二つ星は「遠回りしてでも訪れる価値がある素晴らしい料理」、三つ星は「そのために旅行する価値がある卓越した料理」の価値基準らしい。
ミシュランガイド東京に掲載されているレストランは150軒で、最も卓越した料理と評価される「三つ星」は8軒。「二つ星」は25軒、「一つ星」は117軒選ばれている。フランスやイタリア料理が多いのかと思いきや、ガイド全体では日本料理が6割を占めている。和食への評価が世界的に高まっていることがベースにあるのだろう。ちなみに、一つ星は「カテゴリーで特に美味しい料理」、二つ星は「遠回りしてでも訪れる価値がある素晴らしい料理」、三つ星は「そのために旅行する価値がある卓越した料理」の価値基準らしい。 なく、静かで落ち着いていて、客層は老紳士・淑女然としたお年寄りが多いのだ。
なく、静かで落ち着いていて、客層は老紳士・淑女然としたお年寄りが多いのだ。 変えられてしまった人々も多い。そんな被災者の生の声をつづった「住民の生活ニーズと復興への課題」というリポートがある。金沢大学能登半島地震学術調査部会の第2回報告会(3月8日)で提出されたものだ。その中からいくつか拾ってみる。
変えられてしまった人々も多い。そんな被災者の生の声をつづった「住民の生活ニーズと復興への課題」というリポートがある。金沢大学能登半島地震学術調査部会の第2回報告会(3月8日)で提出されたものだ。その中からいくつか拾ってみる。