★「へんざいもん」の味
金沢大学が能登半島で展開している「里山里海自然学校」は廃校となった小学校の施設を再活用して開講している。ここでは生物多様性調査や里山保全活動、子供たちへの環境教育、キノコ山の再生などに取り組 んでいる。もう一つの活動の目玉が「食文化プロジェクト」だ。
んでいる。もう一つの活動の目玉が「食文化プロジェクト」だ。
学校の施設だったので、給食をつくるための調理設備が残っていた。それに改修して、コミュニティ・レストランをつくろうと地域のNPOのメンバーたちが動き営業にこぎつけた。その食堂名が「へんざいもん」。愛嬌のある響きだが、人名ではない。この土地の方言で、漢字で当てると「辺採物」。自家菜園でつくった野菜などを指す。「これ、へんざいもんですけど食べてくだいね」と私自身、自然学校の近所の人たちから差し入れにあずかることがある。このへんざいもんこそ、生産者の顔が見える安 心安全な食材である。
心安全な食材である。
地元では「そーめんかぼちゃ」と呼ぶ金糸瓜(きんしうり)、大納言小豆など、それこそ地域ブランド野菜と呼ぶにふさわしい。そんな食材の数々を持ち寄って、毎週土曜日のお昼にコミュニティ・レストラン「へんざいもん」は営業する。コミュニティ・レストランを直訳すれば地域交流食堂だが、それこそ郷土料理の専門店なのである。ある日のメニューを紹介しよう。
ご飯:「すえひろ舞」(減農薬の米)
ごじる:大豆,ネギ
天ぷら:ナス,ピーマン
イカ飯:アカイカ,もち米
ユウガオのあんかけ:ユウガオ,エビ,花麩
ソウメンカボチャの酢の物:金糸瓜、キュウリ
カジメの煮物:カジメ,油揚げ
フキの煮物:フキ
インゲンのゴマ和え:インゲン
上記のメニューがワンセットで700円。すべて地域の食材でつくられたもの。郷土料理なので少々解説が必要だ。「ごじる」は汁物のこと。能登では、田の畦(あぜ)に枝豆を植えている農家が多い。大豆を収穫すると、粒のそろった良い大豆はそのまま保存されたり、味噌に加工されたりして、形の悪いもの、小さいものをすり潰して「ごじる」にして食する。カジメとは海藻のツルアラメのこと。海がシケの翌日は海岸に打ち上げられる。これを細く刻んで乾燥させる。能登では油揚げと炊き合わせて精進料理になる。
里山里海自然学校の研究員や、環境問題などの講義を受けにやって来る受講生や地域の人たちで40席ほどの食堂はすぐ満員になる。最近では小学校の児童やお年寄りのグループも訪れるようになった。週1回のコミュニティ・レストランだが、まさに地域交流の場となっている。金沢大学の直営ではなく、地域のNPOに場所貸しをしているだけなのだが、おそらく郷土料理を専門にした「学食」は全国でもここだけと自負している。
※写真・上は「へんざいもん」で料理を楽しむ。写真・下は文中のメニュー。赤ご膳が祭り料理風で和む
⇒19日(金)朝・金沢の天気 くもり
 んでしまった。
んでしまった。 教育界では子供たちの理科離れが進んでいるとよくいわれるが、メディアの世界では科学記事の割合が広がり、たとえば朝日新聞社では30年前に20人ほどだった科学担当記者は現在では50人ほどに増えている。戦後は60年安保、70年安保と大学キャンパスでも政治闘争の嵐が吹き荒れた。が、高度成長に伴ってハイテク、ロボット、宇宙、IT、新型感染症、医療・生命倫理、食の安全と危機管理、そして環境へと、メディアの記事テーマは政治・社会から科学への「理系シフト」が起きている。それが極まったのが、ことし8月の洞爺湖サミットだ。地球温暖化についての科学的な研究の収集、整理のための政府間機構であるIPCCの科学者たちが動いて、地球環境問題をサミットの主議題に押し上げたといわれる。少なくとも、政治家が地球環境問題を無視できないような状態になった。科学者のメッセージで世界が動く時代に入ったともいえる。
教育界では子供たちの理科離れが進んでいるとよくいわれるが、メディアの世界では科学記事の割合が広がり、たとえば朝日新聞社では30年前に20人ほどだった科学担当記者は現在では50人ほどに増えている。戦後は60年安保、70年安保と大学キャンパスでも政治闘争の嵐が吹き荒れた。が、高度成長に伴ってハイテク、ロボット、宇宙、IT、新型感染症、医療・生命倫理、食の安全と危機管理、そして環境へと、メディアの記事テーマは政治・社会から科学への「理系シフト」が起きている。それが極まったのが、ことし8月の洞爺湖サミットだ。地球温暖化についての科学的な研究の収集、整理のための政府間機構であるIPCCの科学者たちが動いて、地球環境問題をサミットの主議題に押し上げたといわれる。少なくとも、政治家が地球環境問題を無視できないような状態になった。科学者のメッセージで世界が動く時代に入ったともいえる。 想像したのは強盗が入るなどの最悪の事態。すると奥の方で懐中電灯の明かりが揺れている。「やっぱり」と思い。大声で「誰かいるのか」と凄んだ。すると奥から家内の声、「停電なの」。力が抜ける。
想像したのは強盗が入るなどの最悪の事態。すると奥の方で懐中電灯の明かりが揺れている。「やっぱり」と思い。大声で「誰かいるのか」と凄んだ。すると奥から家内の声、「停電なの」。力が抜ける。 有川氏が組合長を務める「かが森林組合」は日本海側で唯一FSC認証を取得している。FSC(Forest Stewardship Council=森林管理協議会)は国際的な森林認証制度を行なう第三者機関。この機関の認証を取得するには4000万円ほどの経費がかかり、毎年、環境や経営面での厳しい査察を受ける。林業をめぐる経営環境そのものが厳しいのにさらに環境面でのチェックを受けるは、普通だったら資金的にも精神的にも体力は持たない、と思う。ところが、その「逆境」こそがバネになるというのが今回の講義のポイントなのだ。
有川氏が組合長を務める「かが森林組合」は日本海側で唯一FSC認証を取得している。FSC(Forest Stewardship Council=森林管理協議会)は国際的な森林認証制度を行なう第三者機関。この機関の認証を取得するには4000万円ほどの経費がかかり、毎年、環境や経営面での厳しい査察を受ける。林業をめぐる経営環境そのものが厳しいのにさらに環境面でのチェックを受けるは、普通だったら資金的にも精神的にも体力は持たない、と思う。ところが、その「逆境」こそがバネになるというのが今回の講義のポイントなのだ。 以下、講義の概要。大学の地域連携とは何か。国立大学の担当セクションを見渡してみると取り組み方法はインドア型とアウトドア型の2つのタイプに分類できそうだ。インドア型は、窓口を開いておいて来客があれば対応するというもの。持ち込まれた課題に関して、その課題の解決に役立ちそうな教授陣(教授や准教授)を紹介する。この方法は多くの大学で実施されていて、金沢大学でもさまざまな案件が持ち込まれる。多種多様な相談事が持ち込まれるものの、すべての案件に十分対応できるわけではない。さらに、仮に相談には乗ることができても、時間を割いて現場に足を運んでくれる熱意のある人材となるとそう多くはなく、もどかしさを感じることもままある。これは何も金沢大学に限った話ではない。
以下、講義の概要。大学の地域連携とは何か。国立大学の担当セクションを見渡してみると取り組み方法はインドア型とアウトドア型の2つのタイプに分類できそうだ。インドア型は、窓口を開いておいて来客があれば対応するというもの。持ち込まれた課題に関して、その課題の解決に役立ちそうな教授陣(教授や准教授)を紹介する。この方法は多くの大学で実施されていて、金沢大学でもさまざまな案件が持ち込まれる。多種多様な相談事が持ち込まれるものの、すべての案件に十分対応できるわけではない。さらに、仮に相談には乗ることができても、時間を割いて現場に足を運んでくれる熱意のある人材となるとそう多くはなく、もどかしさを感じることもままある。これは何も金沢大学に限った話ではない。 2004年の国立大学法人化をきっかけに、大学の役割はこれまでの教育と研究に社会貢献が加わった。大学によっては、「地域連携」と称したりもする。金沢大学もその担当セクションの名称を地域貢献推進室(02-04年度)、社会貢献室(05-07年度)、地域連携推進センター(08年度~)と組織再編に伴い変えてきた。民間企業だと、さしあたりCSR推進部といったセクション名になるだろう。CSRは企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)をいい、企業が利益を追求するのみならず、社会へ与える影響に責任を持ち、社会活動にも参加するという意味合い。しかし、よく考えてみれば、大学はもともと利益を追求しておらず、本来の使命は教育と研究であり、そのものが社会貢献である。金沢大学でも社会貢献セクションの設立に際して、「大学の使命そのものが社会貢献であり、さらに社会貢献を掲げ一体何をするのか」といった意見もあったようだ。
2004年の国立大学法人化をきっかけに、大学の役割はこれまでの教育と研究に社会貢献が加わった。大学によっては、「地域連携」と称したりもする。金沢大学もその担当セクションの名称を地域貢献推進室(02-04年度)、社会貢献室(05-07年度)、地域連携推進センター(08年度~)と組織再編に伴い変えてきた。民間企業だと、さしあたりCSR推進部といったセクション名になるだろう。CSRは企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)をいい、企業が利益を追求するのみならず、社会へ与える影響に責任を持ち、社会活動にも参加するという意味合い。しかし、よく考えてみれば、大学はもともと利益を追求しておらず、本来の使命は教育と研究であり、そのものが社会貢献である。金沢大学でも社会貢献セクションの設立に際して、「大学の使命そのものが社会貢献であり、さらに社会貢献を掲げ一体何をするのか」といった意見もあったようだ。 先日、石川県から「ヘルスツーリズム」の研究委託を受けた准教授(栄養学)から相談があった。「能登の料理を研究してみたいのですが・・・」と。委託したのは県企画振興部で、健康にプラスになるツアーを科学的に裏付けし、新たな観光資源に育てるという狙いが行政側にある。キノコや魚介類など山海の食材に恵まれた能登は食材の宝庫だ。准教授の目の付けどころは、その中から機能性に富んだ食材を発掘し、抗酸化作用や血圧低下作用などの機能性評価を行った上で 四季ごとにメニュー化する。能登の郷土料理でよく使われる食材の一つであるズイキの場合、高い抗酸化作用や視覚改善作用が期待されるという。
先日、石川県から「ヘルスツーリズム」の研究委託を受けた准教授(栄養学)から相談があった。「能登の料理を研究してみたいのですが・・・」と。委託したのは県企画振興部で、健康にプラスになるツアーを科学的に裏付けし、新たな観光資源に育てるという狙いが行政側にある。キノコや魚介類など山海の食材に恵まれた能登は食材の宝庫だ。准教授の目の付けどころは、その中から機能性に富んだ食材を発掘し、抗酸化作用や血圧低下作用などの機能性評価を行った上で 四季ごとにメニュー化する。能登の郷土料理でよく使われる食材の一つであるズイキの場合、高い抗酸化作用や視覚改善作用が期待されるという。 もともとは、ことし3月に出版された「パラダイス鎖国 忘れられた大国・日本」 (海部美知、アスキー新書)のタイトルから引用された言葉だ。ことし1月のダボス会議で、「Japan: A Forgotten Power?(日本は忘れられた大国なのか)」というセッションが開かれ、国際的に日本の内向き志向が論議になったという。高度経済成長から貿易摩擦の時代を経て、日本はいつの間にか、世界から見て存在感のない国になってしまっている。その背景には、安全や便利さ、そしてモノの豊かさ日本は欧米以上になり、外国へのあこがれも昔ほど持たなくなったことがある。明治以来の欧米に追いつけ追い越せのコンプレックスは抜け切ったともいえる。ハングリー精神とかチャレンジ精神という言葉は死語になりつつあり、リスクを取らないことが美徳であるかのような社会の風潮だ。これでは人は育たず、社会も会社も停滞する。
もともとは、ことし3月に出版された「パラダイス鎖国 忘れられた大国・日本」 (海部美知、アスキー新書)のタイトルから引用された言葉だ。ことし1月のダボス会議で、「Japan: A Forgotten Power?(日本は忘れられた大国なのか)」というセッションが開かれ、国際的に日本の内向き志向が論議になったという。高度経済成長から貿易摩擦の時代を経て、日本はいつの間にか、世界から見て存在感のない国になってしまっている。その背景には、安全や便利さ、そしてモノの豊かさ日本は欧米以上になり、外国へのあこがれも昔ほど持たなくなったことがある。明治以来の欧米に追いつけ追い越せのコンプレックスは抜け切ったともいえる。ハングリー精神とかチャレンジ精神という言葉は死語になりつつあり、リスクを取らないことが美徳であるかのような社会の風潮だ。これでは人は育たず、社会も会社も停滞する。 さて、シリーズ「能登の旋風(かぜ)」は里山里海国際交流フォーラム「能登エコ・スタジアム2008」のイベントで拾った話題を紹介している。9月13日から17日にかけての「能登エコ・スタジアム2008」は3つのフォーラム、6つのプログラム、1つのツアーから構成されていたが、17日にシニアコース(シニア短期留学)の修了式をもって、すべてのメニューを完了した。また、同日は生物多様性条約のムハマド・ジョグラフ事務局長の能登視察も終了した。一連のイベントメニューの中でのVIP視察だった。
さて、シリーズ「能登の旋風(かぜ)」は里山里海国際交流フォーラム「能登エコ・スタジアム2008」のイベントで拾った話題を紹介している。9月13日から17日にかけての「能登エコ・スタジアム2008」は3つのフォーラム、6つのプログラム、1つのツアーから構成されていたが、17日にシニアコース(シニア短期留学)の修了式をもって、すべてのメニューを完了した。また、同日は生物多様性条約のムハマド・ジョグラフ事務局長の能登視察も終了した。一連のイベントメニューの中でのVIP視察だった。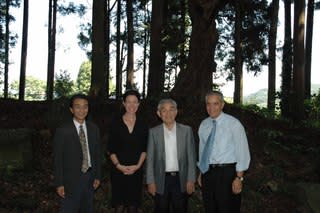 今回のイベントで印象に残った2枚の写真。持続可能なこと、それは地下に封じ込められた化石燃料を掘り出して、燃焼させ、二酸化炭素を排出することではない。二酸化炭素を吸収し、光合成によって成長した植物をエネルギー化すること。里の生えるススキ、カヤ類を燃料化する試みが始まっている。それらをペレット化して燃料、あるいは家畜の飼料にする。奥能登では戦後、1800haもの畑地造成が行われたが、そのうち1000haが耕作放棄されススキ、カヤが生い茂っている。それをなんとかしたいとの発想でバイオマス研究から実用化の段階に向けて試行が続いている。能登エコ・スタジアムのコース「バイオエコツーリズム」ではその試みに興味を持った若者たちが大勢集まってきた。そして実際にススキを刈り取り、ペレット化を体験したのである。上の写真はその刈り入れの様子だ。地域エネルギーの可能性を感じさせる光景に見えた。
今回のイベントで印象に残った2枚の写真。持続可能なこと、それは地下に封じ込められた化石燃料を掘り出して、燃焼させ、二酸化炭素を排出することではない。二酸化炭素を吸収し、光合成によって成長した植物をエネルギー化すること。里の生えるススキ、カヤ類を燃料化する試みが始まっている。それらをペレット化して燃料、あるいは家畜の飼料にする。奥能登では戦後、1800haもの畑地造成が行われたが、そのうち1000haが耕作放棄されススキ、カヤが生い茂っている。それをなんとかしたいとの発想でバイオマス研究から実用化の段階に向けて試行が続いている。能登エコ・スタジアムのコース「バイオエコツーリズム」ではその試みに興味を持った若者たちが大勢集まってきた。そして実際にススキを刈り取り、ペレット化を体験したのである。上の写真はその刈り入れの様子だ。地域エネルギーの可能性を感じさせる光景に見えた。